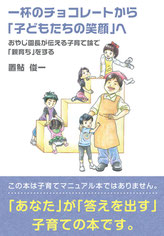2024年
7月
26日
金
「自由」と「自律」
明日からのサマーキャンプに備えて、年長以外の園児には申し訳ないですが、今日はプールなしで、教室内でゲーム大会をしました。熱中症予防の最大の対応は何だと思いますか。「水分補給!」と思ったあなた。もちろん正解ですが、一番の効果は「慣れる」ことです。「暑熱順化」と言います。人間の体が暑さに慣れて順応した状態を指します。
人体の体温調節の主たる機能は発汗作用、つまり汗をかくことです。冬から春にかけては機会が減るので適切に働きません。これが、体の不調や熱中症を起こしやすくする原因の一つです。7月からスタートした屋上プールで、子どもたちの「暑熱順化」は、進んだと思われますが、今日は大事を取りました。
年長園児は、サマーキャンプという非日常の生活にワクワクドキドキです。ついつい、自由奔放な行動を取ってしまうかもしれません。初日の川遊びは、楽しみがいっぱいですが、リスクもいっぱいです。最初にライフジャケットで浮く練習をしてから、先生たちも一緒に川に入って、危険個所を確認しながら遊びます。毎年恒例の「岩からジャンプ!」も、すぐ下で先生が待ち構えています。
8人の年長園児の集団生活となるサマーキャンプには「自律」が大切になります。その上で、いつもはできない「自由」を満喫する遊びを体験させたいと思っています。サマーキャンプで「自由」を楽しむには「自律」があってこそですね。
たった2日間ですが、サマーキャンプを終えた子どもたちは、大きな成長を遂げます。「自律」も「自立」も両方獲得します。「友情」「協力」・・・仲間同士で学ぶことも多いですね。そんな子どもたちを成長を見届けながら、明日からの2日間を過ごします。
次回のブログは、サマーキャンプが終わった、日曜日に更新します。子どもたちの素晴らしいエピソードも珍道中もどうぞお楽しみに!
2024年
7月
25日
木
阪神甲子園球場100周年
今日は、卒園児の小学生が8人も集合しました。久々に会った同士、会話も弾みます。成績表を交換して、「あーだこーだ」言っています。そして、うれしかったのは、小5の男子が、保育園の卒園記念品の国語辞典をもってきました。それには、付箋がびっしりあります。1年ごとに付箋の色も変えていました。卒園式の時には、「この国語辞典を引いた文字に線を引いて真っ黒にしてください」と伝えたので、本当に感動しました。
昨日、プールが飛ばされてしまったので、屋根付きの新プールを導入しました。新しモノ好きの園児たちが、さっそく集まって遊びます。大プールも空気漏れがひどくなったので新調しました。たっぷりと水を入れて、小学生と年長園児で水しぶきです。
さて、阪神甲子園球場が8月1日に生誕100周年を迎えます。みなさんは、甲子園球場にどんな思い入れがありますか。日々、夏の甲子園大会への出場校が決まっていきます。私も、中学・高校時代に、甲子園のアルプススタンドで母校の応援をしました。中学の時は、試合途中で雷雨となり、びしょ濡れになりながら応援したものの再試合。高校の時は、蔦監督率いる名門池田高校に惜敗しました。今もしっかりと記憶に残っています。
夏の甲子園は8月にあることがミソです。旧盆があって、終戦記念日には「黙とう」を行いますね。その中で、テレビを観ている国民が平和をかみしめながら野球観戦をするのがいいのです。
甲子園球場は、戦争の影響をもちろん受けています。すでに戦時色が濃くなりつつあった1943年には、内野スタンドが金属提出によって取り外され、やがて球音が響かなくなります。グランドは、なんと芋畑になったのです。終戦後は米軍に接取されます。グランドに球音が戻ったのは1947年です。春夏の甲子園大会もプロ野球も再開されます。敗戦から再起する人々を勇気づけます。大学のアメリカンフットボールの「甲子園ボウル」も、この年からスタートしたそうです。
その後の高校野球は、私もうっすらと記憶しています。「怪物江川卓」の球の速いこと。「ドカベン香川伸行」はそのまんま漫画の世界でした。桑田・清原のKKコンビのPL高校からは、多くのプロ野球選手が排出されました。「ゴジラ松井の5打席連続敬遠」「松坂世代」「ハンカチ王子VSマー君」そして、大谷翔平も甲子園球児でした。
阪神タイガースの記憶では、やはり、バース・掛布・岡田のバックスクリーン3連発です。この年日本一になった阪神タイガースは、本当に強かったですね。
試合には関係ないですが、私のもう一つの思い出は「かちわり氷」です。ビニール袋にかち割った氷が入っているだけで、ストローでチューチューしてもよし。頭を冷やすのに使ってもよし。氷をガリガリ食べるのもよし。この甲子園名物を食べたことがありますか。
現在の甲子園球場は、電光掲示板ですが、手書き時代の選手名のボードも記憶に残りますね。まだまだ、あげればきりがありませんが、みなさんにとっての「阪神甲子園球場」は、どんな思い出が詰まっていますか。
2024年
7月
24日
水
スーパーのレジ 座ってお仕事?!
今日は、週末に迫ったサマーキャンプを前に、年長園児は、ライフジャケットを身につけて、うつ伏せと仰向けに浮く練習をしました。「体の力を抜いて!」と言えば言うほど体に力が入ってしまう5歳女の子です。本番では、深くて川の流れがあります。水も緑色です。本番では、ライフジャケットで浮く練習を入念に行うことにします。
そして、プールが終わってから大事件が起きました。ライフジャケットや水を抜いたプールをおひさまの下で乾かせておきます。昼過ぎに片付けに行ったところ、まるで台風のような暴風雨&雷ゴロゴロです。ペンギンプールとプールの屋根が無くなっていました。どうやら風に飛ばされてしまったようです。他のプールとライフジャケットも屋上に散乱していました。ずぶ濡れになりながら、それらを確保しました。30分くらいで雨風はおさまったのですが、屋上から見下ろしても、ペンギンプール・プールの屋根・たらい3つ・ライフジャケット1つは、見つかりません。とんだハプニングでした。
さて、様々な業界で働き手不足が深刻になっています。雇う側は従業員を確保しようと職場環境の改善に動いています。その中でも、私の常識では考えられない、レジでの接客を座ってもできるようにイスが導入されたスーパーマーケットがあらわれました。
埼玉県では有名な「ベルク」というスーパーマーケットのある店舗では、各レジのカウンターに置かれているのが黒いイスです。レジ打ちをしている従業員は、立ったり座ったりさまざまで、イスは高さが調整できます。お客様がレジに並んでいない『待機」の時に座っている人が多いそうですが、「立ちっぱなしのレジの仕事で、少しでも座れる時間があると楽です」と腰痛持ちのスタッフは言います。
ヨーロッパや韓国など、海外で「座ってレジ」は珍しいことではないそうです。「7、8時間立ちっぱなしもある仕事。疲労していたのではお客様への笑顔も出ない。従業員の負担軽減も理由でした」とベルクのシステム改革部のマネージャーは言います。
お客様の反応はいかに。それが、批判的な反応はほとんどないようです。毎日買い物に来るお客様は「座ってても全く気にならない。今まで何で立ったままだったんだろう、と思うくらい」と話します。
レジでのイス導入も、数年前から当たり前になった、身だしなみ基準緩和も、セルフレジ導入も、「従業員が少しでも働きやすくなるように」は、表の言葉で、本音は、人手不足解消への対策です。スーパーマーケットだけでなく、警備の世界でも「座ったまま警備」も始まっているようです。
私たち消費者の立場で言えば、セルフレジなどは、サービスの実質低下ですね。気心知れた店員さんとの会話もなく、一人黙々と会計を済ませる。買い物の楽しみも、人によっては半減します。しかし、今後、少子高齢化がさらに進み、働く人が減り、長期的な人手不足が続く中では、以前のような至れり尽くせりのサービスを消費者が期待するのは難しくなっています。
私たちは、サービスについては「諦めるものと、そうでないもの」をしっかりと区分けして考える時代になっているのかもしれません。
2024年
7月
23日
火
実生活で生きる言語力
こうも暑い日が続くと、屋上プールをやってないと干上がってしまいそうです。今日もボランティアのパパがスイカを差し入れてくれました。スイカ割り大会がスタートです。昨日に比べると、バットで叩く力が増しています。年長園児のところでスイカにひびが入り、最後の小学1年生で、見事にまっ二つ割れました。大歓声です。
さて、保育園では、子どもたちが、遊びの中での会話を通じて、コミュニケーション能力を磨いています。もちろん、子どもたちは、コミュニケーションという言葉は分からないので、先生たちが「コミュニケーションができているかなぁ~?」という勝手なモノサシで見ているのです。
子どもたちを見ていると、「もう少し言葉を足せば・・もっと違う言い方をすれば・・」なんて思うことは、日常茶飯事です。これが、小学生・中学生になると、言語力が高くなっているので、もっと細かい点で、気になることが多くなりますね。
では、私たち大人は、子どもたちに「実生活で役に立つ言語力」を身につけさせるには、どんなことをすればいいのか・・・考えたことがありますか。
京都にある、あるお寺に掲げられている言葉です。これが、なかなか的を得ています。
「何を話せるかが知性/ 何を言わないかが品性/ どのように伝えるかが人間性/ 」
どうですか・・・言葉を用いて他者と生きる難しさをズバリ表した言葉ですね。では、学校の授業などで扱う言語力は、この3つのうちでどれでしょうか。そう、「何を話せるかが知性」です。学校の先生が、どんなに素敵な授業をしても、子どもたちには、知性しか教えることができないのです。
では、品性と人間性を子どもたちは、どうやって学ぶことができるのでしょうか。それは、授業ではなく、友だちとの関わりの中で、「今は、言わないでおこう」とか「もう少し優しい言い方にしてみよう」を自然と身につけていくのです。これが、コミュニケーション能力なのかもしれません。
そうだ。品性は、大人の立ち振る舞いから子どもが学ぶことですね。大人が普段使う言葉が、最高の日本語であるように、私たち大人も考える必要があるようです。あっ~私も頭が痛いです。(笑)
2024年
7月
22日
月
素直に感動したいなぁ~
今日は、小学生が1年生から5年生まで5人集合です。赤ちゃんを見ると「かわいい!」と今日は世話係を頑張ってくれた5年生女子・・・さすが役に立ちます。小3男子は、ルービックキューブをいとも簡単に完成させていました。屋上プールでは、ボランティアのパパが、大きなスイカを差し入れてくれたので、今シーズン初の「スイカ割り」で盛り上がりました。「おいしい!うまい!おかわり!」の声が響きます。
さて、今日は3人の小学校1年生が登園しました。夏休みに、おうちに持ち帰ったのが、「アサガオ」です。すでに、花が咲いているそうです。夏休みの課題は、朝顔の種を収穫して、その種を来年の1年生に、つなぐことだそうです。自分たちも、先輩から引き継いだ種で花を咲かせたのです。何だか、素敵な話ですね。
アサガオは、一日花ですので、朝から昼にかけて花を咲かせたら、もう翌日には、同じ花ビラは開きません。花はしぼんだままで、今度は「種」になる準備を始めるのです。この観察を、目を輝かせながら、1年生たちは行うのでしょう。子どもたちが、小さな植物を慈しむ心は、まるで天使のようですね。
詩人の相田みつをさんはこう言います。「子どものためにやらなくてはならない事は沢山あるけれど、その中でも一番大切だと思っている事は、子どもが小さいうちに、心の中に美しいものを見て、素直に感動する心を養っていくこと。これが親の大事な務めなんだよ」
では、どうやったら子どもの心の中に、感動の心が芽生えるのか。相田さんは続けます。「まず親が感動しなくては駄目だよ。親の感動は、必ず子どもの心に伝わって、感動する心が芽生えるのだから」
相田さんの詩に「感動とは 感じて 動く と書くんだなあ」があります。まさに、私たち大人は、子どもの「感じる心」を大切にしたいですね。アサガオのような植物からも、ダンゴムシ・てんとう虫・空を飛ぶクマバチやトンボからも、子どもたちの「感じる心」が伝わってきます。いつの時代も、多くのことは自然から教わることが多いですね。私たち大人も、子どもの頃を振り返ってみると、つくづくそう思います。
大人になっても、素直に感動する心を持ち続けたいものです。特に子どもの前では、子どもと同じ目線になってみませんか。
2024年
7月
21日
日
暑いぞ!嵐山・小川
我が家の庭が、伸びた雑草で景観を乱していたので、涼しい朝のうちに「草むしり」をします。朝6時だというのにすでにお日様が顔を出していました。朝から汗だくです。(笑)
でも、ゴミ袋3つ分、しっかりと仕事をして満足の汗です。朝風呂を浴びて、武蔵嵐山に出発です。
今週末のサマーキャンプまで、1週間となりました。特に川遊びをする場所は、ぶっつけ本番というわけにはいかないので、下見に行ってきました。嵐山渓谷で川遊びをします。途中、バーベキューで有名な河原を通るのですが、人がまばらです。この暑さでは、バーベキューをする気にもなりませんね。
そして、サマーキャンプ最初の目的地に到着します。月川荘キャンプ場は、川遊びをするには、もってこいのロケーションです。流れがゆっくりの場所もあるので、足が届かなくても、園長につかまって、楽しく遊ぶことができます。そして、岩からのジャンプは、子どもたちの勇気を引き出す絶好のポイントです。今日は、川の水量がやや多かったですね。この1週間まとまった雨がなければ、水量が下がって、楽しい川遊びができそうです。いつも、子どもたちが並んで記念写真を撮る橋の上に立って、下を流れる川を眺めます。今年の8人の園児たちは「怖~い!」と言わずに立っていられるか、想像していました。
小川げんきプラザまでの道のりを確認します。何度も通っている道ですが、サマーキャンプの2日間が、小川町の七夕祭りです。交通規制があるので、バイパス経由に変更します。
二日目のワークショップの場所は、東秩父村です。小川町の隣り村です。埼玉県でただ一つの「村」が、東秩父村です。ホワイトきゃんばすに登園していた保護者が、ここに移住をして、古民家をリフォームしたショップをオープンさせました。昨年のサマーキャンプから、ここでお世話になっています。
今週末は、子どもたちを連れて、いよいよサマーキャンプです。舞台は整いました。あとは、主演の子どもたちが、どんな演技を見せてくれるか・・・楽しみですね。
2024年
7月
20日
土
小学生・・・夏休みスタート
本日登園した小学生が、成績通知表を持ってきました。いつのまにか、保育園ホワイトきゃんばすに登園する小学生は、園長が頼んだわけでもないのに、通知表を持ってくるようになりました。今日は、2つの小学校の通知表を見ましたが、過去と比べると、各教科の評価がなされるだけで、担任のコメント欄もありませんでした。クラス全員分のコメントを書くことは、担任の仕事量を増やすことにつながるので、ここも「働き方改革」なのでしょうが、毎月「子どもたちの成長記」を書いているおやじ園長にとっては、何だか物足りなく思いました。
小学生時代の成績など、大人になってからの人生にさほど影響を与えないことを知ってる私たちの世代ですが、小学生にとっては、「絶対にC評価は、取りたくない!」と言っていたり、「俺が思っているのと、先生の評価が違うんだよな~」と、私に熱く語ったり、ただただ、わたしは「よく頑張ったなぁ~」と聞いているだけですが、子どもにとっては、親以外の大人に、何か言ってもらうのも大事なことのようです。
ということで、さいたま市内の小中学生は、昨日が終業式で、いよいよ、今日から夏休みです。小学校は、8月27日(火)までが夏休みです。この長い夏休み期間をどうやって過ごしていくか・・・親も大変です。(笑)
もちろん、夏休みの宿題はしっかりあります。ただし、かつてのように「こんなにたくさんあるの!?」という感じではなくて、「読書感想文」「工作」「書道」の中から1つ選択するような、子どもたちに選ばせるスタイルに変わってきているようです。
1か月以上ある夏休みです。理想は、子ども自身で夏休みの過ごし方を考えるのが、一番いいと思いますが、「自分で考えなさい!」と突き放しても、効果があるとは思えませんね。
やはり親が、少し考える必要がありそうです。夏しかない「花火大会」「盆踊り」などの地域のお祭りなどのスケジュールを子どもと共有して「行きたい!」と言わせたいですね。そして、夏休みだからこそ、「図書館で過ごす」新たなライフスタイルを身につけさせたいものです。最近では、おしゃれで、とても居心地がいい図書館が増えています。親も、子どもと一緒に、本と向き合ってみるのもいいですね。
そして、スポーツ&レジャー・・・これも、子どのリクエストの中から、現実的に実行できるプランを親子で考えるのです。
親は、少しだけ、子どもを誘導するものの、子どもが「自分で決めた!自分で考えた!」と思えることが、充実した夏休みにつながることは、間違いありません。今年の夏休みも、多くの卒園児が保育園にやってきます。1年生から5年生まで・・・話を聞くのが楽しみな、おやじ園長です。
2024年
7月
19日
金
最後の体操教室
いよいよ今日が最後の体操教室となってしまいました。近隣の大型ショッピングセンターに移設となり、子どもたちが、毎週金曜日に楽しみにしていた体操教室も終わりです。
現在小学校6年生になった卒園児が、年長の時に体操教室がスタートしました。週1回コースの授業料の半額で、寺子屋全員を指導していただくことで、契約をしました。通常、親が子どもを体操教室に通わせるには、送り迎えをしなければなりません。保育園の体操教室は、親が仕事をしている間に、保育園のプログラムとして行われているので、保護者からも大好評で、子どもたちも週に一度のお楽しみでした。
今でも忘れませんが、契約の商談時、体操教室を運営する会社の専務に、「ひょっとしたら、ホワイトきゃんばすの中から、将来のオリンピック選手が出るかもしれないですね」と言ったら、「絶対にありません!」と強く否定されてしまいました。「オリンピック代表になるには、毎日何時間も練習しているので・・・週○日の体操教室の役割は、体操が楽しくなることです」とのことでした。
その通り、子どもたちは、体操教室を通じて、楽しみながら、できなかったことができるようになっていきました。鉄棒を前にすると、恐怖心で泣き出してしまう園児が、練習を重ねる中で前回りを一人でできるようになったり、とび箱を前に、最後の勇気が湧いてこないで、失速していた園児が、ためらいもなく、とび箱を飛べるようになったり・・・
そんな子どもたちに、「挑戦する心」が育ったのも、体操教室のおかげです。
今まで、指導に関わった先生たちは、10人以上になります。中には、「○○君には、是非、通常の体操教室に入ってもらいたい」と、名指しでスカウトがあったり、現在の年長男子を「ビッグ4」と呼んでいただき、その運動能力を高く評価していただきました。踏み台をジャンプして、空中で前回りをするプログラムに、ビッグ4が挑戦させてもらったこともありました。
保育園ホワイトきゃんばすにとっても、「体操教室があります。ここでは○○をやっています」というのは、屋上の環境と共に、大きな付加価値になっていました。ホワイトきゃんばすのオリジナルユニホームを着て、子どもたちが躍動した6年間・・・体操教室に感謝の意を込めて、最後の日を子どもたちと楽しく過ごしました。
2024年
7月
18日
木
新たなお米需要
今日は、1週間ぶりのプール遊びです。ボランティアの保護者が3人も来ていただきました。子どもたちは、「○○くんのママだ!」「○○くんのパパだ!」と大騒ぎです。そして、サマーキャンプに行く年長園児は、ライフジャケットを着て水に浮く練習をしました。初めてライフジャケットを着る園児もいますので、今日は、「浮く」感覚を身につけます。
さて、今日は「パックごはん」の話です。パックごはんの歴史は浅く、1980年代後半に、当時の新潟県食品研究所で研究が始まったのが、最初だと言われています。そして、誰もが知る「サトウのごはん」が、サトウ食品から初めて商品化されました。1995年の阪神・淡路大震災以降、非常食品として急速に広まっていきました。
私も、最初は非常食品としての認識でした。でも今は違います。共働き世帯や一人暮らしの増加に伴って、料理に割く時間が減り、食事を手軽に済ませたい人が増えているようで、毎日の食卓に欠かせない存在になっているようです。俳優の吉沢亮さんが出演するアイリスオーヤマのテレビCMで「炊飯器売れなくなっても知りませんよ」と言っていますが、外国人など、炊飯器が家にない人にとっても、パックごはんは便利ですね。
農林水産省によると、国内の主食用米の収穫量は、2008年の865万トンから2023年には661万トンと、約3/4に減少しています。パンやパスタなど食の多様化が進んだことが主な要因ですが、今後も人口減少が続くなか、ますます国内需要は縮小していくことが予測されます。しかし、パックごはんは、同じ期間で9万トンから20万トンと2倍以上に増えています。
サトウ食品やアイリスオーヤマといった大手メーカーは、今年新たな製造ラインを稼働させているそうです。「パックごはん」の認識は、すぐに食べられる便利なごはんというイメージから、「おいしさ」を追求する競争が始まっているようです。最近では、北海道の「ゆめぴりか」、山形県の「つや姫」といった高価格帯のブランド米を使ったパックごはんや、減農薬・無農薬米を使ったものなど、付加価値を高めた商品作りになっています。
私は、パックごはんを買う習慣がないので、今までは、スルーしていましたが、今日は、じっくりと、パックごはんコーナーを見てみます。
2024年
7月
17日
水
歴史の学び方
今日は、気温も上がらず、ずっと曇りの天気予報だったので、早々に「プールお休み」を告知しました。朝は予報通りでしたが、子どもたちが屋上に行く時間には、うっすらと晴れ間が出ていました。朝の6時45分からプールに水を入れますので、急きょプールに変更とはいきません。プールボランティアを予定していたパパ2人も、子どもたちと屋上遊びをしていただきました。かけっこをしたり、ぐるぐる回されたり、子どもたちは、いつもと違う屋上遊びに大興奮です。
さて、最近は、様々な歴史番組が放映されています。私は大好きですので、よく見ています。例えば、NHKBSの「英雄たちの選択」では、史実ではなく、「もしあなたが、○○だったら、どんな選択をしますか?」という問いに、歴史に精通するゲスト陣が、自分の見解を述べながら選択する流れになっています。
皆さんが、中学高校時代の歴史の授業は、どんな授業でしたか。私の場合は、年号や出来事を暗記するイメージが残っていますね。テストでも、鎌倉幕府は、何年に開設されたか?のような、年号を答える問題もありました。
現在放映されている歴史番組の多くは、「○○年に△△が起きた」という紹介の域を超えて、「過去の歴史から、今現在、そして、これからの私たちの進むべき道を学ぶ」という、歴史的な出来事を様々な角度から考察する内容になっています。だから、面白いのです。
2022年度から、高校の必履修科目となったのが、「歴史総合」です。近現代の日本史と世界史を融合し、日本だけでなく世界との相互的な視野を学ぶ内容です。来年、2025年1月の大学入学共通テストで出題が始まります。
当然、高校現場の授業が、知識詰め込みからの脱却が求められます。ある高校の授業です。テーマは「穀物法廃止論争を考える」です。1830年代以降に英国で起きた、穀物の輸入を制限する法律「穀物法」を巡る存続派と廃止派の論争について、生徒たちが班に分かれて話し合います。「年号を覚えるのではなく、なぜ起きたのかを考えて」と教師は強調します。授業では、当時の風刺画や小麦の価格の変動グラフ、廃止派の決議文などの資料が用意され、生徒は教科書も参考にしながら意見を出し合います。
「この頃、東アジアでは何が起きていた?」と教師は、さらに問いかけます。生徒たちは、英国が自由貿易を推進していく中で、中国・清とのアヘン戦争(1840年~42年)が起きた経緯を確認。こうして、歴史的な背景や意義について繰り返し議論が進みます。
生徒の一人は、「歴史の勉強は暗記ばかりと思っていたけど、歴史が動く背景を知ると面白い。他の人と議論することで考えが深まる」と言います。こうして、歴史総合の授業は、教師の一方的な知識を教える授業ではなく、グループワークや教科書にない史料などを使い、知識の活用を促します。
どうですか・・・歴史の授業が楽しくなっていると思いませんか。私たち大人は、子どもたちに「歴史の勉強は、これから起きる未来において、どのような選択をすれば、解決することにつながるのか・・・を学ぶ大事な勉強なんだよ。だから、歴史上の人物に自分がなったつもりで考えてみようよ・・・」と、伝えることが大切ですね。
2024年
7月
16日
火
進化する イチゴ
連休明けの保育園・・・雨が降ったりやんだり、気温も低いのでプールはなしにして、屋上フリータイムです。ファームの野菜が、たくさん収穫できました。子どもたちは、インゲン豆をたらい一杯分収穫して、どや顔です。大中小のトマトに、ゴーヤ・キュウリ・白なす・ピーマン・オクラと、ちょっとした八百屋さんができるくらいです。しかし、カラスにきれいに食べられていたスイカ2つを発見。子どもたちの嘆き声が響きます。
さて、今日は「イチゴ」の話です。昨日訪れた南阿蘇鉄道の「見晴台駅」では、キリン午後の紅茶のCM撮影が行われ、上白石萌歌さんが、ホームでヘッドホーンで目をつぶって歌っていると、列車に気がつかないで乗り過ごすシーンが有名です。今、熊本県産のイチゴを使った「イチゴティー」を限定販売していて、見晴台駅の自販機は、すべて午後の紅茶イチゴになっています。
関東に住んでいる人にとっては、熊本産のイチゴ?というイメージですが、全国の収穫量では、栃木県・福岡県に次いで3位となっています。国連食糧農業機関(FAO)によると、2022年の世界のイチゴの生産量は957万トンで、中国が335万トンで最も多く、日本は16万トンで11位です。えっ!そんなに低いの?と思った方が多いと思います。中国などは、ジャムなど加工に回る量が多く、生食での消費量は、日本が世界一です。日本産のイチゴは、海外でも「甘くて香りがいい」と人気が高まり、23年の輸出実績は、10年前の20倍になっているそうです。香港や台湾では、富裕層向けに高額で販売されています。
日本の生産量は、世界11位にもかかわらず、イチゴの品種登録数は310種(6月末現在)で、世界の品種の半分以上になっています。つまり、生食で「おいしいイチゴ」を求めて、品種改良が毎年のように進んでいるとうわけです。埼玉県が誇る「あまりん」は、品評会では堂々の1位ですが、埼玉県のイチゴ生産量は、日本のベスト5にも入りません。つまり、量より質の戦略です。
好きな果物ランキング(6月マイボイスの調査)では、イチゴは72.1%の支持を集め、桃や梨を抑えてトップです。日本人の「イチゴ愛」は不動なのです。「イチゴは品種改良しやすく、値崩れせず値段も安定しているので新規参入しやすい。生き残りには、各産地のブランド戦略が試される」と専門家は語ります。
暑さに弱いイチゴも、安定栽培される工場のような完全管理での栽培も可能になってきました。そうなると、夏場は海外産の輸入に頼っていたのが、季節を問わず、日本のおいしいイチゴが食べられるようになるかもしれませんね。日本人の「イチゴ愛」をしばらくは、見守っていきましょう。
2024年
7月
15日
月
四国・九州 おやじ旅
昨日今日と、連休を利用して「おやじ旅」に行ってきました。中学・高校時代の同期・先輩・後輩6人のおやじ旅です。
日本地図を思い浮かべてください。昨日は、東京6:00「のぞみ1号」で岡山に朝9時過ぎに到着。瀬戸大橋を渡って、四国に入ります。坊ちゃん・道後温泉で有名な愛媛県松山へ。夜10時のフェリーで、今朝5時には、九州の小倉に着いていました。小倉から大分へ。大分からは、阿蘇のカルデラを横断し、熊本へ向かいます。1泊2日で、四国と九州にまで足を延ばしました。いつものように、こんなハチャメチャなおやじ旅を楽しんでいたのです。現在、阿蘇熊本空港でこのブログを書いています。
今日は、「おやじ旅」の中でも、2つのいい話を紹介します。1つ目は、四国松山駅から30分くらい離れた、伊予灘線の「下灘(しもなだ)駅」のボランティア夫婦の話です。「下灘駅」は、青春18きっぷのポスターに何度もなり、駅のホームのすぐ後ろが海というロケーションの有名な駅です。ベンチに恋人と後ろ向きに座って写真を撮るのが、定番になっています。そこに、ボランティアのシニア夫婦がいます。「私も旅が大好きで、色々なところで人々の世話になったので、自分が住むこの『下灘駅』を通して、恩返しをしたいと思っているんです」と言います。奥様も、到着する列車を降りるお客様の誘導や声掛けをしています。ここは、夕日が海に沈むので、絵に描いたようなローケーションなのです。たぶん違うと思いますが、あの「千と千尋の神隠し」で、千尋が海に沈む線路を歩くシーンのモデル駅とも言われています。
ガイドの男性は、下灘駅から見える島の解説をしてくれました。「決して人に話したらいけない!」と言われましたが、下灘駅から見える島が、日本テレビで放映されている「ダッシュ島」だそうです。(言ってしまった!)彼は、「こうして、ここに来てくれた人が喜んでくれれば、毎日おいしい酒が飲める」と微笑みます。そんな人生を送る二人がとても素敵に見えました。うらやましいですね。
2つ目は、本日訪れた、「南阿蘇鉄道」です。昨年、熊本地震から7年・・・ついに完全復旧したローカル線です。今日が、ちょうど全線開通1周年記念日でした。テレビでもよく放映される「トロッコ列車」にも乗りました。南阿蘇鉄道の素晴らしいところは、沿線住民の鉄道愛です。列車が通ると、必ず手を振ってくれるます。そして、多くの駅で、カフェやちょっとしたショップがあります。その店のオーナーが、駅のホームで、お客様を笑顔と、時にはギターを弾いて迎えてくれるのです。こんな気持ちがいい思いはなかなか経験できません。そして、車掌のトークが最高です。ずっと、楽しい話を続けてくれて、大満足の「南阿蘇鉄道」でした。地方のローカル線を支える地域住民の素敵な想いが伝わりました。
旅の思い出は、一生の想い出になります。これからも素敵な旅をしていきたいですね。では、今から羽田空港まで、旅の締めくくりです。
2024年
7月
14日
日
自動水栓蛇口の神様
今日は、自動水栓の蛇口の話です。保育園に入園したばかりの園児が、手洗い場で、蛇口に手をかざしたままじっとしていることがあります。そう、自動水栓に慣れてしまっているからです。JR東日本の新幹線内の自動水栓シェア100%・全世界の航空機シェアの25%・国内全コンビニの80%のシャアを誇る自動水栓の会社が、株式会社バイタルです。知る人ぞ知る会社です。驚くことに、世界で1種類しかない「ネコ専用自動水栓」もこの会社が作ってしまったようです。
今日は、そんなバイタルで職場の神様と呼ばれる「島田より子」さんの話です。彼女は、自動水栓デルマンシリーズの組みたて、検査、梱包、出荷作業を一手に担っています。普通は、男性の職人がイメージされますが、彼女は、あと2年で70歳になる大ベテランです。
「自動水栓の仕事には30年前から携わっていますが、最初は、仕事がなくて会社全体がどん底だった時もありました」と言います。機械化が進んだ製造ラインを想像しますが、基盤に電子部品を取り付けるはんだ付けや電動ドライバーでのビス留めなど、すべてを手作業で組み立てているそうです。
実績を重ね、累計出荷台数は50万台を突破します。コンビニ、新幹線、航空機などに導入され「日本人なら一度は使っている自動水栓」までになったのです。コロナ禍では需要が跳ね上がり、生産が追いつかないほど多忙な時期を経験します。
島田さんは、コンビニやレストランに入ると必ずトイレに行き、自動水栓の調子を確認してしまうそうです。「何年たっても大切に使ってもらっているのを見るとうれしくなる。まだまだ頑張って作らないと、という気持ちになります」と話します。
どうですか・・・みなさんが、自動水栓を使う時は、島田さんという女性が噛んでいることを思い出してください。
2024年
7月
13日
土
子どもの魚離れを防ぐ体験
今日は、久々の屋上プールではなく、普通の屋上遊びです。トマト・白なす・オクラ・インゲン豆・ゴーヤを収穫して、子どもたちのお土産にします。「おれ!ゴーヤがいい!」という小学3年男子・・・小学生になると、あの苦みのおいしさが分かるようです。ビールはダメですが・・・(笑)
さて、みなさんの食卓には、どのくらいの頻度で「魚」料理が並びますか。世代によっても変わってくるでしょう。我が家は、魚と肉がフィフティフィフティと言いたいところですが、わずかに肉が上回っていますね。そして、現代の子どもは、さらに魚を食べることが少なくなっているようです。
えっ?・・・保育園の子どもたちの話を聞くと、「○○寿司に行ってきたよ!」と回転ずしの名前がよく上がります。お寿司の形ならモグモグ食べます。骨を取ったり、箸を巧みに使うのは苦手なようです。中には、回転ずしに行っても、マグロなどの魚ではなく、ポテト・うどん・ラーメン・スイーツなど、寿司とは関係のないものを食べている実態もあるようです。
そんな中、「おさかなせんせい」と呼ばれる都内の飲食店を経営する北川浩太郎さんは、2022年から幼稚園や保育園で計100回以上「おさかな体験教室」を行っています。ある幼稚園では、イカに触れる体験をします。子どもたちは、発泡スチロール箱に入ったイカを触ります。「なんかぷよぷよするね」・・・そして、北川さんがイカをさばきながら、くちばしや内臓などの部位を説明します。そして、調理をしてみんなで食べます。
体験教室の後、子どもが魚に興味を持つ変化があったと答えた保護者は5割を超えるそうです。「子どもが魚好きになれば家庭でも魚料理を作る頻度が上がる」と、体験教室を行った幼稚園の園長は期待します。
魚介類の摂取量は、水産白書によると2019年データでは、1~6歳を除くと、15~19歳が1日43グラムと一番少ないそうです。まさに、若者の魚離れが加速しているようです。保育園でも、火曜日は「お魚給食の日」にしていますが、やはり給食全体での「おさかな構成比」は低いのが実態です。
そんな中で、福島県いわき市では、2020年に「魚食の推進に関する条例」を制定し、毎月7日を魚食の日として地元の魚介類の普及を図ります。小中学校の給食で、地元の魚を提供し、「学校で食べる魚はおいしい」と子どもたちには好評のようです。
「おさかなせんせい」体験のように「魚に触り、調理する体験を通して、楽しくおいしく味わうことが大切で、どのように漁獲され、食卓に届くのかを伝えることも魚への関心を持つきっかけになる」と専門家は語ります。
どちらにしろ、食肉と比べると、明らかに種類が多い魚類ですので、バランスよく子どもたちには食べてもらいたいですね。水族館に行くのも良し、角上魚類のような鮮魚店に連れて行って、魚をさばく姿を見せても良し、子どもたちのワクワクドキドキ体験が、キーワードですね。
2024年
7月
12日
金
自転車が倒れないための3つの力
今日は、ナイトツアーでホタル観賞の予定でしたが、あいにくの雨で中止としました。史上最大総勢75名が参加予定でしたので、残念がる子どもたちと保護者の声が広がります。今月中は、まだホタルが見られますので、ピークの夜8時に、ホタルエリアで楽しんでもらいたいですね。あらためて家族で北本自然観察公園に行くというコメントが、連絡ノートにありました。
さて、8月いっぱいの屋上遊びは「プール遊び」が中心となります。子どもたちは、泳ぎも水遊びも合わせて楽しんでもらいますが、「自転車が倒れないで進むのはなぜ?」という記事を目にしてしまいました。
保育園ホワイトきゃんばすの子どもたちの特徴の一つが、「小学生になる前に自転車に乗れるようになる」です。実は、ここ数年、年少園児が3月末までには、全員が乗れるようになっていますので、寺子屋園児全員クリアが続いています。そして、現在小学2年生の男の子が記録した、2歳8か月という自転車最年少記録は、いまだに破られていません。
子どもたちは、自転車をスイスイ走らせる先輩たちに影響を受け、先生たちの個々の能力に合わせた指導法で、自転車に乗れるようになります。ただし、一度「自転車に乗れるようになりたい!」と宣言した園児には、技術論よりも精神論で乗れるようにしているのが現実です。
そんなやり方ですので、一度、冷静に自転車が倒れない科学的根拠を確認したいと思います。まずは、補助輪がないのに、どうして前に進むのか。どうやら、3つの力が伝わって進むようになるようです。
1つは、ペダルをこいで、自転車を前に動かそうとする力が働きます。2つ目は、地球に引っ張られる力、つまり重力が下向きに働きます。3つ目は、曲がる時に車輪が真ん中ら外へ押し出される横の力が働きます。つまり、同時に「前と下と横」の三方向に力が加わるので、バランスが保たれて倒れないのです。
重力の力に負けない、右左に曲がっても、それを支える前に進む力があれば、転ばないのです。要は、バランスをまっすぐに保ち、力強く、ペダルをこぐことができるようになれば、理論的には、自転車の乗れるようになるのです。
プールが終わって、自転車練習が始まると、精神論だけでなく、この理論で、冷静に子どもたちを「自転車クリア」に導きたいと思っています。
2024年
7月
11日
木
ガチャガチャは日本の文化!?
今日は、雨が降っていたのでプールは中止にして、教室内で体を動かしました。大玉送りを久しぶりにやってみます。2歳・3歳児には大きすぎたようです。そして、盛り上がるのが、「椅子取りゲーム」です。2回ともに、年長園児が優勝したのですが、3歳児の男の子が3位に入り大躍進です。
さて、現在年間3千万人超のペースで訪れるインバウンド観光客のお土産になる人気商品は何だと思いますか?そうです。カプセルトイこと、通称「ガチャガチャ」「ガチャポン」です。
ガチャガチャのインバウンド需要が高まったきっかけのひとつは、2016年に成田空港第2ターミナルの一角にカプセルベンダーをズラリと並べた専門コーナーの登場だそうです。空きスペースを使って何かできないかと、ガチャガチャが並んだのです。考えた人は凄いですね。日本旅行を楽しみ、帰国する際に両替できない小銭の使い道としては、もってこいです。
現在のカプセルトイの中心価格は300円程度です。日本円は、今や世界有数の最弱通貨ですので、かさばらないカプセルトイは、何個でも買える最高の日本土産になるのです。「何が出てくるかわからない」というゲーム性があり、カプセルの中には、フィギアやミニチュア、スマホやバッグなどにつけられるアクセサリーやチャームなど、細かなディテールやデザイン性の高いもの・・・さらに、これでもか!というくらい豊富なキャラクター展開があって、手軽な日本土産になっているようです。
手軽などころか、完成度の高い芸術作品と言っても過言ではありませんね。日本のアニメやポケモン・サンリオなどの作品やキャラクターは、海外人気が高いこともあって、カプセルトイなら、そんなキャラクター商品が安価で大量に展開されてることが、SNSや動画サイトで外国人に、広く知れ渡っているようです。
ガチャガチャだけでなく、外国人には「トミカ」のミニカーも大人気だそうです。保育園の年長男子は、「トミカをもっともっとたくさん欲しい!」と七夕の短冊に書きましたが
、トミカショップには多くの外国人が訪れているそうです。
私が、子どもの頃から親しんだ「ガチャガチャ」は、今では、カプセルトイとして、世界に誇る文化となったのかもしれませんね。日本は、たかが300円だって、完成度が高い物しか市場に出さないという誇りも合わせて・・・立派な芸術文化なのです。
2024年
7月
10日
水
桑の実の話
今日も屋上プールでは、水分&ミネラル補給で、ミニトマトを食べます。子どもたちは、お代わりして「おいしい!」と食べるのですが、今年のトマトは、多くが虫に食べられています。まだ、青いうちに蛾がトマトに卵を産んで、幼虫がトマトに穴をあけて食べまくるのです。農薬を使っていないので、毎年虫の被害となるのですが、今年は、かなり多くて残念です。でも、トマトはたくさん植えているので、元気なトマトをいただきます。
さて、朝刊に「桑の実」の話がありました。保育園の子どもたちは「マルベリー食べるぞ!」と、屋上にある桑の木に登り、お猿さんのように桑の実のつまみ食いをし、桑の実が終わっても、プールが始まるまでは、木登りを楽しんでいました。
今日は、岩手県の里山に暮らす、安部智穂さんの話です。
「今年は庭の桑の実が鈴なりで大豊作です。桑の実は、雨が降るたびにみずみずしく膨らみ、太陽に照らされて黒々と色づき、半年ほどかけて徐々に熟していきます。私は、毎日夕方の1時間を充てています。
柔らかくて潰れやすいので、収穫にはコツがいります。まず、ザルを左手に持ち、枝の下に添えます。ギターの弦をはじくように、右手の指先で完熟した桑の実をポロポロとザルに落としていきます。水でさっと洗って、ザルに上げ、乾いた布をかけて半日おいてしっかり水気を切ります。
保存瓶に移し、あらかじめ氷砂糖を溶かしておいたウオッカをヒタヒタに注げば、3か月後には果実酒のできあがり。深紅に染まった赤ワインのような果実酒は、食前酒として楽しんでいます。
ウオッカを吸った桑の実は、パウンドケーキの具材にします。水気を切り薄力粉をふるいにかけ、ケーキの生地に混ぜ込みます。焼き上がったケーキは、しっとりとした生地と、ツブツブ、プチプチとした桑の実の食感がたまりません。ほんのりとした酸味が口の中に広がります。
おいしい桑の実を楽しみにしているのは、私たちだけではありません。野鳥や昆虫たち。時にはタヌキやキツネ。そして、夜にはクマも来ているようです。姿を見せることはありませんが、木の下に残された茶色の立派な置き土産がその訪問を教えてくれます。特に、桑の実が大好物なのはアナグマです。6月下旬ごろになると、桶職人をしている夫の作業場の床下にすみつき、日に何度も現れては落ちた桑の実をモグモグ・・・。
雨の季節にあでやかに熟す桑の実は、たくさんの生命を楽しませ、育みます。今年もみんなで分け合って、いただきます!」
どうですか・・・こんな暮らしに、とても憧れる私です。
2024年
7月
09日
火
ゲーム 尊い命
昨夜は、北本自然観察公園に行き、ホタルの下見に行ってきました。ホタルゾーンに入ったばかりは、ホタルがチラホラと光を放っているだけですが、奥に行けば行くほど、幻想的な風景になっていきます。手をかざすと、私の手にホタルが止まりました。12日のナイトツアーも雨さえ降らなければ、多くのホタルが期待できそうです。そして、光ると言えば、今日の寺子屋では、「ヤコウタケ」という光るキノコを観察しました。年長男の子のママが持ってきてくれました。テントの中で教室を暗くして観察します。緑色に光るキノコに子どもたちは不思議顔で言葉を失います。私は、このキノコを小笠原諸島の父島で見たことがありました。小笠原では、「グリーンペペ」と呼ばれています。
さて、話題を変えて、今日は命の話です。戦争も長期化すると、ニュース映像に慣れてしまい、どこか人ごとのように感じている人も多いのではないでしょうか。今は、人が人に暴力を振る事件が常態化していること。そして、そのニュースを自分ごととして捉えることが難しいですね。
そんな時に、遊んでもらいたいゲームがあります。「尊い命」です。このゲームは、プレーヤーが拷問者となって、少女に拷問するとう内容です。プレーヤーは、少女を「つねる」「おどす」「ビンタ」で、肉体的・精神的に追い詰める一方で、「休けい」「やさしくする」で回復させられます。このアメとムチを使い分けながら少女を手なずけ、尋問をして情報を聞き出していきます。ただし、尋問の過程で体力をゼロにしてしまうと、「尊い命」が亡くなるのです。
一方で、ある要件をクリアすると少女を「逃がす」ことができます。でも、このゲームの目的は「逃がす」こととは明示されていません。要は、プレーヤーがどう受け止めるかで、ゲームの意味が変わってくるのです。ちなみに、少女を逃がすと、少女は最後に拷問者であるプレーヤーに笑顔を見せてくれるそうです。これを見て、何か良いことをした気分になる人も多いようですが、そこには、「都合の良い思い込み」があり、なぜ、拷問されるのが「少女」なのか、拷問者の性別によって、内容が変わるのか?などを考えると、単純なゲームですが、様々な思考が膨らみます。私もやってみましたが、何度やっても、少女を逃がすことができず、笑顔を見ることはできませんでした。
私たちは、暴力=悪という価値観の下に生きていますが、実際には暴力も戦争も絶えることはありません。このゲームは、自らの内なる暴力性を自覚するためのものでもあるようです。なかなか深いですね。
2024年
7月
08日
月
言葉の美しさ
今日のように、朝の天気予報で、「今年一番の暑さになる予定です」と言われると、覚悟ができるのですが、とにかく毎日暑いですね。そして、夕立が半端ない状況です。ここ数年の当たり前の出来事かもしれないですが、子どもたちは、今日も元気にプール遊びです。ファームで収穫した、トマトとキュウリを食べながら、子どもたちは、ミネラル吸収で、熱中症対策です。
さて、すでに真夏の天気で、梅雨らしくありませんが、まだ明けてはいません。雨が降ると、子どもたちは外遊びができないし、保育園ではプールに入れなくなってしまいます。でも、日本には、雨を表す美しい言葉が多くあります。
緑雨(りょくう)・・・青々とした新緑に降り注ぐ雨
紅雨(こうう)・・・春に咲いた花に降る雨
白雨(はくう)・・・夏の明るい空から降ってくる雨
黒雨(こくう)・・・空が真っ黒になるような大雨
そして、春雨・夕立・時雨などは、季語にもなっていますね。季節の移ろいを、日本の言葉の美しさと共に味わうことができますね。
ある小学校の先生の話です。雨の日に、教室で勉強をしていると「先生、雨がポツンポツンになってきた」「えーポトンポトンだよ」「でもさっきはザーザーだったよね」と、子どもたちから雨の音がたくさん出てきたのです。「せっかくだから、みんなで雨の音を聞こう!」という展開になり、かっぱと傘と雨靴を履いて、校庭に行くことになりました。
「先生、見て見て!雨粒が鉄棒にぶらさがっている!」
「雨粒も逆立ちを頑張っているんじゃないかな」
「なんだか光っていてきれいだね」
「水たまりに傘が映っている」
「水たまりに入ると面白いよ」
などなど、子どもたちの発見は止まりません。
どうですか・・・素敵な授業ですね。机上の学習をたまには、放り投げて、外に飛び出して、言葉遊びをするのもいいですね。子どもたちの心に残る授業になることでしょう。
2024年
7月
07日
日
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
昨日は、おやじ3人で大宮にある昭和レトロな店で飲んでいました。元会社の先輩で、私以外の二人は、今年61歳になって定年退職後、嘱託社員として同じ会社で働いています。65歳までは嘱託社員、75歳まではアルバイトで働き続けることができます。契約は1年ですので、自分都合でいつでも「や~めた!」とも言えるし、会社から「もういらない!」と言われる可能性もあります。
これからは、日本の多くの企業で、こんな働き方が当たり前の時代になっていきます。というか、すでになっています。年齢を重ねても、「お前が必要だ!」と周りが思ってくれれば、やりがいは持続できます。どちらにしろ、自分のモチベーションを維持していくために、どんな仕事をしていくか・・・そんなことを考える年齢でもありますね。
さて、仕事が忙しいサラリーマンのあなたは、最近、ゆっくりと本を読んでいますか。働いていると、読書に限らず音楽や絵画などに触れる文化的生活と日々の生活を両立させるのが難しいですね。私も、読む本といえば、教育や保育に関わる本、このブログで紹介するような内容の本ばかりで、ここ何年も「純愛小説」は読んでいません。(笑)
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の著者である三宅さんは、明治以降の労働と読書傾向を追いながら、日本の働き方変遷を語ります。「明治、大正時代は、読書はエリート層が教養を得るための手段で、戦前から戦後になると中産階級がエリートに続けとばかりに読書に親しみ、オイルショック以降は読書は娯楽になります。バブル崩壊は、本よりスマホからの情報が優先されるようになった」と言います。
「スマホは今自分に必要な情報をだけを提供してくれますが、小説などの本は自分に関係のない情報(ノイズ)が多分に含まれている。実は、そのノイズこそが知識や教養なのに、毎日働いている生活ではそれを受けとめる余裕がなくなる」と続けます。
これからの働き方は、全身全霊で仕事に身を捧げるのはいい加減やめた方がどうか。と作者の三宅さんは提案します。すでに、「全身全霊で仕事なんてやってないよ」という若者は多いかもしれませんが、仕事、家庭、趣味にそれぞれの居場所を作る生活が、自分の人生を豊かにすることは、間違いないようです。
仕事に疲れたら、酒を飲むのもいいですが、たまには本を読みたいものですね。
2024年
7月
06日
土
道端のカタバミ
あまりにも暑さに、土曜日ですがプールを楽しみました。水着がない小学生も、洋服のまま泳いでいます。ファームのキュウリに塩を振って、子どもたちはモグモグと食べています。このシンプルな食べ方で、熱中症対策にもなっています。(笑)
さて、今日は、文科省科学技術・学術政策研究所から「ナイスステップな研究者」に選ばれた千葉大学准教授の深野さんの話です。
みなさん、カタバミという野草をご存じですか。クローバーに似た葉で、黄色のかわいらしい花を咲かせます。しかし、繁殖力がとても強い厄介な雑草でもあります。花が終わり種になると、パッと周りに種が飛び散り、様々な場所で繁殖が始まります。もっとやっかいなことは、根がどんどん広がって、多年草なので、一年を通じて広がっていきます。花は、黄色のかわいい形状ですが、保育園のファームでも、このカタバミがすぐに広がっていきます。
深野さんは、コロナ禍に近所を散歩中に、葉の色が赤くなったカタバミを見つけます。野外調査を始めると、都市部の宅地付近のカタバミは赤く、そこから数十メートル離れ、暑さが和らぐ公園のカタバミは緑色です。わずかな距離の違いでも葉色が変わっていたことで、「都市の高温が影響しているのかも?」とひらめいたそうです。研究の結果、赤い色素は、都市の高温からカタバミが受ける熱ストレスを和らげているいる可能性があることをつきとめます。
深野さんは、日本のモンシロチョウは、羽の特徴に雌雄で差があるが、欧州などではそれがないことは、まさに千年単位で生じたもの言います。また、直物や昆虫だけでなく、人間心理も進化の視点から研究をしています。現代人が虫嫌いになった理由について、進化心理学の視点で迫ったものです。
「虫嫌いを増やしたのは、都市化によって虫を見る場所が室内に移ったことや、虫の種類を区別できなくなったため」と、13,000人を対象にした調査の結果から仮説を提唱します。
これは、保育園の子どもたちを見ていると納得できますね。屋上で見る虫には、大きな嫌悪感は抱きませんが、教室内で虫を発見した時の「ギャー!」という叫び声は止まりません。外で虫を見る習慣が少なくなれば、子どもたちが虫嫌いになっていくのは、間違いありません。
深野さんの研究は、私たちが気がつかないような視点で行われています。これからも、彼の取り組みに注目したいですね。
2024年
7月
05日
金
子どものスポーツクライミング
いよいよ渋沢栄一の新一万円札など、新紙幣が発行されました。保育園ママの一人が、銀行に勤務しているので、早々に新紙幣を両替してもらいました。朝の会で、子どもたちに、立体感覚の新紙幣を見せます。年長園児は、数字は読めますので、これは10,000円5,000円1000円と言い当てます。さすがに、「埼玉県深谷市出身の渋沢栄一」さんの名前は出てきませんが、新紙幣に興味津々でした。
さて、子どものスポーツクライミングの世界が、どんどん広がっているようです。東京都港区は、すべての公立の小学校と幼稚園にボルダリング設備を設置したそうです。港区の小学校では、休み時間になると、ボルダリング壁のマットの前に大勢の児童が列を作ります。壁は高さ4メートル幅5メートルです。ホールドの色や形状、大きさはさまざまで、ホールドを自由に使って登るのは比較的簡単ですが、色分けされた一部のホールドだけを使って登ろうとすると難易度が高くなるそうです。
「頭を使わないと登れない。ホールドをどう持てば体を押し上げられるのか、考えて登っている」と小3女子が言います。挑戦を繰り返しているうちに、自然に考える癖がつくそうで、保護者の評判は上々です。
東京オリンピックで、日本人選手がメダルを獲得する姿を見ていると、スゴイ握力があるから登れると思いがちですが、握力だけでなく、全身を使うスポーツであることが分かります。「バランス感覚や柔軟性も養われる。壁をどう攻略すればいいか、思考力も鍛えられる」と専門家は言います。
スポーツクライミングは、体操教室やスイミングスクールと同じで体力の向上につながりますが、頭を使って手順を考えないとゴールにたどり着けないので、何度もの失敗を乗り越えてやり遂げたときに大きな達成感が得られます。「体を使ったチェス」とも呼ばれているそうです。
全国でもクライミングジムの数は、どんどん増え続けているそうです。そして、子どもたちにとっては、もう一つの魅力は、手を伸ばせば「世界」につながる競技ということです。野球やサッカー、バスケでは競技人口も多くて競合が激しいですが、スポーツクライミングはまだまだこれからの競技です。
どうですか・・・あなたのお子様の習い事の候補になるのでは。
2024年
7月
04日
木
小学生が政党をつくり模擬選挙
今日も屋上はプール日和です。今年は、水を怖がる園児がほとんどいなくて、ボランティアの保護者も、そんな子どもたちと本気で楽しんでいます。ボランティアスケジュールもほとんど埋まってきました。何度もボランティアに参加してくれるパパもいます。
さて、東京都江東区の小学校で面白い取り組みが行われました。6年生がクラスの枠組みを超えて、子ども中心になっていない身の回りの問題を考え、同じ考えを持つ子どもたちで政党を結成。そして、カリキュラムの最後に行われる「子どもまんなか総選挙」に向けての活動です。
昨年4月の施行された「子ども基本法」に使われている「こどもまんなか」という言葉に注目して、この取り組みがスタートしたようです。クラスの枠を超えて、政党を結成するという考えは、6年生の担任の話し合いで決まったそうです。
では、どんな政党が名乗りを上げたかというと・・・
「イベン党」・・・イベントを増やして明るい江東区に!イベントを通じて経験を豊富に!何と関係者は、ほとんどボランティアなので、お金がかからない!
「こどもハッピー党」・・・子どもたちの暮らしを大切にします。子どもたちのためのスペースづくりを行う。生活を充実させる工夫を実践する。
「健康精進党」・・・健康的で安全な生活を!!運動不足の解消対策。ミストシャワーを設置します。
「NO!ストレスの会」・・・いいめがない学校にします!
こんな感じで、3クラスを解体し、11の政党が生まれました。子どもたちは話し合いを重ね、互いに歩み寄るような姿も多く見られたようです。総選挙は、体育館で行われ、子どもたち・教員・地域の人・保護者が見守る中、「ぜひ、わが党に一票を!」というプレゼンが行われたのです。
これは、小学生でありながら、まさに「キャリア教育」と言えますね。チームで話し合う点は、非認知能力がぐんぐん成長したことでしょう。「最後までやり抜く」ことができた、子どもたちは、大きく成長したことは間違いありませんね。
こんな素敵な取り組みが、広がっていけばうれしいです。
2024年
7月
03日
水
「みんなちがって、みんないい」の子どもへの説明
今日から、屋上プールには、プールボランティアのパパやママにも一緒に頑張っていただきます。ミッションは、ずぶ濡れになって、子どもたちと遊ぶことです。6歳男の子のパパが、本日のターゲットです。「予想以上に子どもたちの暴れっぷりは激しかったです」と言っていました。でも、思う存分楽しめたようです。
さて、私も大好きな、詩人金子みすゞさんの「みんなちがって、みんないい」という言葉があります。人間は、みんな違っていて、個性という大切な特徴を持っていて違っているのが当たり前で、違っていても悪くないし、恥ずかしいことでもなく、みんなが大切な存在です。そして、同じようなタイプの集まりよりも、違うタイプの集まりの中から、大きな発見や、解決策が生まれるのです。という意味です。
ただし、保育園の子どもたちに、「みんな違っていてもいいんだよ~」を説得力ある言いかたで伝えるには、なかなか難しいですね。そこで、いい例えを見つけました。そのまま引用します。
「みんなは、焼き肉を食べたことがありますか。焼き肉は好きですか。あの焼き肉のおいしいタレは、にんにく、ショウガ、唐辛子、こしょう、砂糖、蜂蜜、みりん、ごま油、しょうゆ、レモン汁などを混ぜ合わせて作ります。甘いものや辛い物、酸っぱいものが混ざっておいしくなるのだそうです。人間も同じで、いろいろな違う人が一緒に力を合わせるから楽しいのです」
これなら、子どもにも分かり易いですね。そして、「人と違うことを笑ったり、同じもの同士でかたまって、人をからかって、バカにして笑う人間だけにはならないでください。世界の違う文化や風習を楽しみ、素敵だと思える心が、世界を歩んでいける人になるのです」
どうですか・・・我が子に話しをしてみませんか。
2024年
7月
02日
火
令和6年度プール開き
今日は、待ちに待ったプール開きです。昨日から、プールの配置などいろいろレイアウト作りをしていました。今年のプールは6つあります。①大きいプール②スライダープール③ファインディングニモプール④ジャブジャブプール⑤屋根付きプール⑥ペンギンプールです。これにベビー用のたらいプールも用意しました。ニモプールとペンギンプールは、保護者からいただきました。屋上にある、自転車・ストライダー・三輪車の多くも保護者からの贈り物です。ありがたいですね。
子どもたちが、屋上に到着すると、お日様が出てきました。きちんと準備体操をして、「ゆっくりプールに入るんだよ~」と先生が言うものの、年長男子は、次々に大きいプールにダイブして水しぶきを上げます。「おいおい・・・」ですが、子どもたちの勢いは止められません。
大きいプールは、年長園児が中心になって遊んでいますが、スイミングスクールに通い始めた2歳児が、年長園児たちと同じように、カッパのごとく泳いでいます。スゴイ光景です。
もちろん、ニモプール・ペンギンプールでまったりと過ごす子もいます。園児それぞれが、自分に合ったプール遊びを初日から見つけたようです。でも、子どもたちが一番楽しんでいたのは、水鉄砲での戦いごっこです。「お友だちが、やめて!」と言ったら、やらないという、シンプルなルールですが、誰一人「やめて!」とは言いません。一番若い先生が、子どもたちのターゲットにされていました。びっしょりです。
明日からは、プールボランティアのパパママが参加していただきます。壮絶な水かけ合戦が、例年繰り広げますので、子どもたちは、手ぐすねを引いて待っています。また、ボランティアの保護者にとっても、我が子がいつも遊んでいる園児と直接かかわることで、より深く保育園を感じてもらうことができます。
さて、プール初日にはしゃぎ過ぎた子どもたちは・・・お昼寝タイムでは、午後3時の終了時間になっても、なかなか起きてきません。しっかり遊んで、たっぷり寝る・・・子どもたちの規則正しい生活です。(笑)
8月末まで、屋上プールでどんな物語が生まれるか・・・期待しましょう!
2024年
7月
01日
月
長岡大花火
今日は、6人の園児が体調不良でお休みです。手足口病が3人です。明日からのプールを前に、子どもたちが早く元気に登園できるよう祈ります。そして、本日入園手続きにいらした保護者が凄かったです。入園に関して持ち物等の説明を主任がするのですが、紙にメモは取りません。すべて、スマホに瞬時に打ち込んでいくのです。昭和のおやじには、まったくついていけませんね。(笑)
さて、日本3大花火の一つに数えられる、新潟県長岡市の花火大会を見たことがありますか。私は、サラリーマン時代に、新潟県を担当したことがあり、今は閉店してなくなってしまった「大和(だいわ)百貨店長岡店」の食品課長とビール片手に楽しみました。「一生に一度は行きたい」と言われる花火大会ですが、まさにその言葉通りのスケールです。
信濃川の河川敷で見たのですが、打ち上げの場所が近いこともあって、まさに頭上に大きな尺玉の花火が上がるのです。そのまま火の粉が自分の頭に落ちてきそうです。2023年の長岡花火大会を20台以上のカメラで迫った圧巻のドキュメント映画「長岡大花火 打ち上げ、開始でございます」が、公開されました。
毎年8月2、3日の2日間で打ち上げられる花火には、空襲や新潟県中越地震など数々の苦難の歴史と、「復興」や「平和」の思いが込められています。平原綾香さんのJupiterにのせて、今までとは違うスケールの花火に、誰もが度肝を抜かれました。音楽と花火のコラボレーションが見事なのです。
この映画の坂上監督は、「花火って一瞬で消えてしまうなかに、どこか自分のこれまでを
振り返らせるようなところがあると僕は感じている。世界中のどんな人の心も動かすエモーショナルさがあり、国境を超えると感じます。その美しさと迫力をぜひ劇場で楽しんでください」と言います。
確かに、映画館のスクリーンで見たら、長岡大花火の迫力が伝わってくるでしょうね。この映画を見てから、本物の長岡花火大会に行きたいものです。今年は、金曜日・土曜日と最高の曜日まわりです。
今日から、7月に入りました。各地の花火大会は、コロナ前の規模に戻りつつあります。みなさんは、どこの花火大会に出かけますか。
2024年
6月
30日
日
やり投げ 北口棒花
笑顔というのは、本当にまわりを明るくさせてくれますね。保育園の園児の中にも、笑顔が素敵な子はたくさんいます。そんな、笑顔と実力で、パリオリンピック陸上やり投げの日本代表選手が、北口棒花(はるか)さんです。
昨年8月の世界陸上では最終6投目で66m73をマークして逆転優勝。女子フィールド種目では日本人初の金メダル獲得となりました。今シーズンも好調が続いています。北口さんは、今年3月に広告会社が発表した「アスリートイメージ評価調査」では、総合ランキングで大谷翔平に次ぐ2位。「親しみやすい」アスリートでは1位に輝きました。野球やバスケットボールならともかく、やり投げのようなマイナー種目では異例です。「笑い声が耳に残って覚えてくださっていて、笑うとバレるので、一緒にいるみんなに『笑うな』って言われます」と本人コメントです。
北口選手の自己ベストは67m38ですが、「ぶっちゃけていうと、私練習では55m飛べてまあまあいいラインなんですよ。で、本番では65mとか投げるタイプなんで。やっている自分も、予想できない試合に臨んで、投げてやっとわかることが多いんです」と言います。これは、単純に「本番に強い」ではなく、「練習で飛ばないのはめちゃくちゃ考えて投げているからです。気をつけたい所が10個あったら練習では10個全部考えながら投げるけど、試合ではそれを2、3個に減らす。その分、迷いなく全力で投げられるんです」と言います。
北口選手は、小さい頃から陸上をやっていたわけではありません。小学生ではバトミントンで全国大会で団体優勝をしています。あのバトミントン五輪代表の山口茜さんと対戦したこともあるそうです。中学時代には水泳に打ち込み、全国大会に出場します。
高校に入学して陸上部に入ります。やり投げを始めてわずか2か月で北海道大会を制覇し、2年生の時に、全国大会で優勝するのです。北口選手は、小さい頃から試合をしてきたおかげで、どういう気持ちで試合に臨むといいのかとか、どういう準備をすべきかというのがわかって取り組めているといいます。
先日、アメリカのスポーツデータ分析を行う会社が、パリオリンピックでの日本の金メダル予想を12個としましたが、その1つは、女子陸上やり投げの北口選手です。今年から栄養士に食事管理をお願いしているそうで、練習拠点のチェコでは、小麦の料理が多く、シチューやカレーなど重めなので、日本のご飯を中心にした食事を取っているそうです。
さぁ~パリ五輪では、注目の選手の一人として、期待しましょう。
2024年
6月
29日
土
いじめるのは「しずかちゃん」
子どものネットいじめが、過去最多を更新したそうです。2022年度のデータでは、いじめ全体の約3.5%が「ネットいじめ」と、まだ割合は低いように感じますが、5年前の2倍になり、過去最多となったのです。LINEでの仲間外しや無視などの陰湿な内容です。
今日は、小学校5年の卒園児が登園したので、小学生でのネット問題について聞いてみました。すでに、クラスの半分以上が「マイスマホ」を持っています。彼が友だちとのコミュニケーションで利用しているのは、LINEです。しかし、彼のクラスでは、ネットいじめは、まったくないと言います。彼は、何かあればすぐに「声をあげる」ことができる性格なので、彼の周りでは、陰湿ないじめが起こりにくいのでしょう。
現実は、親が家事などで忙しい時に、子どもにYouTubeなどの動画を見せていることもぱり、すでに2歳でネット利用率60%です。この環境なので、小学生にはスマホを持たせない・・・というのは、土台無理な話ですね。塾や習い事での安全確認で子どもにスマホを持たせることもありますね。
いじめも時代の流れで変化をしていて、今では、かつての、ドラえもんのジャイアンのようなガキ大将タイプではなく、しずかちゃんのような清楚な優等生がいじめの主犯だそうです。ネット時代では、ジャイアンのように暴力を振るえばそれを動画に撮られて拡散され、逆にいじめられます。しずかちゃんが、LINEなどを駆使し、いじめの頂点に立っているというわけです。
ある心理学者は、ねっといじめが起きる背景をこう言います。「ネットいじめは、手段として直接手を下すわけでも相手の苦しむ顔を見るわけでもありません。しかも、子どもたちはSNSでの投稿に慣れているので、いつもの投稿の延長のように、匿名でできるため、罪悪感を抱きにくい」「学校という集団の中で、子どもたちはメンバーが固定されている。子どもたちの社会は、村社会のように流動性が低く、このメンバーが嫌だと思ってもすぐに変えることができない。こうした集団では強い同調圧が働き、誰かが誰かをいじめていても『ノー』と言えず、放置してしまう仕組みが生まれる」の2つをあげます。
それでは、子どもたちをネットいじめから守るにはどうすればいいのか。1つは、大人が子どもの居場所を多角化し、いじめを見つけた時はいじめた理由を絶対に肯定しないことが重要と言います。子どもは、学校以外に居場所があれば、集団内のメンバーに嫌われても『ノー』と言うことができます。そして、いじめの本質はスケープゴートなので、いじめに関わった子どもは、いじめた理由を正当化しようとしますが、何であろうと肯定してはいけないのです。
昔からですが、いじめを受けた子どもは、親も含め誰にも相談できないことが多いです。最近では、いじめ相談アプリもあるそうです。匿名で学校の外で相談することができます。
そして、私のPTAの経験上、いじめをなくす手段として効果的なのが、校長先生や担任の先生が「うちの学校にはいじめがあります」「うちのクラスでは、今いじめが起きています」と全員の前で話をすることです。「大人が目を光らせているぞ!」は、私たち大人の役割として大切なのです。
2024年
6月
28日
金
一歩先を行く中学入試問題
今日はかなり強い雨が降りました。屋上は、湖のようになっています。そこで、とび箱やマットを出してきて、教室内で体操教室です。とび箱が盛り上がります。当然、年長と年少の比較や、個人の運動能力の差があります。全身筋肉でできているかのようなバネを持つ5歳男の子は、まるで体操選手のような高い跳躍を見せます。しかし、最初は飛べない園児も飛び方の基本を教えるだけで、格段に上手になります。こんなところからも、「基本が大切」というのが、よくわかりますね。
さて、今日は中学入試問題の話です。中学入試というと、膨大な知識を身につけて問題に対峙するというイメージが強いですが、それは、過去のことになりつつあるようです。過去問題集を出版する「声の教育者」の後藤さんは、「2015年あたりから記述が増えたり、設問数を減らして、考える時間を増やしたりするなど、思考力を問う問題が増加しました」と話します。
では、具体的にどんな問題が出されているか、興味がありますね。
慶應中学校の問題です。解答用紙には、キリンとパンダの絵があります。問題は、「キリンの模様・パンダの模様を描きなさい」です。普段よく目にしているようで意外と覚えていないものが問題になりました。「受験勉強ばかりでなく、いろいろなことに興味を持って観察して欲しいという学校からのメッセージが込められています」と後藤さんは言います。
2021年に、センター試験に代わって、大学入学共通テストが導入されました。問題文に会話が引用されて長文になり、グラフや表などの資料が付記され、読解力や思考力が重視されるようになりましたが、実は、中学入試は大学入試が変わる前から、難関中学を中心に読解力、思考力が試される問題が出題されているようです。
では、もう一問・・・開成中学校の国語の問題です。問題は、カニ弁当を売り切った営業社員と、売り残した営業社員について販売部長が社長に報告する場面の描写から始まります。「新宿支店の大西社員は、販売用に500個のカニ弁当を発注し、池袋支店の小池社員は450個のカニ弁当を発注しました。最終的には、新宿支店の大西社員は500個完売しますが、池袋支店の小池社員は、20個の売れ残りを発生させてしまいました。この問題には、午前9時の開店から午後19時の閉店までの売れ行き総数のグラフが示されています」
販売部長の報告を聞いた社長は、売り切った大西社員よりも売れ残した小池社員を評価しました。ここで問題です。「大西社員より小池社員の方を高く評価した社長の考えはどのように考えられるでしょうか。『たしかに』『しかし』『一方』『したがって』の4つの言葉を使って説明しなさい」
どうですか・・・中学入試の問題ですよ。大人でも、難しい問題です。ポイントは、販売総数のグラフを見ると、大西販売員は、閉店前の18時にすでに500個完売させていたのです。
このヒントで、ピンときましたね。大人の私の答えは、「大西販売員は、たしかに500個完売させました。しかし、小池社員は430個しか販売できなかったことになります。一方、グラフを見ると大西販売員は、18時には完売してしまったので、閉店前の1時間に商品があれば、さらに売上が取れたことになります。したがって、大西販売員は、発注見込みが甘く、販売チャンスロスを発生させてしまったのです。最後まで、完売を目指して頑張った小池販売員の方が、評価が高いと言えます」
こんな答えを中学受験をする小学校6年生が答えるなんて、私の想像の範疇を超えています。しかし、このような問題を解くには、知識の詰め込みだけではできないことだけは、間違いないです。これからの若者には、「考える力」がますます問われるということです。私たち大人も、子どもに考えさせるアプローチが大切ですね。
2024年
6月
27日
木
心を鍛える
今日は、「どろんこ遊び」の日です。どろんこ広場を田植え前のように、ドロドロにします。気持ちいい!と感じるか、気持ち悪い!と感じるかは子ども次第ですが、今年は、大いに盛り上がり大成功です。年長男子4人が、泥水に顔からダイブします。それを見ていた他の園児に「楽しい!」が伝わり、見事に全員が泥だらけになりました。7月からプールが始まりますが、このメンバーなら、プール時間が楽しく盛り上がりそうです。
さて、もうすぐ、パリオリンピック・パラリンピックが開催されます。あるオリンピック選手のコーチの話を聞いてください。「体力や技術を高めることはもちろん必要だが、それ以上に心を鍛えることが大切だ。行動は、すべて気持ちに支えられている」と言います。
身体と精神のバランスが大事であることは、私たちも漠然と認識してるところですが、心を鍛えるには、具体的にどのようにすればいいのか・・・具体論が知りたいですね。
そのコーチは「それは、あいさつをすること、返事をすること、履物をそろえることの3つです」と、たった3つのことが大事だと言います。
なんだか、当たり前のことに思えますね。あいさつや返事をすることの大切さは何となく分かるのですが、履物をそろえることとはどういうことだと思いますか。「はきものをそろえると、心もそろう」「ぬぐときにそろえておくと、はくときに心がみだれない」のだそうです。何げない動作に人の心は鍛えられていくのですね。
「心を鍛える」を考えると何か大きな努力をしなければいけないと思いがちですが、まずは、3つの当たり前のことを当たり前にすることが大切です。子どもには、教えやすい内容ですね。
2024年
6月
26日
水
北風と太陽
昨年夏に飼育していたカブトムシが卵を産み、幼虫として越冬し、サナギから、ついに成虫になりました。今日は、オスが1匹とメス2匹を観察しました。子どもたちは、「俺が捕まえる!」とやる気になっていたのですが、カブトムシの足は爪が強くて痛いので、思わず手を放してしまいます。今シーズン初カブトムシです。
さて、今日は、子どもが不登校になったある母親の話です。
子どもに「学校へ行かなくてもいいよ」と言える親はどのくらいいるだろうか。私の場合、自分の価値観や過去の経験上、その選択肢はなかった。息子が小6の時に学校に行き渋った。でも、私は何としても行かせようとした。この行為は、息子にとって断崖絶壁から突き落とされることだったに違いない。当時の私は「休んだら行きづらくなるし、勉強が分からないとますますやばい」と思い、毎朝「起きて!学校に間に合わないよ?お母さんは会社に行かなければいけないんだけど!」と息子を引きずり出し、小学校の先生方と一緒になって、あの手この手で何とか登校させた。私は「北風と太陽」の北風で、旅人の息子を凍えさせるばかりだった。旅人が求めていたのは北風ではなく「安心して旅に出れる暖かい太陽」だった。息子は旅に出る意欲を失い、反抗することもなく、殻に閉じこもってしまった。旅をする意味も、まだ見ぬ新しい世界への興味さえも失ってしまった。
この話のように、結局、引きこもりになってしまった息子でしたが、母親は、フリースクールという場所があることを知り、息子は、中学時代のほぼすべてをフリースクールで過ごし、現在は不登校になることなく、高校に通っているそうです。
皆さんも、よくご存じの「北風と太陽」の童話では、太陽が絶対的な正解であり、北風のような対応をとるべきではないとされています。この母親の場合も、北風の対応を取ってしまったがために、我が子が引きこもりになってしまったのです。
でも、我が子に対する、アメとムチのバランスが、それぞれの親子で違うように、北風の対応をした方が、子どもの成長につながることもありますね。太陽が100%正解とは、私は思っていません。
それゆえに、子育ては難しいのですが、北風の厳しさの中にも、愛情を持つ母親を私は知っていますし、太陽の優しさが、甘やかしにつながって、がまんができない子どもになってしまうこともあるでしょう。時と場合で、北風と太陽を使い分ける必要だってありますね。
ということで、今日は、北風ばかり悪者扱いしないで!という話でした。
2024年
6月
25日
火
「納得解」を見つける
今日の寺子屋では、久々に「しりとり探検」をしました。お店で売っている商品をしりとりをしながら探していく、探検ゲームです。メガネ→ねんど→ドーナツ→ツナ→なす→すいか→貝まで進み、答えた園児が、売場を探しますが、なかなか見つからないときは、みんなで協力して「あそこじゃないの?」と探します。そして、貝→イチゴと答え、みんなでイチゴ売場に向かいました。しかし、そこには桃が並んでいて、イチゴは売っていませんでした。すると、年長男子が「イチゴはしゅんじゃないから、もう売ってないんだよ」と言ったのです。旬という言葉を知っているなんて、スゴイ!
さて、ここで問題です。「友だちから手紙が届きました。ところが、切手が不足していたため、足りない料金を自分が支払うことになりました。皆さんなら、足りない料金を自分が支払ったことを、手紙を出した友だちに話しますか。それとも話しませんか」
次の問題です。「逆に、自分が出した手紙の不足分の料金を、友だちが支払ったとします。そのことを自分に話してほしいですか。それとも話してほしくないですか」
答えは、それぞれ半分ずつにはなりませんでした。自分が料金の不足分を支払ったときには「話さない」けど、友だちが不足分を支払ったときには、自分に「話してほしい」と答えた人が多かったのです。私も、同じでした。
でも、それって、おかしいですね。このように、たとえ同じ問題であっても、立場を変えると考えが変わってしまうことが、この世の中にはたくさんあります。今回の問題は、正解がない問題です。私たちは、これからの人生の中で「原子力発電」「死刑制度」「クローン問題」「脳死・臓器移植」といった問題をどう考えたらいいか、いずれも正解はありません。
しかし、そのときに大切なことは、自分が知っているわずかな情報だけで判断しないことです。自分とは違う考えの人の立場で情報を集め、公平な目で比べる必要があります。よく、「相手の立場になって考えなさい」というアドバイスがありますね。
こうして、人によって考え方が違うのは当たり前のことですが、同じ人でも、その時に置かれている立場によって「答え」は変化し続けるものです。最近よく聞かれる言葉に「納得解」があります。正解がない問題があっても、いたずらに対立することなく、自分が納得できる「納得解」を共に見つけようとすることが、これからの世の中には必要なのかもしれません。
ひょっとしたら、戦争のない平和な世界は、それぞれ立場が違う国が「納得解」を見つけ合うことかもしれませんね。
2024年
6月
24日
月
70歳までどう働くか
今日は、サマーキャンプ2日目に行う、着物の端切れを使ったワークショップの打ち合わせをしました。東秩父村で起業した、ホワイトきゃんばすの元保護者に来ていただきました。今年度は、埼玉県内の中学校3校で、起業についての講演を行うそうです。2年生・3年生を相手に、どんな話をするか、今から構想を練っているとのこと。「中学生相手に起業の話なんか、早いんじゃないの?」と思ったあなた。子どもたちが、社会に出てどんな仕事をするのか…その中に、「起業して自分で会社をおこす」という選択肢だってありますね。何より、子どもたちが、自分の将来に夢を持ってもらうには、熱い起業家の話は、持ってこいと言えます。
さて、合計特殊出生率が過去最低と報道されてから、少子高齢化をどうする?という議論が高まっています。0.99と初めて1を割った東京都の知事選でも公約の大きな柱として掲げられています。しかし、ここ1~2年の短期間で、少子化が解消されるわけではありません。反対に高齢化問題については、労働人口が減っていくのが分かっているので、「元気なうちは働く」ことが当たり前になっていきます。そうです。これからは、70歳までどう働くかを考えないといけません。保育園のパパママは、まだ先の話ですが、親世代は、バッチリ当てはまります。
あのニトリは、7月から65歳迄の再雇用の上限年齢を70歳に引き上げます。給料も、定年前の最大9割を維持できるようにするそうです。社内からは、歓声があがったそうです。かつての日本は、「シニアなんて・・・」という雰囲気があふれ、「厄介者扱い」でしたが、今では、その経験を生かせると、重要な戦力として受け止められています。
国の調査では、2023年で「努力義務」と定める70歳までの就業機会確保措置をすでに実施済みの企業は29.7%と3割に迫っています。ある大手メーカーの資料には次のような趣旨の記述が並びます。「現在3%の60歳以上の従業員の比率が10年以内に17%に上昇する。60歳以上の人材の一層の戦力化を図る・・・」どうですか、企業は、シニア戦力を活用しないと生き残れなくなるのです。例えば、TOPPANホールディングスは、50歳以上の社員が全社員の31%を占めるので、この層が頑張らないと、会社も傾くというわけです。
今の若者は、終身雇用など全く考えていないでしょうが、現在50歳以上の昭和世代は、新卒で入社して約30年以上頑張ってきました。そして、ようやく一息つけると思ったら、あと20年が待っていた。という感じです。その20年をどう働いていけばいいのか。
色々な考えがあります。50代前半のキャリアとそれ以降は「別の物」と考え、どこかの段階で一度ポストオフし、その後は仕事の負荷を下げながらプレーヤーとして働き続けるイメージが私の中では、しっくりします。もちろん、ずっと同じ会社にいる必要はありません。50歳まで転職したことがない社歴は、決して誇らしいことではなく、「辞めて他の道を選ぶ自由」だってあることを忘れてはいけませんね。
かつて、お荷物のシニアが、「そんな給料じゃ働かないよ!」と言えるような時代になってきたのです。体が元気に動く限り、自分の価値は、いつまでも高くありたいものですね。あなたがすでに50歳を超えているならば、70歳までどう働くかを考える必要がありますね。
2024年
6月
23日
日
おやさいクレヨン
関東地方もようやく梅雨入りし、今日は朝から雨が降っています。保育園ホワイトきゃんばすが入るショッピングセンターの4階に、新たにオープンした屋内大型遊園地は、日曜日の雨ですので、大盛況になります。客数が800人を超えるそうです。
さて、「おやさいクレヨン」をご存じですか。10色で、税込み2200円です。値段以上の付加価値を感じる人が、買い求める商品の一つですね。ちなみに、10色は、「りんご」「赤ビーツ」「むらさきいも」「日本藍」「たけすみ」「ほうれんそう」「ねぎ」「パプリカ」「にんじん」「ごぼう」から作られています。どうですか・・・興味がわいてきましたか。
このうちの、「にんじん」「ほうれんそう」「ごぼう」は、埼玉県産の野菜が使われています。形が悪い、傷がついているなどの理由で廃棄されるはずだった野菜が、「アストラフードプラン」という会社の「残りかす」を粉末化する機器を使い原料となります。実際に「おやさいクレヨン」を製造する「mizuiro(みずいろ)」は、国産の米ぬかから採れる「米油」や「ライスワックス」をベースに、本物の野菜の粉末を原材料にして「おやさいクレヨン」を作っています。もちろん、野菜だけの色素だけでは薄いので、顔料も使用していますが、通常のクレヨンで使われる量の1/3以下に抑えられています。この顔料は、食品に使われているものを使用しているので、子どもが誤って口に入れても安心なのです。
保育園的には、子どもたちと「おやさいクレヨン」を使うとしたら、色々なことが想定できます。まずは、野菜の勉強になりますね。「屋上で作っている野菜からでもクレヨンができるかなぁ~」なんて、会話がはずみます。そして、「捨てられるはずだった野菜」がクレヨンに生まれ変わった話は、どのように子どもたちに伝えることができるか。子どもたちがよく知っている言葉に「もったいない」があるので、そこにつながります。普通のクレヨンとの描き比べだってできますね。そして、野菜が苦手な子どもが、野菜が食べられるようになるのは難しいかもしれませんが、野菜への興味を持ってもらうきっかけにはなります。
りんごクレヨンで、リンゴの絵を描く・・・パプリカクレヨンで、黄色のパプリカを描くのも楽しそうですね。クレヨンが、どのようにできるかなんて、普段子どもたちは考えませんが、「おやさいクレヨン」であれば、勉強にもなりますね。
大人が興味を持つクレヨンかもしれません。
2024年
6月
22日
土
いのちの電話 相談員不足
今日の園長課外授業は、さいたま市見沼区の市民の森にある「リスの家」に行ってきました。小1の卒園児2人と年長園児2人は、シマリスが放し飼いされている空間で、それは大興奮です。ここには、約100匹のシマリスがいます。飼育員さんが用意するひまわりの種などを主食としますが、リスの家の中にある「ザクロ」や「ビワ」などの果物も食べます。バッタやカマキリなどの昆虫だって食べてしまいます。シマリスは、10月から4月まで冬眠をしますので、今は活動期です。
さて、今日は「いのちの電話」の話です。深い悩みを抱える人たちの心に、主に電話でのやりとりを通じて寄り添う「いのちの電話」で、相談員の不足が全国的に課題になっているそうです。
「千葉いのちの電話」では、相談員の養成講座の開講式で、今年度は定員40人で募ったところ、受講者は15人だけです。「ロールプレイング」などを通して、傾聴の技術を来年3月まで学びます。ここでは、無償ボランティアの相談員が5交代制で24時間、電話の声に耳を傾けます。2023年度は、「生きるのがつらい」「職場でいじめを受けている」など、約1万8480件の相談が寄せられたそうです。自殺をほのめかす人もあり、相談員は相手が電話を切るまで3~4時間、対応することもあるそうです。
どうですか・・・大変な仕事であることが、あらためて理解できます。こんな大変な仕事にもかかわらず、「電話口で相手が落ち着いた」と言ってくれるなど、気持ちが通じ合ったと思えた時にやりがいを感じると、ある相談員は話します。
相談員になる人たちの動機は様々です。定年後に社会貢献したいという人や、知人や芸能人の自死などを受講のきっかけに挙げる人もいます。ただし、相談員の高齢化が進み、全相談員の4割を70歳代が占めるそうです。毎年、15~20人が辞めていくそうです。
全国的にも同じ傾向で、平均すると10年前よりも2割少ない人数で対応しているそうです。「茨城いのちの電話」では、電話相談の手不足をカバーしようと、SNSでも相談を受けているそうです。文字だけなので、声の調子がわからないので、「はい」「ええ」などの相づちの言葉を頻繁に打ち込むといった工夫が必要で、特別な相談員が担当してるそうです。
悩みを抱える人は、誰かに相談することで、その悩みが少なくなったり、やわらいだりすると言います。そんな相手となってくれる全国の相談人の皆様には、本当に頭が下がる思いです。
2024年
6月
21日
金
赤ちゃんが泣きやむ音
今日は、雨になってしまいましたが、体操教室の日なので、寺子屋園児は、しっかりと体を動かします。飛び箱の上から、ジャンプをしながら、投げたボールをキャッチするプログラムに挑戦しました。ボールを高く上げると、子どもたちは、ジャンプをするのですが、ジャンプとボールを取るタイミングを合わせるのが、かなり難しかったようです。せっかちな園児は、ボールを上げるのと同時にジャンプするので、タイミングが全く合いません。ちゃんと、ボールを取れた園児は、わずかでした。
さて、今日は、「赤ちゃんが泣きやむ音」の研究を20年も続けている、日本音響研究所の鈴木所長の話です。この研究所は、音にまつわる事件や事故で、音響解析や声紋鑑定を行います。1980年代以降は、音から情報が得られることが広まりました。その後、防音などに精通するゼネコンや住宅メーカー、音響工学を研究する大学、そして科捜研など、音を解析する企業や機関からの依頼が増えます。
食品メーカーからは、おいしそうな「食音感」の共同研究や、テレビ局からは「幽霊が出ると言われるスポットの音を調査してほしい」などの変わった依頼もあるそうです。そんな中で、鈴木さんが20年来研究を続けているのが、「赤ちゃんが泣きやむ音」です。きっかけは、あるバラエティー番組からの依頼で「赤ちゃんが泣きやむCMの現象を調査して欲しい」だったそうです。そして、わかったことは、赤ちゃんにとって聞きやすい周波数があることです。その後、この放送を見た玩具メーカーから連絡があり、赤ちゃんが泣きやむおもちゃの開発につながったそうです。
私たちの日常生活の中に「音」がありますが、音に関して「当たり前」と思っていたことが、世間的にはあまり知られていないことが多いと鈴木さんは言います。「例えば、『人の気配』ってありますよね。これは、『音の反射』だと説明できます。たとえ見えなくても、後ろに人がいると感じる感覚は、科学的にも証明できます」と。
ちなみに、赤ちゃんが泣きやむ音は、「ビニール袋をくしゃくしゃにした時の音」「ドライヤーの音」「テレビの砂嵐の音(今のテレビではできないかな?)「掃除機の音」「換気扇の音」「ママの胎内の音」「食器洗いの音」などだそうです。もちろん、個人差があるでしょうが、お試しあれ。
2024年
6月
20日
木
女性の管理職
今日は、屋上ファームで「じゃがいも掘り」をしました。朝のお片付けタイムでは、いつもは10分かかる仕事が、6分で終わりました。じゃがいも掘りを楽しみたい気持ちがそうさせたようです。もちろん、「いつも、こうやりなさい!」なんて、ヤボなことは言いません。(笑)
そして、じゃがいも掘りです。今年は、大豊作です。土の中からゴロゴロとビックなじゃがいもが出てきます。あっという間に、収穫かご3杯がいっぱいになりました。寺子屋園児は、大きなじゃがいもを手にして、ニッコリ。チビちゃんたちは、土で手が汚れるので、ややためらいがちですが、覚悟を決めてがんばりました。じゃがいもは、とれたてよりも数日置いた方がおいしくなるので、来週のお土産です。
さて、今日は女性の管理職の話です。ジェンダー指数の低いといわれる日本ですが、多くの企業で、女性の管理職が増えてきました。しかし、女性管理職に話を聞くと、「責任が大きくなり、精神的な負担が大きい」「労働時間が長くなり、家庭との両立が困難」「これまで、会社には女性管理職がおらず、ロールモデルがいない」「経営トップが、女性登用の意義や必要な体制について十分理解していない」などの意見が挙がってきます。
何だか、デメリットだらけに見えますが、どうやら、そうでもないようです。ある女性は、足を運んだ社外の勉強会で、ジェンダーの専門家の女性から「自分が管理職になって変えていけばいい」とアドバイスを受け、「目から鱗が落ちた」そうです。
彼女は、同時期に課長になった女性の同僚と「このままじゃ、まずいよね」と、育休後に復職しても、しばらくたつと辞めていくケースが多い女性が多いことを問題視します。男性経営陣は「みんな、いろいろ事情があるからね」と楽観的で危機感がありません。そこで、数の力を求めて、慎重に社内根回しをしながら「女性活躍推進プロジェクト」を立ち上げたのです。社外のダイバーシティ勉強会にも顔を出し、様々な企業の参加者から話を聞きます。こうして、制度を作り、社内環境や風土を変えていきます。今では後輩たちに「管理職に就いた方が楽だよ」と伝えているそうです。以前は、自分の目標達成だけしか頭になかったが、今は、視点も目標軸も変わった。「さらに上のポジションを目指してもいいかも」と思うようになったそうです。
実は、こんなデータがあります。管理職経験のある女性に自らの経験について聞いたところ、7割近くが「人生経験としてプラスになった。管理職になって初めて見えてきたことがある」と答えたそうです。
今から10年以上前なら、「女性の管理職が少ないのは、世の中の流れからすると問題」と判断して、意図的に女性を管理職に登用する企業も多かったと思います。ところが、現在は、男女問わず、実力で管理職になるのが当たり前ですね。女性の比重が高くなったのは、女性の能力がもともと男性に劣るものではなかったからです。
家事や子育てなど、当然夫婦が協力するのが当たり前の世の中になってきたとはいえ、出産に伴う女性の負担は大きいです。現実は、女性で管理職に就きたいと思う人は8.6%だそうです。まだまだですね。
年下の上司は当たり前の世の中ですが、年下の女性の上司が、今後さらに増えていくことは間違いありません。管理職は、あくまでも、仕事上の役割です。年上だろうが年下であろうが、男でも女でも、自分の組織を活性化させるのが仕事です。謙虚に、自分の能力を最大限に活かしてほしいですね。
2024年
6月
19日
水
高校の共学化問題
教室内のピアノの上に、七夕飾りが完成しました。寺子屋園児は、それぞれ短冊に願い事が書かれています。3人の園児は、自分で文字を書いていました。それぞれ、子どもたちが自分で考えた願い事ですので、大切な内容ですが、いくつか紹介します。「お金持ちになりたい」「野球選手になりたい」「お花の妖精になりたい」・・・どうですか、妖精以外は、努力次第で、本当になれますね。
さて、今埼玉県では、県立高校の共学化問題が起きています。発端は、県民から寄せられた1件の苦情です。「埼玉県の男子校が女子の入学を拒んでいるのは不適切で、認められるべきだ」とう内容です。具体的には、浦和高校に入学して、東京大学を目指したいのに、女子では入学できないという内容です。これを受けて、県の第三者機関である「男女共同参画苦情処理委員会」は、「早期の共学化」を勧告しました。埼玉県教育委員会は、8月末までに、委員会への報告を求められているのです。もちろん、県立の男子高、女子高の役割や歴史的背景を考えると、どちらかというと、共学化反対の意見の方が多いようです。
全国には、私立の男子高・女子高はたくさんあります。私も男子高出身です。ところが、県立(公立)で、男女が分かれる高校は、埼玉県の12校を筆頭に、群馬県・栃木県・千葉県・鹿児島県の5県だけだそうです。東京の都立高校で男女別学はありません。
第三者機関は、「共学化すれば男女共同参画が進む」という考えですが、これには、私も?ですね。別学でも共学でも、本当に求められるのは、ジャンダーの「公平さ」です。男女が同じ教室にいても、そこに不平等が存在すれば公正ではないし、男女が一緒に過ごすことを生かしたジェンダー教育がなされていなければ「共学」は形だけで、「異性観を学ぶ」ことにはつながりません。当たり前ですが、要は学校がどんな教育方針でジェンダー問題と向き合うかが重要なのです。「男女を分けること自体が差別」という単純な考え方なら、全国の私立高校も共学にしなければいけませんね。
男子高を卒業した私も、女子高を卒業した私の長女も、別学という環境の中で、ジェンダー問題を軽視したことはありません。私の昭和時代は、少し怪しいところはありますが。
「高校生が、やがて大人になり社会に出れば、会社などの組織は、男女で構成されているんだから、学校だって男女共学がいいんじゃない」という意見もありますが、高校生活では、自分が社会に出ることをイメージできる教育は必要ですが、社会の縮図である必要はありません。別学でも、十分に社会に出る自分をイメージできます。
また、共学の方が「性差」をより意識する機会が多いので、将来の役に立つという考えもあります。これなど、大きなお世話で、共学の環境があるがゆえに、自分が「女である、男である」を常に過剰に意識させられる弊害も考えられます。男だから、女だからは、これからの時代には、無くなっていくことです。
埼玉県民の私は、今回のクレームに対応するには、「浦和高校(男子校)と浦和一女(女子校)」や「川越高校(男子校)と川越女子(女子校)」を合併して、東大などの難関大学への合格率が高い高校を作れば、解決できると考えますが、これも愚策ですね。
公立校、私立校問わず、共学校・男子校・女子校など、様々な学校があって、それを選ぶのが、子どもたち自身と保護者です。当然、選ばれる高校になるために、ジャンダー問題だけでなく、様々な教育方針が共感される高校になればいいだけの問題です。現在、私が住む埼玉県で起きている「男女共学問題」・・・ちょっと待った!ですね。
2024年
6月
18日
火
「エレキソルト」スプーン
今日は、まとまった雨が降りました。屋上ファームの野菜にとっては恵みの雨です。明日は元気に満ちた野菜たちを見られそうです。そろそろ、トマトの収穫ができるかもしれません。
そして、今日の寺子屋では、「お尻ずもう」をやってみました。これは、ただお尻の圧力が強い子が勝つとは限りません。タイミングをずらして、一気に攻める知能派園児が優勝しました。予想以上の大盛り上がりです。
さて、私は、健康診断の結果が出ると、医者から色々な苦言を呈されるのですが、その1つに「塩分を控えめでお願いします」があります。このセリフを医者に言われた人は、世の中に多くいることでしょう。
スーパーの棚には、「減塩」と書かれた商品が、あらゆる分野で目につきます。50%減塩しょうゆに20%減塩みそなど、厳密に味を比較したことはないですが、まずいとか、薄味と感じることはあまりないように思います。それでも、ときに物足りなさを感じて、塩を足したくなることもあります。これでは、減塩の意味がありませんね。
40%減塩をうたったレトルトカレーは、素材の味は感じられ、ルーだけ口に運ぶとおいしい。でも、ごはんと一緒にがつがつ食べるには、もっと濃い味があってほしいと感じるようです。ネットのレビューには「塩を振って食べるとうまい!」と書かれていたり。これも本末転倒です。(笑)
これらを解決する、画期的な商品が「エレキソルト」とうスプーンです。塩味の元となるナトリウムイオンは食品中に分散しています。それが舌に触れることで私たちは塩味を感じます。エレキソフトは微弱な電流でイオンの動きをコントロールし、多くのイオンが舌に触れるように調整するのだといいます。実証実験では、減塩食の塩味が、1.5倍程度増強されるとの結果が出たそうです。
どうですか、食塩の取りすぎは解決しつつ、今まで通りの「おいしい食事のある人生」が継続できるという画期的な魔法のスプーンですね。ただし、初回分の予約抽選販売は終了しているようで、6月中旬からハンズ新宿店などで限定販売されるそうです。値段は、1本1万9000円(税込み)です。これを高いと思うか、生涯の健康を考えれば、安い投資と考えるか・・・あなた次第です。
どうやら、エレキソルトは、味をしょっぱくするというよりは、味が際立つスプーンとなるようです。興味のある人は、1万9000円でお試しあれ。
2024年
6月
17日
月
身近なところで「生物多様性」を知る
昨夜は、さいたま市西区内の「栄(さかえ)小学校」で、ホタルの鑑賞会がありました。私がPTAに関わっていた15年前から、「栄小のホタル」は、知る人ぞ知る名物でした。今でも、「西区ホタルと田んぼの会」がメインで、継続的に行われています。保育園でも4家族がホタルを観にいったそうです。栄小学校のホタルは「ヘイケボタル」です。
幼虫時代は、校舎の中にある水槽で、エサのタニシをたっぷり食べて大きくなり、サナギになる前に、「ホタルのお宿」に移されます。ここで、サナギになり成虫になります。ホタルは、幼虫の時から光るので、5月には、すでにホタルのお宿はピカピカしていたそうです。
自然の中で生きるヘイケボタルは、7月に入ってから成虫になるのですが、栄小学校のホタルは、エサをたっぷり食べているので、成長が早いようです。昨日は564名の来場者があったそうです。私も、ホタルを観るまで1時間待ちでした。ざっと、5匹のホタルが舞っていました。
ホタルと言えば、保育園ホワイトきゃんばすで、毎年行っている「ナイトツアー」は、北本自然観察公園のホタルを鑑賞します。今年は、7月12日(金)を予定しています。昨年は、ざっと500匹のホタルがホタルゾーンを舞い、まるでイルミネーションのようでした。栄小学校のホタルは地域の人たちの協力で行われている素晴らしい取り組みですが、蛍の光では、北本の500匹にはかないませんね。
今日は、そんな北本自然観察公園での生物多様性について学びます。昨年の秋から冬にかけて、枯れたナラの木のうち、倒木や落枝の危険性が高い木を伐採・剪定したそうです。伐採した木の多くは「コナラ」という落葉広葉樹です。ちなみに、カブトムシやクワガタが蜜を求めてやってくる木の1つです。コナラの木を伐採するだけで、公園内の生物多様性に変化が現れます。
冬から春先には、枯れ枝から昆虫などを探して食べる「アカゲラ」が、例年よりも多く確認されます。逆に、コナラを食草とするアカシジミやミズイロオナガシジミといった、シジミチョウが、例年現れる5月中旬を過ぎても、今のところ見つかっていません。伐採で日当たりがよくなった場所では、希少なヤマユリが増えたそうです。ナラ枯れによる伐採の影響で、生き物たちのバランスが変化しているのです。公園スタッフは、今後、夏から秋、冬に向けて、雑木林の木陰の減少や景観の変化、搬出できなかった伐採木の残置などの問題が、生物多様性にどのように影響するのか、引き続き見守り、管理していくそうです。
私たちは、日常の生活の中で、「ここに新しいマンションが建った」とか「ここにあったパン屋さん、無くなってしまったね」などの経験をします。でも、人として生きていくには、そんな大きな変化にはつながりません。生死につながる大問題には決してなりませんね。
ところが、自然環境の中では、コナラの木が伐採されるだけで、生物多様性に影響が出てくるのです。私たち人間は、これまで、あまりにも無関心だったのかもしれません。しかし、自然の景色がかわるだけで、動植物にどんな影響があるのか、考えることはできますね。「自然を大切にしよう!」とうスローガンを掲げるのは、簡単なことですが、その深い理由まで、私たちは考える必要があるのです。
2024年
6月
16日
日
失敗を楽しむ脳
今日は父の日ですね。保育園の子どもたちは、冷蔵庫に貼るマグネットをパパにプレゼントしました。もちろんパパの似顔絵があります。母の日と色違いの同じプレゼントです。私にも、娘から日本酒が届きました。もう25歳の立派な社会人の娘からのプレゼントですが、ニンマリと嬉しさをかみしめる父親です。ただし、母の日と比較すると父の日は現実的には、とても寂しいです。母の日の市場規模は1200億円あるのに、父の日は、その半分の600億円しかありません。数字だけなら、父への愛情は、母の半分です。(笑)
この現実は、父親の子どもへのかかわり方と比例しているのかもしれませんね。令和の時代は、父親も育児休暇をとり、家事をこなすのも当たり前になってきているので、何とか、母の日の80%くらいにまで、市場規模が大きくなることを祈りたいです。(笑)
さて、そんな父親ですが、子どもに対して、よく言うこと一つに「失敗を恐れないで、新しいことにどんどん挑戦しなさい」があります。みなさんも言ったことがありますね。私も、保育園の子どもたちに何度も言っています。
最近の子どもたちは、ネット社会が普及し、調べればすぐに答えが分かる時代に生きています。そうなると、失敗する経験は以前よりも少なっているのでしょう。生成AIが、さらに発展すれば、あらゆることについて、AIにアドバイスを求めてしまう社会になるのかもしれません。
脳科学の研究者である、量子科学技術研究開発機構の山田真希子グループリーダーは、脳科学の観点から「失敗や逆境がある時こそ、成功した時により強い幸福感が生まれる」と話します。逆に、失敗を過度に恐れる人の脳では、不安や抑うつに関わる前頭葉の脳機能ネットワークの働きが弱いことなどを明らかにしてきました。
そもそも、日本でベンチャーが少ないのも、失敗への恐れが強いからだといわれています。米国の起業家は、3つ4つの起業の失敗経験を勲章のように誇り、次の挑戦に目を輝かせるといいます。「失敗するのは当たり前。逆に失敗しないと成功はない」という考えです。
あの物理学者「アルバート・アインシュタイン」は、「チャンスは苦境の中にある」との明言を残しました。AIが人間の領域へ侵入しつつある中、人が生きる実感を感じるには、失敗を楽しむ脳が大切になりそうですね。そんな、脳になる訓練方法が現在開発中とのことです。
私たちは、子どもたちへ「失敗を恐れるな!」の言葉に、もう少し具体的なメッセージを考えて、「失敗を楽しむ脳」になってもらいたいですね。
2024年
6月
15日
土
こうばしい日々
今日の園長の課外授業は、「川越氷川神社」のお参りです。風鈴ロードが目的でしたが、本格的に風鈴が飾られるのは、7月7日以降とのこと。しかし、風車と風鈴を見ることができました。そして、一番の出来事は結婚式が行われていたことです。神前式ですので、花嫁さんが白むくでした。子どもたちは、ウエディングドレスはよく見ることがあっても、白むくに感動していました。「白くてきれいだね」とそのまんまの感想です。(笑)
さて、子どもたちにとって、「学校の大人たち」が魅力的であれば、とても居心地がいい場所に変わっていきますね。今日は、江國香織さんの「こうばしい日々」という小説を紹介します。
日本で生まれて、ほどなく家族でアメリカに移った少年「ダイ」の日常を描いています。11歳のダイの学校には、とても魅力的な「学校の大人たち」がいました。学校のランチルームで働く年配の女性や、担任の先生、校長先生・・・誰一人も「黙って指導に従いなさい」「子どもにはわからないだろうけど・・・」と言う大人は一人もいません。共通点は、子どもを見下さず、フラットに語る姿勢です。子どもだからと、適当にごまかさずに、本質的なことを自分の言葉で語る人たちです。
友だちと、取っ組み合いのけんかをしたダイに、「はでにやったそうじゃない」と、笑顔を向け下校を見送る校長。担任の先生は、「1つのことを、初めから知っている人もいるし、途中で気がつく人もいる。最後までわからない人もいるのよ。タイミングって、とても個人的なものなの。だから、誰にも必ず、今だ!っていうタイミングが来るからね」と言います。
ここは、日本の学校ではありません。アメリカの学校っていいなぁ~と思う人もいるかもしれませんが、日本にだって、「学校っていいな」と思える場所は、たくさんあります。そして、そこには、間違いなく魅力的な大人たちがいるのです。
学校だけではありませんね。あなたが、子どもと関わる時に、魅力的な大人でありたいものです。子どもを見下さないことや、フラットに接することも大事ですが、私たちが、子どもたちに胸を張れる「自分スタイル」で生活していることが大事ですね。
2024年
6月
14日
金
なぜ勉強するのか?
昨日は、屋上プールの空気チェックをしたのですが、小学生含めて4人きょうだいの園児のおうちでは、長さ3メートルのプールを2つ並べて遊ぶそうです。飛び込みも水かけも何でもありのプール遊びになるようです。保育園のプールは、7月に入ってスタートしますが、小学校では、すでにプール開きとなっています。さいたま市内の小学校の中には、プール授業を外部委託し、近隣の室内プールで年間を通じて行っている学校が増えてきました。学校プールの老朽化も理由の一つですが、水泳指導は、命にかかわる専門性が高い内容なので、プロに任せよう!というのが、一番の理由ですね。
さて、今日は究極の問いを考えます。「なぜ勉強するのか?」です。子どもから問われたら、親のあなたは何と答えますか。「大人になって困らないため」「夢をかなえるため」といった抽象的な答えが浮かびますね。でも、この答えでは、子どもたちの勉強は進まないかもしれません。(笑)
先日の「おかしの学校」では、ロッテの「パイの実」の製造工程を勉強しました。子どもたちには、「おかしの学校で勉強したんで、おうちでパイの実を食べる時に、このパイは、64回も折りたたんであるとか、チョコレートは注射器のような機械で、パイが焼きあがってから入れるんだよとか、麦芽糖のシャワーでカリカリになるんだよ。とか、ママパパに教えられるね」と話をしました。これも、勉強する具体的な理由の一つですね。
プロ棋士の藤井聡太さんなどの一流のプロは、将棋を打つ時に「自分はこう打つ」という正解が先に思い浮かび、その後に、どうして自分はそう考えたのかを確かめているそうです。私は、てっきり、相手の手を読みながら、先の手を考えていると思っていました。つまり、一流のプロ棋士には、私たちには見えない世界が将棋盤の中に見えているようです。医者もレントゲン写真から病気の正体を見つけ出します。医学を勉強した医者には、私たちには見えないものが見えているのです。
年長の男の子が、今夢中になっているのが、「理科ミラクル」という本です。ママがお風呂に入っていると、一人で本を読んで、ケラケラ笑っているようです。男の子は、決して、将来役に立つから「理科ミラクル」の本で勉強しているなんて、これっぽっちも思っていません。その瞬間を楽しくするために、豊かになるために取り組んでいるのです。
「なぜ勉強するのか?」には、正解がありません。子ども一人一人、年齢によっても、その答えは違ってきます。どうして?は分からなくても、面白くて楽しい勉強なら、子どもたちが一生懸命取り組むのは間違いなさそうです。子どもは、成長過程において、必ず「なぜ勉強するのか?」という疑問を持ちます。小学生になってからか、もっと小さい時かもしれません。そんな時に、親のあなたは、大人のあなたは、あなたが学校の先生なら、何て答えますか。正解がないので、「私はこう思う」をきちんと伝えられればいいと思います。
あなたの答えは何ですか。言えるようにしておいた方がいいかもしれませんね。
2024年
6月
13日
木
フリーランスという生き方
今日は健康診断です。「さぁみんな~今からパンツ一枚になって!」の言葉に、年長年中園児が、「わぁ~はずかしい!」と、大きく反応します。体操着に着替えたり、屋上遊びで汗いっぱいで着がえる時には、何のリアクションもないのに、みんなそろって、パンツ一枚を楽しんでいるようです。そして、先生の聴診器に泣き出す園児はゼロでした。小児科の先生の話では、現在、特定の病気の流行はないそうです。
さて、フリーランスの仕事をみなさんはどう思っていますか。「組織に属さない一匹狼でカッコイイ」と思っている人も多いようですが、そう誰でもできる仕事ではありません。
イラストレーターのTさんは、「なりたくてなったわけじゃなくて」と言います。大学を出て、普通の会社に就職するものの、人前で過度な緊張や不安に駆られる「社交不安障害」と診断されて、30歳で2度の退職を経験します。アルバイトを経て、職業訓練校と民間の養成学校でウエブデザインを学びます。3度目の就職を考えたそうですが、「また同じことを繰り返すかも・・・」という不安がぬぐえず、選んだのが、フリーランスの道でした。オンライン会議やメールが中心で、人付き合いが得意でないTさんには合っていました。それでも、イベントなどに顔を出しては、コツコツと人脈を広げ、仕事を増やしていったそうです。
定年退職を目前にフリーになったNさんは、34年勤めた会社でシステムエンジニアとして働いたそうです。人事部に異動した際にキャリアコンサルタントの資格を取得し、自分の経験を生かし、他人のキャリア形成の相談に乗る。これなら、一生できるのではと考えて、フリーのキャリアコンサルタントになったそうです。1か月に30~40人ほどの相談に応じ、シニアモデル、ウエブライターとしても活動しています。「自由な時間に、できることがたくさんあると気がつきました。会社員時代より忙しいかもしれない」と言います。
総務省は、2022年の就業構造基本調査で初めてフリーランスの実態を調べます。本業がフリーという人は209万人いたそうです。「地元で働きたい」「家族との時間を大切にしたい」など、個人の価値観が多様化していくと、フリーならそれをかなえられると考える人が増えているようです。
しかし、フリーランスは「ひとり」とうイメージが強いですが、実際は、冒頭の二人のように、交流会などに参加し、人脈を築く努力をしていました。ひとりでやるからこそ、余計につながりが重要な仕事ですね。
フリーランスに必要な資質として、①自己研さんを怠らない②他人を巻き込む力がある③セルフマネジメントができるの3つがあると言われています。どうですか、フリーランスで輝いて仕事をしている人は、これらの能力を磨いていかないと、満足な仕事が得られないようです。
そんな資質があるあなた・・・一つの選択肢として考えるのもいいですね。
2024年
6月
12日
水
サーモンは「取る魚」から「育てる魚」へ
今日の連絡ノートには、昨日の「おかしの学校」のコメントがいっぱいです。電車に初めて乗った園児が二人いました。新幹線と並行して走ったこともあり、「また乗りたい!」となったようです。今回は、日本を代表する大手菓子工場の見学ですので、機械化され、ラインを流れるように商品ができていく工程を見学しましたが、お菓子の世界は、パティシエやショコラティエによる手作りスイーツもあります。両方を学びながら、子どもたちの好奇心を伸ばしたいですね。
さて、子どもたちが大好きな「回転ずし」ですが、ネタの人気1位は13年連続で「サーモン」だそうです。マグロではありません。サーモンはただのネタだけでなく、あぶりやカルパッチョなどのアレンジが多様です。私の奥さまは、アボカドサーモンを必ず注文します。なんか、ヘルシーなイメージですね。(笑)
そんなサーモンですが、海水温の上昇による秋サケの不漁が何年も続いています。国内のサケの来遊数(日本の川に戻ってくるサケ)は、1996年の8879万匹をピークに減少し続け、2023年度は約4分の1の2785万匹にまで減少しています。これで、回転すしのネタが確保できるの?と思われるでしょうが、全国で養殖のサケ・マスが拡大しているのです。
国内のサーモン養殖は、約150年前にすでに始まっていました。つかみ取りでなじみのある「淡水のニジマス」が、全国で盛んになりました。そして、昨今のサーモン人気を追いかけるように、「ご当地サーモン」が日本各地で発生します。いよかんのオイルを餌に加えて臭みを抑えた「宇和島サーモン」や地元産レモン果汁を与えた「広島レモンサーモン」、富士山の湧き水で養殖した「ホワイト富士山サーモン」など、全国で120以上あるそうです。
よく、サケとマスはどう違うの?と言われますが、同じ「サケ科」の仲間です。厳密な定義はなく、海にいる大きなものをサケ、川や湖にいる小さなものをマスと呼んで区別していることが多いようです。
私も、さいたま水族館で初めて知ったのですが、川の上流の水のきれいなところで暮らす「ヤマメ」という魚がいますね。でも、そのヤマメの中から「冒険したい!」と海に向かって泳ぎ出し、大きく成長した魚が「サクラマス」です。もともとは同じ魚です。
ともあれ、地球環境を考えながら、私たちの胃袋を満たしてもらうには、サーモンと呼ぶサケ・マスは、「取る魚」から、ますます「育てる魚」になっていくのでしょう。サーモンに限らず、養殖の魚は、これからも増え続けています。ブリなどは、氷見の寒ブリ以外は、天然モノよりも養殖の方がおいしいですね。これも、時代の流れです。
2024年
6月
11日
火
「おかしの学校」に行ってきました
年長・年中園児合計14名を連れて、ロッテ浦和工場「おかしの学校」に行ってきました。人気のお菓子工場の社会科見学ですので、今年度の団体枠は、すべて予約が埋まっているそうです。さいたま市内の小学校3年生がここを社会科見学に利用することが多いのですが、今日は就学前の園児たちですので、担当のお姉さんたちには、とてもかわいらしく映ったようです。(笑)
3月の社会科見学で、「造幣局さいたま支局」に行った時は、JR西大宮駅からさいたま新都心駅まで、電車で移動しました。今日は、ロッテの工場がある、武蔵浦和駅までの移動です。大宮から先、武蔵浦和駅までは、新幹線が並行して走るので、「はやぶさだ!こまちだ!かがやきだ!」と子どもたちの歓声が響きましたが、他のお客様に迷惑をかけることなく到着しました。
駅から歩いて10分・・・お菓子工場に到着です。いよいよ、子どもたちは「おかしの学校」に入学します。ここは、まるでハリーポッターの世界です。MCのお姉さんも、魔法を使います。子どもたちも、気がつくと、「パイの実」の帽子をかぶらされていました。今日は、ロッテを代表するお菓子「パイの実」の生産ラインを見学です。
パイをふっくらサクサクにするために、64層の生地からできていることや、パイに麦芽糖を吹きかけることで、カリッとした食感になること。チョコレートを入れる工程では、上部に取り付けられているパイプから、チョコレートが水道のように流れていくシーンを目の当たりにした子どもたちは、大興奮です。パッケージされ、箱に入れられた「パイの実」が、ロボットだけで人がいない最終工程で、カートンに積まれていく様子まで、しっかりと見学できました。
浦和工場では、パイの実の他に、コアラのマーチ・ガーナチョコレート・トッポ・クランキー・キシリトールガム。そして、雪見だいふく・爽・もな王などのアイスクリームも製造されています。子どもたちにとっては、なじみのあるお菓子ばかりなので、深く記憶に残ったようです。3交代で24時間稼働する、おかしの大工場は、全国に向けて毎日多くのお菓子を作っているのです。
「やった!」と歓声が上がったのは、おかしの学校を無事に卒業して、お菓子の詰め合わせをお土産にもらった時です。企業にしてみれば、子どもたちの「口コミ」が親に伝わることで、さらに宣伝効果がアップするので、とてもリーズナブルな販促費用ですね。
年長園児の中には、おかしの学校で学んだ知識をしっかりと頭にインプットしたようです。おうちに帰ったら、ママパパに、マシンガントーク解説が始まりそうです。(笑)
普段スーパーに並んでいる商品が、どのように作られ、誰が運び、この棚に並んでいるのか・・・何気ない買い物の時間が、子どもたちの「なぜ?どうして?」につながっていくのが、社会科見学のねらいでもありますが、今日は、十分な成果があったようです。
そうだ~お弁当タイム・・・駅前ビルの屋上庭園で食べます。空を見上げれば、高層マンションだらけですが、この不思議な空間もなかなかいいものでした。
2024年
6月
10日
月
「普通」を問い直す
今日の寺子屋は、「七夕飾り」の工作を作りました。折り紙とのりを使って、あーだこーだ言いながら作業を続けます。先生の話をろくに聞かないで、どんどん自分で作業を進めてしまう園児もあれば、まわりをキョロキョロしながら、なかなか進まない園児もあります。個性いろいろの作品がアップしています。これから、「願い事」のメッセージを書いていきますので、楽しみですね。
最近のニュースでは、「合計特殊出生率」が過去最低となり、東京都に至っては、0.99と1を切りました。少子化への歯止めがかからず、この先の日本はどうなる?といった感じです。しかし、保育園ママで、4人目のお子様がお腹に・・・とうれしいニュースがありました。令和の時代・子ども4人は、凄いことですね。
今日は、少し考えさせられる内容です。「渇愛の果て、」という映画は、妊娠、出産にまつわる出来事が、妊婦とその夫、子どもがいる友人といない友人、医師や助産婦など、異なる立場から描かれた作品です。今後全国で順次ロードショー化されます。
この映画では、「出生前診断」が取り上げられます。妊娠中に胎児の発育や異常の有無などを調べる検査です。検査方法は色々あり費用も異なります。出生前診断で「陽性」となり、その後の確定的検査で染色体疾患が見つかった場合、大多数の夫婦が出産を諦めているのが現状だそうです。分かりやすく言うと「あなたのお子さんは、ダウン症です。それでも出産を考えますか」と問われた時の判断です。この判断について、いいとか悪いとかの話ではありません。
この映画の監督・脚本・主演を務める「有田あん」さんは、妊娠した友人が、羊水検査をしたところ、胎児の指が欠損している可能性があるとなったそうです。その友人の話は、「普通でよかったんだけどな。特別かわいかったり、何かに長けていたりと、高望みをしているわけではないのに・・・」
有田さんは、「普通」って何だろうとずっと引っかかったままでした。この映画のテーマは、出生前診断だったのに、「普通って、難しい」に変更し、編集し直したそうです。「普段よく使っている『普通』や『当たり前』といった言葉を、問い直したいと思いました」と。
映画の試写をした際、「子どもが欲しかったのなら、出生前診断は知っておくべき」「障害児でも受け入れろ」「中絶はあり得ない」という感想も寄せられたそうです。「でもそれは、あなたの尺度ですよね」と有田さんは言います。「『あり得ない』って他人に言われてしまったら、当事者たちは、本当の気持ちを声に出せなくなってしまいます」と続けます。
映画の中で、障害のある我が子を「かわいいと思えない」と主人公が吐露する場面があります。有田さんは、「我が子を愛さないといけない、現実を受け入れるべきなど、『べき』を押し付けるのではなく、『私はこう思う』だけで、いいと思うんです」と言います。
ここで、みなさんは、もう一度「普通」を問い直してください。私の場合は、大学の同期が、40歳を過ぎて結婚をしたのですが、その挨拶で、「普通の幸せを大切にしたい」と言ったのです。私にとって、「普通」という言葉が、すごく大切に思えるきっかけになりました。毎日コツコツと、普通に仕事を継続することが、どれだけ大切なことか・・・今も私は、「普通」とは、そんな簡単なことではないと思っています。
でも、今私が言った「普通」と、この映画の「普通でよかったんだけどな~」の「普通」は、意味が違います。有田さんの言う通り「普通って、難しい」ですね。
なんだか、言葉遊びのようになってしまいましたが、あなたにとって「普通」のことって、どんなことですか。当たり前にできることですか。それとも、別の意味ですか。今日は、「普通」を問い直してください。
2024年
6月
09日
日
感覚過敏研究所
「感覚過敏」をご存じですか。主に五感を中心に感覚が過剰に鋭く、日常生活に支障をきたしてしまう症状のことです。
「聴覚で言えば、教室でのざわざわとした話声やシャーペンをカチカチする音が苦手で、視覚なら人ごみの中にいるとすぐに疲れてしまったり、頭痛がしたり。味覚は大変で、食べられるものがほとんどありません。白米は食べられるのですが、においや食感によっては体調が悪くなる」と語るのは、「感覚過敏研究所」所長の加藤さんです。まだ18歳の若者です。加藤さんもその症状を持つ一人で、彼が経験した内容です。服の縫い目やタグが痛い。制服が重い。香水のにおいに耐えられない。といった、日常生活のあらゆる面で苦痛を感じ、中学校では不登校になりフリースクールに転校したそうです。
一般的にほとんど知られていない「感覚過敏」という言葉の可視化に取り組みます。「苦手な音があります」「苦手なニオイがあります」などのキャラクター缶バッジを作ります。そこに五感にかかわるメッセージを載せます。啓発活動は、コロナ禍において「マスクがつけられない意思表示カード」や「せんすマスク」がメディアに取り上げられ、認知度がアップします。
2022年には、アパレルブランドを立ち上げます。パーカーとTシャツ、靴下の開発をします。タグはなくし、縫い目は外側に出すなど、感覚過敏の人に、着心地のいい服を目指します。オンライン販売で、パーカーとTシャツ合わせて千着を売り上げたそうです。
視覚や聴覚に対応した、イヤホンやレンズも開発するものの、嗅覚や味覚、触覚について解決できる対策商品がまだできていないことが課題だそうです。加藤さんが、今力を入れているのが、センサリールームやカームダウンボックスと呼ばれる五感に配慮した空間づくりです。この空間は、音や光やにおいといった刺激をなくすことで落ち着きがもたらされるもので、将来的にはショッピングモールなどへの設置を目指しているそうです。
まだ18歳の加藤さんですが、彼の頭の中には、10年後の理想の未来があります。「今は感覚過敏がただ単につらい『症状』ですが、そのつらさを解消できれば、鋭い感覚によって小さな変化にも気づける『才能』になるんじゃないか。仕事をするときには少し過敏モードで、日常生活ではオフにするといったことができるようになったらいい。そのための研究を続け、私が32歳になるころまでに解決できればいいと目標を立てています」
時代の流れを見れば、目の悪い人のためにメガネというアイテムができ、それが、今では個性としてファッションにつながっています。感覚過敏も一つの個性として尊重する社会になっていくのかもしれません。加藤さんのような若者が、そんな社会への道を作り、私たちがその道をどう歩くかで、社会は変えられるのです。
2024年
6月
08日
土
大宮盆栽村
今日の園長の課外授業は、大宮盆栽村にある「大宮盆栽美術館」に行ってきました。小学生と年長園児4人を連れてです。
ところで、大宮盆栽村は、いつからあると思いますか?かなり古くて、関東大震災の2年後の1925年だそうです。1989年には、第1回世界盆栽大会が、旧大宮市で開かれ、2010年に「大宮盆栽美術館」が開館しました。来年で盆栽村ができてから100年です。最盛期には、約35園の盆栽業者があったそうですが、高齢化や後継者不足などの理由で廃園が相次ぎ、今では6園だけとなってしまいました。
盆栽美術館の2023年度の来館者数は、約5万6000人で、コロナ禍前の水準には達していないそうです。ところが、盆栽は「Bonsai」として。世界的には注目を集めています。外国人だけの入場者数は、コロナ禍前と比較しても130%で、大きく増えています。今日も3組の外国人が、異国語で会話をしながら、盆栽を前に立ち尽くしていました。2023年度は、入場者数の15%が外国人だったそうです。昨年度、初めて外国人向けの解説会を週1回実施したそうですが、今年度は週4回に増やしたそうです。
さいたま市は、外国人客を呼び込もうと、都内の高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン東京」での盆栽展示、若手盆栽師によるデモンストレーションなどを開催しています。しかし、日本の文化である盆栽の国内人気がまだまだです。2023年度から、出生届を出した市民に手のひらサイズの「ミニ盆栽」を贈る事業を始めたそうです。子どもの成長に盆栽の成長を照らしあわせて・・・といったところでしょう。
盆栽美術館で、一番大きな盆栽は、何と樹齢500年です。私は、その盆栽の前で無言で立ち尽くし、戦国時代から、現代を見守ってきたのか・・・と感慨深くなってしまいます。
さて、本日盆栽美術館を見学した4人の子どもたちの反応は???出発する時「ぼんさいってなに?」とあまり興味を示さず、一番年上の小3女子だけが「植木でしょ」と答えます。そして、盆栽美術館に着くや、外国人の姿に、気分が高まったようです。そして、園長の素人解説と、途中からボランティアの解説員の話を聞きながら、「へぇ~そうなんだ・・・すごいね~」といった感じです。入場口で、お姉さんから、盆栽美術館のカードを特別にもらったのが、良かったみたいです。(笑)
明日の日本を担う子どもたちだって、きちんと説明すれば、興味を持ってくれます。さいたま市が誇る盆栽文化は、世界へ広まっていくのです。
2024年
6月
07日
金
紙ストローって、本当にエコ?
今日は、「父の日プレゼント」の制作を行いました。母の日と同じ作品の父の日バージョンです。母の日に比べて、世間的にはトーンダウンしてしまう「父の日」ですが、子どもたちは、ママへのプレゼントと同じ熱量で作っていました。うれしいですね。
さて、いつの間にか、ファーストフードチェーンなどで広まっている「紙ストロー」ですが、SNSでは、「あのぶっといストローの違和感は、並じゃない。おまけに紙製なんで、水分を吸ってすぐヨレヨレになっちまう」といったバッシングがあがっています。それでも、まだ使用しているショップが多いようです。2022年にプラスチック新法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)が施行されてから、2年が経過しました。
プラスチックストローは、ウミガメの鼻から出てきたのが、プラスチックストローだったために、脱プラスチックの悪役ナンバーワンになってしまったのです。ウミガメの映像は、あまりにも痛々しく、「プラスチックストローはけしからん!」という認識が、消費者の中で蔓延してしまったのです。
専門家は、「海洋生物にこんなふうに害を及ぼすプラスチックのほとんどは、不法投棄によって海に流れ出てしまったものです。プラスチックストローを使ったとしても、ゴミとしてきちんと廃棄し処理されるなら、ウミガメの鼻に刺さることはないのです。一方、紙のストローでも不法投棄されれば、分解される前にウミガメが吸い込まない保証はない」と冷静に判断します。確かに、私たちの家庭から出るペットボトルもビニールゴミも、分別してゴミの日にきちんと出しているので、これが海に流出することは、普通に考えればあり得ないことです。
人間は、「何かやらなくては!」と気持ちが先立つと、とにかく「環境にいい」と思えることをマネして行う傾向がありますね。ストローを紙にするのは、分かりやすいストーリーゆえに、加速して広まったのです。紙ストロー問題で言うと、一番いいのは、植物由来の素材を使うバイオマスプラのストローだそうです。焼却処分される場合は、排出するCO²は、紙ストローのわずか33%程度だそうです。実は、プラスチックストローよりも紙ストローの方が、焼却の時に、1.4倍もCO²の排出が多いそうです。あれ!?ですね。
これも有名な話ですが、エコバックもレジ袋に比べると布を張るとう作業に多くのCO²が出るため、100回はつかわないと、CO²の元が取れないそうです。ならば、レジ袋を大拙に使いまわしたほうが、エコというわけです。
太陽光発電が、地球にやさしいという認識が高いですが、太陽光パネルには耐用年数があり、あの大きなパネルをどうやって廃棄するか・・・という問題があるのです。そういう我が家も、そんなことも考えずに、「地球環境のために」という理由で、屋根にはソーラーパネルがあります。
私たちは、紙ストローで踊らされ、エコバックでも踊らされ、「地球環境のために」という「大義名分」に流されているのかもしれませんね。もっと、基本的な生活の中で「ていねいな生活」「ここちよい空間」「自分らしい居場所」を考える時、「これって、地球環境にいいことかな?」と思うことが大切なのかもしれません。当事者意識を持つということは、つきつめれば、こういう事ですね。
2024年
6月
06日
木
物流の2024年問題
朝の自由時間、年長男子が、特大ブロックをつなぎ合わせて、5メートル超の電車を作りました。電車には、次々と子どもたちが乗り、男の子が運転手です。車内アナウンスもあり、素敵な遊びになっていました。こうして、子どもたちの遊びに、今日も心が洗われるのです。(笑)
さて、今年4月から始まった物流の「2024年問題」は、マスコミで多く取り上げられてきました。トラックドライバーやバスの運転手、タクシードライバーなどの時間外労働の上限制限がなされました。
特に、宅配業者では、かねてからの人手不足状況の中、ニーズは、共働きや一人暮らし世帯が増え、週末や夜間配達が増えています。ある配達員は、「残業規制は全く守られていません。残業規制を守ろうとすれば、今以上に利用者のニーズに応えられなくなります。こうした認識や覚悟が利用者にはあるのでしょうか!?」と訴えます。
私たちが、ニュースで2024年問題を見ても、「何か、物流業界は大変ね!人が集まるのかしら?」なんて、どちらかというと、他人ごとに受け止めている人がほとんどです。
冒頭の配達員は、1日に配達を任される荷物は150個前後。午前8時に配送センターに出勤し、2トントラックに荷物を積み込んで都内の担当エリアに向かう。配達を終え、配送センターを経由して帰路に就くのは、午後9時過ぎ。12時間を超える勤務時間中は、常に配達や集荷、伝票チェックに追われ、車内で弁当を食べる時間を確保するのがやっと。毎日、1~2割は不在のために再配達に回る。結局、配達しきれずに夜8時以降は、個人事業の委託業者に荷物を引き継ぐそうです。
過重労働の負担をさらに重苦しくするのが、利用者からの上から目線の態度や課題要求です。「家にいたんだけど・・・」と連絡する利用者。月に5・6人はいるそうです。「インターホンを2回鳴らさせていただきました」と伝えると、「だから鳴ってないんだよ!今度からは電話しろ!」とキレる利用者もあるようです。
日本の消費者はあまりにも要求水準が高い。それが過剰サービスにつながり、物流システム全体を圧迫していると、専門家は言います。コンビニの24時間営業も、スーパーの棚には、形のそろった商品がびっしりと並んでいるのが当たり前という国は、世界でも日本だけだと。
確かに、私たちは、日本という国では、当たり前のサービスと考えていたことが、あまりにも多いことに、気がつきますね。「物流の2024年問題」を解決するには、物流業者の改革以上に、「消費者の行動変容」だと言われています。
急いでもないのに、「翌日配送」にしていませんか?
宅配ボックスや置き配を活用して、再配達をなくす取り組みをしていますか?
在宅時間に変更があった時に、ちゃんと宅配業者に連絡していますか?
複数の商品は、まとめて注文・配達依頼をしていますか?
食品は棚の手前にある消費・賞味期限の近い商品から買っていますか?
地産地消を心がけ、物流負担の軽減に協力していますか?
災害時には必要最低限の注文や購買にとどめていますか?
話は大きくなりますが、働く人の健康や人権を守ることも、持続可能な便利さや豊かさを追求することも、地球環境への負荷を軽減することも、すべてよそ事ではなく、これからの「自分」とつながっていると考える時代になってきたのです。
どうですか?私たち消費者の主体性が、2024年問題を左右するとうわけです。
2024年
6月
05日
水
花を愛でる
「今日は、一人2個まで、ビワを食べてもいいよ!」と声をかけると、子どもたちが次々と、ビワの木の下に集まってきます。すでに、木に登っている年長男子たちです。「甘~い」もあれば「甘酸っぱ~い」もあります。しっかり熟した濃いオレンジ色の実をゲットした園児は「おいし~い」と叫び、少し硬めの黄色に近い実をゲットした園児は、無言で食べています。ビワの種をおうちに持ち帰って、庭に植える園児もいます。私の自宅のビワも、数十年前に庭に植え、いつの間にか実をつけるようになりました。マルベリーの次は、ビワを食べる子どもたちは、何ともたくましいですね。
さて、皆さんのおうちには、花が飾られていますか。花がなくても、人間は生きていけます。お菓子を食べなくても、しっかりと食事をとっておけば、私たちは生きていけるので、お花もお菓子も似ています。しかし、私たちの心を豊かにするためには、花もお菓子も欠かせませんね。
先日、テレビで「切り花のサブスク」の会社が紹介されていました。週に一度定期的に、切り花が届きます。花瓶に入れれば、部屋が華やかになるという作戦です。花屋で購入するよりも安い価格設定になっています。「花屋に行く時間がない」「花に詳しくないので、お任せでかまわない」「毎週どんな花が届くか楽しみ」などなど、花の定期便を利用する人がどんどん増えているそうです。
「食品ロスをなくそう!」というスローガンは、すっかり私たちの生活に入り込んでいます。日本の食品廃棄ロスは、毎日、国民一人がおにぎり○個分捨てている計算になるなんて、よく例えられます。実は、「フラワーロス」もあります。生産栽培された花が、消費されずに廃棄されてしまうことですが、コロナ禍では、入学式・卒業式・冠婚葬祭などの式典が中止となり、花の需要が大幅に落ち込み「フラワーロス」の問題が、表面化しました。今でも、「フラワーロス」は、年間1500億円にもなるそうです。
切り花のサブスクでは、一般的なサイズの40センチの切り花ではなく、25センチの切り花を扱い、専用の小さな花用BOXでポストに投函されます。通用の市場では規格外でロスになってしまう花も活用できます。また、花のチョイスも安価で仕入れた季節の花を活用できるので、コストダウン分を価格に反映させることができるのです。もちろん、届いた花には、花言葉などのコメントがあるので、お客様は、続けるだけで、花の知識もアップするのです。
保育園では、寺子屋の時間で「ママにプレゼントするお花をカップに集めて!」をたまにやります。もちろん、花は屋上にある「野草」です。そして、先日は、朝顔の種をまきました。色水遊びが目的です。卒園児の小学生は、「ムスカリ」「カラスノエンドウ」「オオイヌノフグリ」「ハルジオン」「ホトケノザ」など、マニアックな花の名前を知っています。
花の名前を知らなくても、私たちは生きていけますが、子どもたちには、花の名前も花を愛でる感性もたくさん持ってもらいたいですね。
2024年
6月
04日
火
「香水砂漠」日本
今日は、大きくオレンジ色になった、屋上のビワを食べました。年長男子は、ビワの木に登って、みんなの分を取ってくれます。さるかに合戦で、意地悪をしない猿のようです。マルベリーと違って、1粒が大きいので、モグモグと満足顔で食べる子どもたちです。また、寺子屋では、10月の運動会で行う「30メートル走」をやってみました。「今日1番になれなかった人は、運動会までに頑張ればいいだけだよ」と言っても、勝ち負けにこだわる年長園児です。一番の収穫は、年少3歳児全員が、30メートルを走り切ることができたことです。
さて、今日は香水の話です。皆さんのまわりに、香水を頻繁に使用している人はどのくらいいますか?私のまわりには、ほとんどいません。日本は、香水の売上規模が小さく、世界の業界関係者からは「香水砂漠」とかつては、呼ばれていたそうです。私の勝手なイメージですが、日本人の入浴は、シャワーでなく湯船につかって時間をかけるので、体臭が残ることが少なく、よって、香水でごまかす必要がない。と思うところです。
ところが、ここ数年、日本での香水の売上は伸び始め、昨年の国内市場は、前年比13%増の500億円になったそうです。9年前の402億円から125%も伸びた計算です。
市場規模500億円といっても、イメージがわきませんね。日本のバレンタイン市場が、約1000億円(わずか1か月での売上で、大谷選手の10年分の年収なので、凄い金額です)なので、その半分です。少しはピンときましたね。
ここまで香水市場が拡大したのは、訪日外国人の影響もありますが、「Z世代」がキーマンです。現在10代半ば~20代後半のZ世代の幼少期は、香水のような柔軟剤が登場した頃です。日常的にこの香りに触れているので、香水も抵抗感がなく購入しているようです。
またその上の年代は、ファンションの仕上げや、自分をよりよく見せたくて香水を使う人が多かったですが、コロナ禍以降は、自分が楽しむために使うようになっているそうです。リモートワークで、自宅で過ごす時間が増えて、仕事とプライベートの境界が曖昧になり、気分転換や癒しのために香りを活用する人が増えたようです。通勤時と休日のお出かけとで、香水を使い分けて気分を上げるのです。
男性の利用客も増え、今は、香水のサブスクまであるそうです。オンラインで質問に答えると、月額3890円で、おすすめの香り3種類が自宅に届くそうです。
日本は、「香水砂漠」ではあったかもしれませんが、「お香」や最近では「アロマテラピー」など、自宅などで香りを楽しみ気分転換を図る文化は、昔からありましたね。香りは、心身への効果が大きいと、昨今では医学的にも証明されていますので、香水市場は、まだまだ拡大しそうです。
ここまで、書いておきながら・・・私が香水を使用することは・・・ないかな~。
2024年
6月
03日
月
ぼっち死の館
今日の連絡ノートには、土曜日の親子遠足の感想がびっしりありました。天気に恵まれたこともあり、水上アスレチックがどれだけ楽しかったかが、伝わりました。そして、荒川を学ぶ「ガリバーウオーク」も、意外にも子どもたちは、多くの知識を吸収できたようです。
さて、私が勤務していた会社のOB会長は、神戸で「民生委員(児童委員も兼ねる)」のエリア長をやっています。まさに、地域の方々のために仕事をしています。でも、そんな会長ももうすぐ75歳になろうという年齢です。ずっと、会長は「死ぬまでに本を書く」と言っていました。そして、いよいよそのテーマが見つかったのです。民生委員として、様々な高齢者との出会いをストーリーにするようです。しかし、最後は、ハッピーエンドで、人生の終焉を迎える人々を美しく取り上げるそうです。個人的には、とても楽しみにしています。
とはいえ、現実には高齢化が進む昨今、一人暮らしの高齢者の数が増え続け、家族にみとられずに死を迎える「孤独死」が身近な問題となっています。今日は、齋藤なずな作の「ぼっち死の館」というコミックを紹介します。
舞台は高度経済成長期に建てられた、とある団地です。かつては、ニュータウンとして多くの人々でにぎわいを見せてたこの場所には、現在、独り身の高齢者たちと猫たちが暮らしています。数日前に会話を交わした人が、姿を見掛けないと思ったら、部屋で一人で亡くなっていたということも、ここでは珍しくありません。「生と死」という、シリアスな内容を扱いながらも、この作品にはユーモアがありほのぼのとしたセリフが、読んだ後に満足感をもたらす作品です。
作者の齋藤なずなさんは、現在78歳の女性です。作品内の登場人物たちと同様、長年団地に住んでいます。作品の中で、漫画家の女性が、ある男性住人の孤独死をきっかけに、彼の人生をマンガのストーリーにできないかと考えます。しかし、実際の彼の人生は、「話」としては、うまく割り切れないものがあったのです。「生きてるってなんか、もっとヘンテコで複雑で、わけがわかんない!」とぼやきます。
団地の住人たちが、自分の人生の終結点を意識することで、何げない日常をいとおしく感じます。生きることとは何なのか、限られた人生の中で何ができるのかを考えるために、ヒントを与えてくれるような作品になっています。
私たちは、「頑張って何かを成し遂げた人」や「毎日コツコツ目立たないけど生きてる人」や「未来を担う、子どもたち」などの姿をみることで、「生きる意義」みたいなことを考えることが多いですね。しかし、この作品は、孤独死を身近に感じる人々の暮らしの中から「生きる」を捉えようとしています。
読んでみたくなりましたか。
2024年
6月
02日
日
令和6年度 親子遠足 つづき
お弁当タイムは、「家族が幸せな笑顔に浸る時間」です。ママやパパが作ったお弁当を家族で食べるというシーンは、世の中にたくさんある幸せの中でも、かなり上位にランクインするのではないかと思っています。園長のビデオカメラもー家族ずつ撮らせていただきました。「美味し~い」の笑顔が最高なのです。
とても小さいですが、川の博物館には、川に棲む生き物を観察できる「ミニ水族館」があります。スッポンに驚き、「ニホンイシガメ」「クサガメ」の子ガメたちが、水槽で泳いでいました。保育園と全く一緒です。ジンベイザメもイルカもペンギンもいませんが、生き物が大好きな子どもたちは、ちゃんと「見るべきツボ」を抑えているようです。
そして、午後は、「わくわくランド」で水遊びです。年齢制限があるので、寺子屋園児は
、このウォーターアスレチックで思う存分遊びました。わくわくランドは、川の博物館では一番の人気スポットです。午前中には、すべての時間帯のチケットが完売になることも多いそうです。保育園ホワイトきゃんばすの13:00スタートの会には、学童クラブの小学生も一緒だったので、とにかく、激しい水遊びになりました。ここはプールではなく、水上アスレチックなので、くつ(ウォーターシューズ)を履いて洋服のままで遊びます。手こぎボートにロープ渡り、滝に、浮島を飛び歩くアトラクションなど、子どもたちの冒険心をそそる演出です。見事に、全身びしょ濡れの子どもたちです。
寺子屋以外の園児は、噴水広場で水遊びです。ここにも楽しい演出がいっぱいです。もちろん、チビちゃんたちの服はびしょびしょです。わくわくランドの制限時間が50分なので、遊び足りない寺子屋園児と小学生は、解散後もここで遊び続けていました。
ということで、天気にも恵まれ、子どもたちにとっても、保護者の皆様にとっても、充実した1日になりました。全員、安全で大きなケガも事故もなく過ごせたことは、うれしい限りです。親子遠足の思い出は、子どもたちの心に深く刻まれることでしょう。そして、この思い出が、「明日からも頑張る」「辛いけど何とか乗り切ってみる」とか、「家族一緒の時間は楽しいなぁ~」「仲間と一緒だと何にでも挑戦できそうだ」という気持ちにつながってくれることを期待します。
保護者の皆様・・・親子遠足を楽しんでいただき、本当にありがとうございました。
2024年
6月
01日
土
令和6年度 親子遠足
1週間前から、台風1号の進路がどうなることや?と気をもんでいた親子遠足ですが、ふたを開けると快晴に恵まれました。朝早くからママたちはお弁当作りを頑張り、先日のわくわく教室で「おにぎり」を作った年長園児たちは、自分でおにぎりを握りました。そして、朝10時「埼玉県立 川の博物館」に全員集合しました。
川の博物館の名物の一つが、日本一の水車です。すべて埼玉県内の「西川材」で作られ、直径は24.2メートルもあります。25メートルプールの長さが直径ですので、とてつもない大きさです。まずは、水車をバックに記念撮影です。
午前中は、「かわせみチーム」と「すいしゃチーム」に分かれて、ガイドを聞きながらの見学です。まずは、「ガリバーウオーク」を楽しみます。川の博物館のもう一つの名物が、「荒川大模型173」です。荒川の源流となる「甲武信岳」から、東京湾までの173キロを1/1000の縮尺で再現した、日本一の大型立体地形模型です。荒川にかかる150あまりの橋や鉄道、ダムなどの施設が再現されています。1/1000といっても、なかなかの距離になるので、屋外に設置されています。
ガリバーウオークは、川の博物館の学芸員の方にガイドしてもらいます。大人である保護者や先生たちは、より知識が膨らみました。子どもたちだって、なかなかのものです。お弁当タイムで、問題を出します。「荒川の長さは、日本で何番目ですか?」これには、5歳男の子が15番目と即答です。「では、荒川で日本一のところがあります。それは何?」これは、じっくり考えた男の子が、「川の幅かな?」と正解です。川幅の定義は、堤防から堤防までの距離です。鴻巣市(こうのすし)と吉見町(よしみまち)の間は、川幅2537メートルあり、日本一の川幅と認定されています。平成19年9月の台風9号では、川幅いっぱいまで増水したそうです。
川の博物館の位置は、ちょうど、「山から街へ」景色が移り変わる場所です。子どもたちは、山側と街側の景色を比較しながら、納得していました。このまま下流へ歩いていくと、保育園ホワイトきゃんばすのある場所にやってきます。上江橋・JR川越線鉄橋・治水橋を確認します。そして、いよいよ東京湾の荒川河口へ。「お台場」「葛西臨海公園」そして、何と言っても「東京ディズニーランド」があるので、子どもたちの目が輝きます。「そうなんだ・・・荒川の終わりにディズニーランドがあるんだ!」と、子どもたちの会話が、荒川からディズニーランドのアトラクションに変わっていきます。(笑)
川の博物館の館内でも学びがたくさんありました。秩父山地から切り出した木材を水の力で下流に押し出すために作られた「鉄砲堰(てっぽうぜき)」が、1/4の縮尺で再現されています。実際に水が流れてすごい迫力です。また、荒川を使って物資の輸送に使われていた「荷船」の解説もありました。子どもたちは、ワークショップで「カタツムリ」を作ります。自分で作った大切な作品がお土産になりました。
こんな感じで、午前の部は大人だけでなく、保育園の子どもたちも小学生も「荒川」に興味を持つことができたようです。ガリバーウオークで、ガイドが荒川源流の山頂から、じょうろで水を流し(雨を降らせる)、それが川になって流れていく演出で「つかみはOK!」になったようです。(笑)
つづきは、あした。
2024年
5月
31日
金
サラリーマン川柳 2023年
今日は、朝から台風並みの豪雨でした。太平洋上を北上する台風1号は、温帯低気圧になりましたが、関東から遠ざかってくれたので、明日の遠足はお天気になりそうです。保育園では、寺子屋以外のチビちゃんたちは、「マラカス」を手作りしました。ヤクルトサイズの容器を使って、チビちゃんでも自分の手のひらに収まるサイズです。今日のお土産になったので、おうちでは、シャカシャカうるさいかもしれませんね。
寺子屋園児は、体操教室です。 平均台の上を歩く年少園児は、今まではコロコロ転んでいたのですが、ずいぶんとバランスが取れるようになってきました。まだまだコースアウトしたり、順番が守れなかったりと、ぐだぐだですが、少しずつ前進しています。
さて、昨日、第一生命保険から、2023年のサラリーマン川柳コンクールの作品が発表されました。私も、このサラリーマン川柳を毎年楽しみにしています。ということで、上位10作品を皆さんと楽しんでみます。
1 増えるのは 税と贅肉(ぜいにく) 減る贅沢(ぜいたく)
2 物価高 見ざる買わざる 店行かず
3 マスクなし 2年目社員の 笑顔知る
4 50代 給与も肩も 上がらない
5 PayPayを 覚えた夫の 無駄遣い
6 ダイエット 動画だけ見て 痩せた気に
7 パスワード チャンス3回 覚える子
8 盗み食い ペットカメラに 映る父
9 アレとソレ 用意済むのが 日本流
10 2度聞くな! 言った上司が 3度聞く
どうですか、今年も傑作が多いですね。1位の作品は、家計と健康面の悩みを上手に掛け合わせていて「なるほど」です。2位の作品は、日光東照宮の三猿「見ざる言わざる聞かざる」をもじった作品ですが、私がPTAに関わっていた時の中学1年生の絵画の作品を思い出しました。タイトルは「見たい・言いたい・聞きたい」です。中学生は、好奇心いっぱいで、何でも見たくて言いたくて聞きたくてという気持ちを絵にした作品です。今でも忘れない素晴らしい作品でした。
今回のサラリーマン川柳には、6万6949句の応募があったそうです。入選100作品の中から、このベスト10が決まりました。投票は5万票とのこと。国民的なイベントですので、応募数も多いですね。
こんな感じで、日常を笑い飛ばす余裕が欲しいものです。
2024年
5月
30日
木
歴史教育の転換期
今日は、屋上ファームでキュウリを4本収穫しました。子どもたちは、キュウリが大好きですので、すぐに行列ができます。園長がカットしたキュウリを配っていきます。塩を少しふって、とれたてのキュウリをいただきました。シャキシャキしています。マルベリーを食べて、次にキュウリを食べる子どもたちです。
さて、2年前から、高校の新学習指導要領で、必修科目として「歴史総合」が始まりました。私のような昭和世代の中学高校時代は、学校の教科書を絶対的に正しい歴史として暗記することが求められました。「鎌倉幕府はいつできた?」には、「1192(いいくに)つくろう鎌倉幕府」と語呂合わせで覚えたものです。ちなみに、鎌倉幕府成立は、今は1185年ですが、昭和世代は1192年で暗記していました。
「歴史総合」は、そんな暗記教育の弊害をなくしていこうという目的があり、世界史と日本史を統合した科目です。かつて、高校での世界史は、覚えることが多くて、選択しない生徒が増えてしまいました。そこで世界史を学ぶ機会を作ること。もう一つは、日本史と世界史を切り分けたまま学んでしまうと、日本の特殊性や優位性ばかりが強調されてしまいます。でも、歴史を深く学ぶには、世界の大きな流れや共通性に着目し、国や個人の価値観の違いによる多様性を知ることが大事です。
最近は、歴史を扱うテレビ番組が面白いですね。「歴史探偵」「英雄たちの選択」などを私は毎回見ています。英雄たちの選択は、史実はあるものの、「あなたならどう選択するか?その理由は」まで、自分だったらどうする?の視点がいいですね。歴史が面白いのは、100人いれば100通りの歴史観があることです。「自分だったこうする」を考えることは、将来、困難に出くわした時に、その解決策を考える訓練にもなるでしょう。
歴史総合の原案作りに関わった、小川教諭はこう言います。「混沌とした21世紀で、歴史を学ぶ意義は大きく3つあります。1つは、過去の人々の営みを参考にして、現在の生き方を見つめ直し、未来をどのように創造するかを考えること。2つ目は、多様な人々の生き方、考え方を理解して、対立を乗り越える思考力を磨くこと。最後は、真実をないがしろにする、今の時代に、何が「ファクト(事実)」なのかを見抜く力を養うことです」
日本人が、どちらかというと苦手にしている分野かもしれません。しかし、新しい歴史教育によって、「自分だったらこうする」と考える力が、間違いなく育つことでしょう。もちろん、自分の主張を押し付けるのではなく、他者の価値観を尊重できるような若者が増えてほしいですね。
2024年
5月
29日
水
高校生「いま関心があること」
今日は、久しぶりに屋上遊びができました。昨夜の台風並みの強風の名残りがあり、まだ風が強かったですが、子どもたちは、残り少なくなったマルベリーを食べます。昨日の寺子屋で作った「マルベリージャム」は、朝食でトーストに塗ったり、ヨーグルトに入れたりで、あっという間になくなったおうちが多かったようです。そして、今日の寺子屋は、「廃材工作」です。課題は自由でしたので、ゴジラ・アイスクリーム・恐竜・クラゲのおうち・スポーツカーなどなど・・・子どもたちの発想で、素敵な作品が出来上がりました。
さて、明日の日本を担う「若者」である、高校生が、どんなことに関心をもっているか、気になりますね。ある538人の高校生のアンケートの中から、「いま関心があること」をピックアップします。
物価高騰について・・・もしこのまま高騰し続けたら、私たちが大人になったときにはどうなってしまうのか。
人種差別・ジェンダー問題・・・生まれ持った自分で選べないものによって不当な扱いをうけるようなことがあってはならないと思う。
アイドルのあり方・・・最近SNSでアイドルの容姿を批判している投稿を見て、顔が整っているだけがアイドルの条件ではないと思った。
地球温暖化・・・地球温暖化が進んで、氷が溶け、動物たちがいなくなっているから、どうにかしたいと考えている。
筋トレ・スキンケア・勉強・・・自己肯定感を満たすため、自己不足感を払拭するために行うもの。
格安サイトで服を買うことは?・・・格安サイトの裏には低賃金で長時間働かされている人がいるわけで、そういう人を助けるには、どのようなお金の使い方をしたらよいのか、知りたい。
どうですか・・・大きな問題から、身近な現実論まで、高校生が関心のあることは、いろいろありますね。内容よりも、きちんと問題意識を持つことが大事ですね。
ちなみに、小学生がなりたい職業で、上位にくる、「スポーツ選手」は、今回の538人の高校生に聞いてみると、全体の1.7%しかありません。YouTuberは、たった一人だけだったようです。高校生は「環境問題に携わっている会社」「児童福祉に関わりたい」など、仕事を通じて、社会課題と向き合いたいと考える生徒の割合いが増えるようです。より、現実的で、いま関心があることにつながっていますね。
2024年
5月
28日
火
着衣泳を広めるプロジェクト
今日は、寺子屋の時間で、マルベリージャムを作りました。屋上で、マルベリーを生食している子どもたちですが、ジャムにすれば、トーストに塗ったり、ヨーグルトに入れて食べることもできます。鍋にマルベリーの実を入れて、グツグツ・・・子どもたちが、スプーンで少しずつグラニュー糖を入れて、かき混ぜます。最後にレモン汁をかけます。カップにマルベリージャムを入れてお土産です。モノだけでなく「コト」があるので、子どもが親にうんちくを語りながら、楽しんで欲しいですね。
さて、皆さんは、「着衣泳」(服を着たまま泳ぐ)経験をしたことがありますか。まず、ないでしょうね。私もTシャツで泳ぐことはありますが、ズボン&靴を履いたまま泳いだことはありません。「着衣泳を広めるプロジェクト」という団体があり、そのリーダーは、あの「岩崎恭子」さんです。1992年バルセロナ五輪で、競泳史上最年少の金メダリストになったレジェンドです。
岩崎さんは、20年ほど前のテレビ番組の「金メダリストが着衣泳に挑戦」という企画で、初めて体験したそうです。波のあるプール泳いだそうですが、それはそれは、ヘロヘロになったそうです。そして、東日本大震災の時に、着衣泳のおかげで命が助かったというニュースを知り、着衣泳の大切さを広めていかなければいけないと思ったそうです。
着衣泳では、普通に泳いでもうまく動けません。基本は、頭と足を浮かせた「背浮き」という姿勢だそうです。履いた靴などの浮力を生かすので、服や靴を脱いではいけません。ペットボトルやビニール袋も浮力には役立ちます。登下校中であれば、ランドセルも効果的だそうです。
保育園では、7月末にサマーキャンプを行いますが、屋上プールで、ライフジャケットを着て浮く練習をします。水が苦手な子は、泳ぐ以前に「浮く感覚」を持ちにくいようです。
岩崎さんは、「世界的に見ても、これだけ多くの学校にプールがあるのは日本くらいです。義務教育で水泳を扱う訳をもう一度考えるべきです。水泳を教えることも大事ですが、着衣泳を取り入れて、命を守るための水泳指導を学校で行うべき」と、強く訴えます。
小学校の水泳の時間で、着衣泳がカリキュラムとして、当たり前に取り入れられるようになれば、遊び感覚で、「命の大切さ」を体験することができますね。
2024年
5月
27日
月
見えない「努力の壺」
今日は、お楽しみのイベントがありました。4Fに新しく「キッズランドUS」という室内大型運動施設が誕生しました。朝10時の開園と同時に、保育園の園児全員で遊びに行きました。だいたい園児の8割くらいは、家族と遊びに行ったことがありますが、保育園の友だち同士で遊ぶのは、楽しさが何倍にもなるようです。
ふわふわドーム・ボールプール・エアートランポリン・アスレチック・馬パカパカ・キャンプスペース・ブランコ・トランポリン・乗り物いっぱい・ゲームコーナー・おままごとコーナー・衣装コーナーなどなど、一日中でも遊べるところです。1時間30分があっという間に過ぎて、子どもたちは汗だくになって、満足顔です。おうちでは、ママパパにマシンガントークで、今日の出来事を話し続けるでしょう。(笑)
さて、「子どもを変えた親の一言」の中から、見えない「努力の壺」の話をします。人が何か今までできなかったことに挑戦しようとすると、心の中に「努力の壺」のようなものができると言います。ところが、その壺には4つの特徴があるそうです。
1つ目は、人によって壺の大きさが違うことです。すぐにできるようになる人もいれば、なかなかできるようにならない人がいるのは、そのためです。
2つ目は、「努力の水」を入れ続けなければ、水は乾いてなくなってしまうということです。油断して、努力することを休んでしまうと、あっという間に努力の水は乾いてしまいます。
3つ目は、努力の水が一度でも壺からあふれ出れば、その後に減ることはあっても、なくなってしまうことはないとうことです。自転車に乗ったり、水泳や掛け算九九も、一度できるようになったことは、全くできなくなってしまうことは、ほとんどありません。ちょっと努力すれば、すぐに元に戻ります。
4つ目は、大人の壺より子どもの壺の方がずっと小さいことです。大人になってから努力をしても、なかなか上達しないものです。子どもと大人が一緒に努力し始めたら、子どもの方がすぐに上達するのです。
どうですか・・・あなたの心の中の壺は、努力の水で満たされていますか。我が子に上手に話をして、子どもの「努力の壺」を刺激してみませんか。まぁ~子どももそれぞれですので、効果がなかったら、他の言葉を考えてくださいね。
2024年
5月
26日
日
和ろうそくの魅力
今日は、6月1日に親子遠足で訪問する「埼玉県立 川の博物館」に打合せで行ってきました。天気予報は、今のところ快晴ではありませんが、台風は、関東の太平洋上を通過していると思われますので、お日様の下で遊びたいですね。目玉の「水上アスレチック」は、今日も親子で大賑わいです。チケットも完売するほどの大人気コーナーになっています。詳しい話は、当日のお楽しみです。
さて、今日は「和ろうそく」の話です。一般的に、洋ロウソクが石油系の原料と糸でできた芯で細い灯りになるのに対し、和ろうそくは、櫨(はぜ)などの植物性の原料が主体で、芯に和紙を使います。よく、観光土産で、美しい絵が描かれた和ろうそくを見ることがありますね。
琵琶湖を見渡す、滋賀県にある、和ろうそくの大與(だいよう)の4代目、大西巧(さとし)さんは、「国産・天然の植物100%」のみを扱います。生活様式の変化で従来の需要は減り続けます。2011年には、「お米のろうそく」で、グッドデザイン特別賞を受賞します。関心を呼ぶものの、主な取引先であるお寺での需要が減っていきます。和ろうそくではなく、価格の安い洋ロウソクに切り替えていくのです。
そこで、大西さんは、思い切って海外市場に打って出ます。「夢あるやん、行け!」と3代目の猛反対の中、弟が背中を押します。2019年に渡米し、10日間の営業ツアーで、日本での一年分を売上げたのです。素材を生かした風合いが受け入れられ、欧米風のインテリア雑貨店を中心に取引が増えたそうです。
「私たちが作る和ろうそくの哲学に共感してもらえたと思います。地下から掘り起こす化石燃料ではなく、地上にあるものを原料にすれば、営みに無理がない。そんな価値観を分かち合えた」と大西さんは言います。
もちろん、洋ロウソクと比較すると、和ろうそくは価格が高いです。家庭で使うタイプでも1本300円以上はします。和ろうそくは、ろうが垂れることや油煙をほぼ発生させません。そして、匂いもほとんどないそうです。我が家には、仏壇がありますので、一度和ろうそくを灯したいと思っています。みなさんも、少し「和ろうそく」を気にしてみてください。
2024年
5月
25日
土
学習障害への合理的配慮
今日は、久しぶりに小学生女子と年長女子が、ローラーブレードを楽しみました。一番得意な子が、どんどん先に進んでいきます。「みんな~おそいよ!」と言うと、「これ以上スピード出したら転んじゃうから」と、自分のペースを守る女子です。子どもは、たいがい無謀な挑戦をしてしまうことが多いですが、冷静な女の子に アッパレです。
さて、新年度がスタートして2か月が過ぎようとしています。特に1年生にとっては、初めての小学校生活で、得意なことも苦手なことも見えてきます。発達障害の中でも、自閉症スペクトラム障害や注意欠如多動性障害などは、子どもの行動から判断できることが多いですが、発達障害の一つである「学習障害」については、小学生になって、実際に授業が始まってから目立ってきます。
黒板の字を読むのが苦手。ノートに字を書くのが苦手。算数の計算が苦手。もちろん、単に子どもが不得意な分野であることが多いですが、読み書きや計算など、能力のごく一部だけが極端に苦手な場合は、学習障害の可能性があります。
例えば、A君は字を書くのが苦手でした。幼稚園の頃から、字が裏返しになるなど正確に書けません。小学校入学後には、黒板の文字をノートに写せない、ひらがなが正確に書けないなど、しんどい時間を過ごすことになりました。A君は、知的発達に遅れはなく、幼稚園までは元気に普通に過ごしてきたそうです。お母さんが持参したノートや授業での経過から学習障害である「書字障害」と診断されました。A君の担任は、黒板を写さなくてもいいようにプリントを用意するなど工夫してくれて、A君は楽しく登校できているようです。
この担任のように、工夫して支援することを「合理的配慮」といいます。車椅子の方のための段差解消、難聴の方に伝わりやすくするための工夫など、令和の現代は、様々な場所で「合理的配慮」が進んでいます。この4月からは、民間企業や私立校でも、障害者差別解消法で、合理的配慮が義務付けられています。
学習障害の場合、子どもの「苦手」は治せません。「苦手」に合わせた対応が必要になるのです。これからの世の中が、「合理的配慮」の和で広がるとうれしいですね。
今と比較して、昭和の駅のホームにはあるものがありません。何だと思いますか。それは、黄色の点字ブロックです。今では、当たり前に駅のホームに張りめぐされていますが、つい昔は、合理的配慮はなかったのです。
2024年
5月
24日
金
インティマシー・コーディネーターという仕事
今日は体操教室です。年少園児たちは、ようやく自分で着替えて、水筒を飲めるようになってきました。まだまだ動きは、ヘロヘロで、よく転びますが、「慣れる」ことも成長の一つですね。体操教室の前に、運動会で行う組体操の練習から始めます。「ブリッジ」もずいぶんと様になってきました。こちらは、練習あるのみです。(笑)
さて、今日は、あまり聞き慣れない「インティマシー・コーディネーター(IC)」という仕事についての話です。知っていますか。この仕事は、決してAIに奪われない、ヒトでしかできない仕事です。そして、日本には、この仕事を行っている人は、たった二人しかいません。
映画やドラマの撮影現場で性的な描写やヌードシーンなどにおいて、俳優の同意を取りながら、監督の意向を聞き、制作を円滑に進める調整役です。私は、こんな仕事があることなど知りませんでした。
アメリカなどでは、新人俳優など現場での力が弱い人間が、監督などに、無理やり意にそぐわないシーンを強要されることがありました。2017年にはアメリカで、MeToo運動として、主に女優の側から、性的シーンの撮影における安全確保を求める声が世界的に広がりました。そんな中で、インティマシー・コーディネーターという仕事が生まれたのです。まだ最近誕生した新しい仕事と言えます。
日本に2人いる1人の西山ももこさんは、「ICは、俳優を守る『正義の味方』というイメージで見られがちですが、私たちはあくまでも撮影が安全に行われるための調整役。正義の味方でもないんです」と語ります。西山さんがICの資格を取得したのは、2020年ですので、まだ4年前です。
西山さんは続けます。「私は、映画などに性表現がない方がいいとは思いません。そこに意図や必要性があれば肯定します。だからこそ、だれかの犠牲の上に作品を作ってはいけないのです。俳優、監督、スタッフ全員が安全に良い作品を作るために調整をします」
「ノーという勇気」もギャラの交渉さえも、西山さんは俳優たちのために、調整能力を発揮するのです。
もちろん、現在つくられているすべての映画に、インティマシー・コーディネーターが、配置されているわけではありません。でも、必要な仕事であることには変わりありませんね。かつて、俳優志望の後輩に、「役において、脱ぐシーンがあってもやるのか?」と聞いたことがあるのですが、「ストーリーに必然性があれば、脱ぎます」と答えたのです。俳優・芸能の世界は、私の知らないことが多いので何とも言えませんが、今日は、インティマシー・コーディネーターという仕事の存在だけは覚えてください。
2024年
5月
23日
木
家庭菜園で癒される
今日は、屋上ファームで、チビちゃんたちをメインに、インゲン豆の種をまきました。先日の寺子屋では、「そらいろのたねをまくよ!」と言っても園児たちは信じてくれませんでしたが、チビちゃんたちは、「やった!おうちが、はえてくるかもしれないね」なんて、かわいいことを言っています。
こんな感じで、保育園の子どもたちは、いつも遊んでいる屋上にファームがあるので、野菜にかかわる生活を当たり前に経験しています。そんなこともあって、おうちで、家庭菜園をする家族が多いです。連絡ノートにも、「○○を収穫しました」というコメントをよく見かけます。
とうことで、今日は家庭菜園の話です。近ごろ、家庭菜園に興味を持つ女性が増えているようです。男の場合は、なぜか「畑仕事」というイメージですが、女性だと「家庭菜園」という言い方になるのは、不思議ですね。(笑)
家庭菜園は、一戸建てなら庭で、マンションならベランダでプランターだってできます。市民農園のような場所も、最近は増えてきました。行政が管轄する農園なら、年間でも1万円かからないくらいで借りられます。
週末は農園中心という独身OLは、遊びに誘われても、畑仕事を終わらせてから合流するそうです。「うちの子かわいいでしょ」と、収穫した野菜を仲間におすそ分けです。もちろん、家庭菜園は思い通りにならないこともあります。芽が出なかったり、突然枯れたり病気になったりします。家庭菜園の先輩にアドバイスをもらいながらコミュニケーションも図れますね。台風や大雨の時は気が気でなくなります。例えば、夏野菜の代表「トマト」は、1本の茎を成長させるために、枝芽を欠く作業が必要になります。保育園の屋上ファームでも1日何もしないと、枝芽がたくさん出てきます。週末作業だと、半日はこんな作業で時間が流れます。でも、「手間暇をかけた分だけ成果が見えます。私にとって、最高の癒しです」と、独身OLにとっては、極上の時間になっているようです。
東京都心でも仕事帰りに立ち寄れる農園もあります。お台場の「ダイバーシティ東京プラザ」の屋上は貸農園になっています。値段は、1区画(3平方メートル)で、月額1万円と、かなり割高ですが、レインボーブリッジを見ながらの畑仕事なんて・・・最高ですね。
「土をいじり、作物を収穫する」ことは、農耕民族のDNAを持つ、人間にとって、プラスのスイッチが入ることは間違いないでしょうが、現代社会のストレスからも回避できて、癒される時間になっているのです。一人でも農園で多くの人と出会うことができるし、ファミリーなら最高の時間です。
さて、「タキイ種苗」が20歳以上の600人にネットアンケートを行った結果、「家庭菜園で野菜などを作っていますか?」の問いに、規模の大小はある者の、21.8%もの人が家庭菜園を行っているとの結果が出ました。私は、正直多いと思いました。
家庭菜園用のコスチュームもどんどんオシャレになっていますね。自分の時間や趣味を大切にするライフスタイルの中に、「家庭菜園」は、堂々の上位ランクインですね。
2024年
5月
22日
水
わくわく教室でおにぎり作りました
毎日、何かしら、明るいニュースが流れるように、暗いニュースもテレビをつければ、子どもの目に入ります。「暗いニュース、子どもに見せる?」のアンケート調査では、「見せる」「見せない」「どちらとも言えない」が、それぞれ1/3ずつに分かれるようです。
見せる派は、「特に子ども関連の事件や事故などは、あえて見せて説明して危険回避を教える」「子どもが疑問に思ったことは、親の考えや事実を正直に伝えた方が子どものためになる」。見せない派は、「世界が怖いものだと植え付ける可能性があるので、知るのはまだ早い」「戦争などはまだ理解できず、戦いごっこのネタになるだけだから」「地震などの災害は、トラウマになりやすいから」。
親の考え方や、子どもの性格で対応は変わるのでしょうが、親子の会話のきっかけになり、子どもが自分で考えることにつながるように、親は持っていきたいですね。
さて、今日は、年長園児8人が、「わくわく教室」で学び合いました。今回は「米について学び、おにぎりを自分たちで作る」です。歩いてすぐの公民館のキッチンに向かう年長園児たち・・・「やった!今日はわくわく教室だ!」と歓喜するものの、具体的に何をするのか、説明できる園児は数人です。(笑)
かっぽう着姿になり、手を洗って、「わくわく教室」がスタートしました。稲が大きくなって、米が収穫できる流れを本で学びます。実際に稲穂から1粒の米をちぎって、もみ殻を手ではがして、玄米にしてみます。5歳男の子は「何だか、茶色っぽくて、おうちの米と色が違う」ことに気がつきました。なかなかの観察眼です。
米を研ぐという言葉も覚えました。最初のとぎ水は、牛乳みたいに白かったのに、4回目は、普通の水に近くなってきました。子どもたちは、おうちでも、米を研ぐところから手伝いをすることでしょう。そして、耐熱ガラスの鍋で10分間中火でお米の様子を観察します。鍋の底からブクブクと泡が出てきて、米が踊り出します。ごはんの匂いがしてきました。そして、泡が鍋の上までモクモクと上がってきます。火を弱火にしてさらに10分、最後は蒸らしてごはんが炊きあがりました。おうちでは、炊飯器でご飯を炊くので、中の様子がわかりませんが、今日は、ガラスの鍋なのでまる見えです。
そして、いよいよ、子どもたちのおにぎり作りです。おかか醤油おにぎりは、三角おにぎりにします。鮭おにぎりは、のりを使って、自分が作りたい、自由作品としました。ハート形のおにぎりがあったり、海苔をちぎって顔にする園児たち。「何を作ったのか、わからなくなっちゃった」という園児もいました。もちろん、自分で作ったおにぎりを「いただきます!」です。あっという間に完食でした。
6月1日の親子遠足と11日のお菓子工場見学では、年長園児は自分でおにぎりを作ってくることでしょう。今日も、子どもたちの「わくわく」を大いに引き出すことができました。最後に、「ママやパパに伝えたいこと」を一人一人話してもらいます。「おにぎりを自分で作ったことが楽しかった」「米を研ぐのが、初めてで楽しかった」「鍋の中でお米がいい匂いだった」などなど・・・今日は、お米のこと・ごはんのこと・おにぎりのこと・・・など、会話が弾むことでしょう。
しばらくは、ママの料理のお手伝いが続きそうです。(笑)
2024年
5月
21日
火
宿題って必要? ②
今日は朝から快晴です。いつもよりも少し早く屋上遊びを始めました。桑の木のまわりには子どもたちが集まり、マルベリーのつまみ食いが始まりました。令和の時代には、あまり見られないワイルドな光景です。そして、カメ池では、今シーズン初めての「卵」を採集しました。4つの卵を飼育ケースに入れて、子どもたちと観察します。この卵は、ニホンイシガメかクサガメか、それともイシガメクサガメハーフのウンキュウか・・・楽しみです。赤ちゃんガメ誕生は2か月後です。
さて、宿題って必要?2日目は、宿題不要派の意見を中心に聞いてもらいます。東京都庁そばの新宿区立西新宿小学校は、全学年で、毎日の宿題を昨年春から「原則なし」にしました。夏休みの読書感想文も自由研究も一律には求めていないそうです。長井校長の考えは、「児童それぞれの学習の進み度合いを踏まえず、単に計算ドリルや漢字練習を一律に課すことに疑問を感じていました。児童自身が『自分に必要なことだ』と思えない宿題では、効率は得られない」とのことです。
もちろん、西新宿小学校では、宿題なしのほったらかしではありません。「自学ノート」という取り組みを行っており、児童が自分でテーマを考えて調べたことをまとめ、先生に見せるのです。例えば、社会の授業をきっかけに中東情勢に興味を持ち、新聞記事を切り抜いて感想を書いたり、自学ノートに「長い国名」ランキングをまとめて先生に提出する児童があったそうです。ある保護者は、「宿題がないことが、興味を持ったことを掘り下げたり、遊びの中にも勉強の芽があることに気づいたりする良いきっかけにもなっています」と言います。
こうした、「宿題をなくす学校」は、各地で増えているそうです。長崎市立長崎中学校は、2022年度から一律の宿題をやめ、生徒本人が決めた内容で家庭学習に取り組んでいます。山形県新庄市や岐阜県でも自主学習に転換する動きがあるようです。
そもそも、日本での宿題の始まりは、近代的な学校の整備が進んだ、明治時代の1900年代初頭とされています。「音読・漢字・計算ドリル」といった宿題は、日本の学校教育の習慣として、根付いてしまったようです。昭和の頃は、「宿題って必要?」なんて、思う人などほとんどいなかったのかもしれませんね。
令和の今、改めて聞きますが、あなたは「宿題は必要だと思いますか?それとも、なくした方がいいですか?」
私が考えるには、夏休みの自由研究などを除いて、毎日出されるような日本の宿題の多くは、「認知能力」という、学習能力を高める内容です。これには、どうしても個人差があって、一律の宿題では、問題が発生します。ところが、自分で考える課題は「非認知能力」を高める内容です。自主性が問われるのです。
宿題がどうのこうの前に、「子どもたちに必要な学力は?」を考えると、非認知能力の割合が今後高くなっていきます。そうであれば、宿題という言い方が適切かはわかりませんが、「自分で考える」「仲間と協力する」課題をこれからは多くしていかなければならないと思います。
「従来の習慣化した宿題からの脱却・・・そして、子どもたちが自分で考える新たな課題への変換・・・」これで、決まりでしょ。
2024年
5月
20日
月
宿題って必要? ①
今日は雨になってしまったので、教室内でプチ体操教室です。サッカーのドリブル・マット運動・とび箱・鉄棒など、しっかりと体を動かしました。雨の日は屋上遊びができないので、お昼寝タイムに熟睡できるように、運動のプログラムが多くなります。
さて、私が小・中学生の頃は、宿題は、ほぼ毎日出ていた記憶があります。そして、宿題を忘れようものなら、先生からきつく叱られました。今でも、ある調査では、毎日宿題を出す小学校教員の割合は90%以上もありますが、どうやら、「宿題なし」の学校が増えつつあるようです。そこで、今日・明日は、「宿題って必要?」について考えます。
今日は、「宿題賛成派」の意見を中心に取り上げます。学校のカリキュラムを定めた小学校向けの「学習指導要領」には、「家庭との連携を図りながら、児童の学習習慣が確立するよう配慮する」とう記載はありますが、「宿題」という言葉はありません。中学校向けも同様です。宿題を出す出さないは、実は学校の判断に委ねられています。
昨年8月、高松市議会に「宿題の原則廃止」を求める陳情が提出されました。ところが、賛成は、市議40人中1人にとどまり、不採択となりました。高松市の教育委員会は「学習習慣を作る」といった面で、宿題は有効だとしています。
では、子どもたちの意見はどうでしょうか。放課後に教室を開放している埼玉県新座市の小学校で話を聞くと、「面倒くさいけど、将来の役に立つ。算数の問題がすらすら解けるようになった時はうれしかった」「宿題がないと、ユーチューブを見たり、ゲームをしたりしてしまう」という声が聞こえてきました。
教員の意見は、「子どもに学習内容を定着させるには、何回も反復させることが大事。家庭でその機会を作る宿題の役割は大きい」「塾や通信教育で勉強させる家庭もあれば、その余裕がない家庭もある現実を見てきた。宿題は、全員に平等に勉強させることがでる。生きていくのに不可欠な学力を下支えする面もある」といったところです。
う~ん・・・ここまでの意見は、おっしゃる通りの内容ですね。宿題をなくして、子どもたちの自主性を伸ばすような取り組みだって、あるはずでは・・・
明日は、宿題不要派の意見を考えることにします。
2024年
5月
19日
日
ウォーターボーイズ
誰もやってこなかったことを周囲の困難を克服してやり遂げるというストーリーは、たまらなく大好きな私です。埼玉県立川越高校の文化祭では、何万人もの観客を魅了する、今も続く「ウォーターボーイズ」は、1986年に初めて披露されました。
当時3年生で水泳部員だった、現在は55歳の北川さんは、引退した7月下旬に仲間に呼びかけます。「シンクロやろうぜ!」。3年生11人のうち、北川さんの他に5人が賛同しました。しかし、文化祭当日は、1・2年生が試合で、「水泳部は活動なし」と学校には伝えていたそうです。今からの申請は、通らないと諦め、6人は「ゲリラ的に決行するしかない」と決断したのです。
カーン、カーン、カーン・・・部員の一人が演技を告げる鐘を鳴らしました。「何が起きるんだ」来場者たちが、プールの横にある4階建ての校舎の窓から、一斉に顔を出します。それを合図に、北川さんは、仲間とプールサイドの真ん中に駆け出し、一列に並びます。女子の水着に似せようと、上半身はタンクトップ姿。「始めます」と叫ぶと、水中へと飛び込みます。
6人は水面に浮き、プールに円を描く。水中で声を出しながら足を上げ、手をそろえて踊った。最期は3段ピラミッドの一番上の部員が、後方宙返りで締めくくった。歓声がプールにも届く。「みんなで心を通わせて一つのことをやり遂げ、誰かに喜んでもらうことの素晴らしさを知った」と北川さんは語ります。
ゲリラ公演は大成功し、2年後には水泳部が正式な企画として始めた文化祭限定の「男のシンクロ」は、川越高の名物になっていったのです。それから10年が過ぎた1999年、当時の部長畠山さんは、「おれたちの代で大きなことをやろう」とテレビ番組に電話をかけると、報道番組「ニュースステーション」で取り上げてくれることになったのです。
そして、ついに「ウォーターボーイズ」は、2001年9月に映画化されました。そして、大ヒットしたのは、まだ記憶に新しいところですね。畠山さんは、俳優たちに演技指導をする大役を任されたのです。
ゲリラ公演を行って「男のシンクロ」を初めて行った北川さんは、大手出版社の「小学館」に入社し、「図鑑NEO」シリーズの編集を行い、大ヒット図鑑にしました。「新しいものを取り入れなければ意味がない」という気持ちだったそうです。
そして、映画化につながった畠山さんは、2浪して歯学部に入学します。現在は親知らずの抜歯に特化したクリニックを開いたそうです。2か月先まで予約が埋まっている人気だそうです。
どうも、この二人には、「新しいことを考え、誰もやっていないことに挑戦する精神は、水泳部で学んだ私の原点」という思いがあるようです。こんな話を聞くと、保育園の子どもたちには、こんな生き方をしてもらいたいなぁ~と、思ってしまう私です。
2024年
5月
18日
土
寝台列車は必要です!
今日は、小学生が7人も集合です。屋上では、マルベリーの実をずっと採っていました。「これ、午後のおやつで食べるんだ!」と、ザルにいっぱい収穫してくれました。木に登り、収穫したマルベリーをきちんと洗うまで、自分たちでやり遂げます。さすが、小学生ですね。
さて、昨日のブログでは「リニア新幹線」の話をしましたが、今日は対極にある「寝台列車」についてです。まずは、寝台列車と聞いて、何をイメージしますか。まずは、1988年に青函トンネルが開通して、飛行機を使用しない北海道への観光需要が高まるとみて、上野-札幌間で「北斗星」・大阪-札幌間で「トワイライトエクスプレス」が相次いで導入されました。北斗星では、すでに斜陽になっていた食堂車をつないで、フランス料理のフルコースを提供しました。豪華個室寝台を連結するなどして、鉄道での移動そのものを旅として楽しんでもらう発想が、ヒットにつながりました。「北斗星」も「トワイライトエクスプレス」も豪華な「カシオペア」も廃止されてしまいますが、今でも「JR九州のななつ星」「JR東日本の四季島」「JR西日本の瑞風」らの不定期の豪華列車に引き継がれています。今でも平均倍率が14倍だそうで、なかなか予約ができない人気列車です。
では、ここで問題です。現在、唯一定期運行を続ける寝台特急は何でしょうか?それは、1998年に運行開始となった「サンライズ瀬戸・出雲」です。東京駅を一緒に出発しますが、岡山で車両が切り離されて、四国の高松と山陰の出雲に向かいます。今でも、週末は予約が取りづらい列車です。
国鉄時代の話ですが、「ブルートレイン」という言葉を聞いたことがありますか。東京から九州を結ぶ「あさかぜ」が有名ですが、専用の20系客車を製造し、編成を固定し、冷暖房を完備、窓を閉め切ることで騒音を低減、空気ばね台車で振動も抑える車両は、またたくまに大人気となりました。私も父の実家が福岡県でしたので、「はやぶさ号」に小学生の頃に乗りました。廊下通路に折りたたみイスで、ずっと車窓を眺めていました。わくわくして、眠れなかった記憶があります。しかし、ブルートレインの全盛期は長く続かず、新幹線が博多まで伸び、飛行機との競合もあり、2005年の「あさかぜ」がラストランとなりました。
世の中が、タイパ(時間対効果)を求める風潮が高くなり、夜通し、時間をかけて移動する寝台列車は減ってしまいました。しかし、旅行というものが、「非日常」の頂点とするならば、「寝台特急」「夜行列車」での旅は、「非日常」のもっとも大きな演出効果となることは間違いありません。
旅のスタイルが、さらに多様化していく今後・・・やっぱり「寝台列車」は、必要です。こう思うのは、私だけではありませんよ!個人的には、豪華寝台特急でない、座席タイプの夜行列車の復活を願う私です。上野ー青森間を走っていた夜行急行列車は、私が学生の頃には3本もありました。「八甲田(東北本線経由)」「十和田(常磐線経由)」「津軽(奥羽線経由)」・・・なんかが復活したら、たまらんのです。(笑)
2024年
5月
17日
金
リニアモーターカーって本当に必要!?
今日から、体操教室の前に、教室内で「運動会の組体操」の練習をスタートさせました。年長・年中園児は、すでに経験していますが、年少園児にとっては、「組体操」は、高い壁です。今日は、「かかし」→「飛行機」→「ヨット」→「ブリッジ」の4つだけですが、グダグダです。先輩たちにお手本を見せてもらって、フォローしてもらって、少しだけ、形になった感じです。まだ先は長いので、あせらずに、じっくりと教えていきます。
さて、リニア新幹線で、岐阜県内の14か所の水源で、井戸などの水位低下が起こり、いったん工事を中断したというニュースが入ってきました。これで、また開業日が延びてしまうのかと少し残念な気持ちになった人が多かったと思います。もっと言えば、静岡県内の工事をストップさせていた、静岡県の川勝知事が突然の辞職を表明したので、「これで、早期開業に弾みがついた!当初予定の2027年品川ー名古屋間開業は、JR東海は断念したけど、2030年くらいには何とかなるのでは・・・」と思ったのも、つかの間です。
リニアモーターカーに関しては、私がまだ子どもの頃から、ずっと話題になっていて「夢の超特急」という、プラスのイメージばかりが私の頭にはインプットされてきました。リニア構想は、私が生まれる前の1962年(昭和37年)に、東京ー大阪間を1時間以内で結ぶ超高速鉄道をつくるというビジョンから始まります。最初の東京オリンピックが行われた昭和39年に、同じく東海道新幹線が開業したので、リニアモーターカーは、新幹線開業の2年前には、構想があったことになります。
1979年(昭和54年)に、初の実験車両が走り、無人走行で517キロを記録し、世界最速の記録を出しました。それから、何度も試験運転が繰り返されたのです。何度も、実験が行われ、その映像を見てきましたが、いつの間にか「いつになったらできるんだよ!」という感じにもなりましたね。1962年の構想から、当初予定していた2027年に開業したとしても、65年もかかったことになります。どれだけの、時間と金が動いたことか。
東京ー名古屋間を40分、将来は東京ー大阪間を67分で結ぶ、時速500キロの超特急です。リニア新幹線が開業すると「首都圏・中京圏・近畿圏の三大都市圏が一つの巨大都市圏となり、人と人とが会うことで新たなイノベーションが生み出され、余暇の過ごし方などライフスタイルの変化を通じて豊かで多様な暮らしを実現するなど、新たな可能性が生まれる」と考えられます。JR東海が自費でリニアを建設するので、「民営」ではあるものの、リニア新幹線は国策であることは間違いないです。
私たち国民は、リニアからは「夢」のイメージが強く与えられますが、コロナ禍が終わり、国民の価値観も変わりました。ここにきて、「負」の側面も含めて、きちんと議論すべきではないかという考えが大きくなってきたようです。環境問題は、やはり、ないがしろにされてる部分が多いのです。
私は、鉄道に乗るのが大好きですので、リニア新幹線が具体化した時は、胸が躍りました。しかし、品川ー名古屋間286キロのうち、約86%がトンネルであることがわかって、「なんだよ!リニアは地下鉄で車窓を楽しむことができないじゃないか!」と、急に気持ちがさめてしまいました。旅をするなら、富士山を見ながら、普通の新幹線か東海道線でのんびりがいいと思っています。
「国」の立場は、もう後戻りできない!かもしれませんが、もう一度「リニアモーターカーって本当に必要?」を議論するべきなのかもしれません。
2024年
5月
16日
木
日本一来館者数の多い図書館
マルベリー(桑の実)のつまみ食いが、激しくなってきました。木に登って、他の園児が届かない場所で、むさぼり食べる5歳男の子。どろんこ広場にある桑の木は、小さいのに枝にびっしりと実がついています。高い所にある枝を切って子どもたちに渡すと、原始時代のヒトが、木の実に集まるような、そんな光景に映ります。そして、体長10センチほどのヒヨドリもマルベリーを食べています。鳥たちも、ここは、しっかりと栄養を取っているようです。
さて、昨日は午前中には保育園を抜けて、勤務していた会社のOB総会に出席しました。司会進行が私の仕事です。元日に能登半島地震が起きた、石川県金沢市から参加した方の話を聞くことができました。震災の生々しい話と、インバウンドで外国人観光客が激増している話です。テレビでは、円安を反映して、箱根の高級ホテルに泊まり、ランチを貸し切りする豪華な旅行を楽しむ外国人を取り上げますが、現実は、どうも違うようです。金沢駅から兼六園までは、3キロほど離れているので、通常はバスかタクシーを利用するのですが、外国人は、大きなリュックサックを背負って、歩くのだそうです。タクシーなんてとんでもなくて、バスにも乗らないのです。白人系の外国人は、お土産の爆買いなど全くありません。
今日は、そんな金沢市にある「石川県立図書館」の話です。2022年7月に、香林坊という金沢の中心街からバスで20分ほど離れたところに、移転オープンしました。何と、この図書館の2023年度来館者数は、102万6046人です。1日ざっと3000人近くの人が訪れる計算です。今まで1位だった岡山県立図書館が、年間80万人弱ですので、ダントツで、日本一来館者数の多い図書館となりました。
日本の図書館の99%が、「日本十進分類法(にほんじっしんぶんるいほう)」という、0から9までのアラビア数字のみを用い、大まかな分類から細かい分類へと、順次10ずつの校も項目に細分していく手法で、書籍が並んでいます。例えば、「文学」は「9xx」→「日本文学」は、「91x」→「(日本文学の)小説・物語」は「913」といった感じです。図書館の棚に、こうして数字が書かれているのを見たことがありますね。
しかし、石川県立図書館は、「子どもを育てる」「仕事を考える」「生き方に学ぶ」「本の歴史を巡る」「暮らしを広げる」等々の12のテーマ別にブロックが分けられて、多くの本が面で並んでいます。
管理する側の都合では、日本十進分類法が一番適していますが、読む側に立てば、石川県立図書館の分類の方が、分かりやすくて、本を探す楽しみが増えますね。よく、本屋さんが「イベントコーナー」を作って、推しの本を紹介するような感じです。
そして、驚くことに、こんなサインがガラス窓に次々と投影されます。「記念撮影はお好きな場所で」「閲覧エリアは、ふた付の飲み物持ち込みOK」「おしゃべりOK」「お食事は文化交流エリアで」
どうですか・・・図書館では、おしゃべりをしていると、しーっと注意される場所だったはずなのに・・・今までの図書館の概念が吹っ飛びそうです。
まだまだあります。モノづくり体験スペースには3DプリンターやUV印刷機などがあり、たとえば、新商品の試作品をつくることができます。月に1回、無料で30分のミニコンサートを「だんだん広場」で開いているそうです。オーケストラにとっては、有料の公演に呼び込むきっかけになるようです。
「調べものデスク」という窓口があり、利用者の相談にのり、課題の解決に導くという場所もあります。
私は、石川県立図書館に行ったことはありませんが、これ以外にももっとわくわくするような仕掛けがたくさんあるのでしょう。保育園では、子どもと図書館で本を借りるライフスタイルのママが何人かいますが、こんな図書館が増えていったら、一日中過ごしても飽きないですね。
「子どもに本をたくさん読ませたい」のきっかけになる図書館が、こんな感じで変わっていくのはうれしいですね。
2024年
5月
15日
水
2050年の日本の姿②
昨日の寺子屋では、保育園で飼っている「カブトムシの幼虫」の観察をしました。15匹いるのですが、7月には成虫になります。サナギになる前の、最後の幼虫です。4歳の女の子に「幼虫のお腹にある黒い点は何?」と質問されました。調べてみると、この黒い点々があるのがオスで無いのがメスだそうです。私は、幼虫ではオスメスの区別はつかないと思っていましたが、この黒点でわかるようです。子どもの観察眼は大したものです。
さて、昨日のブログで2050年の日本は、ドラえもんのような世界になっていると言いましたが、今日は、現実的な話です。
都市への人口集中、地方の過疎化問題は、日本の大きな問題ですが、2045年には、東京の人口が減少に転じると言われています。国民は、天災への備えを真剣に考えるようになってきます。南海トラフトや首都直下型といった大地震も予想される中、人口も政治機能も一極集中している東京が被災したらどうなるのか。物流は途絶え、食料や生活用品を確保できなくなる。ひょっとしたら、政府が機能するかもあやしい。その混乱は、これまでの震災の比ではない。そう語るのは、東京大学の養老(ようろう)名誉教授です。
彼は、2050年には、都市への人口集中が解消され、人々が地域ごとに食糧やエネルギーを自給自足して暮らすような、日本の望ましい姿になっているのでは・・・と言います。
「自活する力が重要になる。都会的なシステムに依存せず、自分と身の回りの人で、食糧やエネルギーを自給自足しながら生活を持続させる。文化人類学では、あり合わせのもので、上手にやりくりすることを『ブリコラージュ』というが、その実現が個々に求められる。一つ一つの地域も、そんな生活に見合う、小さなサイズが適切だ。テクノロジーの進化が様々な問題を解決するはずだという話はよく聞く。しかし、物事には必ず両面がある。何かが解決され、楽になることは、何かを考えなくなることでもある」
養老教授は、合理性、経済性、生産性を追求してきた時代とは、まったく逆の方向に進んでいくはずだ。と語ります。一人一人が実感を持ち、暮らしを足元から積み上げていく。それぞれが自活し、居心地の良い日常を送れるようになれば、未来は平和だと言います。
どうですか・・・ドラえもんの世界もいいですが、「幸福な人生」という観点で考えると、私は、こちらの未来に魅力を感じます。みなさんが望む2050年は、どんな日本になっていると思いますか。
2024年
5月
14日
火
2050年の日本の姿①
今日は、晴天で屋上遊びができました。子どもたちは、すぐに「桑の木」のまわりに集まります。目的は、桑の実(マルベリー)を食べることです。年長園児は、自分で赤黒く熟した実を食べています。小さい子は、職員からもらいます。「桑の実をむさぼり食べる子どもたち・・・」とっても、ワイルドです。(笑)
今日は、見学に来ていたママがいたのですが、桑の実の説明を園長がしていると、年長の男の子が、そのママに「マルベリーだよ。食べていいよ」と渡したのです。なんと、優しくて、気遣いのある対応に、感動する園長です。
さて、今日は2050年の日本がどうなっているか?の未来予想です。今から26年後なんて、近い未来と考える人も多いでしょうが、ズバリ当てるのは、難しいですね。人間は、今から100年前に飛行機を開発し、空を飛び始めました。今では、世界中を飛び回り、ロケットで宇宙にも行っています。人間が想像できることで、実現できないことはないと言われていますので、100年後にはタイムマシンができてもおかしくありませんね。
社会を変えるような技術革新を目指す国の大型プロジェクト「内閣府ムーンショット」で、広報を担当する村木さんの話では、2050年は、「ドラえもんの世界になっているかもしれない」そうです。ドラえもんが持ち込んだ、22世紀の技術の多くは実現しているのではないか。と言います。
自宅にある3Dプリンターでボタンを押せばおいしい料理ができるとか、自動車の自動運転が当たり前になり、料理、運転、掃除などは、もはや趣味になっているのかもしれません。仕事の多くはロボットが代替できるようになっていて、人間はもっとクリエイティブで、本当にやりたいことに専念するようになる。複数の職業を持つことも可能になっていく。
もちろん、変えたくないことは、そのまま残ると考えられ、紙の書籍だったり、リモートワークが増えても、人と直接会う機会は大きくは減らない。いわば、人間くさいところは残っていくのでは・・・。いずれにしても、2050年には、生活のために、面倒なことや気が乗らないことをする必要はなくなっているのではないか。好きなことを追求でき、心の余裕が増える世の中が実現しているのでは・・・と村木さんは言います。
1555年、今から400年以上前に、ノストラダムスが「1999年7月に人類が滅亡する」と予言しました。日本でも、大ブームになりましたね。ちょうど、公害などの環境問題が日本で多発したこともあって、私も、少しは不安にかられ、1999年の8月になって、ホッとした記憶があります。
ドラえもんの世界・・・大いに結構。未来は明るくと信じていきたいですね。2050年、日本の若者が自尊心や誇りを持ち、その先も明るい将来を描いて暮らせる国になって欲しいものです。
2024年
5月
13日
月
ハラスメントの境界線
今日の連絡ノートには、土曜日の保育参観の感想がびっしりと書かれていました。ふだん子どもたちが、どんな風に屋上遊びをしているのかが分かり、一緒に遊べて楽しかったことと、防災の話も大いにためになったようです。親子で収穫したタマネギでジンギスカンを楽しんだファミリーもありました。
ジンギスカンといえば、羊の肉を食べますが、1歳未満をラム肉と言い、1歳以上をマトンと呼びます。今、日本中の動物園では、羊の毛刈りが行われています。毛がなくなった羊は、まるでヤギのようですね。羊は、毛を取るために家畜化された動物なので、人が刈ってあげないと一生伸び続けてしまうのです。今、毛を刈るのは、熱中症対策だそうです。
そして、もう一つ「食べ物」の話ですが、昨日のブログで紹介した「男気トマト」。桶川まで行って買ってきました。家にあったトマトと食べ比べると、とても濃い味がします。様々なメディアで取り上げられるだけありますね。
さて、今日の話は「ハラスメント」です。私が大好きだったドラマ「不適切にもほどがある」にでてくるような、今では絶対NGがはびこっていた昭和。「セクハラ」という言葉がなかった時代。「歩くセクハラ」のようない人も、せいぜい「デリカシーのない人」で片付けられ、野放しになっていたことを考えると、ハラスメントに対する意識が高まったことは良いことだといえます。
また、「逆パワハラ」という言葉も生まれ、部下が自分の間違いを認められずに「自分が失敗した原因は、管理職や先輩が注意喚起してくれなかったからだ!」と捉えたり、上司から挑戦を促された時に「やりたくないことを強制的にやらされている」と訴えるケースもあるようです。
ここ数年の管理職向けの研修で重宝されてきたのが「ハラスメントで何がNGか」を伝授する内容だそうです。つまり、ハラスメントの境界線をさぐる内容ですね。でも、ちょっと待った!です。ハラスメントになるかどうかは、お互いの信頼関係で変わってくるのではないかと、昭和世代の私は思うわけで、一律の境界線など引けないでしょ・・・という見解です。
そんな感じですので、今はハラスメントに対して「回避的なマネジメント」に走る管理職が増えてきたそうです。「飲み会やランチに誘わない」「ミスをしても厳しく指導しない」「必要以上にコミュニケーションを取らない」「フィードバックはあまりしない」という上司と部下の距離を感じる職場になっているようです。
私がサラリーマン時代に管理職になったのは、平成になってからですが、部下の趣味や好みといった個人情報まで、頭の中には当たり前にインプットしていました。その理由は、コミュニケーションを図るためには、当然必要な情報と考えたからです。仕事以外の会話も重要であることは言うまでもありませんね。
これからの時代、ハラスメント回避で、さらに、上司と部下は表面上の付き合いになっていくのでしょうか。間違いなく言えるのは、リーダーシップによってすべてを解決するのではなく、チームのメンバーが主体的に行動するような組織が、これからの「組織のあり方」になっていくのでしょう。チームで解決するという思考を持った個々のスキルが問われるのです。
2024年
5月
12日
日
男気トマト
昨夜、北海道や東北の日本海側で、オーロラが見られたというニュースを見て、「えっ!日本でオーロラ見られるの?」と驚きです。詳しい説明はできませんが、太陽フレアが原因で、世界の多くの場所でオーロラ観測ができたそうです。私の友人から、北欧とアラスカで見たオーロラの画像を見せてもらったことがあります。今回日本で見えたオーロラは、えっ!?という感じで、私たちのイメージする映像ではなかったですが、胸が躍る出来事でしたね。
そして、昨日保育参観で親子で収穫した「タマネギ」を朝食でサラダにして食べました。赤タマネギです。奥様曰く、水にさらすと栄養が流れてしまうので、辛みが少ない新タマネギは、切った後に、空気に少し触れさせるだけで大丈夫とのこと。きざみ海苔をかけて、ポン酢で食べました。「うまい!辛くない!」で、朝から幸せです。(笑)
さて、今日の話は「男気トマト」です。埼玉県桶川市にある手島農園のトマトです。遊び心があるネーミングですが、ここのトマトは、水を与えないで栽培した濃厚トマトなのです。
ホワイトきゃんばすファームでも、先日24本のトマトの苗を植えましたが、もともとトマトの原産地は、南米アンデス山脈ですので、雨がほとんど降らない地域です。トマトは、水分を多く含むと、味が水っぽくなるといわれていますので、保育園でもなるべく水を与えないようにするのですが、晴天が続き、苗がシナっとなってしまうと、どうしても水やりをしてしまいます。
「男気トマト」は、種から苗の段階まで、少ない水で成長する力をつけさせようと、1日おちょこ1杯分の水だけで育てます。苗は夕方にはしおれ、夜露で明け方に回復するという繰り返しです。枯れるか、枯れないかギリギリを見極める栽培を1か月続けます。そして、一定の大きさまで育った後は、長期栽培用のハウスに植え替え、その後は水を一切与えずに育てるそうです。
トマトは、土や空気の中の水分をかき集めるようにして生きるそうです。そうやってつけた実は、格段に濃い味に仕上がります。「もう他のトマトは食べられない」「トマトが苦手な子どもが食べられた」という驚きの声が上がります。
手島農園も、「男気トマト」がブランドトマトとして確立するまでには、多くの苦難があったようです。「無料で商品を試食で使っても構わない」とスーパーに試食コーナーの設置をお願いして、お客様に食べてもらうことを実践してきました。
江戸時代から続く農家を2011年に継いだ11代目の手島孝明さんは、明治乳業で13年営業などの仕事を経験しました。そこで培った考え方が、既定路線の農業を改革する力になり、困難を乗り越えることができたのです。
これだけ、うんちくを語りながら、まだ、私は「男気トマト」を食べたことがありません。今日、桶川に買いに行こうかな。(笑)
2024年
5月
11日
土
令和6年度 保育参観
今日は、保育参観を行いました。今年度の新人園児8名のうち、体調不良などで、5人が欠席となってしまいましたが、保育園の中に、パパママ、おじいちゃんおばあちゃん、きょうだいと一緒なので、日常の保育園と違って、元気よく走りまわり、無駄な動きが多い子どもたちです。(笑)
保護者の自己紹介が終わると、今回は、「おうちで地震!どうする?」というタイトルで、東京消防庁に勤務するパパに話をしていただきました。「では、スペシャルゲストの登場です!」に、本物の制服姿のパパが登場したのです。教室内は、園児も保護者もどよめきます。「園長先生の発動を受けて、やってきました!」と、ちゃんと笑いをとります。大事なポイントは、いくつもあるのですが、一番印象に残ったのは、「子どもの名前を呼ばない」です。「○○ちゃん・・・大丈夫かい?」と声をかけると、子どもは、親の方へ移動してしまうので、地震が落ち着いたら、子どもの確認をするのがベストです。どうですか、親の気持ちとしては、いち早く子どもの名前を呼んでしまいますね。
そして、ママへのプレゼントは「ママありがとう!マグネット」です。冷蔵庫の扉で活躍しますが、子どもたちが、ママの顔を描いたので、世界で一つだけのプレゼントです。ママに抱きしめられて、濃厚な時間を過ごした子どもたちは、いよいよ屋上へGO!です。
今回は、屋上でいつも子どもたちがやっている遊びを親子で楽しみました。自転車に三輪車、タイヤアスレチックに砂遊び、しゃぼん玉、お絵かき、野球にドッジボール、カメのエサやりなどなど・・・保護者にとっては、連絡ノートに職員が書く遊びの内容が、よくわかったと思います。
親子レースも盛り上がりました。板の橋渡りと台車カートの親子競争です。寺子屋園児は、親を台車に乗せて、子どもが引っ張ります。この手のレースでは、必ず本気モードのパパママが現れます。(笑)
最後は、親子で玉ねぎの収穫を楽しみました。赤ちゃんの頭ぐらいのビッグタマネギが、ゴロゴロと収穫できました。赤タマネギもあるので、おいしいサラダが楽しめそうです。
しっかりと2時間・・・親子で、保育園の日常を楽しんでもらいました。子どもたちにとっては、パパママと一緒なので、ずっとわくわくしながらの時間だったようです。
タマネギを持って、満足そうに帰る親子を見ると、うれしい気持ちになります。マルベリー(桑の実)も、少しだけ楽しんでもらいました。今日は、親子の会話を充実させて欲しいですね。
本日出席いただいた保護者の皆様・・・お兄ちゃん、お姉ちゃん。本当にありがとうございました。
2024年
5月
10日
金
チーム担任制
今日は、寺子屋園児が屋上にタイヤアスレチックを完成させました。事前に、黄色・青色・ピンク色の3色で、板に色塗りをしていました。タイヤや収穫用ボックスを積み上げて、なかなか楽しそうなタイヤアスレチックの出来上がりです。早速、自分たちで楽しむ子どもたちです。
明日の保育参観では、教室内でママにプレゼントをした後に、屋上に移動して、親子でいつもの遊びを一緒に楽しんでもらいます。その一つが、タイヤアスレチックです。天気予報も晴れですので、明日は大いに楽しんでもらいます。
さて、みなさんは、自分の仕事のスキルをアップさせるために、今までどうやってきましたか。勉強して知識アップ、資格を取る、研修を受けるなど、それぞれあると思いますが、私の場合、一番効果的だったのが、「上司や先輩の技を盗む」です。セロベースの自分から、次々とアイデアが浮かぶことは難しいので、とにかく盗み、自分流にアレンジして、さも、自分が考えたかの如く振舞うのです。(笑)
しかし、「先生」という仕事は、「一国一城の主」のイメージが強く、なかなか他の先生の技を盗むことは難しいですね。
富山県南砺(なんと)市は、市内のすべての小中学校で、「チーム担任制」を導入しています。二人の担任が、2学年合同の授業を行うのです。例えば、小学校3年と4年の道徳の授業が合同で行われます。先生は、3年と4年の担任二人です。「学校のルールって何がある?」と、授業の進行役を4年の担任が務めます。児童から「廊下を走らない」「スマホを持ってこない」「教室で眠らない」など様々な意見が上がります。補佐役の3年生の担任は、それぞれの机を回り、ワークシートに書かれた児童の意見をチャックします。担任がチームを組むことで、お互いのやり方を学び、自らのスキルもアップするとうわけです。
南砺市が「チーム担任制」を導入した背景には、残業の常態化や世代交代により若手教員が増えたことがあったようです。ベテランの大量退職で、指導技術の伝承が減り、教育力低下が危惧されたからです。教員同士が得意教科の授業を担当し合うことで、授業の質も高められたようです。
南砺市では、2020年度から「チーム担任制」を導入していますが、制度導入後に新任が年度途中で退職した事例はゼロになったそうです。1学級だと生活集団が固定されてしまいますが、2学年ごとに教えると、子どもたちの顔ぶれが、毎年度入れ替わり、多様な意見に触れることが可能になりますね。今のところ、道徳・生活・音楽・図工・家庭科・体育などで、合同授業が行われているそうです。国語や算数、社会といった授業でも、異学年で学び合うことも可能です。
異年齢保育のホワイトきゃんばすでは、学年別の合同授業が、どれだけ効果的かは、経験上よく理解できます。私たちが、大人になって社会人となれば、そこには、同じ学年のチームや組織はありません。人は、必ず異年齢の環境でコミュニケーション能力を高めていくのです。
南砺市の「チーム担任制」は、教員にもよし、児童・生徒にもよしの取り組みですね。
2024年
5月
09日
木
どうせ行くなら楽しい地獄
今日は、マルベリー(桑の実)が少しだけ、赤黒く熟してきたので、子どもたちと食べてみました。まだ、酸味が強かったですね。明後日の保育参観で、パパに木に登ってもらって収穫してもらいます。マルベリーをむさぼり食べる子どもたちのワイルドな姿を見てもらいます。そして、1、2歳児の園児たちと「トマト」の苗を植えました。これで、ミニトマト12本・中玉トマト6本・大玉トマト6本、合計24本となり、夏野菜の代表であるトマトをこの夏もたくさん子どもたちと食べようと思っています。
話題は変わりますが、「はて?」というセリフが、今年の流行語ベスト10には必ず入るのではと、勝手に思う私です。このセリフは、女性に弁護士資格が認められていなかった時代に法曹の世界を志すヒロイン・寅子が活躍する朝ドラ「虎に翼」で、寅子が、?となった時に口にするセリフです。日本初の女性裁判所長になる「三淵嘉子」さんを描いたストーリーですが、毎朝、多くの人を元気にしていますね。
寅子が女学校卒業直前に、母役の石田ゆり子さんに、お見合いして結婚しなさいと諭されます。法科へ行きたいのは、お見合いから逃げるためだと母が言うと、「そうだよ、だって私、やっぱりお見合いはしたくない。婚姻制度について調べれば調べるほど、心躍るどころか心がしぼんでいく」と言います。母は、「あなたのような頭のいい女が幸せになるには、頭の悪いふりをするしかない。だから、あなたはできるだけあなたに見合った素敵な殿方と見合いすべし」と続けると、寅子は「愛してくれてありがとう。でも、私には、お母さんがいう幸せも、地獄にしか見えない」と、どうせ進むのなら自分で選択した「楽しい地獄」へ行くことを決心するのです。
朝ドラのヒロインは、一人でぐんぐんと時代を切り開いていく、スーパーヒロインのようなイメージが強いですね。もちろん、寅子もパワフルで、自分の意見をきちんと言える人物に描かれていますが、「スーパーヒロイン」ではなく、「シスターフッド」です。
「シスターフッド」という言葉は、聞き慣れない人が多いかもしれませんが、1960年代から誕生した言葉です。女性同士の連帯や親密な結びつきを示す概念です。寅子は、ドラマの中では、決して一人で戦っているのではありません。法科の仲間たちと前に進んでいますね。現代のシスターフッドは、SNSやメディアで、女性たちの絆を積み上げる活動につながっています。
朝ドラは、当時の時代背景が見えてきます。寅子の同窓生たちは、はつらつとしていますが、通りを歩く他の一般女性たちは、明るい顔をしていません。どちらかというと、しんどそうな顔をしています。寅子のように、法科という道を見つけた人は、まだ誰も踏み入れたことのない、いばらの道でも、恵まれているのかもしれません。苦難も楽しく乗り越える寅子の今後が楽しみですね。
2024年
5月
08日
水
キツネとタヌキ
屋上ファームの「エンドウ豆」が終了しました。1か月以上、子どもたちが収穫をがんばり、お土産で、おうちでもたくさん食べました。エンドウ豆を茹でて、マヨネーズをかけて食べるだけでも、あっという間に食卓から無くなる のです。次の植え付けの準備で、エンドウ豆を引っこ抜くと、ダンゴムシが、ざっと500匹以上出てきました。虫嫌いが見たら倒れてしまうかもしれません。しかし、子どもたちにとっては、最高の観察タイムです。飼育ケースにダンゴムシを集めることに夢中です。「先生見て見て!」という瞳は、輝いています。ここは、私が子ども頃の昭和と、まったく変わらないですね。(笑)
さて、今日はキツネとタヌキの話です。ある森に、キツネとタヌキが住んでいました。キツネは走るのが得意なのですが、泳ぐのが苦手です。一方、タヌキは泳ぐのが得意なのですが、走るのが苦手です。そこでキツネとタヌキは、峠のお地蔵様に願い事をかなえてもらうことにしました。
「お地蔵様、キツネの私は泳ぐのが苦手です。得意になるようにしてください」「お地蔵様、タヌキの私は走るのが苦手です。得意になるようにしてください」すると、お地蔵様がしゃべったではありませんか。「キツネさん、泳ぎが苦手でもいいじゃないですか。あなたは走るのが得意なのだから、その力をもっと伸ばしてごらん」「タヌキさん、走るのが苦手でもいいじゃないですか。あなたは泳ぐのが得意なのだから、その力をもっと伸ばしてごらん」キツネとタヌキは、お地蔵様からの言葉を黙って聞いていました。
その日の夜、夕ご飯を食べながら、キツネとタヌキは話し合いました。タヌキが言います。「お地蔵様の言う通りだよ。私たちは一人一人違うのだから、自分の良さをもっと伸ばせばいいんだよ」ところが、キツネは言います。「お地蔵様の言うことはおかしい。私は走るのが得意だけど、泳ぎも得意になりたいんだ」
さぁ~これを読んだあなたは、キツネとタヌキのどちらの考えに近いですか。もちろん、どちらかが正解で、どちらかが不正解ということはありません。親として、我が子にはキツネかタヌキか、どちらの考えを伝えますか。
保育園としては、子どもたちに、キツネのように「あれもこれもできるように、がんばってみよう!」と言いたいところですが、これも、相手次第です。この言葉が、プレッシャーに感じる園児もいます。
大人からのアドバイスは、自分がキツネの思考でも、相手のことを考えてタヌキの選択もあるでしょうし、その逆もありますね。「アメとムチのバランス」と同じように、子どもに対してのアドバイスは、なかなか難しいものです。そうだ。一番いいのは「自分で考えてごらん」かもしれません。
2024年
5月
07日
火
接客の身だしなみが緩和へ
ゴールデンウイークが終わり、今日から「日常」の保育園生活が始まりました。今年は、故郷への帰省以外は、わりと近場で過ごした家族が多かったようです。それでも、日々の活動記録を連絡ノートで拝見すると、「体力おばけ」と言われるくらい、子どもたちはアクティブです。「保育園で早くお友だちと遊びたい」という園児も多かったようで、今日の保育園は、連休明けですが、いつも通りです。
さて、最近では、小売店や飲食店などで働く人たちの身だしなみが、つい数年前と比較しても変化していますね。髪の色を明るく染めたり、ネイルを施したり・・・個人の好みや価値観を尊重した自由な装いは、従業員の意欲向上や人材確保にもつながっているようです。
といった感じで、「時代の流れ」と肯定的に受け止められるようになったものの、私のような昭和世代は、やっぱり、飲食店や食品を扱う店舗では、「清潔な身だしなみ」でないと、「ちょっとなぁ~」という気持ちになるものです。
就職情報会社マイナビが昨年実施した調査では、全国559社のうち、36.7%が直近5年間で、従業員の身だしなみの規定を緩和していました。多様性や個性を尊重するというものの、本音では、人手不足が深刻化し、売り手市場になっているからです。服装規定の緩和は、ファッションに関心の高い若者を呼び込む方策の一つになっています。
スーパーのアピタ・ユニーは、2022年、創業以来初めて服装ルールを緩和し、頭髪と爪の色を自由としました。当初懸念したお客様からの否定的な反応はごくわずかで、むしろ、個性的な外見がお客様とのコミュニケーションのきっかけになったり、白髪を染めているシニア世代の従業員から「自由になれる」と喜びの声が上がり、職場の雰囲気が明るくなったそうです。
回転寿司チェーンのスシローは、昨年11月、髪の色などに関する見だしなみのルールを改めた際、イスラム教徒の女性が頭を覆うために直用するスカーフも認めたそうです。
また、従業員が付ける名札の見直しも進んでいます。客によるつきまといや理不尽な要求などの「カスタマーハラスメント(カスハラ)」から、従業員を守るためです。タリーズコーヒーは、2022年に名札の表記をイニシャルのみにしたそうです。従業員がSNS上でつきまといの被害を受けたためです。「安心して働ける」とのことです。
男性のヒゲを認めたあるスーパーでは、退職を検討していた従業員が撤回を申し出たという例もあったそうです。外国人の従業員が増えている今、「人材の定着、確保にもつながるはず」という考えです。
働くスタッフの人材確保という現実は理解しますが、やはり、お客様がどう受け止めるかが大事ですね。「当店の服装ルールは、○○です」としっかりと打ち出し、お客様にきちんと説明できていることが必要だと思う、昭和世代の私ですが、みなさんは、どう思いますか。
2024年
5月
06日
月
サザエさんの「昭和図鑑」⑨ 食べ物
昨夜は、府中にある大國魂(おおくにたま)神社の「くらやみ祭」に行ってきました。1000年以上の歴史がある、大國魂神社の例大祭です。神事は人の目に触れてはいけないという考えで、灯りをともさずに「くらやみ」の中で行われていたことから、こう呼ばれているようです。今では、もちろん「くらやみ」ではないですが、かつては、男女無礼講で、子孫繁栄を願ったといわれています。
昨日の5月5日は、「おいで」といわれる、「神興渡御(みこしとぎょ)」が行われ、祭りのクライマックスでした。大太鼓をまるでバットのようなバチで叩きます。その大きな音と共に、この祭りの重厚な時間が味わえるのです。太鼓の音と、人々が身につける烏帽子(えぼし)には、太鼓の神輿が所属する屋号が書かれており、その雰囲気もこの祭りの威厳を保っているのです。こんな歴史のある祭りですので、すごい人ごみです。大國魂神社の境内に並ぶ500ほどの屋台で、まともに買い物ができないくらいの、人人人でした。ちなみに、直径2メートル2.5トンの世界最大の太鼓が、先頭を露払いとして登場しました。
くらやみ祭では、交通規制がひかれていましたが、そんな中でもウーバーイーツで食べ物を運ぶ姿を何人も見かけました。コロナが終息しても、食べ物を出前する手段として、今でも需要が高いですね。
昭和の頃の「出前」は、もっとカッコよかったですね。自転車に乗って、何段にもそばを重ねて、まるで曲芸のような出前が、昭和にはよく見られました。そば屋、すし屋、ラーメン屋が、昭和の出前の定番でした。自転車の曲芸の他には、スーパーカブと呼ばれる、出前専用に開発された50ccバイクで配達をします。
ここで問題です。昭和の「出前」と、現在のフードデリバリーでの一番大きな違いはなんでしょうか?
はい。それは、食器を返すか返さないかの違いです。昭和の出前は、食べ終わった頃を見はからって。食器を取りにいきました。現在のように、紙やプラなどの捨ててもいい簡易容器ではなかったので、出前を取ることは、とても贅沢な食事だったのです。昭和の頃は、来客があった時には、出前をとっておもてなしをしたのです。
昭和の出前は、エコでもあったのですね。そして、出前専用の業者があったわけではなく、そば屋さんなどの各店舗が、「店舗外売上」の獲得のために、チラシを配って、外商活動を行ったのです。昭和の「商いの魂」を感じますね。
2024年
5月
05日
日
サザエさんの「昭和図鑑」⑧ 子どもの遊び
昨日は、次女を連れて「もんじゃ焼き」を食べに行きました。はい、今や観光地となっている「月島」のもんじゃストリートです。私の祖父が、月島から歩いて行ける「佃島」に住んでいました。小学生の時から、一人で電車に乗って、おじいちゃんのおうちに、よく遊びに行っていました。この時は、今のようにもんじゃストリートではなく、ただの「西仲商店街」です。かつては、地元の子どもたちが安くておいしい「もんじゃ焼き」を食べていたのですが、昭和が終わり、いつのまにか観光地化し、墨田川沿いには、高層マンションが立ち並びます。私たちが食べていた店に、外国人が入店しました。スマホの翻訳機能で店員さんとやり取りして、チーズがたっぷり入ったもんじゃ焼きを注文します。店員さんが作っていましたが、この体験は、まさに日本の思い出の一つになったことでしょう。「アメージング!」と叫んでいたような~(笑)
さて、今日は子どもの日ですね。昭和の子どもの遊びを思い出してみます。「あやとり」をやったことはありますか。一人でも二人でもどこでもできる遊びですが、私が小学校の頃は、クラスで女子だけでなく男子もやっていました。「東京タワー」「橋」「ほうき」などの定番技で盛り上がります。あやとりには、約3千種類の技があるそうです。でも、あやとりは、今でも、保育園でたまに子どもたちが遊んでいます。
「チャンバラ」は、まさに昭和の男子の、ごっこ遊びの代表的なものでした。私より年上世代では、時代劇のマネが多かったようです。あのスピルバーグ監督の「スターウォーズ」に出てくるライトセーバーは、日本の時代劇の映画に影響を受けたものと言われています。もちろん、保育園の子どもたちも、プラスチックの刀を手に今でも戦っています。
そして、「おままごと」は、女子の定番ごっこ遊びです。「ままごと」は漢字で書くと、「飯事」となります。保育園の子どもたちの多くは、「おままごと」=「料理ごっこ・食べ物屋さんごっこ」と思えるくらい、食べものを作っていることが多いです。漢字の意味などもちろん知らないですが、フライパンを使って、草やファームの野菜を使って料理をしています。
あれ?昭和の子どもたちの遊びは、もっとたくさんありますが、「あやとり」「チャンバラ」「おままごと」は、令和の子どもたちにとっても、遊びの選択肢の一つとして、残っています。
昭和も、令和の今でも、子どもたちは、遊びを作る天才です。それは、時代が流れても変わらないことですね。
2024年
5月
04日
土
サザエさんの「昭和図鑑」⑦ 場所
昨日行った、わたらせ渓谷鉄道の始発駅「桐生」から200メートルほど歩くと、「西桐生」というレトロで小さな駅があります。上毛電鉄の始発駅です。「中央前橋駅」という、JR前橋駅からかなり離れた場所までの区間を1時間かけて走ります。昭和の時代に、京王井の頭線で走っていた車両が現役で活躍しています。上毛電鉄は、自転車を車内に持ち込むことができて、地元の高校生が通学に使用し、住民がちょっとした買い物に自転車で乗り込みます。
上毛電鉄は、スイカやパスモといったICカードは使えません。もちろん、自動改札ではなく、改札口では、駅員さんが特殊な鋏で、入鋏(にゅうきょう)します。このシーンわかりますか?切符に、鋏を入れることで、使用開始を示したのです。この入鋏作業が、いつのまにかスタンプに代替えされ、今では、当たり前の自動改札となり、スタンプも姿を消すのです。改札で駅員が、鋏をカチカチさせる音が、またたまらなくいいのです。上毛電鉄には、「改札口で駅員が鋏を入れる」場所が、まだ残っていたのです。
駅には、今はなくなってしまった場所が、まだあります。何かわかりますか?そう、「伝言板」です。私もこの伝言板を書き込んだことがあります。「太郎へ・・・もう待ちきれないから、悪いけど先に行ってる。次郎」のようなメッセージです。これが、1990年代には、携帯電話の普及が進んだことから、必要性がなくなりました。また、落書きが増えたことで、伝言板の役割も消えていったのかもしれません。
私が学生の頃、駅で待ち合わせをしている時に、「伝言板」を読むのが楽しみでした。中には、イラスト付きの芸術的なメッセージもありましたね。令和の今は、携帯で簡単に検索できるので、待ち合わせ駅に遅れることも少なくなりましたが、昭和のアナログ時代では、「○○駅まで、だいたい1時間くらいだろう」と、勘に頼っていました。早く到着するか遅刻するか、その人の性格次第でした。私も、大学時代にデートの約束で、池袋駅に待ち合わせをしました。時間になっても彼女は現れません。30分経過して相手の家に電話すると「家を出た」とのこと。こうなったら、意地でも待ってやろうと、本1冊読み終えてしまいました。待つこと2時間、これは、今でも破られることのない、私の待たされ時間の最高記録となりました。家を出るのが30分遅くなったことと、バスの大渋滞が理由でした。2位間も待つと、怒りを超えて、悟りの境地になり、一切文句を言わなかった自分を思い出します。(笑)
昭和の駅にあった「伝言板」・・・令和の駅で見つけることができたら、うれしいですね。手書きのぬくもりがいいのです。
2024年
5月
03日
金
サザエさんの「昭和図鑑」⑥ 環境問題
今日からゴールデンウイーク後半戦ですね。私は、プチ旅に行ってきました。場所は、わたらせ渓谷鉄道です。群馬県の桐生(きりゅう)から、栃木県の間藤(まとう)まで、渡良瀬川沿いを走る路線です。トロッコ列車が観光列車として走っており、今日はすべてのトロッコ列車が満席でした。
美しい景色を楽しんだのですが、もう一つの目的がありました。わたらせ渓谷鉄道は、国鉄・JR時代は「足尾(あしお)線」として運行されていました。私が中学生の頃に、足尾駅で切符を紛失してしまい、駅員からは、キセルの疑いをかけられた苦い記憶がありました。結局ポケットにありました。(笑)
「足尾銅山」を聞いたことがありますか。足尾は、江戸時代から昭和にかけて、約400年にわたって「銅山のまち」として栄えていたのです。1610年に銅山が発見されると、幕府の管轄下におかれます。多くの人たちが集まり、江戸の中期には、千軒の家があったとされています。
明治時代になると、機械による技術向上や、設備の導入で生産量を急速に伸ばしました。明治二十年代には日本の銅の40%を産出する日本一の銅山となりました。富国強兵や、世界大戦後の高度成長期など、日本の近代化を進める日本産業の礎の一つとなったのです。
しかし、足尾銅山には、光だけでなく影の部分もありました。私が中学時代の現代国語の教師の夏休みの課題が、社会派の小説を多く書いた城山三郎さんの「辛酸(しんさん)田中正造と足尾鉱毒事件」です。そう、影の部分は、銅山から排出された、「鉱害」が、人や自然環境を壊していったことです。
足尾銅山の鉱毒で甚大な被害を受け、反対運動の急先鋒となった谷中村(やなかむら)は、絶体絶命に危機にありました。鉱山の資本家と結託した政府が、村の土地を買収し、遊水池として沈めようとしていたのです。反対運動の指導者、田中正造は、国会議員でしたが、村を守るため、政治権力に法廷での対決を挑みます。しかし、それは苦難に満ちた闘いで、国は全く動かず、田中正造は、天皇に直訴するも通じません。
こうして、足尾銅山鉱毒事件は、日本最初の公害闘争となったのです。その後、環境問題が取り上げられるようになりました。「水俣病」は、熊本県水俣湾周辺の化学工場などから海に排出された水銀に汚染された魚を長期間、日曜的に食べたことによる中毒です。「イタイイタイ病」は、岐阜県神岡鉱山から排出されたカドミウム汚染です。
令和の時代なら、環境が最優先で、開発が進められるようになりましたが、昭和以前は、経済を優先することに、多くの政治家は、疑問すら思わなかったのです。
皆さんは、わたらせ渓谷鉄道のトロッコ列車の観光を考えたら、必ず、足尾銅山に寄ってください。ただし、観光施設では、あまり影の部分は見えてきませんね。「足尾銅山を世界遺産に!」の活動が行われています。私見ですが、世界遺産になるには、「ここで400年も銅を産出したんだ」だけではダメです。負の遺産にもスポットを当てて、環境問題にまで巻き込んだ、日本で最初のまちというフレームでアピールしてもらいたいですね。
足尾銅山は、昭和48年に閉山となりました。掘られた坑道の長さは、東京→博多間に匹敵します。閉山から、50年以上が過ぎているので、わたらせの自然は、見事に美しく復活しています。
2024年
5月
02日
木
サザエさんの「昭和図鑑」⑤ 道具
今日は、ようやく晴れました。ふだん子どもたちが、タイヤアスレチックで遊んでいる、長い板に、水性ペンキで色を塗りました。スカイブルー、ピンク、イエローの3色です。どうせ遊ぶなら、華やかにカラフルに楽しもうという作戦です。ペンキを塗る子どもたちの目が真剣です。
さて、今日の「昭和図鑑」は、平成・令和の子どもたちが知らない道具「マッチ」です。私が、小学生くらいの頃は、ライターよりも、マッチを使った記憶の方が残っていますね。父に、マッチの擦り方を教えてもらって、先の少し膨らんだ部分を箱のヘリで擦るのが、なんともわくわくしました。シュッと炎が上がる瞬間が、たまらなかったです。でも、むやみにマッチを使うと、火事になると、本気で大人から怒られたものです。
保育園の読み聞かせで、「マッチ売りの少女」の話をすると、最後は、寒さに凍えて少女が死んでしまう悲しい物語にもかかわらず、子どもたちは、マッチをよく知らないので、悲しみに浸ることもありません。
ガスコンロや石油ストーブに点火する時に、マッチを使いましたが、一番多くマッチが使われたのが、タバコに火をつける時です。そのため、「スナック」や「バー」が、マッチを配っていました。箱に、店のデザインや広告を印刷したマッチを宣伝用として使用したのです。
サザエさんでは、マスオさんが、上着のポケットから、スナックやバーのマッチが見つかってしまって、ばつの悪い顔をします。私の父親の世代は、まさに、「あるある」の光景だったのです。この頃は、マッチのコレクターもたくさんいたようですね。
実は、私は今でもマッチを使っています。仏壇のろうそくに火をつける時には、やっぱり、ライターよりもマッチがしっくりきます。ほのかな火薬の香りもいいものです。
マッチは、ライター以前の火をつける道具ではありますが、なんとなく、夜の世界の大人の時間が垣間見えるような、そんな不思議な道具ですね。この夏のサマーキャンプでは、マッチを使い方を子どもたちに教えることにします。
2024年
5月
01日
水
サザエさんの「昭和図鑑」④ 事件
5月に入りました。昨日4月の保育園のDVDを保護者の皆様に渡したのですが、早速、視聴した親子・・・体操教室で、空中回転するすご技を見せてくれた5歳男の子のママは、その身体能力に驚愕したそうで、おじいちゃんおばあちゃんに動画を送ったそうです。男の子の「どや顔!」が目に浮かびます。(笑)
今日は、朝からまとまった雨です。そこで、子どもたちは「母の日」プレゼント制作をしました。何ができるか?5月11日の保育参観までのお楽しみですが、たいがい、子どもたちは、事前にママに話してしまいます。(笑)
さて、今日は「3億円事件」です。昭和には、数えきれないくらいの事件が発生していますが、私も子どもながら、この事件のインパクトがいかに大きかったかを父に熱く語られて記憶しています。昭和43年、東京都府中市で金融機関の現金輸送車に積まれた約3億円の現金が、白バイ警官に扮した男に奪われるという、後世にまで語り継がれる前代未聞の大事件が起きたのです。この3億円は、東芝の府中工場の従業員に支払われるはずのボーナスでした。この事件を機に、多くの企業で、給料の銀行振り込みが普及したそうです。給料袋を手渡しするというイメージは、令和の若者では考えられないでしょう。
当時の3億円は、今の価値では、10億円に値すると言われています。令和になって、10億円強奪事件が起きたとなれば、やっぱり大事件ですね。
様々な謎が解決されないまま、3億円事件は、昭和50年に時効が成立しました。この3億円には、日本の保険会社で保険が掛けられていたので、ボーナスは翌日には全従業員に支給されました。その保険会社も再保険をかけていて、日本以外の保険会社で全額分が補填されたのです。よって、日本国内で金銭的損失を被った人がいなかったことから、被害総額2億9430万の語呂で「憎しみのない強盗」とも言われたのです。
しかし、捜査に投入された警察官は、延べ17万1346人、捜査費用は7年間で9億7200万円以上が投じられるなど、空前の大捜査となったのです。3億円事件は、日本犯罪史に名を残す未解決事件となり、多くの映画やテレビドラマなどで放映されてきました。
時々、府中街道を車で走ると、西国分寺駅を過ぎて、3億円事件の現場を通過します。私の頭の中に、白バイ姿の犯人の顔がよぎります。この犯人が生きているならば、まだ70歳前後です。何を想うか・・・ですね。
2024年
4月
30日
火
サザエさんの「昭和図鑑」③ 社会
今日は、屋上遊びの時間になると、雨が上がりました。子どもたちには、屋上ファームの仕事を頑張ってもらいます。まずは、ようやくホームセンターで見つけた「白なす」の苗を植えました。昨年、この白なすを育てたのですが、とろけるように美味しくて、今年も挑戦です。黒いなすの苗は、多くの種類が売っていますが、白なすは、たまに見かけるだけです。急いでゲットしました。
そして、ついに菜の花をすべて引っこ抜きます。「俺は、力持ちだ!」という園児が集まって、あっという間です。長い間、この菜の花は、花摘みだけでなく、食べる方でも活躍しました。菜の花畑の後には、ミニトマトを植えます。寺子屋の時間では、サツマイモの苗を植えました。これは、夏をはさんで、しっかりと大きくなって秋に収穫です。芋ほりで、子どもたちと盛り上がります。
さて、今日は、昭和の社会では当たり前に行われていた「ストライキ」を思い出してもらいます。ストライキとは、労使交渉において、労働者が、賃金アップや労働環境の改善を求めて労働を行わずに抗議することです。
昭和の終わりには、「スト決行」のニュースを聞かなくなりましたが、昭和30年代後半から50年代までは、。春闘(春の賃上げや夏のボーナス交渉)の季節になると、メーカーや工場だけでなく、電車やバスもストライキを決行することが頻繁にありました。ピーク時は、全国で年間千件以上もあったそうです。
電車が止まれば、サラリーマンは通勤できず、会社を休むことになります。組合側は、「賃上げ要求をのまないと、ストライキをするぞ。そうなれば、社会は混乱し、鉄道会社の信頼を落とすことになるぞ!」と、会社側にゆさぶりをかけるのです。しかし、当時は、「やれるもんならやってみろ!」とばかりに、会社側も強気で、労使ともに、妥結への歩み寄りが、なかなかされなかったのです。
私も、高校大学時代、ストで電車が動かないので、休校となり「ラッキー!」と思ったものの、電車が動かないので、どこにも遊びに行けず・・・という記憶が残っています。しかし、現在は、働き方も様々で、正社員でも労働組合に加入していない人も増えています。労働組合の存在意義は、昭和と令和では大きく異なっているのが現実なので、今後ストライキなんかないだろうと、思っていました。
ところが、記憶に新しいところで、昨年8月31日に、西武百貨店池袋本店でストライキが行われ、お店は、まる一日定休日となりました。このストライキが行われた目的は、池袋西武で働く仲間を守る、お客様から愛されるブランドを守る戦いでしたので、他の百貨店の組合トップたちも応援に駆けつけました。世論も「よくがんばった!」とひいき目に受け止めたのです。
私は、サラリーマン時代に、東京支部の執行委員長をやったことがあります。労使交渉では、社長に対して、きちんとモノを言いました。業務では、なかなか言えませんが、組合のトップの立場で、「組合員の生活を守る」という大義のために戦ったのです。もちろん、殴り合いのケンカではありません。言葉による交渉ですので、勉強もしなければ、経営者相手に言い負かされてしまいます。
「要求通りの回答がなければ、スト決行!」という切羽詰まった状況を何度も経験しました。とても、熱かったですね。令和の時代だって、ストライキに変わる、熱い何かが、働く若者の中に必ずあるのでしょう。時代が変わっても、そこは変わらないで欲しいですね。
2024年
4月
29日
月
サザエさんの「昭和図鑑」② 生活習慣
昨日は、田無神社に行ってきました。少しミーハー(昭和です)な言い方をすれば、金・青・赤・白・黒の五龍神が鎮座する最強パワースポットです。そんな神社知らない?と思ったあなた。今年は「辰年」ですね。ここには5つの龍がこの神社を守っているのです。それぞれの龍には、行列ができていました。私も、しっかりと並んでお参りをします。私は、初めて参拝するので、いきなり、願い事をするのではなく、住所と名前を言って、「初めてお参りさせていただきます。よろしくおねがいします」だけにとどめます。これが、初参拝のルールです。
さて、昨日は田無近辺に、「大正10年創業のたばこ屋」という、古い看板を掲げたたばこ屋さんを見つけました。たばこの販売は、昭和も令和の今も許可制で、一定の範囲内にたばこ屋がある場合は販売許可が出ません。昭和20~30年代のたばこ屋は、たばこを売ることはもちろん、公衆電話が設置され、切手やはがきの販売も担当していました。
ところで「たばこ屋」というと、なぜかおばあちゃんが店番をしていることが多いと思いませんか?それには理由がありまして、たばこの仕入れ価格は小売価格の約9割で、利益率は、わずか1割程度しかないのです。そのために、昭和のたばこ屋は、自宅兼店舗で「小遣い稼ぎに高齢者が営むもの」と見なされていたのです。
そんなたばこは、昭和の生活習慣の中に、しっかりと根付いていました。たばこをふかしながらの会議など、どの会社でも見られたのです。私が20歳代の営業会議では、会議室が、たばこの煙でいっぱいでした。(笑)
日清戦争後の1898年(明治31年)、政府は国家収入を増やす目的で、たばこの製造販売を「国営化」し、国が喫煙を奨励したこともあって、成人男性の喫煙率は、ピーク時1966年(昭和41年)は、なんと83.7%もあったのです。昭和の終わり頃から、たばこが体に与える害悪が広く知られるようになり、喫煙者が減っていきます。昭和60年には、日本専売公社が民営化され、受動喫煙の防止を目的とした改正健康増進法が2018年(平成30年)に成立しました。令和4年の直近のデータでは、喫煙率は男性25%、女性は7%だそうです。
今では、電車の中では、喫煙することができないばかりか、駅での喫煙も禁止されるようになりました。歩きたばこはNGで、街の片隅にある喫煙所で、肩身が狭い喫煙者の姿を見るだけです。今の若者は、たばこを吸うことがオシャレとも思わないし、他の楽しいことがたくさんあるし、単純に健康リスクを考えているのでしょう。近い将来には、紙たばこは、なくなっているのかもしれませんね。
2024年
4月
28日
日
サザエさんの「昭和図鑑」① 仕事
世の中は、昨日からゴールデンウイークです。テレビ報道を見ていると「安・近・短」がキーワードだそうです。安い値段で、近場を日帰りなど短いスケジュールで…といった意味です。円安で海外旅行もアジアの近場で過ごし、国内旅行も宿泊料金アップで日帰りで過ごす人が多いようです。観光地に人があふれているのは、円安で日本にやってくる外国人です。
そもそも「安近短」という言葉は、昭和の終わりにバブル崩壊で、贅沢ができない状況になり、旅行は「安近短」で過ごすということで、使われた言葉です。私のような昭和世代は、「安近短」という言葉を聞くと、昭和を思い出します。
ということで、ゴールデンウイークは、昭和の懐かしさに浸ってもらいます。日本国民に深く愛されているサザエさんは、戦前から戦後の復興期、高度成長期と日本人の心に寄り添った名作漫画です。最初は、昭和21年~49年に、夕刊フクニチ、朝日新聞など新聞紙上で連載されました。新聞で毎日掲載されたサザエさんは、当時の世相が色濃く反映されています。
今日は、昭和にあって、令和の今では、ほとんど見ることがなくなった仕事の一つ、「エレベーターガール」の話です。
昭和の女子たちの憧れの仕事の一つが、エレベーターガールでした。制服&帽子の当時の最先端の服装で百貨店のエレベーターに乗降する女性は、昭和4年に、松坂屋上野店に初めて配属されたそうです。
昭和の終わりまで、多くの百貨店のエレベーターに乗務し、運転の操作や各階の案内をしました。バブルが崩壊し平成となり、百貨店業界全体が経営不振に陥ります。人件費節減のターゲットとして、エレベーターガールが矢面に立たされます。また、誰でも簡単に操作ができるエレベーターの普及もあって、日本初のエレベーターガールを排出した、松坂屋上野店では、2007年(平成19年)に廃止となりました。
私は、入社初年度は、日本橋の三越本店に配属となったのですが、喜左衛門(きざえもん)に行くと、そこに当時、奉仕部という部署だった、エレベーターガールが昼食をとっているではありませんか。22歳の私は、同じテーブルに座ったのは言うまでもありません。(笑)ちなみに、喜左衛門(きざえもん)という言葉は、三越の隠語で「食事」という意味です。「喜左衛門に行ってきます」と言えば、「食事休憩に行ってきます」という意味です。
令和の今では、エレベーターガールは、絶滅危惧種になったと思いますか。大丈夫です。
私が知る限りでは、日本橋髙島屋で立派に仕事をしています。日本橋髙島屋には、国の重要文化財になった手動式のエレベーターがあります。このエレベーターは、エレベーターガールでないと動かせないのです。私が日本橋髙島屋を担当していた時は、必ず、1階正面入口から入店し、手動式エレベーターにリスペクトしてから仕事をしていました。(本当です)
そう、令和では、エレベーターガールの仕事は、付加価値としてお客様の支持をいただいているのです。そう簡単になくなりませんね。
2024年
4月
27日
土
イチローズモルトの立役者
今日は、小学1年生男の子が久しぶりに保育園にやってきました。積もる話があったようで、小学校生活のことをたくさん教えてくれました。1年生ですので、まだ午後の授業はなく、給食が終わると学童保育へ移動する生活だそうです。今は、新しい環境を自分の力で乗り越えようとしているところです。「こうすればいいよ」と園長からの一方的なアドバイスは控えて、聞き役に徹しています。こうして、小学生になってからも成長を見ることができるのが、うれしいですね。
さて、今日は「イチローズモルト」の話です。もう世界的に有名になった2004年創業の埼玉県秩父にあるベンチャーウイスキーです。設立者の肥土伊知郎の名前に由来して、ウイスキーは、イチローズモルトとうネーミングです。
しかし、イチローズモルトは、最初から爆発的なヒットとなったわけではありません。ここには、ブランドアンバサダーとして活躍する「吉川由美」さんの存在がありました。いくら良質の酒を造っても、その良さを正確に伝えないと、売れる物も売れません。
彼女は、イチローズモルトブームが起こる前の、2005年に帝国ホテルでバーテンダーとして働いている時、棚に並ぶ世界中のウイスキーの先に広がる世界にひかれたそうです。本を読み知識を得るが物足りず、本場のスコットランドに旅立ちます。その後、ニューヨークで過ごした2年間で英語を勉強し、2011年には、スコットランドに単身移住します。蒸留所に住み込み、夏は世界中のウイスキー愛好家が集まるバーで働く日々を送ったそうです。そこで飲んだ、日本のウイスキーのおいしさに驚くのです。
秩父蒸留所のウイスキーを国内外に伝える仕事をしたいという思いが募り、帰国後に面接を受けて採用されます。イチローズモルトを知ってもらうため、世界中でセミナーを開くなど、地道な活動で、2013年からは、売上が急増します。今では、「秩父といえばウイスキー」と認知されるようになったのです。
そして、2019年には「ワールドウイスキー・ブランド・アンバサダー・オブ・ザ・イヤー」を吉川さんは受賞します。
どうですか・・・今では、多くの人に知られる「イチローズモルト」ですが、こんな、縁の下の力持ちの存在があったのです。なかなか、手に入りませんが、飲む機会があれば、「吉川由美」さんの存在を思い出してください。
2024年
4月
26日
金
給食が不安
今日の体操教室では、プログラムの最後に「チャレンジタイム」がありました。助走して踏み台をジャンプ→目の前のとび箱に手をつかないで、空中で前回りして着地です。どうですか、イメージできましたか。この大技に、年長男子4名が挑戦しました。体操教室の先生からは、「ビッグ4」と呼ばれ、ずば抜けた身体能力があります。そして、この大技を見事クリアーするのです。私もビデオに撮りながら、思わず「スゴイ!」と叫んでいました。
さて、今日の話は「給食」です。新年度がスタートし、小学校1年生の児童にとっては、「好き嫌いが多い」「食べるのが遅い」という不安を抱える保護者も多いかと思います。
保育園ホワイトきゃんばすでも、今まで多くの園児が、この問題にぶつかってきました。例えば、小食の園児に対しては、最初は少なめに盛りつけて、おかわりを促して完食体験を経験させる。ふりかけごはんにするなど、子どもが好きな食べ方にする。苦手な食材は少なめにしたり、小さく切って、食べられたら大げさに褒める。みそ汁の野菜が苦手な園児は、スープごはんにしてみる。
子どもへの対応は、一人一人違うので、今までトライしたやり方は限りないですね。そんな中で、一番効果があったのが、屋上ファームで収穫体験した野菜を「これは、みんなが屋上でとった野菜だよ。新鮮でおいしいからね~」すると、他の園児から「おいしい!おいしい!」の大合唱が起こり、つられて食べられるようになります。今、屋上ファームでは、絹さやエンドウ豆が収穫ラッシュですが、効果があるのは、ファームで自分が収穫した野菜だけで、スーパーで買った絹さやエンドウ豆は効果がないようです。
小学生の子どもを持つ親で、我が子の給食に不安がある場合は、具体的に担任とすり合わせしておくのが大事ですね。ただし、「よろしくおねがいします」だけではいけません。①食べるのが遅い理由②家庭での工夫③本人の気持ち④これまでの体験・・・など、具体的に伝えるのがいいですね。
「本人は『早くしなさい』と求められるとプレッシャーを感じてしまうので、保育園時代は、『ゆっくりでいいよ』と言われると時間内に完食できていたようです」といった伝え方です。小学校で給食を食べる時間は、だいたい20分です。
難しいことではありますが、『給食の時間が苦手』と子どもに思わせないようにしたいものですね。
2024年
4月
25日
木
石川佳純サンクスツアー
今日は、汗ばむような陽気になりました。屋上遊びの子どもたちは、汗びっしょりです。終わりを迎える「菜の花」を引っこ抜く作業を「力持ち集合!」の掛け声で集まった園児たちの力でやってみました。「ぼくは…わたしは力持ちよ!」と園児がたくさん集まります。自己肯定感の高い子どもたちです。この場所には、ミニトマトの苗を植えます。
さて、卓球女子の五輪メダリストで、昨年5月に現役を引退した石川佳純さんが、全国各地を巡回し、子どもたちに卓球を教える「47都道府県サンクスツアー」が、先日、ちょうど折り返し点の24回を終えたそうです。
正直、スター性のある石川さんなら、タレント活動で稼ぎまくることもできるでしょうが、彼女は、子どもたちの成長のために、どのようにアスリートが貢献すればいいか、その一つの形を示しています。
石川さんのツアーの理念は「スポーツの魅力と、応援してくれたファンへの感謝を伝えること」だそうです。卓球の技術も教えますが、決して競技普及だけにはとらわれません。行く先々で、子どもたちに「卓球じゃなくてもいいから、いろいろなことにチャレンジしてほしい」と強調します。
あの大谷翔平選手が、日本全国の小学校にグローブを送ったのは、「このグローブでキャッチボールをしてスポーツを楽しむきっかけになってもらいたい」という考えで、野球以外のスポーツも挑戦して欲しいと願っているそうです。石川さんは、12歳で故郷の山口市を離れ、大阪の中学に進学します。「夢に向かう、人生でも大きな一歩でした。そんな経験を踏まえ、子どもたちには『きっかけ』を見つけてほしい」と願っています。
石川さんは、2月に、中学生活の不安を感じる小学6年生を前に、チャレンジ精神の価値を説きます。「新しい生活が始まると、うれしいこと、楽しいこと、もしかしたら苦しいこともあるかもしれない。でも不安を気にせず飛び込んで。好きなことは『なぜこんなにエネルギーが湧くのだろう』という気持ちにさせてくれる。自分が『これだ』と思えるものに出会えるように、どんどん挑戦してほしい」と背中を押します。
子どもたちから「やめたくなったことはありますか」と質問されると、「何度もあります」と素直に答えます。「落ち込んだり、頑張っても結果がダメな時も、『昨日より今日』と思って、工夫を重ねてきた。努力は、良い時も悪い時も続けられるから大事なんです」と言います。
どうですか、石川さんのメッセージに目を輝かせて聴き入る子どもたちの姿が想像できますね。こういった、現役選手や元アスリートが子どもたちと交流し、スポーツの魅力を伝える機会が、これからもどんどん増えていくとうれしいですね。
2024年
4月
24日
水
オタフクソースのお好み焼課
今日の連絡ノートには、昨日のピクニックランチのお弁当箱が空っぽで、「ママお弁当作ってくれてありがとう」という我が子のコメントに、涙する母親が4人もいました。やはり、ママへの最高のプレゼントは「空っぽのお弁当箱」でした。
今日は、その流れで食べ物の話です。広島の人たちが愛するのは、広島カープだけでなく、お好み焼きとそれに使われる「オタフクソース」です。私は、何人かの広島出身の知り合いがいますが、お好み焼きを語り出すと、「お好み焼きは、○○じゃないといけない」という長いウンチクが始まります。そして、「オタフクソース」が決め手と言います。
大阪のお好み焼きは、具材を混ぜて焼きます。もちろん、こちらも私は大好きですが、広島人は、こう言います。「広島のお好み焼きには、サンドイッチの美学がある。上から、生地、キャベツの甘味、香ばしい豚バラ肉、パリッと焼いた麺、一番下に卵のうまみが重なり、ソースをまとっている。層の上から下まで、一口で食べないとダメなんだ。おいしいお好み焼きは、キャベツが甘いんだ」なんて話が止まりません。(笑)
そんな、広島のお好み焼きを引き立てる「オタフクソース」は、2022年10月に100周年を迎えた、老舗企業なんです。そして、「お好み焼課」というユニークな部署があるそうです。
1998年に発足した「お好み焼課」は、今まで20年以上も、お好み焼きの普及、研究に特化した部署だそうです。店を開業したい人のために焼き方の研修、小学校での出前授業を開く。お好み焼き店を食べ歩いて市場調査やお好み焼きを研究して新しいレシピ作りもしているそうです。まさに、お好み焼きを作り、食べることが仕事なのです。
どうですか・・・こんな部署があるからこそ、広島のお好み焼きは、今でも広島人のDNAとして、組み込まれているのかもしれませんね。そして、オタフクソースは、会社の利益を考えれば、いかにオタフクソースが売れるようにするか・・・でしょうが、お好み焼き文化を守り、広げていくことが、社会的役割なのかもしれません。
お好み焼課は、今では、新入社員の人気部署ナンバーワンだそうです。そして、世界に向けて、お好み焼きを広げようとしています。外国人相手に、全編英語版の「お好み焼き教室」も行っているようです。新入社員研修では、海外を旅して、その土地の人にお好み焼きを知ってもらう取り組みがあるようです。
さぁ~そろそろ、お好み焼きが食べたくなりましたね。今日は、広島風にチャレンジしてみませんか。
2024年
4月
23日
火
生成AIの利用に挑戦すること
今日は、寺子屋園児は「ピクニックランチ」でした。今年度1回目ですので、年少の寺子屋3番さんにとっては、初めて、屋上にレジャーシートを敷いてのお弁当タイムです。事前に近くの公園で、家族のピクニックを経験し、お弁当箱を開けて、自分で食べる練習をした年少の男の子もいました。年長園児は慣れたもので、「ママお弁当作ってくれてありがとう!」と、ここぞとばかりに、ビデオカメラに向かって話します。ママにとっては、空っぽのお弁当箱が、一番のプレゼントですね。全員完食です。
さて、小中学校では、オンラインツールを使っての授業が当たり前になってきました。そこで、生成AIを使っての授業を導入したいと考える先生も多くなっています。でも、「自分の頭で考えない」といった、マイナス面への影響も気になるところです。最近起きたことでは、中学校の理科の授業で誤った情報をコピペして答えた生徒が多数出て、問題になった出来事もありました。
そこで、ある人のアドバイスを聞いてもらうことにします。
「AIツールを教育に取り入れる際は、批判的思考を育むことが重要です。まず、AIを情報のソースではなく、アイデアの発想や解決策を見つけるための補助ツールとして位置づけ、生徒が自ら考える力を伸ばすよう導くことが大切です。また、生徒がAIを使用した場合には、その情報をどのように得たかを正確に報告させ、情報の出典を批判的に評価する習慣を身につけさせましょう。授業ではAIの機能と限界を理解し、誤情報を見分ける技術やリテラシーを高める内容を取り入れることが望ましいです」
どうですか・・・このコメントは、皮肉なことに、生成AIに200字以内で回答してくださいと指示して、出てきた文章です。私は、「しっかり書けた模範回答」と、何の疑いもなく思いました。
インターネットとう言葉が、今では当たり前に使われていますが、インターネットを使うようになったのは、私が社会人になってからです。最初は、会議資料も手書きで作り、OHPという道具を使って、投影していました。PHS→携帯電話→スマホの流れも、ここ数十年の短いスパンでの出来事です。
生成AIを規制しよう…という流れは、現実的に不可能でしょう。ならば、生成AIを導入して、私たちは、人間として「どう扱うのがいいのか」を考えるしかないですね。生成AIが作成したアドバイスは、的を得ていますが、そんなのイヤと考えるなら、自分で考えるしかありません。
2024年
4月
22日
月
大人の「学び直し」
今日は、今年度初の階段レースをしました。まずは、階段を使った避難訓練からです。1階から、さらに降りた場所に非常ドアがあることを確認してから、ガチの階段レースです。年少の寺子屋3番園児は、階段を下りるのが少し怖いようで、手すりにつかまって、ゆっくりと降ります。保育園の帰りも、時々階段を利用しながら、慣れるのが一番です。
さて、昨日、BSNHKの「舟を編む」というドラマが最終回でした。三浦しをん原作で、2013年には、松田龍平・宮﨑あおい主演で、映画化もされたので、知っている人も多いと思います。主人公が、新しく刊行する辞書『大渡海(だいとかい)』の編集部に迎えられ、個性豊かなメンバーと辞書の世界に没頭していく姿を描いた作品です。「辞書は、言葉の海を渡る舟、編集者はその海を渡る舟を編んでいく」という意味で、この書名が付いています。
私は、中学時代の現代国語教師の影響で、辞書で引いた言葉には、必ず傍線を引いていました。中学高校、そして社会人になっても使い続けています。今でも、辞書を引くと、たまたま傍線が引かれてあって、「いつ調べたんだろう?」と想いを巡らせます。スマホですぐに、言葉の意味が調べられる時代ですが、やっぱり、辞書を使うと、「学んだ」という気持ちになるものですね。私にとっては、辞書は「大人の学び直し」でもあります。
みなさんは、「ガクサン」というコミックをご存知ですか。「学習参考書」というニッチなテーマを扱った、教育者の間でも話題になった佐原実波作の作品です。舞台は、学習参考書を取り扱う出版社です。そこへ中途入社した茅野うるしが配属されます。同じ部署には、ありとあらゆる参考書を熟知している参考書オタク福山が、上司として、うるしとかかわります。
この作品の神髄は、単に参考書の紹介にとどまらず、福山は、勉強の仕方が分からない中学生に、参考書を使って勉強することの意義を説きます。「体系的に何かを理解していくその方法をものにしろ。そうすりゃ年を食っても勉強以外でも好きなことを何だって身につけられる人間になれる」つまり、勉強することは、学びの方法を身に付けることでもあると言うのです。
どの参考書を使うかだけでなく、「どのように」使うかに焦点を当てる本作は、実在する参考書が取り上げられています。
中学高校生は、勉強しなければ・・・とあせる中で、勉強のやりかたがわからないことが多いですね。この本では、その方法を具体的に教えてくれます。そして、私たち大人になってからの勉強は、やらされる勉強ではなく、「やりたい勉強」をすることが多いです。そんな時に、この「ガクサン」がパートナーとして役に立つのかもしれません。
2024年
4月
21日
日
お肉の話
保育園の子どもたちは、よく回転すしのチェーン店の名前を出します。「お寿司大好き」というよりも、サイドメニューや演出を楽しんでいるようです。日本人の魚離れは年々進んでいて、2011年には、魚の消費量が肉に抜かれてしまいました。私は、肉も魚も大好きですが、やはり肉を食べる機会が増えています。
今日は、全国食肉事業協同組合連合会が、子ども向けに出している「なるほど!ザ・お肉ブック」で、お肉の勉強です。あくまで、子ども向けです。
和牛の場合、約30キロで生まれてきます。すぐに立ち上がり、10か月で体重は約300キロにもなります。2年半かけて、しっかりとおいしい肉になるように育てられて、30か月後に約750キロになって食肉センターに出荷されます。750キロは、ざっと小学6年生18人分です。
家畜としては、世界で一番多いのが豚です。豚は、半年で約10匹、1年間で約20匹の子ぶたを生みます。生まれた時の体重は、わずか1.5キロですが、6か月後には約110キロになって、出荷されます。常に何かを食べているというイメージですね。
これよりも、もっと短いサイクルで、出荷されるのが、ニワトリです。ニワトリの卵は、約20日間温められて、ひよこになります。そのあと、わずか50日で大人になって、出荷されるのです。和牛や乳牛の「黄色のイヤリング」には、10桁の番号が書かれています。この番号は、牛肉になった時のラベルやプライスカードも書かれていて、牛が生まれたところや育ったところなどがわかるようになっています。安心・安全の取り組みですね。
お肉の部位も大事です。牛肉のステーキなら「サーロイン」でローストビーフなら「モモ肉」。豚肉のとんかつなら、ヒレもいいですが、ほど良い脂肪が、コクと甘さを感じる「ロース」が、私は好きですね。鶏肉は、モモ・ムネ・手羽さきなどそれぞれ特徴があります。肉の部位によって、どんな料理があうのか、我が子と楽しむのもいいですね。
最後に、「いただきます」と「ごちそうさま」の意味を子どもと一緒に考えてみましょう。「いただきます」には、頭の上に食べものを押し上げて「いただく」と、牛豚鳥などの命を「いただく」ことの両方の意味があります。どちらも、食べものに対して「ありがとう」の気持ちを伝える言葉です。
「ごちそうさま」の「ちそう」は、漢字で「馳走」と書きますが、「馳走」には「走りまわる」という意味があります。走りまわって食べ物を用意してくれた人たちに、無事にごはんを食べて命をつなげたことへの「ありがとう」の気持ちを伝える言葉なのです。
まだ、小さい子どもには通用する、大切な食育ですね。
2024年
4月
20日
土
学校は楽しくするところ
本日登園した、小学校1年生の女の子は、ふだんは、寡黙で、ペラペラとおしゃべりをするようなタイプではありませんので、「小学校はどうだい?」と聞いてみると、友だちになった3人の女の子の話をしてくれました。そして、同じ小学校には、5人の卒園児が通っているのですが、他の4人の様子も教えてくれました。みな、元気に頑張っているようです。
今日の女の子のように、「楽しい」と思うのはうれしいことですが、そもそも、学校は楽しいところではありません。こう言うと、えっ!?と思いますね。
ある教師の話です。「私が教師になって間もない頃のことです。授業がうまくできず、子どもたちとの関係もうまくいかず、学校が楽しくなくなってしまいました。そこで、先輩の先生に相談することにしました。その先輩は、しばらく私の話を黙って聞いてくださったのですが、私が話し終えると、こう言ったのです。『○○先生。学校はたのしいところじゃないんだよ。楽しくするところなんだよ』この言葉を聞いた私は、目から鱗が落ちるような思いがしました」
どうやら、この先生は、学校が楽しくない原因を周りに押し付けていたのです。これは、学校に限らず、私たちの職場環境でも当てはまりますね。自分が主体的に動きもしないで、上司、先輩たちや社風のせいにして、「やる気が出ないんだよ!」と言っていることなど、私にも心当たりがあります。
ここ数年間は、コロナへの感染防止のために、多くの学校行事が延期や中止になってしまいました。「コロナだから仕方ない」とあきらめて、「楽しくない時間」を過ごした人も多かったと思います。しかし、そんな中でも、楽しくすることができたのかもしれませんね。
今日の小1女子は、きっと、自分の力で学校を楽しくする行動を自然と行っているのだと思います。そして、私たち大人は、子どもが「楽しくない」と言ってきた時に、じっくりと話を聞いて、「じゃ、楽しくするにはどうすればいいか・・・考えて見ようよ」と、一緒に知恵を出すのが大切ですね。
2024年
4月
19日
金
1970年の大阪万博
毎年のことですが、年少園児の体操教室は、バタバタです。体操着に着替えるのが、まずは大きな壁です。うまくいきません。水筒を自分で飲むのもままならない園児もいます。先生と先輩たちの力を借りて、てんやわんやで頑張ります。体操教室本番でも、マットに寝転がって、まるで、ゲームコーナーのボールプールのごとく、はしゃいでしまいます。こうして、ハチャメチャ体操教室が始まるのです。今は、じっと辛抱の時です。(笑)
さて、来年2025年に行われる大阪万博は、建設が間に合わないとか、参加国が減少するとか、そもそもやる必要があるの?とか、問題が山積みですが、1970年に行われた大阪万博は、それはそれは、すごい盛り上がりでした。私も、一応、親に連れて行ってもらったのですが、子どもだったので、ほとんど覚えていません。
この1970年の大阪万博のコンサートで名曲が発表されました。ジローズの「戦争を知らない子供たち」です。♬戦争が終わって僕らが生まれた~戦争を知らずに僕らは育った~♪という歌ですが、ご存知ですか。
現在の日本の大人たちの大半は戦争を知りません。私も同じです。もちろん、子どもたちも戦争を知りません。ところが、世界中には「戦争しか知らない子どもたち」がたくさんいます。
奈良・薬師寺の大谷師は、こんな法話を説いています。「朝から雨が降っていると、大半の皆さんは、今日はついていないな、と考えます。しかし、空から雨ではなく弓矢や槍が降ってきたらどうします。ましてや、爆弾やミサイルが落ちてこないのは、とても幸せなことではないですか」
まさに、1970年の大阪万博は、日本の高度成長期と重なったことも大ブームの要因でしたが、平和の祭典という意味も大きかったと思います。ならば、2025年大阪万博も、平和を考える機会になれば、意義ある祭典となるのでしょう。
2024年
4月
18日
木
おじさん1人ディズニー
エンドウ豆を毎日必死になって、収穫する3人きょうだい。葉の色も豆の色も緑なので、まずは見分けることが大事です。次は、どのくらいの大きさなら収穫可能か・・・これも、経験によって、食べ頃サイズを収穫できるようになりました。給食に使用されるので、貢献度が高いのです。(笑)
さて、今日は夢の国の話です。コロナ前、まだ東京ディズニーランドに年間パスポートがあった頃、何人かの「1人ディズニー」を楽しむ人を知っていました。アトラクションに乗ることよりも、パレードを楽しむ人たちで、全員女性でした。ところが、最近では、「おじさん1人ディズニー」というライフスタイルが現れたようです。もともと、他の遊園地と違って、東京ディズニーランドは、カップルやグループ、家族で行くところとう概念は当てはまりませんが、さすがに「おじさん1人」は、???ですね。
あるおじさんの場合は、「きっかけは十数年前に娘を初めてディズニーシーに連れて行った時です。その日は、ディズニーシーの人気キャラクター『ダッフィー』のぬいぐるみの発売日でした。並ぶのが大嫌いだったのですが、娘のために2時間半並んで買い与えると、娘はとんでもない素敵な笑顔を見せてくれたのです」これを機に、このおじさんは、シーズンごとに発売されるダッフィーシリーズのグッズを購入するために、ディズニーシーに通うようになり、はまったそうです。「あそこは夢の国というだけあって、僕のようなごりごりのおじさんがダッフィーのぬいぐるみを抱えて1人で歩いていても受け入れてもらえるんです」と語ります。
そもそも1人ディズニーは、ショーやパレードを見学する際は、推しのキャラクターやダンサーの近くを陣取りたい。自分の好きなアトラクションだけを楽しみたい。食事の時間や内容もすべて自分の好みで決めたい。こんな人が、一人で行くメリットを感じているのです。おじさん1人客によく見られるのが、ビールとつまみを片手に、水辺の静かなベンチでたたずむ姿だそうです。
どうですか・・・「おじさん1人ディズニー」を理解できましたか。誰にも邪魔されずにゆったり落ち着いて、非日常的な空間に身を浸すことができるのが、まさに至福の時間なのでしょう。東京ディズニーランドの楽しみ方は、どんどん広がっているようですね。
2024年
7月
26日
金
「自由」と「自律」
明日からのサマーキャンプに備えて、年長以外の園児には申し訳ないですが、今日はプールなしで、教室内でゲーム大会をしました。熱中症予防の最大の対応は何だと思いますか。「水分補給!」と思ったあなた。もちろん正解ですが、一番の効果は「慣れる」ことです。「暑熱順化」と言います。人間の体が暑さに慣れて順応した状態を指します。
人体の体温調節の主たる機能は発汗作用、つまり汗をかくことです。冬から春にかけては機会が減るので適切に働きません。これが、体の不調や熱中症を起こしやすくする原因の一つです。7月からスタートした屋上プールで、子どもたちの「暑熱順化」は、進んだと思われますが、今日は大事を取りました。
年長園児は、サマーキャンプという非日常の生活にワクワクドキドキです。ついつい、自由奔放な行動を取ってしまうかもしれません。初日の川遊びは、楽しみがいっぱいですが、リスクもいっぱいです。最初にライフジャケットで浮く練習をしてから、先生たちも一緒に川に入って、危険個所を確認しながら遊びます。毎年恒例の「岩からジャンプ!」も、すぐ下で先生が待ち構えています。
8人の年長園児の集団生活となるサマーキャンプには「自律」が大切になります。その上で、いつもはできない「自由」を満喫する遊びを体験させたいと思っています。サマーキャンプで「自由」を楽しむには「自律」があってこそですね。
たった2日間ですが、サマーキャンプを終えた子どもたちは、大きな成長を遂げます。「自律」も「自立」も両方獲得します。「友情」「協力」・・・仲間同士で学ぶことも多いですね。そんな子どもたちを成長を見届けながら、明日からの2日間を過ごします。
次回のブログは、サマーキャンプが終わった、日曜日に更新します。子どもたちの素晴らしいエピソードも珍道中もどうぞお楽しみに!
2024年
7月
25日
木
阪神甲子園球場100周年
今日は、卒園児の小学生が8人も集合しました。久々に会った同士、会話も弾みます。成績表を交換して、「あーだこーだ」言っています。そして、うれしかったのは、小5の男子が、保育園の卒園記念品の国語辞典をもってきました。それには、付箋がびっしりあります。1年ごとに付箋の色も変えていました。卒園式の時には、「この国語辞典を引いた文字に線を引いて真っ黒にしてください」と伝えたので、本当に感動しました。
昨日、プールが飛ばされてしまったので、屋根付きの新プールを導入しました。新しモノ好きの園児たちが、さっそく集まって遊びます。大プールも空気漏れがひどくなったので新調しました。たっぷりと水を入れて、小学生と年長園児で水しぶきです。
さて、阪神甲子園球場が8月1日に生誕100周年を迎えます。みなさんは、甲子園球場にどんな思い入れがありますか。日々、夏の甲子園大会への出場校が決まっていきます。私も、中学・高校時代に、甲子園のアルプススタンドで母校の応援をしました。中学の時は、試合途中で雷雨となり、びしょ濡れになりながら応援したものの再試合。高校の時は、蔦監督率いる名門池田高校に惜敗しました。今もしっかりと記憶に残っています。
夏の甲子園は8月にあることがミソです。旧盆があって、終戦記念日には「黙とう」を行いますね。その中で、テレビを観ている国民が平和をかみしめながら野球観戦をするのがいいのです。
甲子園球場は、戦争の影響をもちろん受けています。すでに戦時色が濃くなりつつあった1943年には、内野スタンドが金属提出によって取り外され、やがて球音が響かなくなります。グランドは、なんと芋畑になったのです。終戦後は米軍に接取されます。グランドに球音が戻ったのは1947年です。春夏の甲子園大会もプロ野球も再開されます。敗戦から再起する人々を勇気づけます。大学のアメリカンフットボールの「甲子園ボウル」も、この年からスタートしたそうです。
その後の高校野球は、私もうっすらと記憶しています。「怪物江川卓」の球の速いこと。「ドカベン香川伸行」はそのまんま漫画の世界でした。桑田・清原のKKコンビのPL高校からは、多くのプロ野球選手が排出されました。「ゴジラ松井の5打席連続敬遠」「松坂世代」「ハンカチ王子VSマー君」そして、大谷翔平も甲子園球児でした。
阪神タイガースの記憶では、やはり、バース・掛布・岡田のバックスクリーン3連発です。この年日本一になった阪神タイガースは、本当に強かったですね。
試合には関係ないですが、私のもう一つの思い出は「かちわり氷」です。ビニール袋にかち割った氷が入っているだけで、ストローでチューチューしてもよし。頭を冷やすのに使ってもよし。氷をガリガリ食べるのもよし。この甲子園名物を食べたことがありますか。
現在の甲子園球場は、電光掲示板ですが、手書き時代の選手名のボードも記憶に残りますね。まだまだ、あげればきりがありませんが、みなさんにとっての「阪神甲子園球場」は、どんな思い出が詰まっていますか。
2024年
7月
24日
水
スーパーのレジ 座ってお仕事?!
今日は、週末に迫ったサマーキャンプを前に、年長園児は、ライフジャケットを身につけて、うつ伏せと仰向けに浮く練習をしました。「体の力を抜いて!」と言えば言うほど体に力が入ってしまう5歳女の子です。本番では、深くて川の流れがあります。水も緑色です。本番では、ライフジャケットで浮く練習を入念に行うことにします。
そして、プールが終わってから大事件が起きました。ライフジャケットや水を抜いたプールをおひさまの下で乾かせておきます。昼過ぎに片付けに行ったところ、まるで台風のような暴風雨&雷ゴロゴロです。ペンギンプールとプールの屋根が無くなっていました。どうやら風に飛ばされてしまったようです。他のプールとライフジャケットも屋上に散乱していました。ずぶ濡れになりながら、それらを確保しました。30分くらいで雨風はおさまったのですが、屋上から見下ろしても、ペンギンプール・プールの屋根・たらい3つ・ライフジャケット1つは、見つかりません。とんだハプニングでした。
さて、様々な業界で働き手不足が深刻になっています。雇う側は従業員を確保しようと職場環境の改善に動いています。その中でも、私の常識では考えられない、レジでの接客を座ってもできるようにイスが導入されたスーパーマーケットがあらわれました。
埼玉県では有名な「ベルク」というスーパーマーケットのある店舗では、各レジのカウンターに置かれているのが黒いイスです。レジ打ちをしている従業員は、立ったり座ったりさまざまで、イスは高さが調整できます。お客様がレジに並んでいない『待機」の時に座っている人が多いそうですが、「立ちっぱなしのレジの仕事で、少しでも座れる時間があると楽です」と腰痛持ちのスタッフは言います。
ヨーロッパや韓国など、海外で「座ってレジ」は珍しいことではないそうです。「7、8時間立ちっぱなしもある仕事。疲労していたのではお客様への笑顔も出ない。従業員の負担軽減も理由でした」とベルクのシステム改革部のマネージャーは言います。
お客様の反応はいかに。それが、批判的な反応はほとんどないようです。毎日買い物に来るお客様は「座ってても全く気にならない。今まで何で立ったままだったんだろう、と思うくらい」と話します。
レジでのイス導入も、数年前から当たり前になった、身だしなみ基準緩和も、セルフレジ導入も、「従業員が少しでも働きやすくなるように」は、表の言葉で、本音は、人手不足解消への対策です。スーパーマーケットだけでなく、警備の世界でも「座ったまま警備」も始まっているようです。
私たち消費者の立場で言えば、セルフレジなどは、サービスの実質低下ですね。気心知れた店員さんとの会話もなく、一人黙々と会計を済ませる。買い物の楽しみも、人によっては半減します。しかし、今後、少子高齢化がさらに進み、働く人が減り、長期的な人手不足が続く中では、以前のような至れり尽くせりのサービスを消費者が期待するのは難しくなっています。
私たちは、サービスについては「諦めるものと、そうでないもの」をしっかりと区分けして考える時代になっているのかもしれません。
2024年
7月
23日
火
実生活で生きる言語力
こうも暑い日が続くと、屋上プールをやってないと干上がってしまいそうです。今日もボランティアのパパがスイカを差し入れてくれました。スイカ割り大会がスタートです。昨日に比べると、バットで叩く力が増しています。年長園児のところでスイカにひびが入り、最後の小学1年生で、見事にまっ二つ割れました。大歓声です。
さて、保育園では、子どもたちが、遊びの中での会話を通じて、コミュニケーション能力を磨いています。もちろん、子どもたちは、コミュニケーションという言葉は分からないので、先生たちが「コミュニケーションができているかなぁ~?」という勝手なモノサシで見ているのです。
子どもたちを見ていると、「もう少し言葉を足せば・・もっと違う言い方をすれば・・」なんて思うことは、日常茶飯事です。これが、小学生・中学生になると、言語力が高くなっているので、もっと細かい点で、気になることが多くなりますね。
では、私たち大人は、子どもたちに「実生活で役に立つ言語力」を身につけさせるには、どんなことをすればいいのか・・・考えたことがありますか。
京都にある、あるお寺に掲げられている言葉です。これが、なかなか的を得ています。
「何を話せるかが知性/ 何を言わないかが品性/ どのように伝えるかが人間性/ 」
どうですか・・・言葉を用いて他者と生きる難しさをズバリ表した言葉ですね。では、学校の授業などで扱う言語力は、この3つのうちでどれでしょうか。そう、「何を話せるかが知性」です。学校の先生が、どんなに素敵な授業をしても、子どもたちには、知性しか教えることができないのです。
では、品性と人間性を子どもたちは、どうやって学ぶことができるのでしょうか。それは、授業ではなく、友だちとの関わりの中で、「今は、言わないでおこう」とか「もう少し優しい言い方にしてみよう」を自然と身につけていくのです。これが、コミュニケーション能力なのかもしれません。
そうだ。品性は、大人の立ち振る舞いから子どもが学ぶことですね。大人が普段使う言葉が、最高の日本語であるように、私たち大人も考える必要があるようです。あっ~私も頭が痛いです。(笑)
2024年
7月
22日
月
素直に感動したいなぁ~
今日は、小学生が1年生から5年生まで5人集合です。赤ちゃんを見ると「かわいい!」と今日は世話係を頑張ってくれた5年生女子・・・さすが役に立ちます。小3男子は、ルービックキューブをいとも簡単に完成させていました。屋上プールでは、ボランティアのパパが、大きなスイカを差し入れてくれたので、今シーズン初の「スイカ割り」で盛り上がりました。「おいしい!うまい!おかわり!」の声が響きます。
さて、今日は3人の小学校1年生が登園しました。夏休みに、おうちに持ち帰ったのが、「アサガオ」です。すでに、花が咲いているそうです。夏休みの課題は、朝顔の種を収穫して、その種を来年の1年生に、つなぐことだそうです。自分たちも、先輩から引き継いだ種で花を咲かせたのです。何だか、素敵な話ですね。
アサガオは、一日花ですので、朝から昼にかけて花を咲かせたら、もう翌日には、同じ花ビラは開きません。花はしぼんだままで、今度は「種」になる準備を始めるのです。この観察を、目を輝かせながら、1年生たちは行うのでしょう。子どもたちが、小さな植物を慈しむ心は、まるで天使のようですね。
詩人の相田みつをさんはこう言います。「子どものためにやらなくてはならない事は沢山あるけれど、その中でも一番大切だと思っている事は、子どもが小さいうちに、心の中に美しいものを見て、素直に感動する心を養っていくこと。これが親の大事な務めなんだよ」
では、どうやったら子どもの心の中に、感動の心が芽生えるのか。相田さんは続けます。「まず親が感動しなくては駄目だよ。親の感動は、必ず子どもの心に伝わって、感動する心が芽生えるのだから」
相田さんの詩に「感動とは 感じて 動く と書くんだなあ」があります。まさに、私たち大人は、子どもの「感じる心」を大切にしたいですね。アサガオのような植物からも、ダンゴムシ・てんとう虫・空を飛ぶクマバチやトンボからも、子どもたちの「感じる心」が伝わってきます。いつの時代も、多くのことは自然から教わることが多いですね。私たち大人も、子どもの頃を振り返ってみると、つくづくそう思います。
大人になっても、素直に感動する心を持ち続けたいものです。特に子どもの前では、子どもと同じ目線になってみませんか。
2024年
7月
21日
日
暑いぞ!嵐山・小川
我が家の庭が、伸びた雑草で景観を乱していたので、涼しい朝のうちに「草むしり」をします。朝6時だというのにすでにお日様が顔を出していました。朝から汗だくです。(笑)
でも、ゴミ袋3つ分、しっかりと仕事をして満足の汗です。朝風呂を浴びて、武蔵嵐山に出発です。
今週末のサマーキャンプまで、1週間となりました。特に川遊びをする場所は、ぶっつけ本番というわけにはいかないので、下見に行ってきました。嵐山渓谷で川遊びをします。途中、バーベキューで有名な河原を通るのですが、人がまばらです。この暑さでは、バーベキューをする気にもなりませんね。
そして、サマーキャンプ最初の目的地に到着します。月川荘キャンプ場は、川遊びをするには、もってこいのロケーションです。流れがゆっくりの場所もあるので、足が届かなくても、園長につかまって、楽しく遊ぶことができます。そして、岩からのジャンプは、子どもたちの勇気を引き出す絶好のポイントです。今日は、川の水量がやや多かったですね。この1週間まとまった雨がなければ、水量が下がって、楽しい川遊びができそうです。いつも、子どもたちが並んで記念写真を撮る橋の上に立って、下を流れる川を眺めます。今年の8人の園児たちは「怖~い!」と言わずに立っていられるか、想像していました。
小川げんきプラザまでの道のりを確認します。何度も通っている道ですが、サマーキャンプの2日間が、小川町の七夕祭りです。交通規制があるので、バイパス経由に変更します。
二日目のワークショップの場所は、東秩父村です。小川町の隣り村です。埼玉県でただ一つの「村」が、東秩父村です。ホワイトきゃんばすに登園していた保護者が、ここに移住をして、古民家をリフォームしたショップをオープンさせました。昨年のサマーキャンプから、ここでお世話になっています。
今週末は、子どもたちを連れて、いよいよサマーキャンプです。舞台は整いました。あとは、主演の子どもたちが、どんな演技を見せてくれるか・・・楽しみですね。
2024年
7月
20日
土
小学生・・・夏休みスタート
本日登園した小学生が、成績通知表を持ってきました。いつのまにか、保育園ホワイトきゃんばすに登園する小学生は、園長が頼んだわけでもないのに、通知表を持ってくるようになりました。今日は、2つの小学校の通知表を見ましたが、過去と比べると、各教科の評価がなされるだけで、担任のコメント欄もありませんでした。クラス全員分のコメントを書くことは、担任の仕事量を増やすことにつながるので、ここも「働き方改革」なのでしょうが、毎月「子どもたちの成長記」を書いているおやじ園長にとっては、何だか物足りなく思いました。
小学生時代の成績など、大人になってからの人生にさほど影響を与えないことを知ってる私たちの世代ですが、小学生にとっては、「絶対にC評価は、取りたくない!」と言っていたり、「俺が思っているのと、先生の評価が違うんだよな~」と、私に熱く語ったり、ただただ、わたしは「よく頑張ったなぁ~」と聞いているだけですが、子どもにとっては、親以外の大人に、何か言ってもらうのも大事なことのようです。
ということで、さいたま市内の小中学生は、昨日が終業式で、いよいよ、今日から夏休みです。小学校は、8月27日(火)までが夏休みです。この長い夏休み期間をどうやって過ごしていくか・・・親も大変です。(笑)
もちろん、夏休みの宿題はしっかりあります。ただし、かつてのように「こんなにたくさんあるの!?」という感じではなくて、「読書感想文」「工作」「書道」の中から1つ選択するような、子どもたちに選ばせるスタイルに変わってきているようです。
1か月以上ある夏休みです。理想は、子ども自身で夏休みの過ごし方を考えるのが、一番いいと思いますが、「自分で考えなさい!」と突き放しても、効果があるとは思えませんね。
やはり親が、少し考える必要がありそうです。夏しかない「花火大会」「盆踊り」などの地域のお祭りなどのスケジュールを子どもと共有して「行きたい!」と言わせたいですね。そして、夏休みだからこそ、「図書館で過ごす」新たなライフスタイルを身につけさせたいものです。最近では、おしゃれで、とても居心地がいい図書館が増えています。親も、子どもと一緒に、本と向き合ってみるのもいいですね。
そして、スポーツ&レジャー・・・これも、子どのリクエストの中から、現実的に実行できるプランを親子で考えるのです。
親は、少しだけ、子どもを誘導するものの、子どもが「自分で決めた!自分で考えた!」と思えることが、充実した夏休みにつながることは、間違いありません。今年の夏休みも、多くの卒園児が保育園にやってきます。1年生から5年生まで・・・話を聞くのが楽しみな、おやじ園長です。
2024年
7月
19日
金
最後の体操教室
いよいよ今日が最後の体操教室となってしまいました。近隣の大型ショッピングセンターに移設となり、子どもたちが、毎週金曜日に楽しみにしていた体操教室も終わりです。
現在小学校6年生になった卒園児が、年長の時に体操教室がスタートしました。週1回コースの授業料の半額で、寺子屋全員を指導していただくことで、契約をしました。通常、親が子どもを体操教室に通わせるには、送り迎えをしなければなりません。保育園の体操教室は、親が仕事をしている間に、保育園のプログラムとして行われているので、保護者からも大好評で、子どもたちも週に一度のお楽しみでした。
今でも忘れませんが、契約の商談時、体操教室を運営する会社の専務に、「ひょっとしたら、ホワイトきゃんばすの中から、将来のオリンピック選手が出るかもしれないですね」と言ったら、「絶対にありません!」と強く否定されてしまいました。「オリンピック代表になるには、毎日何時間も練習しているので・・・週○日の体操教室の役割は、体操が楽しくなることです」とのことでした。
その通り、子どもたちは、体操教室を通じて、楽しみながら、できなかったことができるようになっていきました。鉄棒を前にすると、恐怖心で泣き出してしまう園児が、練習を重ねる中で前回りを一人でできるようになったり、とび箱を前に、最後の勇気が湧いてこないで、失速していた園児が、ためらいもなく、とび箱を飛べるようになったり・・・
そんな子どもたちに、「挑戦する心」が育ったのも、体操教室のおかげです。
今まで、指導に関わった先生たちは、10人以上になります。中には、「○○君には、是非、通常の体操教室に入ってもらいたい」と、名指しでスカウトがあったり、現在の年長男子を「ビッグ4」と呼んでいただき、その運動能力を高く評価していただきました。踏み台をジャンプして、空中で前回りをするプログラムに、ビッグ4が挑戦させてもらったこともありました。
保育園ホワイトきゃんばすにとっても、「体操教室があります。ここでは○○をやっています」というのは、屋上の環境と共に、大きな付加価値になっていました。ホワイトきゃんばすのオリジナルユニホームを着て、子どもたちが躍動した6年間・・・体操教室に感謝の意を込めて、最後の日を子どもたちと楽しく過ごしました。
2024年
7月
18日
木
新たなお米需要
今日は、1週間ぶりのプール遊びです。ボランティアの保護者が3人も来ていただきました。子どもたちは、「○○くんのママだ!」「○○くんのパパだ!」と大騒ぎです。そして、サマーキャンプに行く年長園児は、ライフジャケットを着て水に浮く練習をしました。初めてライフジャケットを着る園児もいますので、今日は、「浮く」感覚を身につけます。
さて、今日は「パックごはん」の話です。パックごはんの歴史は浅く、1980年代後半に、当時の新潟県食品研究所で研究が始まったのが、最初だと言われています。そして、誰もが知る「サトウのごはん」が、サトウ食品から初めて商品化されました。1995年の阪神・淡路大震災以降、非常食品として急速に広まっていきました。
私も、最初は非常食品としての認識でした。でも今は違います。共働き世帯や一人暮らしの増加に伴って、料理に割く時間が減り、食事を手軽に済ませたい人が増えているようで、毎日の食卓に欠かせない存在になっているようです。俳優の吉沢亮さんが出演するアイリスオーヤマのテレビCMで「炊飯器売れなくなっても知りませんよ」と言っていますが、外国人など、炊飯器が家にない人にとっても、パックごはんは便利ですね。
農林水産省によると、国内の主食用米の収穫量は、2008年の865万トンから2023年には661万トンと、約3/4に減少しています。パンやパスタなど食の多様化が進んだことが主な要因ですが、今後も人口減少が続くなか、ますます国内需要は縮小していくことが予測されます。しかし、パックごはんは、同じ期間で9万トンから20万トンと2倍以上に増えています。
サトウ食品やアイリスオーヤマといった大手メーカーは、今年新たな製造ラインを稼働させているそうです。「パックごはん」の認識は、すぐに食べられる便利なごはんというイメージから、「おいしさ」を追求する競争が始まっているようです。最近では、北海道の「ゆめぴりか」、山形県の「つや姫」といった高価格帯のブランド米を使ったパックごはんや、減農薬・無農薬米を使ったものなど、付加価値を高めた商品作りになっています。
私は、パックごはんを買う習慣がないので、今までは、スルーしていましたが、今日は、じっくりと、パックごはんコーナーを見てみます。
2024年
7月
17日
水
歴史の学び方
今日は、気温も上がらず、ずっと曇りの天気予報だったので、早々に「プールお休み」を告知しました。朝は予報通りでしたが、子どもたちが屋上に行く時間には、うっすらと晴れ間が出ていました。朝の6時45分からプールに水を入れますので、急きょプールに変更とはいきません。プールボランティアを予定していたパパ2人も、子どもたちと屋上遊びをしていただきました。かけっこをしたり、ぐるぐる回されたり、子どもたちは、いつもと違う屋上遊びに大興奮です。
さて、最近は、様々な歴史番組が放映されています。私は大好きですので、よく見ています。例えば、NHKBSの「英雄たちの選択」では、史実ではなく、「もしあなたが、○○だったら、どんな選択をしますか?」という問いに、歴史に精通するゲスト陣が、自分の見解を述べながら選択する流れになっています。
皆さんが、中学高校時代の歴史の授業は、どんな授業でしたか。私の場合は、年号や出来事を暗記するイメージが残っていますね。テストでも、鎌倉幕府は、何年に開設されたか?のような、年号を答える問題もありました。
現在放映されている歴史番組の多くは、「○○年に△△が起きた」という紹介の域を超えて、「過去の歴史から、今現在、そして、これからの私たちの進むべき道を学ぶ」という、歴史的な出来事を様々な角度から考察する内容になっています。だから、面白いのです。
2022年度から、高校の必履修科目となったのが、「歴史総合」です。近現代の日本史と世界史を融合し、日本だけでなく世界との相互的な視野を学ぶ内容です。来年、2025年1月の大学入学共通テストで出題が始まります。
当然、高校現場の授業が、知識詰め込みからの脱却が求められます。ある高校の授業です。テーマは「穀物法廃止論争を考える」です。1830年代以降に英国で起きた、穀物の輸入を制限する法律「穀物法」を巡る存続派と廃止派の論争について、生徒たちが班に分かれて話し合います。「年号を覚えるのではなく、なぜ起きたのかを考えて」と教師は強調します。授業では、当時の風刺画や小麦の価格の変動グラフ、廃止派の決議文などの資料が用意され、生徒は教科書も参考にしながら意見を出し合います。
「この頃、東アジアでは何が起きていた?」と教師は、さらに問いかけます。生徒たちは、英国が自由貿易を推進していく中で、中国・清とのアヘン戦争(1840年~42年)が起きた経緯を確認。こうして、歴史的な背景や意義について繰り返し議論が進みます。
生徒の一人は、「歴史の勉強は暗記ばかりと思っていたけど、歴史が動く背景を知ると面白い。他の人と議論することで考えが深まる」と言います。こうして、歴史総合の授業は、教師の一方的な知識を教える授業ではなく、グループワークや教科書にない史料などを使い、知識の活用を促します。
どうですか・・・歴史の授業が楽しくなっていると思いませんか。私たち大人は、子どもたちに「歴史の勉強は、これから起きる未来において、どのような選択をすれば、解決することにつながるのか・・・を学ぶ大事な勉強なんだよ。だから、歴史上の人物に自分がなったつもりで考えてみようよ・・・」と、伝えることが大切ですね。
2024年
7月
16日
火
進化する イチゴ
連休明けの保育園・・・雨が降ったりやんだり、気温も低いのでプールはなしにして、屋上フリータイムです。ファームの野菜が、たくさん収穫できました。子どもたちは、インゲン豆をたらい一杯分収穫して、どや顔です。大中小のトマトに、ゴーヤ・キュウリ・白なす・ピーマン・オクラと、ちょっとした八百屋さんができるくらいです。しかし、カラスにきれいに食べられていたスイカ2つを発見。子どもたちの嘆き声が響きます。
さて、今日は「イチゴ」の話です。昨日訪れた南阿蘇鉄道の「見晴台駅」では、キリン午後の紅茶のCM撮影が行われ、上白石萌歌さんが、ホームでヘッドホーンで目をつぶって歌っていると、列車に気がつかないで乗り過ごすシーンが有名です。今、熊本県産のイチゴを使った「イチゴティー」を限定販売していて、見晴台駅の自販機は、すべて午後の紅茶イチゴになっています。
関東に住んでいる人にとっては、熊本産のイチゴ?というイメージですが、全国の収穫量では、栃木県・福岡県に次いで3位となっています。国連食糧農業機関(FAO)によると、2022年の世界のイチゴの生産量は957万トンで、中国が335万トンで最も多く、日本は16万トンで11位です。えっ!そんなに低いの?と思った方が多いと思います。中国などは、ジャムなど加工に回る量が多く、生食での消費量は、日本が世界一です。日本産のイチゴは、海外でも「甘くて香りがいい」と人気が高まり、23年の輸出実績は、10年前の20倍になっているそうです。香港や台湾では、富裕層向けに高額で販売されています。
日本の生産量は、世界11位にもかかわらず、イチゴの品種登録数は310種(6月末現在)で、世界の品種の半分以上になっています。つまり、生食で「おいしいイチゴ」を求めて、品種改良が毎年のように進んでいるとうわけです。埼玉県が誇る「あまりん」は、品評会では堂々の1位ですが、埼玉県のイチゴ生産量は、日本のベスト5にも入りません。つまり、量より質の戦略です。
好きな果物ランキング(6月マイボイスの調査)では、イチゴは72.1%の支持を集め、桃や梨を抑えてトップです。日本人の「イチゴ愛」は不動なのです。「イチゴは品種改良しやすく、値崩れせず値段も安定しているので新規参入しやすい。生き残りには、各産地のブランド戦略が試される」と専門家は語ります。
暑さに弱いイチゴも、安定栽培される工場のような完全管理での栽培も可能になってきました。そうなると、夏場は海外産の輸入に頼っていたのが、季節を問わず、日本のおいしいイチゴが食べられるようになるかもしれませんね。日本人の「イチゴ愛」をしばらくは、見守っていきましょう。
2024年
7月
15日
月
四国・九州 おやじ旅
昨日今日と、連休を利用して「おやじ旅」に行ってきました。中学・高校時代の同期・先輩・後輩6人のおやじ旅です。
日本地図を思い浮かべてください。昨日は、東京6:00「のぞみ1号」で岡山に朝9時過ぎに到着。瀬戸大橋を渡って、四国に入ります。坊ちゃん・道後温泉で有名な愛媛県松山へ。夜10時のフェリーで、今朝5時には、九州の小倉に着いていました。小倉から大分へ。大分からは、阿蘇のカルデラを横断し、熊本へ向かいます。1泊2日で、四国と九州にまで足を延ばしました。いつものように、こんなハチャメチャなおやじ旅を楽しんでいたのです。現在、阿蘇熊本空港でこのブログを書いています。
今日は、「おやじ旅」の中でも、2つのいい話を紹介します。1つ目は、四国松山駅から30分くらい離れた、伊予灘線の「下灘(しもなだ)駅」のボランティア夫婦の話です。「下灘駅」は、青春18きっぷのポスターに何度もなり、駅のホームのすぐ後ろが海というロケーションの有名な駅です。ベンチに恋人と後ろ向きに座って写真を撮るのが、定番になっています。そこに、ボランティアのシニア夫婦がいます。「私も旅が大好きで、色々なところで人々の世話になったので、自分が住むこの『下灘駅』を通して、恩返しをしたいと思っているんです」と言います。奥様も、到着する列車を降りるお客様の誘導や声掛けをしています。ここは、夕日が海に沈むので、絵に描いたようなローケーションなのです。たぶん違うと思いますが、あの「千と千尋の神隠し」で、千尋が海に沈む線路を歩くシーンのモデル駅とも言われています。
ガイドの男性は、下灘駅から見える島の解説をしてくれました。「決して人に話したらいけない!」と言われましたが、下灘駅から見える島が、日本テレビで放映されている「ダッシュ島」だそうです。(言ってしまった!)彼は、「こうして、ここに来てくれた人が喜んでくれれば、毎日おいしい酒が飲める」と微笑みます。そんな人生を送る二人がとても素敵に見えました。うらやましいですね。
2つ目は、本日訪れた、「南阿蘇鉄道」です。昨年、熊本地震から7年・・・ついに完全復旧したローカル線です。今日が、ちょうど全線開通1周年記念日でした。テレビでもよく放映される「トロッコ列車」にも乗りました。南阿蘇鉄道の素晴らしいところは、沿線住民の鉄道愛です。列車が通ると、必ず手を振ってくれるます。そして、多くの駅で、カフェやちょっとしたショップがあります。その店のオーナーが、駅のホームで、お客様を笑顔と、時にはギターを弾いて迎えてくれるのです。こんな気持ちがいい思いはなかなか経験できません。そして、車掌のトークが最高です。ずっと、楽しい話を続けてくれて、大満足の「南阿蘇鉄道」でした。地方のローカル線を支える地域住民の素敵な想いが伝わりました。
旅の思い出は、一生の想い出になります。これからも素敵な旅をしていきたいですね。では、今から羽田空港まで、旅の締めくくりです。
2024年
7月
14日
日
自動水栓蛇口の神様
今日は、自動水栓の蛇口の話です。保育園に入園したばかりの園児が、手洗い場で、蛇口に手をかざしたままじっとしていることがあります。そう、自動水栓に慣れてしまっているからです。JR東日本の新幹線内の自動水栓シェア100%・全世界の航空機シェアの25%・国内全コンビニの80%のシャアを誇る自動水栓の会社が、株式会社バイタルです。知る人ぞ知る会社です。驚くことに、世界で1種類しかない「ネコ専用自動水栓」もこの会社が作ってしまったようです。
今日は、そんなバイタルで職場の神様と呼ばれる「島田より子」さんの話です。彼女は、自動水栓デルマンシリーズの組みたて、検査、梱包、出荷作業を一手に担っています。普通は、男性の職人がイメージされますが、彼女は、あと2年で70歳になる大ベテランです。
「自動水栓の仕事には30年前から携わっていますが、最初は、仕事がなくて会社全体がどん底だった時もありました」と言います。機械化が進んだ製造ラインを想像しますが、基盤に電子部品を取り付けるはんだ付けや電動ドライバーでのビス留めなど、すべてを手作業で組み立てているそうです。
実績を重ね、累計出荷台数は50万台を突破します。コンビニ、新幹線、航空機などに導入され「日本人なら一度は使っている自動水栓」までになったのです。コロナ禍では需要が跳ね上がり、生産が追いつかないほど多忙な時期を経験します。
島田さんは、コンビニやレストランに入ると必ずトイレに行き、自動水栓の調子を確認してしまうそうです。「何年たっても大切に使ってもらっているのを見るとうれしくなる。まだまだ頑張って作らないと、という気持ちになります」と話します。
どうですか・・・みなさんが、自動水栓を使う時は、島田さんという女性が噛んでいることを思い出してください。
2024年
7月
13日
土
子どもの魚離れを防ぐ体験
今日は、久々の屋上プールではなく、普通の屋上遊びです。トマト・白なす・オクラ・インゲン豆・ゴーヤを収穫して、子どもたちのお土産にします。「おれ!ゴーヤがいい!」という小学3年男子・・・小学生になると、あの苦みのおいしさが分かるようです。ビールはダメですが・・・(笑)
さて、みなさんの食卓には、どのくらいの頻度で「魚」料理が並びますか。世代によっても変わってくるでしょう。我が家は、魚と肉がフィフティフィフティと言いたいところですが、わずかに肉が上回っていますね。そして、現代の子どもは、さらに魚を食べることが少なくなっているようです。
えっ?・・・保育園の子どもたちの話を聞くと、「○○寿司に行ってきたよ!」と回転ずしの名前がよく上がります。お寿司の形ならモグモグ食べます。骨を取ったり、箸を巧みに使うのは苦手なようです。中には、回転ずしに行っても、マグロなどの魚ではなく、ポテト・うどん・ラーメン・スイーツなど、寿司とは関係のないものを食べている実態もあるようです。
そんな中、「おさかなせんせい」と呼ばれる都内の飲食店を経営する北川浩太郎さんは、2022年から幼稚園や保育園で計100回以上「おさかな体験教室」を行っています。ある幼稚園では、イカに触れる体験をします。子どもたちは、発泡スチロール箱に入ったイカを触ります。「なんかぷよぷよするね」・・・そして、北川さんがイカをさばきながら、くちばしや内臓などの部位を説明します。そして、調理をしてみんなで食べます。
体験教室の後、子どもが魚に興味を持つ変化があったと答えた保護者は5割を超えるそうです。「子どもが魚好きになれば家庭でも魚料理を作る頻度が上がる」と、体験教室を行った幼稚園の園長は期待します。
魚介類の摂取量は、水産白書によると2019年データでは、1~6歳を除くと、15~19歳が1日43グラムと一番少ないそうです。まさに、若者の魚離れが加速しているようです。保育園でも、火曜日は「お魚給食の日」にしていますが、やはり給食全体での「おさかな構成比」は低いのが実態です。
そんな中で、福島県いわき市では、2020年に「魚食の推進に関する条例」を制定し、毎月7日を魚食の日として地元の魚介類の普及を図ります。小中学校の給食で、地元の魚を提供し、「学校で食べる魚はおいしい」と子どもたちには好評のようです。
「おさかなせんせい」体験のように「魚に触り、調理する体験を通して、楽しくおいしく味わうことが大切で、どのように漁獲され、食卓に届くのかを伝えることも魚への関心を持つきっかけになる」と専門家は語ります。
どちらにしろ、食肉と比べると、明らかに種類が多い魚類ですので、バランスよく子どもたちには食べてもらいたいですね。水族館に行くのも良し、角上魚類のような鮮魚店に連れて行って、魚をさばく姿を見せても良し、子どもたちのワクワクドキドキ体験が、キーワードですね。
2024年
7月
12日
金
自転車が倒れないための3つの力
今日は、ナイトツアーでホタル観賞の予定でしたが、あいにくの雨で中止としました。史上最大総勢75名が参加予定でしたので、残念がる子どもたちと保護者の声が広がります。今月中は、まだホタルが見られますので、ピークの夜8時に、ホタルエリアで楽しんでもらいたいですね。あらためて家族で北本自然観察公園に行くというコメントが、連絡ノートにありました。
さて、8月いっぱいの屋上遊びは「プール遊び」が中心となります。子どもたちは、泳ぎも水遊びも合わせて楽しんでもらいますが、「自転車が倒れないで進むのはなぜ?」という記事を目にしてしまいました。
保育園ホワイトきゃんばすの子どもたちの特徴の一つが、「小学生になる前に自転車に乗れるようになる」です。実は、ここ数年、年少園児が3月末までには、全員が乗れるようになっていますので、寺子屋園児全員クリアが続いています。そして、現在小学2年生の男の子が記録した、2歳8か月という自転車最年少記録は、いまだに破られていません。
子どもたちは、自転車をスイスイ走らせる先輩たちに影響を受け、先生たちの個々の能力に合わせた指導法で、自転車に乗れるようになります。ただし、一度「自転車に乗れるようになりたい!」と宣言した園児には、技術論よりも精神論で乗れるようにしているのが現実です。
そんなやり方ですので、一度、冷静に自転車が倒れない科学的根拠を確認したいと思います。まずは、補助輪がないのに、どうして前に進むのか。どうやら、3つの力が伝わって進むようになるようです。
1つは、ペダルをこいで、自転車を前に動かそうとする力が働きます。2つ目は、地球に引っ張られる力、つまり重力が下向きに働きます。3つ目は、曲がる時に車輪が真ん中ら外へ押し出される横の力が働きます。つまり、同時に「前と下と横」の三方向に力が加わるので、バランスが保たれて倒れないのです。
重力の力に負けない、右左に曲がっても、それを支える前に進む力があれば、転ばないのです。要は、バランスをまっすぐに保ち、力強く、ペダルをこぐことができるようになれば、理論的には、自転車の乗れるようになるのです。
プールが終わって、自転車練習が始まると、精神論だけでなく、この理論で、冷静に子どもたちを「自転車クリア」に導きたいと思っています。
2024年
7月
11日
木
ガチャガチャは日本の文化!?
今日は、雨が降っていたのでプールは中止にして、教室内で体を動かしました。大玉送りを久しぶりにやってみます。2歳・3歳児には大きすぎたようです。そして、盛り上がるのが、「椅子取りゲーム」です。2回ともに、年長園児が優勝したのですが、3歳児の男の子が3位に入り大躍進です。
さて、現在年間3千万人超のペースで訪れるインバウンド観光客のお土産になる人気商品は何だと思いますか?そうです。カプセルトイこと、通称「ガチャガチャ」「ガチャポン」です。
ガチャガチャのインバウンド需要が高まったきっかけのひとつは、2016年に成田空港第2ターミナルの一角にカプセルベンダーをズラリと並べた専門コーナーの登場だそうです。空きスペースを使って何かできないかと、ガチャガチャが並んだのです。考えた人は凄いですね。日本旅行を楽しみ、帰国する際に両替できない小銭の使い道としては、もってこいです。
現在のカプセルトイの中心価格は300円程度です。日本円は、今や世界有数の最弱通貨ですので、かさばらないカプセルトイは、何個でも買える最高の日本土産になるのです。「何が出てくるかわからない」というゲーム性があり、カプセルの中には、フィギアやミニチュア、スマホやバッグなどにつけられるアクセサリーやチャームなど、細かなディテールやデザイン性の高いもの・・・さらに、これでもか!というくらい豊富なキャラクター展開があって、手軽な日本土産になっているようです。
手軽などころか、完成度の高い芸術作品と言っても過言ではありませんね。日本のアニメやポケモン・サンリオなどの作品やキャラクターは、海外人気が高いこともあって、カプセルトイなら、そんなキャラクター商品が安価で大量に展開されてることが、SNSや動画サイトで外国人に、広く知れ渡っているようです。
ガチャガチャだけでなく、外国人には「トミカ」のミニカーも大人気だそうです。保育園の年長男子は、「トミカをもっともっとたくさん欲しい!」と七夕の短冊に書きましたが
、トミカショップには多くの外国人が訪れているそうです。
私が、子どもの頃から親しんだ「ガチャガチャ」は、今では、カプセルトイとして、世界に誇る文化となったのかもしれませんね。日本は、たかが300円だって、完成度が高い物しか市場に出さないという誇りも合わせて・・・立派な芸術文化なのです。
2024年
7月
10日
水
桑の実の話
今日も屋上プールでは、水分&ミネラル補給で、ミニトマトを食べます。子どもたちは、お代わりして「おいしい!」と食べるのですが、今年のトマトは、多くが虫に食べられています。まだ、青いうちに蛾がトマトに卵を産んで、幼虫がトマトに穴をあけて食べまくるのです。農薬を使っていないので、毎年虫の被害となるのですが、今年は、かなり多くて残念です。でも、トマトはたくさん植えているので、元気なトマトをいただきます。
さて、朝刊に「桑の実」の話がありました。保育園の子どもたちは「マルベリー食べるぞ!」と、屋上にある桑の木に登り、お猿さんのように桑の実のつまみ食いをし、桑の実が終わっても、プールが始まるまでは、木登りを楽しんでいました。
今日は、岩手県の里山に暮らす、安部智穂さんの話です。
「今年は庭の桑の実が鈴なりで大豊作です。桑の実は、雨が降るたびにみずみずしく膨らみ、太陽に照らされて黒々と色づき、半年ほどかけて徐々に熟していきます。私は、毎日夕方の1時間を充てています。
柔らかくて潰れやすいので、収穫にはコツがいります。まず、ザルを左手に持ち、枝の下に添えます。ギターの弦をはじくように、右手の指先で完熟した桑の実をポロポロとザルに落としていきます。水でさっと洗って、ザルに上げ、乾いた布をかけて半日おいてしっかり水気を切ります。
保存瓶に移し、あらかじめ氷砂糖を溶かしておいたウオッカをヒタヒタに注げば、3か月後には果実酒のできあがり。深紅に染まった赤ワインのような果実酒は、食前酒として楽しんでいます。
ウオッカを吸った桑の実は、パウンドケーキの具材にします。水気を切り薄力粉をふるいにかけ、ケーキの生地に混ぜ込みます。焼き上がったケーキは、しっとりとした生地と、ツブツブ、プチプチとした桑の実の食感がたまりません。ほんのりとした酸味が口の中に広がります。
おいしい桑の実を楽しみにしているのは、私たちだけではありません。野鳥や昆虫たち。時にはタヌキやキツネ。そして、夜にはクマも来ているようです。姿を見せることはありませんが、木の下に残された茶色の立派な置き土産がその訪問を教えてくれます。特に、桑の実が大好物なのはアナグマです。6月下旬ごろになると、桶職人をしている夫の作業場の床下にすみつき、日に何度も現れては落ちた桑の実をモグモグ・・・。
雨の季節にあでやかに熟す桑の実は、たくさんの生命を楽しませ、育みます。今年もみんなで分け合って、いただきます!」
どうですか・・・こんな暮らしに、とても憧れる私です。
2024年
7月
09日
火
ゲーム 尊い命
昨夜は、北本自然観察公園に行き、ホタルの下見に行ってきました。ホタルゾーンに入ったばかりは、ホタルがチラホラと光を放っているだけですが、奥に行けば行くほど、幻想的な風景になっていきます。手をかざすと、私の手にホタルが止まりました。12日のナイトツアーも雨さえ降らなければ、多くのホタルが期待できそうです。そして、光ると言えば、今日の寺子屋では、「ヤコウタケ」という光るキノコを観察しました。年長男の子のママが持ってきてくれました。テントの中で教室を暗くして観察します。緑色に光るキノコに子どもたちは不思議顔で言葉を失います。私は、このキノコを小笠原諸島の父島で見たことがありました。小笠原では、「グリーンペペ」と呼ばれています。
さて、話題を変えて、今日は命の話です。戦争も長期化すると、ニュース映像に慣れてしまい、どこか人ごとのように感じている人も多いのではないでしょうか。今は、人が人に暴力を振る事件が常態化していること。そして、そのニュースを自分ごととして捉えることが難しいですね。
そんな時に、遊んでもらいたいゲームがあります。「尊い命」です。このゲームは、プレーヤーが拷問者となって、少女に拷問するとう内容です。プレーヤーは、少女を「つねる」「おどす」「ビンタ」で、肉体的・精神的に追い詰める一方で、「休けい」「やさしくする」で回復させられます。このアメとムチを使い分けながら少女を手なずけ、尋問をして情報を聞き出していきます。ただし、尋問の過程で体力をゼロにしてしまうと、「尊い命」が亡くなるのです。
一方で、ある要件をクリアすると少女を「逃がす」ことができます。でも、このゲームの目的は「逃がす」こととは明示されていません。要は、プレーヤーがどう受け止めるかで、ゲームの意味が変わってくるのです。ちなみに、少女を逃がすと、少女は最後に拷問者であるプレーヤーに笑顔を見せてくれるそうです。これを見て、何か良いことをした気分になる人も多いようですが、そこには、「都合の良い思い込み」があり、なぜ、拷問されるのが「少女」なのか、拷問者の性別によって、内容が変わるのか?などを考えると、単純なゲームですが、様々な思考が膨らみます。私もやってみましたが、何度やっても、少女を逃がすことができず、笑顔を見ることはできませんでした。
私たちは、暴力=悪という価値観の下に生きていますが、実際には暴力も戦争も絶えることはありません。このゲームは、自らの内なる暴力性を自覚するためのものでもあるようです。なかなか深いですね。
2024年
7月
08日
月
言葉の美しさ
今日のように、朝の天気予報で、「今年一番の暑さになる予定です」と言われると、覚悟ができるのですが、とにかく毎日暑いですね。そして、夕立が半端ない状況です。ここ数年の当たり前の出来事かもしれないですが、子どもたちは、今日も元気にプール遊びです。ファームで収穫した、トマトとキュウリを食べながら、子どもたちは、ミネラル吸収で、熱中症対策です。
さて、すでに真夏の天気で、梅雨らしくありませんが、まだ明けてはいません。雨が降ると、子どもたちは外遊びができないし、保育園ではプールに入れなくなってしまいます。でも、日本には、雨を表す美しい言葉が多くあります。
緑雨(りょくう)・・・青々とした新緑に降り注ぐ雨
紅雨(こうう)・・・春に咲いた花に降る雨
白雨(はくう)・・・夏の明るい空から降ってくる雨
黒雨(こくう)・・・空が真っ黒になるような大雨
そして、春雨・夕立・時雨などは、季語にもなっていますね。季節の移ろいを、日本の言葉の美しさと共に味わうことができますね。
ある小学校の先生の話です。雨の日に、教室で勉強をしていると「先生、雨がポツンポツンになってきた」「えーポトンポトンだよ」「でもさっきはザーザーだったよね」と、子どもたちから雨の音がたくさん出てきたのです。「せっかくだから、みんなで雨の音を聞こう!」という展開になり、かっぱと傘と雨靴を履いて、校庭に行くことになりました。
「先生、見て見て!雨粒が鉄棒にぶらさがっている!」
「雨粒も逆立ちを頑張っているんじゃないかな」
「なんだか光っていてきれいだね」
「水たまりに傘が映っている」
「水たまりに入ると面白いよ」
などなど、子どもたちの発見は止まりません。
どうですか・・・素敵な授業ですね。机上の学習をたまには、放り投げて、外に飛び出して、言葉遊びをするのもいいですね。子どもたちの心に残る授業になることでしょう。
2024年
7月
07日
日
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
昨日は、おやじ3人で大宮にある昭和レトロな店で飲んでいました。元会社の先輩で、私以外の二人は、今年61歳になって定年退職後、嘱託社員として同じ会社で働いています。65歳までは嘱託社員、75歳まではアルバイトで働き続けることができます。契約は1年ですので、自分都合でいつでも「や~めた!」とも言えるし、会社から「もういらない!」と言われる可能性もあります。
これからは、日本の多くの企業で、こんな働き方が当たり前の時代になっていきます。というか、すでになっています。年齢を重ねても、「お前が必要だ!」と周りが思ってくれれば、やりがいは持続できます。どちらにしろ、自分のモチベーションを維持していくために、どんな仕事をしていくか・・・そんなことを考える年齢でもありますね。
さて、仕事が忙しいサラリーマンのあなたは、最近、ゆっくりと本を読んでいますか。働いていると、読書に限らず音楽や絵画などに触れる文化的生活と日々の生活を両立させるのが難しいですね。私も、読む本といえば、教育や保育に関わる本、このブログで紹介するような内容の本ばかりで、ここ何年も「純愛小説」は読んでいません。(笑)
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の著者である三宅さんは、明治以降の労働と読書傾向を追いながら、日本の働き方変遷を語ります。「明治、大正時代は、読書はエリート層が教養を得るための手段で、戦前から戦後になると中産階級がエリートに続けとばかりに読書に親しみ、オイルショック以降は読書は娯楽になります。バブル崩壊は、本よりスマホからの情報が優先されるようになった」と言います。
「スマホは今自分に必要な情報をだけを提供してくれますが、小説などの本は自分に関係のない情報(ノイズ)が多分に含まれている。実は、そのノイズこそが知識や教養なのに、毎日働いている生活ではそれを受けとめる余裕がなくなる」と続けます。
これからの働き方は、全身全霊で仕事に身を捧げるのはいい加減やめた方がどうか。と作者の三宅さんは提案します。すでに、「全身全霊で仕事なんてやってないよ」という若者は多いかもしれませんが、仕事、家庭、趣味にそれぞれの居場所を作る生活が、自分の人生を豊かにすることは、間違いないようです。
仕事に疲れたら、酒を飲むのもいいですが、たまには本を読みたいものですね。
2024年
7月
06日
土
道端のカタバミ
あまりにも暑さに、土曜日ですがプールを楽しみました。水着がない小学生も、洋服のまま泳いでいます。ファームのキュウリに塩を振って、子どもたちはモグモグと食べています。このシンプルな食べ方で、熱中症対策にもなっています。(笑)
さて、今日は、文科省科学技術・学術政策研究所から「ナイスステップな研究者」に選ばれた千葉大学准教授の深野さんの話です。
みなさん、カタバミという野草をご存じですか。クローバーに似た葉で、黄色のかわいらしい花を咲かせます。しかし、繁殖力がとても強い厄介な雑草でもあります。花が終わり種になると、パッと周りに種が飛び散り、様々な場所で繁殖が始まります。もっとやっかいなことは、根がどんどん広がって、多年草なので、一年を通じて広がっていきます。花は、黄色のかわいい形状ですが、保育園のファームでも、このカタバミがすぐに広がっていきます。
深野さんは、コロナ禍に近所を散歩中に、葉の色が赤くなったカタバミを見つけます。野外調査を始めると、都市部の宅地付近のカタバミは赤く、そこから数十メートル離れ、暑さが和らぐ公園のカタバミは緑色です。わずかな距離の違いでも葉色が変わっていたことで、「都市の高温が影響しているのかも?」とひらめいたそうです。研究の結果、赤い色素は、都市の高温からカタバミが受ける熱ストレスを和らげているいる可能性があることをつきとめます。
深野さんは、日本のモンシロチョウは、羽の特徴に雌雄で差があるが、欧州などではそれがないことは、まさに千年単位で生じたもの言います。また、直物や昆虫だけでなく、人間心理も進化の視点から研究をしています。現代人が虫嫌いになった理由について、進化心理学の視点で迫ったものです。
「虫嫌いを増やしたのは、都市化によって虫を見る場所が室内に移ったことや、虫の種類を区別できなくなったため」と、13,000人を対象にした調査の結果から仮説を提唱します。
これは、保育園の子どもたちを見ていると納得できますね。屋上で見る虫には、大きな嫌悪感は抱きませんが、教室内で虫を発見した時の「ギャー!」という叫び声は止まりません。外で虫を見る習慣が少なくなれば、子どもたちが虫嫌いになっていくのは、間違いありません。
深野さんの研究は、私たちが気がつかないような視点で行われています。これからも、彼の取り組みに注目したいですね。
2024年
7月
05日
金
子どものスポーツクライミング
いよいよ渋沢栄一の新一万円札など、新紙幣が発行されました。保育園ママの一人が、銀行に勤務しているので、早々に新紙幣を両替してもらいました。朝の会で、子どもたちに、立体感覚の新紙幣を見せます。年長園児は、数字は読めますので、これは10,000円5,000円1000円と言い当てます。さすがに、「埼玉県深谷市出身の渋沢栄一」さんの名前は出てきませんが、新紙幣に興味津々でした。
さて、子どものスポーツクライミングの世界が、どんどん広がっているようです。東京都港区は、すべての公立の小学校と幼稚園にボルダリング設備を設置したそうです。港区の小学校では、休み時間になると、ボルダリング壁のマットの前に大勢の児童が列を作ります。壁は高さ4メートル幅5メートルです。ホールドの色や形状、大きさはさまざまで、ホールドを自由に使って登るのは比較的簡単ですが、色分けされた一部のホールドだけを使って登ろうとすると難易度が高くなるそうです。
「頭を使わないと登れない。ホールドをどう持てば体を押し上げられるのか、考えて登っている」と小3女子が言います。挑戦を繰り返しているうちに、自然に考える癖がつくそうで、保護者の評判は上々です。
東京オリンピックで、日本人選手がメダルを獲得する姿を見ていると、スゴイ握力があるから登れると思いがちですが、握力だけでなく、全身を使うスポーツであることが分かります。「バランス感覚や柔軟性も養われる。壁をどう攻略すればいいか、思考力も鍛えられる」と専門家は言います。
スポーツクライミングは、体操教室やスイミングスクールと同じで体力の向上につながりますが、頭を使って手順を考えないとゴールにたどり着けないので、何度もの失敗を乗り越えてやり遂げたときに大きな達成感が得られます。「体を使ったチェス」とも呼ばれているそうです。
全国でもクライミングジムの数は、どんどん増え続けているそうです。そして、子どもたちにとっては、もう一つの魅力は、手を伸ばせば「世界」につながる競技ということです。野球やサッカー、バスケでは競技人口も多くて競合が激しいですが、スポーツクライミングはまだまだこれからの競技です。
どうですか・・・あなたのお子様の習い事の候補になるのでは。
2024年
7月
04日
木
小学生が政党をつくり模擬選挙
今日も屋上はプール日和です。今年は、水を怖がる園児がほとんどいなくて、ボランティアの保護者も、そんな子どもたちと本気で楽しんでいます。ボランティアスケジュールもほとんど埋まってきました。何度もボランティアに参加してくれるパパもいます。
さて、東京都江東区の小学校で面白い取り組みが行われました。6年生がクラスの枠組みを超えて、子ども中心になっていない身の回りの問題を考え、同じ考えを持つ子どもたちで政党を結成。そして、カリキュラムの最後に行われる「子どもまんなか総選挙」に向けての活動です。
昨年4月の施行された「子ども基本法」に使われている「こどもまんなか」という言葉に注目して、この取り組みがスタートしたようです。クラスの枠を超えて、政党を結成するという考えは、6年生の担任の話し合いで決まったそうです。
では、どんな政党が名乗りを上げたかというと・・・
「イベン党」・・・イベントを増やして明るい江東区に!イベントを通じて経験を豊富に!何と関係者は、ほとんどボランティアなので、お金がかからない!
「こどもハッピー党」・・・子どもたちの暮らしを大切にします。子どもたちのためのスペースづくりを行う。生活を充実させる工夫を実践する。
「健康精進党」・・・健康的で安全な生活を!!運動不足の解消対策。ミストシャワーを設置します。
「NO!ストレスの会」・・・いいめがない学校にします!
こんな感じで、3クラスを解体し、11の政党が生まれました。子どもたちは話し合いを重ね、互いに歩み寄るような姿も多く見られたようです。総選挙は、体育館で行われ、子どもたち・教員・地域の人・保護者が見守る中、「ぜひ、わが党に一票を!」というプレゼンが行われたのです。
これは、小学生でありながら、まさに「キャリア教育」と言えますね。チームで話し合う点は、非認知能力がぐんぐん成長したことでしょう。「最後までやり抜く」ことができた、子どもたちは、大きく成長したことは間違いありませんね。
こんな素敵な取り組みが、広がっていけばうれしいです。
2024年
7月
03日
水
「みんなちがって、みんないい」の子どもへの説明
今日から、屋上プールには、プールボランティアのパパやママにも一緒に頑張っていただきます。ミッションは、ずぶ濡れになって、子どもたちと遊ぶことです。6歳男の子のパパが、本日のターゲットです。「予想以上に子どもたちの暴れっぷりは激しかったです」と言っていました。でも、思う存分楽しめたようです。
さて、私も大好きな、詩人金子みすゞさんの「みんなちがって、みんないい」という言葉があります。人間は、みんな違っていて、個性という大切な特徴を持っていて違っているのが当たり前で、違っていても悪くないし、恥ずかしいことでもなく、みんなが大切な存在です。そして、同じようなタイプの集まりよりも、違うタイプの集まりの中から、大きな発見や、解決策が生まれるのです。という意味です。
ただし、保育園の子どもたちに、「みんな違っていてもいいんだよ~」を説得力ある言いかたで伝えるには、なかなか難しいですね。そこで、いい例えを見つけました。そのまま引用します。
「みんなは、焼き肉を食べたことがありますか。焼き肉は好きですか。あの焼き肉のおいしいタレは、にんにく、ショウガ、唐辛子、こしょう、砂糖、蜂蜜、みりん、ごま油、しょうゆ、レモン汁などを混ぜ合わせて作ります。甘いものや辛い物、酸っぱいものが混ざっておいしくなるのだそうです。人間も同じで、いろいろな違う人が一緒に力を合わせるから楽しいのです」
これなら、子どもにも分かり易いですね。そして、「人と違うことを笑ったり、同じもの同士でかたまって、人をからかって、バカにして笑う人間だけにはならないでください。世界の違う文化や風習を楽しみ、素敵だと思える心が、世界を歩んでいける人になるのです」
どうですか・・・我が子に話しをしてみませんか。
2024年
7月
02日
火
令和6年度プール開き
今日は、待ちに待ったプール開きです。昨日から、プールの配置などいろいろレイアウト作りをしていました。今年のプールは6つあります。①大きいプール②スライダープール③ファインディングニモプール④ジャブジャブプール⑤屋根付きプール⑥ペンギンプールです。これにベビー用のたらいプールも用意しました。ニモプールとペンギンプールは、保護者からいただきました。屋上にある、自転車・ストライダー・三輪車の多くも保護者からの贈り物です。ありがたいですね。
子どもたちが、屋上に到着すると、お日様が出てきました。きちんと準備体操をして、「ゆっくりプールに入るんだよ~」と先生が言うものの、年長男子は、次々に大きいプールにダイブして水しぶきを上げます。「おいおい・・・」ですが、子どもたちの勢いは止められません。
大きいプールは、年長園児が中心になって遊んでいますが、スイミングスクールに通い始めた2歳児が、年長園児たちと同じように、カッパのごとく泳いでいます。スゴイ光景です。
もちろん、ニモプール・ペンギンプールでまったりと過ごす子もいます。園児それぞれが、自分に合ったプール遊びを初日から見つけたようです。でも、子どもたちが一番楽しんでいたのは、水鉄砲での戦いごっこです。「お友だちが、やめて!」と言ったら、やらないという、シンプルなルールですが、誰一人「やめて!」とは言いません。一番若い先生が、子どもたちのターゲットにされていました。びっしょりです。
明日からは、プールボランティアのパパママが参加していただきます。壮絶な水かけ合戦が、例年繰り広げますので、子どもたちは、手ぐすねを引いて待っています。また、ボランティアの保護者にとっても、我が子がいつも遊んでいる園児と直接かかわることで、より深く保育園を感じてもらうことができます。
さて、プール初日にはしゃぎ過ぎた子どもたちは・・・お昼寝タイムでは、午後3時の終了時間になっても、なかなか起きてきません。しっかり遊んで、たっぷり寝る・・・子どもたちの規則正しい生活です。(笑)
8月末まで、屋上プールでどんな物語が生まれるか・・・期待しましょう!
2024年
7月
01日
月
長岡大花火
今日は、6人の園児が体調不良でお休みです。手足口病が3人です。明日からのプールを前に、子どもたちが早く元気に登園できるよう祈ります。そして、本日入園手続きにいらした保護者が凄かったです。入園に関して持ち物等の説明を主任がするのですが、紙にメモは取りません。すべて、スマホに瞬時に打ち込んでいくのです。昭和のおやじには、まったくついていけませんね。(笑)
さて、日本3大花火の一つに数えられる、新潟県長岡市の花火大会を見たことがありますか。私は、サラリーマン時代に、新潟県を担当したことがあり、今は閉店してなくなってしまった「大和(だいわ)百貨店長岡店」の食品課長とビール片手に楽しみました。「一生に一度は行きたい」と言われる花火大会ですが、まさにその言葉通りのスケールです。
信濃川の河川敷で見たのですが、打ち上げの場所が近いこともあって、まさに頭上に大きな尺玉の花火が上がるのです。そのまま火の粉が自分の頭に落ちてきそうです。2023年の長岡花火大会を20台以上のカメラで迫った圧巻のドキュメント映画「長岡大花火 打ち上げ、開始でございます」が、公開されました。
毎年8月2、3日の2日間で打ち上げられる花火には、空襲や新潟県中越地震など数々の苦難の歴史と、「復興」や「平和」の思いが込められています。平原綾香さんのJupiterにのせて、今までとは違うスケールの花火に、誰もが度肝を抜かれました。音楽と花火のコラボレーションが見事なのです。
この映画の坂上監督は、「花火って一瞬で消えてしまうなかに、どこか自分のこれまでを
振り返らせるようなところがあると僕は感じている。世界中のどんな人の心も動かすエモーショナルさがあり、国境を超えると感じます。その美しさと迫力をぜひ劇場で楽しんでください」と言います。
確かに、映画館のスクリーンで見たら、長岡大花火の迫力が伝わってくるでしょうね。この映画を見てから、本物の長岡花火大会に行きたいものです。今年は、金曜日・土曜日と最高の曜日まわりです。
今日から、7月に入りました。各地の花火大会は、コロナ前の規模に戻りつつあります。みなさんは、どこの花火大会に出かけますか。
2024年
6月
30日
日
やり投げ 北口棒花
笑顔というのは、本当にまわりを明るくさせてくれますね。保育園の園児の中にも、笑顔が素敵な子はたくさんいます。そんな、笑顔と実力で、パリオリンピック陸上やり投げの日本代表選手が、北口棒花(はるか)さんです。
昨年8月の世界陸上では最終6投目で66m73をマークして逆転優勝。女子フィールド種目では日本人初の金メダル獲得となりました。今シーズンも好調が続いています。北口さんは、今年3月に広告会社が発表した「アスリートイメージ評価調査」では、総合ランキングで大谷翔平に次ぐ2位。「親しみやすい」アスリートでは1位に輝きました。野球やバスケットボールならともかく、やり投げのようなマイナー種目では異例です。「笑い声が耳に残って覚えてくださっていて、笑うとバレるので、一緒にいるみんなに『笑うな』って言われます」と本人コメントです。
北口選手の自己ベストは67m38ですが、「ぶっちゃけていうと、私練習では55m飛べてまあまあいいラインなんですよ。で、本番では65mとか投げるタイプなんで。やっている自分も、予想できない試合に臨んで、投げてやっとわかることが多いんです」と言います。これは、単純に「本番に強い」ではなく、「練習で飛ばないのはめちゃくちゃ考えて投げているからです。気をつけたい所が10個あったら練習では10個全部考えながら投げるけど、試合ではそれを2、3個に減らす。その分、迷いなく全力で投げられるんです」と言います。
北口選手は、小さい頃から陸上をやっていたわけではありません。小学生ではバトミントンで全国大会で団体優勝をしています。あのバトミントン五輪代表の山口茜さんと対戦したこともあるそうです。中学時代には水泳に打ち込み、全国大会に出場します。
高校に入学して陸上部に入ります。やり投げを始めてわずか2か月で北海道大会を制覇し、2年生の時に、全国大会で優勝するのです。北口選手は、小さい頃から試合をしてきたおかげで、どういう気持ちで試合に臨むといいのかとか、どういう準備をすべきかというのがわかって取り組めているといいます。
先日、アメリカのスポーツデータ分析を行う会社が、パリオリンピックでの日本の金メダル予想を12個としましたが、その1つは、女子陸上やり投げの北口選手です。今年から栄養士に食事管理をお願いしているそうで、練習拠点のチェコでは、小麦の料理が多く、シチューやカレーなど重めなので、日本のご飯を中心にした食事を取っているそうです。
さぁ~パリ五輪では、注目の選手の一人として、期待しましょう。
2024年
6月
29日
土
いじめるのは「しずかちゃん」
子どものネットいじめが、過去最多を更新したそうです。2022年度のデータでは、いじめ全体の約3.5%が「ネットいじめ」と、まだ割合は低いように感じますが、5年前の2倍になり、過去最多となったのです。LINEでの仲間外しや無視などの陰湿な内容です。
今日は、小学校5年の卒園児が登園したので、小学生でのネット問題について聞いてみました。すでに、クラスの半分以上が「マイスマホ」を持っています。彼が友だちとのコミュニケーションで利用しているのは、LINEです。しかし、彼のクラスでは、ネットいじめは、まったくないと言います。彼は、何かあればすぐに「声をあげる」ことができる性格なので、彼の周りでは、陰湿ないじめが起こりにくいのでしょう。
現実は、親が家事などで忙しい時に、子どもにYouTubeなどの動画を見せていることもぱり、すでに2歳でネット利用率60%です。この環境なので、小学生にはスマホを持たせない・・・というのは、土台無理な話ですね。塾や習い事での安全確認で子どもにスマホを持たせることもありますね。
いじめも時代の流れで変化をしていて、今では、かつての、ドラえもんのジャイアンのようなガキ大将タイプではなく、しずかちゃんのような清楚な優等生がいじめの主犯だそうです。ネット時代では、ジャイアンのように暴力を振るえばそれを動画に撮られて拡散され、逆にいじめられます。しずかちゃんが、LINEなどを駆使し、いじめの頂点に立っているというわけです。
ある心理学者は、ねっといじめが起きる背景をこう言います。「ネットいじめは、手段として直接手を下すわけでも相手の苦しむ顔を見るわけでもありません。しかも、子どもたちはSNSでの投稿に慣れているので、いつもの投稿の延長のように、匿名でできるため、罪悪感を抱きにくい」「学校という集団の中で、子どもたちはメンバーが固定されている。子どもたちの社会は、村社会のように流動性が低く、このメンバーが嫌だと思ってもすぐに変えることができない。こうした集団では強い同調圧が働き、誰かが誰かをいじめていても『ノー』と言えず、放置してしまう仕組みが生まれる」の2つをあげます。
それでは、子どもたちをネットいじめから守るにはどうすればいいのか。1つは、大人が子どもの居場所を多角化し、いじめを見つけた時はいじめた理由を絶対に肯定しないことが重要と言います。子どもは、学校以外に居場所があれば、集団内のメンバーに嫌われても『ノー』と言うことができます。そして、いじめの本質はスケープゴートなので、いじめに関わった子どもは、いじめた理由を正当化しようとしますが、何であろうと肯定してはいけないのです。
昔からですが、いじめを受けた子どもは、親も含め誰にも相談できないことが多いです。最近では、いじめ相談アプリもあるそうです。匿名で学校の外で相談することができます。
そして、私のPTAの経験上、いじめをなくす手段として効果的なのが、校長先生や担任の先生が「うちの学校にはいじめがあります」「うちのクラスでは、今いじめが起きています」と全員の前で話をすることです。「大人が目を光らせているぞ!」は、私たち大人の役割として大切なのです。
2024年
6月
28日
金
一歩先を行く中学入試問題
今日はかなり強い雨が降りました。屋上は、湖のようになっています。そこで、とび箱やマットを出してきて、教室内で体操教室です。とび箱が盛り上がります。当然、年長と年少の比較や、個人の運動能力の差があります。全身筋肉でできているかのようなバネを持つ5歳男の子は、まるで体操選手のような高い跳躍を見せます。しかし、最初は飛べない園児も飛び方の基本を教えるだけで、格段に上手になります。こんなところからも、「基本が大切」というのが、よくわかりますね。
さて、今日は中学入試問題の話です。中学入試というと、膨大な知識を身につけて問題に対峙するというイメージが強いですが、それは、過去のことになりつつあるようです。過去問題集を出版する「声の教育者」の後藤さんは、「2015年あたりから記述が増えたり、設問数を減らして、考える時間を増やしたりするなど、思考力を問う問題が増加しました」と話します。
では、具体的にどんな問題が出されているか、興味がありますね。
慶應中学校の問題です。解答用紙には、キリンとパンダの絵があります。問題は、「キリンの模様・パンダの模様を描きなさい」です。普段よく目にしているようで意外と覚えていないものが問題になりました。「受験勉強ばかりでなく、いろいろなことに興味を持って観察して欲しいという学校からのメッセージが込められています」と後藤さんは言います。
2021年に、センター試験に代わって、大学入学共通テストが導入されました。問題文に会話が引用されて長文になり、グラフや表などの資料が付記され、読解力や思考力が重視されるようになりましたが、実は、中学入試は大学入試が変わる前から、難関中学を中心に読解力、思考力が試される問題が出題されているようです。
では、もう一問・・・開成中学校の国語の問題です。問題は、カニ弁当を売り切った営業社員と、売り残した営業社員について販売部長が社長に報告する場面の描写から始まります。「新宿支店の大西社員は、販売用に500個のカニ弁当を発注し、池袋支店の小池社員は450個のカニ弁当を発注しました。最終的には、新宿支店の大西社員は500個完売しますが、池袋支店の小池社員は、20個の売れ残りを発生させてしまいました。この問題には、午前9時の開店から午後19時の閉店までの売れ行き総数のグラフが示されています」
販売部長の報告を聞いた社長は、売り切った大西社員よりも売れ残した小池社員を評価しました。ここで問題です。「大西社員より小池社員の方を高く評価した社長の考えはどのように考えられるでしょうか。『たしかに』『しかし』『一方』『したがって』の4つの言葉を使って説明しなさい」
どうですか・・・中学入試の問題ですよ。大人でも、難しい問題です。ポイントは、販売総数のグラフを見ると、大西販売員は、閉店前の18時にすでに500個完売させていたのです。
このヒントで、ピンときましたね。大人の私の答えは、「大西販売員は、たしかに500個完売させました。しかし、小池社員は430個しか販売できなかったことになります。一方、グラフを見ると大西販売員は、18時には完売してしまったので、閉店前の1時間に商品があれば、さらに売上が取れたことになります。したがって、大西販売員は、発注見込みが甘く、販売チャンスロスを発生させてしまったのです。最後まで、完売を目指して頑張った小池販売員の方が、評価が高いと言えます」
こんな答えを中学受験をする小学校6年生が答えるなんて、私の想像の範疇を超えています。しかし、このような問題を解くには、知識の詰め込みだけではできないことだけは、間違いないです。これからの若者には、「考える力」がますます問われるということです。私たち大人も、子どもに考えさせるアプローチが大切ですね。
2024年
6月
27日
木
心を鍛える
今日は、「どろんこ遊び」の日です。どろんこ広場を田植え前のように、ドロドロにします。気持ちいい!と感じるか、気持ち悪い!と感じるかは子ども次第ですが、今年は、大いに盛り上がり大成功です。年長男子4人が、泥水に顔からダイブします。それを見ていた他の園児に「楽しい!」が伝わり、見事に全員が泥だらけになりました。7月からプールが始まりますが、このメンバーなら、プール時間が楽しく盛り上がりそうです。
さて、もうすぐ、パリオリンピック・パラリンピックが開催されます。あるオリンピック選手のコーチの話を聞いてください。「体力や技術を高めることはもちろん必要だが、それ以上に心を鍛えることが大切だ。行動は、すべて気持ちに支えられている」と言います。
身体と精神のバランスが大事であることは、私たちも漠然と認識してるところですが、心を鍛えるには、具体的にどのようにすればいいのか・・・具体論が知りたいですね。
そのコーチは「それは、あいさつをすること、返事をすること、履物をそろえることの3つです」と、たった3つのことが大事だと言います。
なんだか、当たり前のことに思えますね。あいさつや返事をすることの大切さは何となく分かるのですが、履物をそろえることとはどういうことだと思いますか。「はきものをそろえると、心もそろう」「ぬぐときにそろえておくと、はくときに心がみだれない」のだそうです。何げない動作に人の心は鍛えられていくのですね。
「心を鍛える」を考えると何か大きな努力をしなければいけないと思いがちですが、まずは、3つの当たり前のことを当たり前にすることが大切です。子どもには、教えやすい内容ですね。
2024年
6月
26日
水
北風と太陽
昨年夏に飼育していたカブトムシが卵を産み、幼虫として越冬し、サナギから、ついに成虫になりました。今日は、オスが1匹とメス2匹を観察しました。子どもたちは、「俺が捕まえる!」とやる気になっていたのですが、カブトムシの足は爪が強くて痛いので、思わず手を放してしまいます。今シーズン初カブトムシです。
さて、今日は、子どもが不登校になったある母親の話です。
子どもに「学校へ行かなくてもいいよ」と言える親はどのくらいいるだろうか。私の場合、自分の価値観や過去の経験上、その選択肢はなかった。息子が小6の時に学校に行き渋った。でも、私は何としても行かせようとした。この行為は、息子にとって断崖絶壁から突き落とされることだったに違いない。当時の私は「休んだら行きづらくなるし、勉強が分からないとますますやばい」と思い、毎朝「起きて!学校に間に合わないよ?お母さんは会社に行かなければいけないんだけど!」と息子を引きずり出し、小学校の先生方と一緒になって、あの手この手で何とか登校させた。私は「北風と太陽」の北風で、旅人の息子を凍えさせるばかりだった。旅人が求めていたのは北風ではなく「安心して旅に出れる暖かい太陽」だった。息子は旅に出る意欲を失い、反抗することもなく、殻に閉じこもってしまった。旅をする意味も、まだ見ぬ新しい世界への興味さえも失ってしまった。
この話のように、結局、引きこもりになってしまった息子でしたが、母親は、フリースクールという場所があることを知り、息子は、中学時代のほぼすべてをフリースクールで過ごし、現在は不登校になることなく、高校に通っているそうです。
皆さんも、よくご存じの「北風と太陽」の童話では、太陽が絶対的な正解であり、北風のような対応をとるべきではないとされています。この母親の場合も、北風の対応を取ってしまったがために、我が子が引きこもりになってしまったのです。
でも、我が子に対する、アメとムチのバランスが、それぞれの親子で違うように、北風の対応をした方が、子どもの成長につながることもありますね。太陽が100%正解とは、私は思っていません。
それゆえに、子育ては難しいのですが、北風の厳しさの中にも、愛情を持つ母親を私は知っていますし、太陽の優しさが、甘やかしにつながって、がまんができない子どもになってしまうこともあるでしょう。時と場合で、北風と太陽を使い分ける必要だってありますね。
ということで、今日は、北風ばかり悪者扱いしないで!という話でした。
2024年
6月
25日
火
「納得解」を見つける
今日の寺子屋では、久々に「しりとり探検」をしました。お店で売っている商品をしりとりをしながら探していく、探検ゲームです。メガネ→ねんど→ドーナツ→ツナ→なす→すいか→貝まで進み、答えた園児が、売場を探しますが、なかなか見つからないときは、みんなで協力して「あそこじゃないの?」と探します。そして、貝→イチゴと答え、みんなでイチゴ売場に向かいました。しかし、そこには桃が並んでいて、イチゴは売っていませんでした。すると、年長男子が「イチゴはしゅんじゃないから、もう売ってないんだよ」と言ったのです。旬という言葉を知っているなんて、スゴイ!
さて、ここで問題です。「友だちから手紙が届きました。ところが、切手が不足していたため、足りない料金を自分が支払うことになりました。皆さんなら、足りない料金を自分が支払ったことを、手紙を出した友だちに話しますか。それとも話しませんか」
次の問題です。「逆に、自分が出した手紙の不足分の料金を、友だちが支払ったとします。そのことを自分に話してほしいですか。それとも話してほしくないですか」
答えは、それぞれ半分ずつにはなりませんでした。自分が料金の不足分を支払ったときには「話さない」けど、友だちが不足分を支払ったときには、自分に「話してほしい」と答えた人が多かったのです。私も、同じでした。
でも、それって、おかしいですね。このように、たとえ同じ問題であっても、立場を変えると考えが変わってしまうことが、この世の中にはたくさんあります。今回の問題は、正解がない問題です。私たちは、これからの人生の中で「原子力発電」「死刑制度」「クローン問題」「脳死・臓器移植」といった問題をどう考えたらいいか、いずれも正解はありません。
しかし、そのときに大切なことは、自分が知っているわずかな情報だけで判断しないことです。自分とは違う考えの人の立場で情報を集め、公平な目で比べる必要があります。よく、「相手の立場になって考えなさい」というアドバイスがありますね。
こうして、人によって考え方が違うのは当たり前のことですが、同じ人でも、その時に置かれている立場によって「答え」は変化し続けるものです。最近よく聞かれる言葉に「納得解」があります。正解がない問題があっても、いたずらに対立することなく、自分が納得できる「納得解」を共に見つけようとすることが、これからの世の中には必要なのかもしれません。
ひょっとしたら、戦争のない平和な世界は、それぞれ立場が違う国が「納得解」を見つけ合うことかもしれませんね。
2024年
6月
24日
月
70歳までどう働くか
今日は、サマーキャンプ2日目に行う、着物の端切れを使ったワークショップの打ち合わせをしました。東秩父村で起業した、ホワイトきゃんばすの元保護者に来ていただきました。今年度は、埼玉県内の中学校3校で、起業についての講演を行うそうです。2年生・3年生を相手に、どんな話をするか、今から構想を練っているとのこと。「中学生相手に起業の話なんか、早いんじゃないの?」と思ったあなた。子どもたちが、社会に出てどんな仕事をするのか…その中に、「起業して自分で会社をおこす」という選択肢だってありますね。何より、子どもたちが、自分の将来に夢を持ってもらうには、熱い起業家の話は、持ってこいと言えます。
さて、合計特殊出生率が過去最低と報道されてから、少子高齢化をどうする?という議論が高まっています。0.99と初めて1を割った東京都の知事選でも公約の大きな柱として掲げられています。しかし、ここ1~2年の短期間で、少子化が解消されるわけではありません。反対に高齢化問題については、労働人口が減っていくのが分かっているので、「元気なうちは働く」ことが当たり前になっていきます。そうです。これからは、70歳までどう働くかを考えないといけません。保育園のパパママは、まだ先の話ですが、親世代は、バッチリ当てはまります。
あのニトリは、7月から65歳迄の再雇用の上限年齢を70歳に引き上げます。給料も、定年前の最大9割を維持できるようにするそうです。社内からは、歓声があがったそうです。かつての日本は、「シニアなんて・・・」という雰囲気があふれ、「厄介者扱い」でしたが、今では、その経験を生かせると、重要な戦力として受け止められています。
国の調査では、2023年で「努力義務」と定める70歳までの就業機会確保措置をすでに実施済みの企業は29.7%と3割に迫っています。ある大手メーカーの資料には次のような趣旨の記述が並びます。「現在3%の60歳以上の従業員の比率が10年以内に17%に上昇する。60歳以上の人材の一層の戦力化を図る・・・」どうですか、企業は、シニア戦力を活用しないと生き残れなくなるのです。例えば、TOPPANホールディングスは、50歳以上の社員が全社員の31%を占めるので、この層が頑張らないと、会社も傾くというわけです。
今の若者は、終身雇用など全く考えていないでしょうが、現在50歳以上の昭和世代は、新卒で入社して約30年以上頑張ってきました。そして、ようやく一息つけると思ったら、あと20年が待っていた。という感じです。その20年をどう働いていけばいいのか。
色々な考えがあります。50代前半のキャリアとそれ以降は「別の物」と考え、どこかの段階で一度ポストオフし、その後は仕事の負荷を下げながらプレーヤーとして働き続けるイメージが私の中では、しっくりします。もちろん、ずっと同じ会社にいる必要はありません。50歳まで転職したことがない社歴は、決して誇らしいことではなく、「辞めて他の道を選ぶ自由」だってあることを忘れてはいけませんね。
かつて、お荷物のシニアが、「そんな給料じゃ働かないよ!」と言えるような時代になってきたのです。体が元気に動く限り、自分の価値は、いつまでも高くありたいものですね。あなたがすでに50歳を超えているならば、70歳までどう働くかを考える必要がありますね。
2024年
6月
23日
日
おやさいクレヨン
関東地方もようやく梅雨入りし、今日は朝から雨が降っています。保育園ホワイトきゃんばすが入るショッピングセンターの4階に、新たにオープンした屋内大型遊園地は、日曜日の雨ですので、大盛況になります。客数が800人を超えるそうです。
さて、「おやさいクレヨン」をご存じですか。10色で、税込み2200円です。値段以上の付加価値を感じる人が、買い求める商品の一つですね。ちなみに、10色は、「りんご」「赤ビーツ」「むらさきいも」「日本藍」「たけすみ」「ほうれんそう」「ねぎ」「パプリカ」「にんじん」「ごぼう」から作られています。どうですか・・・興味がわいてきましたか。
このうちの、「にんじん」「ほうれんそう」「ごぼう」は、埼玉県産の野菜が使われています。形が悪い、傷がついているなどの理由で廃棄されるはずだった野菜が、「アストラフードプラン」という会社の「残りかす」を粉末化する機器を使い原料となります。実際に「おやさいクレヨン」を製造する「mizuiro(みずいろ)」は、国産の米ぬかから採れる「米油」や「ライスワックス」をベースに、本物の野菜の粉末を原材料にして「おやさいクレヨン」を作っています。もちろん、野菜だけの色素だけでは薄いので、顔料も使用していますが、通常のクレヨンで使われる量の1/3以下に抑えられています。この顔料は、食品に使われているものを使用しているので、子どもが誤って口に入れても安心なのです。
保育園的には、子どもたちと「おやさいクレヨン」を使うとしたら、色々なことが想定できます。まずは、野菜の勉強になりますね。「屋上で作っている野菜からでもクレヨンができるかなぁ~」なんて、会話がはずみます。そして、「捨てられるはずだった野菜」がクレヨンに生まれ変わった話は、どのように子どもたちに伝えることができるか。子どもたちがよく知っている言葉に「もったいない」があるので、そこにつながります。普通のクレヨンとの描き比べだってできますね。そして、野菜が苦手な子どもが、野菜が食べられるようになるのは難しいかもしれませんが、野菜への興味を持ってもらうきっかけにはなります。
りんごクレヨンで、リンゴの絵を描く・・・パプリカクレヨンで、黄色のパプリカを描くのも楽しそうですね。クレヨンが、どのようにできるかなんて、普段子どもたちは考えませんが、「おやさいクレヨン」であれば、勉強にもなりますね。
大人が興味を持つクレヨンかもしれません。
2024年
6月
22日
土
いのちの電話 相談員不足
今日の園長課外授業は、さいたま市見沼区の市民の森にある「リスの家」に行ってきました。小1の卒園児2人と年長園児2人は、シマリスが放し飼いされている空間で、それは大興奮です。ここには、約100匹のシマリスがいます。飼育員さんが用意するひまわりの種などを主食としますが、リスの家の中にある「ザクロ」や「ビワ」などの果物も食べます。バッタやカマキリなどの昆虫だって食べてしまいます。シマリスは、10月から4月まで冬眠をしますので、今は活動期です。
さて、今日は「いのちの電話」の話です。深い悩みを抱える人たちの心に、主に電話でのやりとりを通じて寄り添う「いのちの電話」で、相談員の不足が全国的に課題になっているそうです。
「千葉いのちの電話」では、相談員の養成講座の開講式で、今年度は定員40人で募ったところ、受講者は15人だけです。「ロールプレイング」などを通して、傾聴の技術を来年3月まで学びます。ここでは、無償ボランティアの相談員が5交代制で24時間、電話の声に耳を傾けます。2023年度は、「生きるのがつらい」「職場でいじめを受けている」など、約1万8480件の相談が寄せられたそうです。自殺をほのめかす人もあり、相談員は相手が電話を切るまで3~4時間、対応することもあるそうです。
どうですか・・・大変な仕事であることが、あらためて理解できます。こんな大変な仕事にもかかわらず、「電話口で相手が落ち着いた」と言ってくれるなど、気持ちが通じ合ったと思えた時にやりがいを感じると、ある相談員は話します。
相談員になる人たちの動機は様々です。定年後に社会貢献したいという人や、知人や芸能人の自死などを受講のきっかけに挙げる人もいます。ただし、相談員の高齢化が進み、全相談員の4割を70歳代が占めるそうです。毎年、15~20人が辞めていくそうです。
全国的にも同じ傾向で、平均すると10年前よりも2割少ない人数で対応しているそうです。「茨城いのちの電話」では、電話相談の手不足をカバーしようと、SNSでも相談を受けているそうです。文字だけなので、声の調子がわからないので、「はい」「ええ」などの相づちの言葉を頻繁に打ち込むといった工夫が必要で、特別な相談員が担当してるそうです。
悩みを抱える人は、誰かに相談することで、その悩みが少なくなったり、やわらいだりすると言います。そんな相手となってくれる全国の相談人の皆様には、本当に頭が下がる思いです。
2024年
6月
21日
金
赤ちゃんが泣きやむ音
今日は、雨になってしまいましたが、体操教室の日なので、寺子屋園児は、しっかりと体を動かします。飛び箱の上から、ジャンプをしながら、投げたボールをキャッチするプログラムに挑戦しました。ボールを高く上げると、子どもたちは、ジャンプをするのですが、ジャンプとボールを取るタイミングを合わせるのが、かなり難しかったようです。せっかちな園児は、ボールを上げるのと同時にジャンプするので、タイミングが全く合いません。ちゃんと、ボールを取れた園児は、わずかでした。
さて、今日は、「赤ちゃんが泣きやむ音」の研究を20年も続けている、日本音響研究所の鈴木所長の話です。この研究所は、音にまつわる事件や事故で、音響解析や声紋鑑定を行います。1980年代以降は、音から情報が得られることが広まりました。その後、防音などに精通するゼネコンや住宅メーカー、音響工学を研究する大学、そして科捜研など、音を解析する企業や機関からの依頼が増えます。
食品メーカーからは、おいしそうな「食音感」の共同研究や、テレビ局からは「幽霊が出ると言われるスポットの音を調査してほしい」などの変わった依頼もあるそうです。そんな中で、鈴木さんが20年来研究を続けているのが、「赤ちゃんが泣きやむ音」です。きっかけは、あるバラエティー番組からの依頼で「赤ちゃんが泣きやむCMの現象を調査して欲しい」だったそうです。そして、わかったことは、赤ちゃんにとって聞きやすい周波数があることです。その後、この放送を見た玩具メーカーから連絡があり、赤ちゃんが泣きやむおもちゃの開発につながったそうです。
私たちの日常生活の中に「音」がありますが、音に関して「当たり前」と思っていたことが、世間的にはあまり知られていないことが多いと鈴木さんは言います。「例えば、『人の気配』ってありますよね。これは、『音の反射』だと説明できます。たとえ見えなくても、後ろに人がいると感じる感覚は、科学的にも証明できます」と。
ちなみに、赤ちゃんが泣きやむ音は、「ビニール袋をくしゃくしゃにした時の音」「ドライヤーの音」「テレビの砂嵐の音(今のテレビではできないかな?)「掃除機の音」「換気扇の音」「ママの胎内の音」「食器洗いの音」などだそうです。もちろん、個人差があるでしょうが、お試しあれ。
2024年
6月
20日
木
女性の管理職
今日は、屋上ファームで「じゃがいも掘り」をしました。朝のお片付けタイムでは、いつもは10分かかる仕事が、6分で終わりました。じゃがいも掘りを楽しみたい気持ちがそうさせたようです。もちろん、「いつも、こうやりなさい!」なんて、ヤボなことは言いません。(笑)
そして、じゃがいも掘りです。今年は、大豊作です。土の中からゴロゴロとビックなじゃがいもが出てきます。あっという間に、収穫かご3杯がいっぱいになりました。寺子屋園児は、大きなじゃがいもを手にして、ニッコリ。チビちゃんたちは、土で手が汚れるので、ややためらいがちですが、覚悟を決めてがんばりました。じゃがいもは、とれたてよりも数日置いた方がおいしくなるので、来週のお土産です。
さて、今日は女性の管理職の話です。ジェンダー指数の低いといわれる日本ですが、多くの企業で、女性の管理職が増えてきました。しかし、女性管理職に話を聞くと、「責任が大きくなり、精神的な負担が大きい」「労働時間が長くなり、家庭との両立が困難」「これまで、会社には女性管理職がおらず、ロールモデルがいない」「経営トップが、女性登用の意義や必要な体制について十分理解していない」などの意見が挙がってきます。
何だか、デメリットだらけに見えますが、どうやら、そうでもないようです。ある女性は、足を運んだ社外の勉強会で、ジェンダーの専門家の女性から「自分が管理職になって変えていけばいい」とアドバイスを受け、「目から鱗が落ちた」そうです。
彼女は、同時期に課長になった女性の同僚と「このままじゃ、まずいよね」と、育休後に復職しても、しばらくたつと辞めていくケースが多い女性が多いことを問題視します。男性経営陣は「みんな、いろいろ事情があるからね」と楽観的で危機感がありません。そこで、数の力を求めて、慎重に社内根回しをしながら「女性活躍推進プロジェクト」を立ち上げたのです。社外のダイバーシティ勉強会にも顔を出し、様々な企業の参加者から話を聞きます。こうして、制度を作り、社内環境や風土を変えていきます。今では後輩たちに「管理職に就いた方が楽だよ」と伝えているそうです。以前は、自分の目標達成だけしか頭になかったが、今は、視点も目標軸も変わった。「さらに上のポジションを目指してもいいかも」と思うようになったそうです。
実は、こんなデータがあります。管理職経験のある女性に自らの経験について聞いたところ、7割近くが「人生経験としてプラスになった。管理職になって初めて見えてきたことがある」と答えたそうです。
今から10年以上前なら、「女性の管理職が少ないのは、世の中の流れからすると問題」と判断して、意図的に女性を管理職に登用する企業も多かったと思います。ところが、現在は、男女問わず、実力で管理職になるのが当たり前ですね。女性の比重が高くなったのは、女性の能力がもともと男性に劣るものではなかったからです。
家事や子育てなど、当然夫婦が協力するのが当たり前の世の中になってきたとはいえ、出産に伴う女性の負担は大きいです。現実は、女性で管理職に就きたいと思う人は8.6%だそうです。まだまだですね。
年下の上司は当たり前の世の中ですが、年下の女性の上司が、今後さらに増えていくことは間違いありません。管理職は、あくまでも、仕事上の役割です。年上だろうが年下であろうが、男でも女でも、自分の組織を活性化させるのが仕事です。謙虚に、自分の能力を最大限に活かしてほしいですね。
2024年
6月
19日
水
高校の共学化問題
教室内のピアノの上に、七夕飾りが完成しました。寺子屋園児は、それぞれ短冊に願い事が書かれています。3人の園児は、自分で文字を書いていました。それぞれ、子どもたちが自分で考えた願い事ですので、大切な内容ですが、いくつか紹介します。「お金持ちになりたい」「野球選手になりたい」「お花の妖精になりたい」・・・どうですか、妖精以外は、努力次第で、本当になれますね。
さて、今埼玉県では、県立高校の共学化問題が起きています。発端は、県民から寄せられた1件の苦情です。「埼玉県の男子校が女子の入学を拒んでいるのは不適切で、認められるべきだ」とう内容です。具体的には、浦和高校に入学して、東京大学を目指したいのに、女子では入学できないという内容です。これを受けて、県の第三者機関である「男女共同参画苦情処理委員会」は、「早期の共学化」を勧告しました。埼玉県教育委員会は、8月末までに、委員会への報告を求められているのです。もちろん、県立の男子高、女子高の役割や歴史的背景を考えると、どちらかというと、共学化反対の意見の方が多いようです。
全国には、私立の男子高・女子高はたくさんあります。私も男子高出身です。ところが、県立(公立)で、男女が分かれる高校は、埼玉県の12校を筆頭に、群馬県・栃木県・千葉県・鹿児島県の5県だけだそうです。東京の都立高校で男女別学はありません。
第三者機関は、「共学化すれば男女共同参画が進む」という考えですが、これには、私も?ですね。別学でも共学でも、本当に求められるのは、ジャンダーの「公平さ」です。男女が同じ教室にいても、そこに不平等が存在すれば公正ではないし、男女が一緒に過ごすことを生かしたジェンダー教育がなされていなければ「共学」は形だけで、「異性観を学ぶ」ことにはつながりません。当たり前ですが、要は学校がどんな教育方針でジェンダー問題と向き合うかが重要なのです。「男女を分けること自体が差別」という単純な考え方なら、全国の私立高校も共学にしなければいけませんね。
男子高を卒業した私も、女子高を卒業した私の長女も、別学という環境の中で、ジェンダー問題を軽視したことはありません。私の昭和時代は、少し怪しいところはありますが。
「高校生が、やがて大人になり社会に出れば、会社などの組織は、男女で構成されているんだから、学校だって男女共学がいいんじゃない」という意見もありますが、高校生活では、自分が社会に出ることをイメージできる教育は必要ですが、社会の縮図である必要はありません。別学でも、十分に社会に出る自分をイメージできます。
また、共学の方が「性差」をより意識する機会が多いので、将来の役に立つという考えもあります。これなど、大きなお世話で、共学の環境があるがゆえに、自分が「女である、男である」を常に過剰に意識させられる弊害も考えられます。男だから、女だからは、これからの時代には、無くなっていくことです。
埼玉県民の私は、今回のクレームに対応するには、「浦和高校(男子校)と浦和一女(女子校)」や「川越高校(男子校)と川越女子(女子校)」を合併して、東大などの難関大学への合格率が高い高校を作れば、解決できると考えますが、これも愚策ですね。
公立校、私立校問わず、共学校・男子校・女子校など、様々な学校があって、それを選ぶのが、子どもたち自身と保護者です。当然、選ばれる高校になるために、ジャンダー問題だけでなく、様々な教育方針が共感される高校になればいいだけの問題です。現在、私が住む埼玉県で起きている「男女共学問題」・・・ちょっと待った!ですね。
2024年
6月
18日
火
「エレキソルト」スプーン
今日は、まとまった雨が降りました。屋上ファームの野菜にとっては恵みの雨です。明日は元気に満ちた野菜たちを見られそうです。そろそろ、トマトの収穫ができるかもしれません。
そして、今日の寺子屋では、「お尻ずもう」をやってみました。これは、ただお尻の圧力が強い子が勝つとは限りません。タイミングをずらして、一気に攻める知能派園児が優勝しました。予想以上の大盛り上がりです。
さて、私は、健康診断の結果が出ると、医者から色々な苦言を呈されるのですが、その1つに「塩分を控えめでお願いします」があります。このセリフを医者に言われた人は、世の中に多くいることでしょう。
スーパーの棚には、「減塩」と書かれた商品が、あらゆる分野で目につきます。50%減塩しょうゆに20%減塩みそなど、厳密に味を比較したことはないですが、まずいとか、薄味と感じることはあまりないように思います。それでも、ときに物足りなさを感じて、塩を足したくなることもあります。これでは、減塩の意味がありませんね。
40%減塩をうたったレトルトカレーは、素材の味は感じられ、ルーだけ口に運ぶとおいしい。でも、ごはんと一緒にがつがつ食べるには、もっと濃い味があってほしいと感じるようです。ネットのレビューには「塩を振って食べるとうまい!」と書かれていたり。これも本末転倒です。(笑)
これらを解決する、画期的な商品が「エレキソルト」とうスプーンです。塩味の元となるナトリウムイオンは食品中に分散しています。それが舌に触れることで私たちは塩味を感じます。エレキソフトは微弱な電流でイオンの動きをコントロールし、多くのイオンが舌に触れるように調整するのだといいます。実証実験では、減塩食の塩味が、1.5倍程度増強されるとの結果が出たそうです。
どうですか、食塩の取りすぎは解決しつつ、今まで通りの「おいしい食事のある人生」が継続できるという画期的な魔法のスプーンですね。ただし、初回分の予約抽選販売は終了しているようで、6月中旬からハンズ新宿店などで限定販売されるそうです。値段は、1本1万9000円(税込み)です。これを高いと思うか、生涯の健康を考えれば、安い投資と考えるか・・・あなた次第です。
どうやら、エレキソルトは、味をしょっぱくするというよりは、味が際立つスプーンとなるようです。興味のある人は、1万9000円でお試しあれ。
2024年
6月
17日
月
身近なところで「生物多様性」を知る
昨夜は、さいたま市西区内の「栄(さかえ)小学校」で、ホタルの鑑賞会がありました。私がPTAに関わっていた15年前から、「栄小のホタル」は、知る人ぞ知る名物でした。今でも、「西区ホタルと田んぼの会」がメインで、継続的に行われています。保育園でも4家族がホタルを観にいったそうです。栄小学校のホタルは「ヘイケボタル」です。
幼虫時代は、校舎の中にある水槽で、エサのタニシをたっぷり食べて大きくなり、サナギになる前に、「ホタルのお宿」に移されます。ここで、サナギになり成虫になります。ホタルは、幼虫の時から光るので、5月には、すでにホタルのお宿はピカピカしていたそうです。
自然の中で生きるヘイケボタルは、7月に入ってから成虫になるのですが、栄小学校のホタルは、エサをたっぷり食べているので、成長が早いようです。昨日は564名の来場者があったそうです。私も、ホタルを観るまで1時間待ちでした。ざっと、5匹のホタルが舞っていました。
ホタルと言えば、保育園ホワイトきゃんばすで、毎年行っている「ナイトツアー」は、北本自然観察公園のホタルを鑑賞します。今年は、7月12日(金)を予定しています。昨年は、ざっと500匹のホタルがホタルゾーンを舞い、まるでイルミネーションのようでした。栄小学校のホタルは地域の人たちの協力で行われている素晴らしい取り組みですが、蛍の光では、北本の500匹にはかないませんね。
今日は、そんな北本自然観察公園での生物多様性について学びます。昨年の秋から冬にかけて、枯れたナラの木のうち、倒木や落枝の危険性が高い木を伐採・剪定したそうです。伐採した木の多くは「コナラ」という落葉広葉樹です。ちなみに、カブトムシやクワガタが蜜を求めてやってくる木の1つです。コナラの木を伐採するだけで、公園内の生物多様性に変化が現れます。
冬から春先には、枯れ枝から昆虫などを探して食べる「アカゲラ」が、例年よりも多く確認されます。逆に、コナラを食草とするアカシジミやミズイロオナガシジミといった、シジミチョウが、例年現れる5月中旬を過ぎても、今のところ見つかっていません。伐採で日当たりがよくなった場所では、希少なヤマユリが増えたそうです。ナラ枯れによる伐採の影響で、生き物たちのバランスが変化しているのです。公園スタッフは、今後、夏から秋、冬に向けて、雑木林の木陰の減少や景観の変化、搬出できなかった伐採木の残置などの問題が、生物多様性にどのように影響するのか、引き続き見守り、管理していくそうです。
私たちは、日常の生活の中で、「ここに新しいマンションが建った」とか「ここにあったパン屋さん、無くなってしまったね」などの経験をします。でも、人として生きていくには、そんな大きな変化にはつながりません。生死につながる大問題には決してなりませんね。
ところが、自然環境の中では、コナラの木が伐採されるだけで、生物多様性に影響が出てくるのです。私たち人間は、これまで、あまりにも無関心だったのかもしれません。しかし、自然の景色がかわるだけで、動植物にどんな影響があるのか、考えることはできますね。「自然を大切にしよう!」とうスローガンを掲げるのは、簡単なことですが、その深い理由まで、私たちは考える必要があるのです。
2024年
6月
16日
日
失敗を楽しむ脳
今日は父の日ですね。保育園の子どもたちは、冷蔵庫に貼るマグネットをパパにプレゼントしました。もちろんパパの似顔絵があります。母の日と色違いの同じプレゼントです。私にも、娘から日本酒が届きました。もう25歳の立派な社会人の娘からのプレゼントですが、ニンマリと嬉しさをかみしめる父親です。ただし、母の日と比較すると父の日は現実的には、とても寂しいです。母の日の市場規模は1200億円あるのに、父の日は、その半分の600億円しかありません。数字だけなら、父への愛情は、母の半分です。(笑)
この現実は、父親の子どもへのかかわり方と比例しているのかもしれませんね。令和の時代は、父親も育児休暇をとり、家事をこなすのも当たり前になってきているので、何とか、母の日の80%くらいにまで、市場規模が大きくなることを祈りたいです。(笑)
さて、そんな父親ですが、子どもに対して、よく言うこと一つに「失敗を恐れないで、新しいことにどんどん挑戦しなさい」があります。みなさんも言ったことがありますね。私も、保育園の子どもたちに何度も言っています。
最近の子どもたちは、ネット社会が普及し、調べればすぐに答えが分かる時代に生きています。そうなると、失敗する経験は以前よりも少なっているのでしょう。生成AIが、さらに発展すれば、あらゆることについて、AIにアドバイスを求めてしまう社会になるのかもしれません。
脳科学の研究者である、量子科学技術研究開発機構の山田真希子グループリーダーは、脳科学の観点から「失敗や逆境がある時こそ、成功した時により強い幸福感が生まれる」と話します。逆に、失敗を過度に恐れる人の脳では、不安や抑うつに関わる前頭葉の脳機能ネットワークの働きが弱いことなどを明らかにしてきました。
そもそも、日本でベンチャーが少ないのも、失敗への恐れが強いからだといわれています。米国の起業家は、3つ4つの起業の失敗経験を勲章のように誇り、次の挑戦に目を輝かせるといいます。「失敗するのは当たり前。逆に失敗しないと成功はない」という考えです。
あの物理学者「アルバート・アインシュタイン」は、「チャンスは苦境の中にある」との明言を残しました。AIが人間の領域へ侵入しつつある中、人が生きる実感を感じるには、失敗を楽しむ脳が大切になりそうですね。そんな、脳になる訓練方法が現在開発中とのことです。
私たちは、子どもたちへ「失敗を恐れるな!」の言葉に、もう少し具体的なメッセージを考えて、「失敗を楽しむ脳」になってもらいたいですね。
2024年
6月
15日
土
こうばしい日々
今日の園長の課外授業は、「川越氷川神社」のお参りです。風鈴ロードが目的でしたが、本格的に風鈴が飾られるのは、7月7日以降とのこと。しかし、風車と風鈴を見ることができました。そして、一番の出来事は結婚式が行われていたことです。神前式ですので、花嫁さんが白むくでした。子どもたちは、ウエディングドレスはよく見ることがあっても、白むくに感動していました。「白くてきれいだね」とそのまんまの感想です。(笑)
さて、子どもたちにとって、「学校の大人たち」が魅力的であれば、とても居心地がいい場所に変わっていきますね。今日は、江國香織さんの「こうばしい日々」という小説を紹介します。
日本で生まれて、ほどなく家族でアメリカに移った少年「ダイ」の日常を描いています。11歳のダイの学校には、とても魅力的な「学校の大人たち」がいました。学校のランチルームで働く年配の女性や、担任の先生、校長先生・・・誰一人も「黙って指導に従いなさい」「子どもにはわからないだろうけど・・・」と言う大人は一人もいません。共通点は、子どもを見下さず、フラットに語る姿勢です。子どもだからと、適当にごまかさずに、本質的なことを自分の言葉で語る人たちです。
友だちと、取っ組み合いのけんかをしたダイに、「はでにやったそうじゃない」と、笑顔を向け下校を見送る校長。担任の先生は、「1つのことを、初めから知っている人もいるし、途中で気がつく人もいる。最後までわからない人もいるのよ。タイミングって、とても個人的なものなの。だから、誰にも必ず、今だ!っていうタイミングが来るからね」と言います。
ここは、日本の学校ではありません。アメリカの学校っていいなぁ~と思う人もいるかもしれませんが、日本にだって、「学校っていいな」と思える場所は、たくさんあります。そして、そこには、間違いなく魅力的な大人たちがいるのです。
学校だけではありませんね。あなたが、子どもと関わる時に、魅力的な大人でありたいものです。子どもを見下さないことや、フラットに接することも大事ですが、私たちが、子どもたちに胸を張れる「自分スタイル」で生活していることが大事ですね。
2024年
6月
14日
金
なぜ勉強するのか?
昨日は、屋上プールの空気チェックをしたのですが、小学生含めて4人きょうだいの園児のおうちでは、長さ3メートルのプールを2つ並べて遊ぶそうです。飛び込みも水かけも何でもありのプール遊びになるようです。保育園のプールは、7月に入ってスタートしますが、小学校では、すでにプール開きとなっています。さいたま市内の小学校の中には、プール授業を外部委託し、近隣の室内プールで年間を通じて行っている学校が増えてきました。学校プールの老朽化も理由の一つですが、水泳指導は、命にかかわる専門性が高い内容なので、プロに任せよう!というのが、一番の理由ですね。
さて、今日は究極の問いを考えます。「なぜ勉強するのか?」です。子どもから問われたら、親のあなたは何と答えますか。「大人になって困らないため」「夢をかなえるため」といった抽象的な答えが浮かびますね。でも、この答えでは、子どもたちの勉強は進まないかもしれません。(笑)
先日の「おかしの学校」では、ロッテの「パイの実」の製造工程を勉強しました。子どもたちには、「おかしの学校で勉強したんで、おうちでパイの実を食べる時に、このパイは、64回も折りたたんであるとか、チョコレートは注射器のような機械で、パイが焼きあがってから入れるんだよとか、麦芽糖のシャワーでカリカリになるんだよ。とか、ママパパに教えられるね」と話をしました。これも、勉強する具体的な理由の一つですね。
プロ棋士の藤井聡太さんなどの一流のプロは、将棋を打つ時に「自分はこう打つ」という正解が先に思い浮かび、その後に、どうして自分はそう考えたのかを確かめているそうです。私は、てっきり、相手の手を読みながら、先の手を考えていると思っていました。つまり、一流のプロ棋士には、私たちには見えない世界が将棋盤の中に見えているようです。医者もレントゲン写真から病気の正体を見つけ出します。医学を勉強した医者には、私たちには見えないものが見えているのです。
年長の男の子が、今夢中になっているのが、「理科ミラクル」という本です。ママがお風呂に入っていると、一人で本を読んで、ケラケラ笑っているようです。男の子は、決して、将来役に立つから「理科ミラクル」の本で勉強しているなんて、これっぽっちも思っていません。その瞬間を楽しくするために、豊かになるために取り組んでいるのです。
「なぜ勉強するのか?」には、正解がありません。子ども一人一人、年齢によっても、その答えは違ってきます。どうして?は分からなくても、面白くて楽しい勉強なら、子どもたちが一生懸命取り組むのは間違いなさそうです。子どもは、成長過程において、必ず「なぜ勉強するのか?」という疑問を持ちます。小学生になってからか、もっと小さい時かもしれません。そんな時に、親のあなたは、大人のあなたは、あなたが学校の先生なら、何て答えますか。正解がないので、「私はこう思う」をきちんと伝えられればいいと思います。
あなたの答えは何ですか。言えるようにしておいた方がいいかもしれませんね。
2024年
6月
13日
木
フリーランスという生き方
今日は健康診断です。「さぁみんな~今からパンツ一枚になって!」の言葉に、年長年中園児が、「わぁ~はずかしい!」と、大きく反応します。体操着に着替えたり、屋上遊びで汗いっぱいで着がえる時には、何のリアクションもないのに、みんなそろって、パンツ一枚を楽しんでいるようです。そして、先生の聴診器に泣き出す園児はゼロでした。小児科の先生の話では、現在、特定の病気の流行はないそうです。
さて、フリーランスの仕事をみなさんはどう思っていますか。「組織に属さない一匹狼でカッコイイ」と思っている人も多いようですが、そう誰でもできる仕事ではありません。
イラストレーターのTさんは、「なりたくてなったわけじゃなくて」と言います。大学を出て、普通の会社に就職するものの、人前で過度な緊張や不安に駆られる「社交不安障害」と診断されて、30歳で2度の退職を経験します。アルバイトを経て、職業訓練校と民間の養成学校でウエブデザインを学びます。3度目の就職を考えたそうですが、「また同じことを繰り返すかも・・・」という不安がぬぐえず、選んだのが、フリーランスの道でした。オンライン会議やメールが中心で、人付き合いが得意でないTさんには合っていました。それでも、イベントなどに顔を出しては、コツコツと人脈を広げ、仕事を増やしていったそうです。
定年退職を目前にフリーになったNさんは、34年勤めた会社でシステムエンジニアとして働いたそうです。人事部に異動した際にキャリアコンサルタントの資格を取得し、自分の経験を生かし、他人のキャリア形成の相談に乗る。これなら、一生できるのではと考えて、フリーのキャリアコンサルタントになったそうです。1か月に30~40人ほどの相談に応じ、シニアモデル、ウエブライターとしても活動しています。「自由な時間に、できることがたくさんあると気がつきました。会社員時代より忙しいかもしれない」と言います。
総務省は、2022年の就業構造基本調査で初めてフリーランスの実態を調べます。本業がフリーという人は209万人いたそうです。「地元で働きたい」「家族との時間を大切にしたい」など、個人の価値観が多様化していくと、フリーならそれをかなえられると考える人が増えているようです。
しかし、フリーランスは「ひとり」とうイメージが強いですが、実際は、冒頭の二人のように、交流会などに参加し、人脈を築く努力をしていました。ひとりでやるからこそ、余計につながりが重要な仕事ですね。
フリーランスに必要な資質として、①自己研さんを怠らない②他人を巻き込む力がある③セルフマネジメントができるの3つがあると言われています。どうですか、フリーランスで輝いて仕事をしている人は、これらの能力を磨いていかないと、満足な仕事が得られないようです。
そんな資質があるあなた・・・一つの選択肢として考えるのもいいですね。
2024年
6月
12日
水
サーモンは「取る魚」から「育てる魚」へ
今日の連絡ノートには、昨日の「おかしの学校」のコメントがいっぱいです。電車に初めて乗った園児が二人いました。新幹線と並行して走ったこともあり、「また乗りたい!」となったようです。今回は、日本を代表する大手菓子工場の見学ですので、機械化され、ラインを流れるように商品ができていく工程を見学しましたが、お菓子の世界は、パティシエやショコラティエによる手作りスイーツもあります。両方を学びながら、子どもたちの好奇心を伸ばしたいですね。
さて、子どもたちが大好きな「回転ずし」ですが、ネタの人気1位は13年連続で「サーモン」だそうです。マグロではありません。サーモンはただのネタだけでなく、あぶりやカルパッチョなどのアレンジが多様です。私の奥さまは、アボカドサーモンを必ず注文します。なんか、ヘルシーなイメージですね。(笑)
そんなサーモンですが、海水温の上昇による秋サケの不漁が何年も続いています。国内のサケの来遊数(日本の川に戻ってくるサケ)は、1996年の8879万匹をピークに減少し続け、2023年度は約4分の1の2785万匹にまで減少しています。これで、回転すしのネタが確保できるの?と思われるでしょうが、全国で養殖のサケ・マスが拡大しているのです。
国内のサーモン養殖は、約150年前にすでに始まっていました。つかみ取りでなじみのある「淡水のニジマス」が、全国で盛んになりました。そして、昨今のサーモン人気を追いかけるように、「ご当地サーモン」が日本各地で発生します。いよかんのオイルを餌に加えて臭みを抑えた「宇和島サーモン」や地元産レモン果汁を与えた「広島レモンサーモン」、富士山の湧き水で養殖した「ホワイト富士山サーモン」など、全国で120以上あるそうです。
よく、サケとマスはどう違うの?と言われますが、同じ「サケ科」の仲間です。厳密な定義はなく、海にいる大きなものをサケ、川や湖にいる小さなものをマスと呼んで区別していることが多いようです。
私も、さいたま水族館で初めて知ったのですが、川の上流の水のきれいなところで暮らす「ヤマメ」という魚がいますね。でも、そのヤマメの中から「冒険したい!」と海に向かって泳ぎ出し、大きく成長した魚が「サクラマス」です。もともとは同じ魚です。
ともあれ、地球環境を考えながら、私たちの胃袋を満たしてもらうには、サーモンと呼ぶサケ・マスは、「取る魚」から、ますます「育てる魚」になっていくのでしょう。サーモンに限らず、養殖の魚は、これからも増え続けています。ブリなどは、氷見の寒ブリ以外は、天然モノよりも養殖の方がおいしいですね。これも、時代の流れです。
2024年
6月
11日
火
「おかしの学校」に行ってきました
年長・年中園児合計14名を連れて、ロッテ浦和工場「おかしの学校」に行ってきました。人気のお菓子工場の社会科見学ですので、今年度の団体枠は、すべて予約が埋まっているそうです。さいたま市内の小学校3年生がここを社会科見学に利用することが多いのですが、今日は就学前の園児たちですので、担当のお姉さんたちには、とてもかわいらしく映ったようです。(笑)
3月の社会科見学で、「造幣局さいたま支局」に行った時は、JR西大宮駅からさいたま新都心駅まで、電車で移動しました。今日は、ロッテの工場がある、武蔵浦和駅までの移動です。大宮から先、武蔵浦和駅までは、新幹線が並行して走るので、「はやぶさだ!こまちだ!かがやきだ!」と子どもたちの歓声が響きましたが、他のお客様に迷惑をかけることなく到着しました。
駅から歩いて10分・・・お菓子工場に到着です。いよいよ、子どもたちは「おかしの学校」に入学します。ここは、まるでハリーポッターの世界です。MCのお姉さんも、魔法を使います。子どもたちも、気がつくと、「パイの実」の帽子をかぶらされていました。今日は、ロッテを代表するお菓子「パイの実」の生産ラインを見学です。
パイをふっくらサクサクにするために、64層の生地からできていることや、パイに麦芽糖を吹きかけることで、カリッとした食感になること。チョコレートを入れる工程では、上部に取り付けられているパイプから、チョコレートが水道のように流れていくシーンを目の当たりにした子どもたちは、大興奮です。パッケージされ、箱に入れられた「パイの実」が、ロボットだけで人がいない最終工程で、カートンに積まれていく様子まで、しっかりと見学できました。
浦和工場では、パイの実の他に、コアラのマーチ・ガーナチョコレート・トッポ・クランキー・キシリトールガム。そして、雪見だいふく・爽・もな王などのアイスクリームも製造されています。子どもたちにとっては、なじみのあるお菓子ばかりなので、深く記憶に残ったようです。3交代で24時間稼働する、おかしの大工場は、全国に向けて毎日多くのお菓子を作っているのです。
「やった!」と歓声が上がったのは、おかしの学校を無事に卒業して、お菓子の詰め合わせをお土産にもらった時です。企業にしてみれば、子どもたちの「口コミ」が親に伝わることで、さらに宣伝効果がアップするので、とてもリーズナブルな販促費用ですね。
年長園児の中には、おかしの学校で学んだ知識をしっかりと頭にインプットしたようです。おうちに帰ったら、ママパパに、マシンガントーク解説が始まりそうです。(笑)
普段スーパーに並んでいる商品が、どのように作られ、誰が運び、この棚に並んでいるのか・・・何気ない買い物の時間が、子どもたちの「なぜ?どうして?」につながっていくのが、社会科見学のねらいでもありますが、今日は、十分な成果があったようです。
そうだ~お弁当タイム・・・駅前ビルの屋上庭園で食べます。空を見上げれば、高層マンションだらけですが、この不思議な空間もなかなかいいものでした。
2024年
6月
10日
月
「普通」を問い直す
今日の寺子屋は、「七夕飾り」の工作を作りました。折り紙とのりを使って、あーだこーだ言いながら作業を続けます。先生の話をろくに聞かないで、どんどん自分で作業を進めてしまう園児もあれば、まわりをキョロキョロしながら、なかなか進まない園児もあります。個性いろいろの作品がアップしています。これから、「願い事」のメッセージを書いていきますので、楽しみですね。
最近のニュースでは、「合計特殊出生率」が過去最低となり、東京都に至っては、0.99と1を切りました。少子化への歯止めがかからず、この先の日本はどうなる?といった感じです。しかし、保育園ママで、4人目のお子様がお腹に・・・とうれしいニュースがありました。令和の時代・子ども4人は、凄いことですね。
今日は、少し考えさせられる内容です。「渇愛の果て、」という映画は、妊娠、出産にまつわる出来事が、妊婦とその夫、子どもがいる友人といない友人、医師や助産婦など、異なる立場から描かれた作品です。今後全国で順次ロードショー化されます。
この映画では、「出生前診断」が取り上げられます。妊娠中に胎児の発育や異常の有無などを調べる検査です。検査方法は色々あり費用も異なります。出生前診断で「陽性」となり、その後の確定的検査で染色体疾患が見つかった場合、大多数の夫婦が出産を諦めているのが現状だそうです。分かりやすく言うと「あなたのお子さんは、ダウン症です。それでも出産を考えますか」と問われた時の判断です。この判断について、いいとか悪いとかの話ではありません。
この映画の監督・脚本・主演を務める「有田あん」さんは、妊娠した友人が、羊水検査をしたところ、胎児の指が欠損している可能性があるとなったそうです。その友人の話は、「普通でよかったんだけどな。特別かわいかったり、何かに長けていたりと、高望みをしているわけではないのに・・・」
有田さんは、「普通」って何だろうとずっと引っかかったままでした。この映画のテーマは、出生前診断だったのに、「普通って、難しい」に変更し、編集し直したそうです。「普段よく使っている『普通』や『当たり前』といった言葉を、問い直したいと思いました」と。
映画の試写をした際、「子どもが欲しかったのなら、出生前診断は知っておくべき」「障害児でも受け入れろ」「中絶はあり得ない」という感想も寄せられたそうです。「でもそれは、あなたの尺度ですよね」と有田さんは言います。「『あり得ない』って他人に言われてしまったら、当事者たちは、本当の気持ちを声に出せなくなってしまいます」と続けます。
映画の中で、障害のある我が子を「かわいいと思えない」と主人公が吐露する場面があります。有田さんは、「我が子を愛さないといけない、現実を受け入れるべきなど、『べき』を押し付けるのではなく、『私はこう思う』だけで、いいと思うんです」と言います。
ここで、みなさんは、もう一度「普通」を問い直してください。私の場合は、大学の同期が、40歳を過ぎて結婚をしたのですが、その挨拶で、「普通の幸せを大切にしたい」と言ったのです。私にとって、「普通」という言葉が、すごく大切に思えるきっかけになりました。毎日コツコツと、普通に仕事を継続することが、どれだけ大切なことか・・・今も私は、「普通」とは、そんな簡単なことではないと思っています。
でも、今私が言った「普通」と、この映画の「普通でよかったんだけどな~」の「普通」は、意味が違います。有田さんの言う通り「普通って、難しい」ですね。
なんだか、言葉遊びのようになってしまいましたが、あなたにとって「普通」のことって、どんなことですか。当たり前にできることですか。それとも、別の意味ですか。今日は、「普通」を問い直してください。
2024年
6月
09日
日
感覚過敏研究所
「感覚過敏」をご存じですか。主に五感を中心に感覚が過剰に鋭く、日常生活に支障をきたしてしまう症状のことです。
「聴覚で言えば、教室でのざわざわとした話声やシャーペンをカチカチする音が苦手で、視覚なら人ごみの中にいるとすぐに疲れてしまったり、頭痛がしたり。味覚は大変で、食べられるものがほとんどありません。白米は食べられるのですが、においや食感によっては体調が悪くなる」と語るのは、「感覚過敏研究所」所長の加藤さんです。まだ18歳の若者です。加藤さんもその症状を持つ一人で、彼が経験した内容です。服の縫い目やタグが痛い。制服が重い。香水のにおいに耐えられない。といった、日常生活のあらゆる面で苦痛を感じ、中学校では不登校になりフリースクールに転校したそうです。
一般的にほとんど知られていない「感覚過敏」という言葉の可視化に取り組みます。「苦手な音があります」「苦手なニオイがあります」などのキャラクター缶バッジを作ります。そこに五感にかかわるメッセージを載せます。啓発活動は、コロナ禍において「マスクがつけられない意思表示カード」や「せんすマスク」がメディアに取り上げられ、認知度がアップします。
2022年には、アパレルブランドを立ち上げます。パーカーとTシャツ、靴下の開発をします。タグはなくし、縫い目は外側に出すなど、感覚過敏の人に、着心地のいい服を目指します。オンライン販売で、パーカーとTシャツ合わせて千着を売り上げたそうです。
視覚や聴覚に対応した、イヤホンやレンズも開発するものの、嗅覚や味覚、触覚について解決できる対策商品がまだできていないことが課題だそうです。加藤さんが、今力を入れているのが、センサリールームやカームダウンボックスと呼ばれる五感に配慮した空間づくりです。この空間は、音や光やにおいといった刺激をなくすことで落ち着きがもたらされるもので、将来的にはショッピングモールなどへの設置を目指しているそうです。
まだ18歳の加藤さんですが、彼の頭の中には、10年後の理想の未来があります。「今は感覚過敏がただ単につらい『症状』ですが、そのつらさを解消できれば、鋭い感覚によって小さな変化にも気づける『才能』になるんじゃないか。仕事をするときには少し過敏モードで、日常生活ではオフにするといったことができるようになったらいい。そのための研究を続け、私が32歳になるころまでに解決できればいいと目標を立てています」
時代の流れを見れば、目の悪い人のためにメガネというアイテムができ、それが、今では個性としてファッションにつながっています。感覚過敏も一つの個性として尊重する社会になっていくのかもしれません。加藤さんのような若者が、そんな社会への道を作り、私たちがその道をどう歩くかで、社会は変えられるのです。
2024年
6月
08日
土
大宮盆栽村
今日の園長の課外授業は、大宮盆栽村にある「大宮盆栽美術館」に行ってきました。小学生と年長園児4人を連れてです。
ところで、大宮盆栽村は、いつからあると思いますか?かなり古くて、関東大震災の2年後の1925年だそうです。1989年には、第1回世界盆栽大会が、旧大宮市で開かれ、2010年に「大宮盆栽美術館」が開館しました。来年で盆栽村ができてから100年です。最盛期には、約35園の盆栽業者があったそうですが、高齢化や後継者不足などの理由で廃園が相次ぎ、今では6園だけとなってしまいました。
盆栽美術館の2023年度の来館者数は、約5万6000人で、コロナ禍前の水準には達していないそうです。ところが、盆栽は「Bonsai」として。世界的には注目を集めています。外国人だけの入場者数は、コロナ禍前と比較しても130%で、大きく増えています。今日も3組の外国人が、異国語で会話をしながら、盆栽を前に立ち尽くしていました。2023年度は、入場者数の15%が外国人だったそうです。昨年度、初めて外国人向けの解説会を週1回実施したそうですが、今年度は週4回に増やしたそうです。
さいたま市は、外国人客を呼び込もうと、都内の高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン東京」での盆栽展示、若手盆栽師によるデモンストレーションなどを開催しています。しかし、日本の文化である盆栽の国内人気がまだまだです。2023年度から、出生届を出した市民に手のひらサイズの「ミニ盆栽」を贈る事業を始めたそうです。子どもの成長に盆栽の成長を照らしあわせて・・・といったところでしょう。
盆栽美術館で、一番大きな盆栽は、何と樹齢500年です。私は、その盆栽の前で無言で立ち尽くし、戦国時代から、現代を見守ってきたのか・・・と感慨深くなってしまいます。
さて、本日盆栽美術館を見学した4人の子どもたちの反応は???出発する時「ぼんさいってなに?」とあまり興味を示さず、一番年上の小3女子だけが「植木でしょ」と答えます。そして、盆栽美術館に着くや、外国人の姿に、気分が高まったようです。そして、園長の素人解説と、途中からボランティアの解説員の話を聞きながら、「へぇ~そうなんだ・・・すごいね~」といった感じです。入場口で、お姉さんから、盆栽美術館のカードを特別にもらったのが、良かったみたいです。(笑)
明日の日本を担う子どもたちだって、きちんと説明すれば、興味を持ってくれます。さいたま市が誇る盆栽文化は、世界へ広まっていくのです。
2024年
6月
07日
金
紙ストローって、本当にエコ?
今日は、「父の日プレゼント」の制作を行いました。母の日と同じ作品の父の日バージョンです。母の日に比べて、世間的にはトーンダウンしてしまう「父の日」ですが、子どもたちは、ママへのプレゼントと同じ熱量で作っていました。うれしいですね。
さて、いつの間にか、ファーストフードチェーンなどで広まっている「紙ストロー」ですが、SNSでは、「あのぶっといストローの違和感は、並じゃない。おまけに紙製なんで、水分を吸ってすぐヨレヨレになっちまう」といったバッシングがあがっています。それでも、まだ使用しているショップが多いようです。2022年にプラスチック新法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)が施行されてから、2年が経過しました。
プラスチックストローは、ウミガメの鼻から出てきたのが、プラスチックストローだったために、脱プラスチックの悪役ナンバーワンになってしまったのです。ウミガメの映像は、あまりにも痛々しく、「プラスチックストローはけしからん!」という認識が、消費者の中で蔓延してしまったのです。
専門家は、「海洋生物にこんなふうに害を及ぼすプラスチックのほとんどは、不法投棄によって海に流れ出てしまったものです。プラスチックストローを使ったとしても、ゴミとしてきちんと廃棄し処理されるなら、ウミガメの鼻に刺さることはないのです。一方、紙のストローでも不法投棄されれば、分解される前にウミガメが吸い込まない保証はない」と冷静に判断します。確かに、私たちの家庭から出るペットボトルもビニールゴミも、分別してゴミの日にきちんと出しているので、これが海に流出することは、普通に考えればあり得ないことです。
人間は、「何かやらなくては!」と気持ちが先立つと、とにかく「環境にいい」と思えることをマネして行う傾向がありますね。ストローを紙にするのは、分かりやすいストーリーゆえに、加速して広まったのです。紙ストロー問題で言うと、一番いいのは、植物由来の素材を使うバイオマスプラのストローだそうです。焼却処分される場合は、排出するCO²は、紙ストローのわずか33%程度だそうです。実は、プラスチックストローよりも紙ストローの方が、焼却の時に、1.4倍もCO²の排出が多いそうです。あれ!?ですね。
これも有名な話ですが、エコバックもレジ袋に比べると布を張るとう作業に多くのCO²が出るため、100回はつかわないと、CO²の元が取れないそうです。ならば、レジ袋を大拙に使いまわしたほうが、エコというわけです。
太陽光発電が、地球にやさしいという認識が高いですが、太陽光パネルには耐用年数があり、あの大きなパネルをどうやって廃棄するか・・・という問題があるのです。そういう我が家も、そんなことも考えずに、「地球環境のために」という理由で、屋根にはソーラーパネルがあります。
私たちは、紙ストローで踊らされ、エコバックでも踊らされ、「地球環境のために」という「大義名分」に流されているのかもしれませんね。もっと、基本的な生活の中で「ていねいな生活」「ここちよい空間」「自分らしい居場所」を考える時、「これって、地球環境にいいことかな?」と思うことが大切なのかもしれません。当事者意識を持つということは、つきつめれば、こういう事ですね。
2024年
6月
06日
木
物流の2024年問題
朝の自由時間、年長男子が、特大ブロックをつなぎ合わせて、5メートル超の電車を作りました。電車には、次々と子どもたちが乗り、男の子が運転手です。車内アナウンスもあり、素敵な遊びになっていました。こうして、子どもたちの遊びに、今日も心が洗われるのです。(笑)
さて、今年4月から始まった物流の「2024年問題」は、マスコミで多く取り上げられてきました。トラックドライバーやバスの運転手、タクシードライバーなどの時間外労働の上限制限がなされました。
特に、宅配業者では、かねてからの人手不足状況の中、ニーズは、共働きや一人暮らし世帯が増え、週末や夜間配達が増えています。ある配達員は、「残業規制は全く守られていません。残業規制を守ろうとすれば、今以上に利用者のニーズに応えられなくなります。こうした認識や覚悟が利用者にはあるのでしょうか!?」と訴えます。
私たちが、ニュースで2024年問題を見ても、「何か、物流業界は大変ね!人が集まるのかしら?」なんて、どちらかというと、他人ごとに受け止めている人がほとんどです。
冒頭の配達員は、1日に配達を任される荷物は150個前後。午前8時に配送センターに出勤し、2トントラックに荷物を積み込んで都内の担当エリアに向かう。配達を終え、配送センターを経由して帰路に就くのは、午後9時過ぎ。12時間を超える勤務時間中は、常に配達や集荷、伝票チェックに追われ、車内で弁当を食べる時間を確保するのがやっと。毎日、1~2割は不在のために再配達に回る。結局、配達しきれずに夜8時以降は、個人事業の委託業者に荷物を引き継ぐそうです。
過重労働の負担をさらに重苦しくするのが、利用者からの上から目線の態度や課題要求です。「家にいたんだけど・・・」と連絡する利用者。月に5・6人はいるそうです。「インターホンを2回鳴らさせていただきました」と伝えると、「だから鳴ってないんだよ!今度からは電話しろ!」とキレる利用者もあるようです。
日本の消費者はあまりにも要求水準が高い。それが過剰サービスにつながり、物流システム全体を圧迫していると、専門家は言います。コンビニの24時間営業も、スーパーの棚には、形のそろった商品がびっしりと並んでいるのが当たり前という国は、世界でも日本だけだと。
確かに、私たちは、日本という国では、当たり前のサービスと考えていたことが、あまりにも多いことに、気がつきますね。「物流の2024年問題」を解決するには、物流業者の改革以上に、「消費者の行動変容」だと言われています。
急いでもないのに、「翌日配送」にしていませんか?
宅配ボックスや置き配を活用して、再配達をなくす取り組みをしていますか?
在宅時間に変更があった時に、ちゃんと宅配業者に連絡していますか?
複数の商品は、まとめて注文・配達依頼をしていますか?
食品は棚の手前にある消費・賞味期限の近い商品から買っていますか?
地産地消を心がけ、物流負担の軽減に協力していますか?
災害時には必要最低限の注文や購買にとどめていますか?
話は大きくなりますが、働く人の健康や人権を守ることも、持続可能な便利さや豊かさを追求することも、地球環境への負荷を軽減することも、すべてよそ事ではなく、これからの「自分」とつながっていると考える時代になってきたのです。
どうですか?私たち消費者の主体性が、2024年問題を左右するとうわけです。
2024年
6月
05日
水
花を愛でる
「今日は、一人2個まで、ビワを食べてもいいよ!」と声をかけると、子どもたちが次々と、ビワの木の下に集まってきます。すでに、木に登っている年長男子たちです。「甘~い」もあれば「甘酸っぱ~い」もあります。しっかり熟した濃いオレンジ色の実をゲットした園児は「おいし~い」と叫び、少し硬めの黄色に近い実をゲットした園児は、無言で食べています。ビワの種をおうちに持ち帰って、庭に植える園児もいます。私の自宅のビワも、数十年前に庭に植え、いつの間にか実をつけるようになりました。マルベリーの次は、ビワを食べる子どもたちは、何ともたくましいですね。
さて、皆さんのおうちには、花が飾られていますか。花がなくても、人間は生きていけます。お菓子を食べなくても、しっかりと食事をとっておけば、私たちは生きていけるので、お花もお菓子も似ています。しかし、私たちの心を豊かにするためには、花もお菓子も欠かせませんね。
先日、テレビで「切り花のサブスク」の会社が紹介されていました。週に一度定期的に、切り花が届きます。花瓶に入れれば、部屋が華やかになるという作戦です。花屋で購入するよりも安い価格設定になっています。「花屋に行く時間がない」「花に詳しくないので、お任せでかまわない」「毎週どんな花が届くか楽しみ」などなど、花の定期便を利用する人がどんどん増えているそうです。
「食品ロスをなくそう!」というスローガンは、すっかり私たちの生活に入り込んでいます。日本の食品廃棄ロスは、毎日、国民一人がおにぎり○個分捨てている計算になるなんて、よく例えられます。実は、「フラワーロス」もあります。生産栽培された花が、消費されずに廃棄されてしまうことですが、コロナ禍では、入学式・卒業式・冠婚葬祭などの式典が中止となり、花の需要が大幅に落ち込み「フラワーロス」の問題が、表面化しました。今でも、「フラワーロス」は、年間1500億円にもなるそうです。
切り花のサブスクでは、一般的なサイズの40センチの切り花ではなく、25センチの切り花を扱い、専用の小さな花用BOXでポストに投函されます。通用の市場では規格外でロスになってしまう花も活用できます。また、花のチョイスも安価で仕入れた季節の花を活用できるので、コストダウン分を価格に反映させることができるのです。もちろん、届いた花には、花言葉などのコメントがあるので、お客様は、続けるだけで、花の知識もアップするのです。
保育園では、寺子屋の時間で「ママにプレゼントするお花をカップに集めて!」をたまにやります。もちろん、花は屋上にある「野草」です。そして、先日は、朝顔の種をまきました。色水遊びが目的です。卒園児の小学生は、「ムスカリ」「カラスノエンドウ」「オオイヌノフグリ」「ハルジオン」「ホトケノザ」など、マニアックな花の名前を知っています。
花の名前を知らなくても、私たちは生きていけますが、子どもたちには、花の名前も花を愛でる感性もたくさん持ってもらいたいですね。
2024年
6月
04日
火
「香水砂漠」日本
今日は、大きくオレンジ色になった、屋上のビワを食べました。年長男子は、ビワの木に登って、みんなの分を取ってくれます。さるかに合戦で、意地悪をしない猿のようです。マルベリーと違って、1粒が大きいので、モグモグと満足顔で食べる子どもたちです。また、寺子屋では、10月の運動会で行う「30メートル走」をやってみました。「今日1番になれなかった人は、運動会までに頑張ればいいだけだよ」と言っても、勝ち負けにこだわる年長園児です。一番の収穫は、年少3歳児全員が、30メートルを走り切ることができたことです。
さて、今日は香水の話です。皆さんのまわりに、香水を頻繁に使用している人はどのくらいいますか?私のまわりには、ほとんどいません。日本は、香水の売上規模が小さく、世界の業界関係者からは「香水砂漠」とかつては、呼ばれていたそうです。私の勝手なイメージですが、日本人の入浴は、シャワーでなく湯船につかって時間をかけるので、体臭が残ることが少なく、よって、香水でごまかす必要がない。と思うところです。
ところが、ここ数年、日本での香水の売上は伸び始め、昨年の国内市場は、前年比13%増の500億円になったそうです。9年前の402億円から125%も伸びた計算です。
市場規模500億円といっても、イメージがわきませんね。日本のバレンタイン市場が、約1000億円(わずか1か月での売上で、大谷選手の10年分の年収なので、凄い金額です)なので、その半分です。少しはピンときましたね。
ここまで香水市場が拡大したのは、訪日外国人の影響もありますが、「Z世代」がキーマンです。現在10代半ば~20代後半のZ世代の幼少期は、香水のような柔軟剤が登場した頃です。日常的にこの香りに触れているので、香水も抵抗感がなく購入しているようです。
またその上の年代は、ファンションの仕上げや、自分をよりよく見せたくて香水を使う人が多かったですが、コロナ禍以降は、自分が楽しむために使うようになっているそうです。リモートワークで、自宅で過ごす時間が増えて、仕事とプライベートの境界が曖昧になり、気分転換や癒しのために香りを活用する人が増えたようです。通勤時と休日のお出かけとで、香水を使い分けて気分を上げるのです。
男性の利用客も増え、今は、香水のサブスクまであるそうです。オンラインで質問に答えると、月額3890円で、おすすめの香り3種類が自宅に届くそうです。
日本は、「香水砂漠」ではあったかもしれませんが、「お香」や最近では「アロマテラピー」など、自宅などで香りを楽しみ気分転換を図る文化は、昔からありましたね。香りは、心身への効果が大きいと、昨今では医学的にも証明されていますので、香水市場は、まだまだ拡大しそうです。
ここまで、書いておきながら・・・私が香水を使用することは・・・ないかな~。
2024年
6月
03日
月
ぼっち死の館
今日の連絡ノートには、土曜日の親子遠足の感想がびっしりありました。天気に恵まれたこともあり、水上アスレチックがどれだけ楽しかったかが、伝わりました。そして、荒川を学ぶ「ガリバーウオーク」も、意外にも子どもたちは、多くの知識を吸収できたようです。
さて、私が勤務していた会社のOB会長は、神戸で「民生委員(児童委員も兼ねる)」のエリア長をやっています。まさに、地域の方々のために仕事をしています。でも、そんな会長ももうすぐ75歳になろうという年齢です。ずっと、会長は「死ぬまでに本を書く」と言っていました。そして、いよいよそのテーマが見つかったのです。民生委員として、様々な高齢者との出会いをストーリーにするようです。しかし、最後は、ハッピーエンドで、人生の終焉を迎える人々を美しく取り上げるそうです。個人的には、とても楽しみにしています。
とはいえ、現実には高齢化が進む昨今、一人暮らしの高齢者の数が増え続け、家族にみとられずに死を迎える「孤独死」が身近な問題となっています。今日は、齋藤なずな作の「ぼっち死の館」というコミックを紹介します。
舞台は高度経済成長期に建てられた、とある団地です。かつては、ニュータウンとして多くの人々でにぎわいを見せてたこの場所には、現在、独り身の高齢者たちと猫たちが暮らしています。数日前に会話を交わした人が、姿を見掛けないと思ったら、部屋で一人で亡くなっていたということも、ここでは珍しくありません。「生と死」という、シリアスな内容を扱いながらも、この作品にはユーモアがありほのぼのとしたセリフが、読んだ後に満足感をもたらす作品です。
作者の齋藤なずなさんは、現在78歳の女性です。作品内の登場人物たちと同様、長年団地に住んでいます。作品の中で、漫画家の女性が、ある男性住人の孤独死をきっかけに、彼の人生をマンガのストーリーにできないかと考えます。しかし、実際の彼の人生は、「話」としては、うまく割り切れないものがあったのです。「生きてるってなんか、もっとヘンテコで複雑で、わけがわかんない!」とぼやきます。
団地の住人たちが、自分の人生の終結点を意識することで、何げない日常をいとおしく感じます。生きることとは何なのか、限られた人生の中で何ができるのかを考えるために、ヒントを与えてくれるような作品になっています。
私たちは、「頑張って何かを成し遂げた人」や「毎日コツコツ目立たないけど生きてる人」や「未来を担う、子どもたち」などの姿をみることで、「生きる意義」みたいなことを考えることが多いですね。しかし、この作品は、孤独死を身近に感じる人々の暮らしの中から「生きる」を捉えようとしています。
読んでみたくなりましたか。
2024年
6月
02日
日
令和6年度 親子遠足 つづき
お弁当タイムは、「家族が幸せな笑顔に浸る時間」です。ママやパパが作ったお弁当を家族で食べるというシーンは、世の中にたくさんある幸せの中でも、かなり上位にランクインするのではないかと思っています。園長のビデオカメラもー家族ずつ撮らせていただきました。「美味し~い」の笑顔が最高なのです。
とても小さいですが、川の博物館には、川に棲む生き物を観察できる「ミニ水族館」があります。スッポンに驚き、「ニホンイシガメ」「クサガメ」の子ガメたちが、水槽で泳いでいました。保育園と全く一緒です。ジンベイザメもイルカもペンギンもいませんが、生き物が大好きな子どもたちは、ちゃんと「見るべきツボ」を抑えているようです。
そして、午後は、「わくわくランド」で水遊びです。年齢制限があるので、寺子屋園児は
、このウォーターアスレチックで思う存分遊びました。わくわくランドは、川の博物館では一番の人気スポットです。午前中には、すべての時間帯のチケットが完売になることも多いそうです。保育園ホワイトきゃんばすの13:00スタートの会には、学童クラブの小学生も一緒だったので、とにかく、激しい水遊びになりました。ここはプールではなく、水上アスレチックなので、くつ(ウォーターシューズ)を履いて洋服のままで遊びます。手こぎボートにロープ渡り、滝に、浮島を飛び歩くアトラクションなど、子どもたちの冒険心をそそる演出です。見事に、全身びしょ濡れの子どもたちです。
寺子屋以外の園児は、噴水広場で水遊びです。ここにも楽しい演出がいっぱいです。もちろん、チビちゃんたちの服はびしょびしょです。わくわくランドの制限時間が50分なので、遊び足りない寺子屋園児と小学生は、解散後もここで遊び続けていました。
ということで、天気にも恵まれ、子どもたちにとっても、保護者の皆様にとっても、充実した1日になりました。全員、安全で大きなケガも事故もなく過ごせたことは、うれしい限りです。親子遠足の思い出は、子どもたちの心に深く刻まれることでしょう。そして、この思い出が、「明日からも頑張る」「辛いけど何とか乗り切ってみる」とか、「家族一緒の時間は楽しいなぁ~」「仲間と一緒だと何にでも挑戦できそうだ」という気持ちにつながってくれることを期待します。
保護者の皆様・・・親子遠足を楽しんでいただき、本当にありがとうございました。
2024年
6月
01日
土
令和6年度 親子遠足
1週間前から、台風1号の進路がどうなることや?と気をもんでいた親子遠足ですが、ふたを開けると快晴に恵まれました。朝早くからママたちはお弁当作りを頑張り、先日のわくわく教室で「おにぎり」を作った年長園児たちは、自分でおにぎりを握りました。そして、朝10時「埼玉県立 川の博物館」に全員集合しました。
川の博物館の名物の一つが、日本一の水車です。すべて埼玉県内の「西川材」で作られ、直径は24.2メートルもあります。25メートルプールの長さが直径ですので、とてつもない大きさです。まずは、水車をバックに記念撮影です。
午前中は、「かわせみチーム」と「すいしゃチーム」に分かれて、ガイドを聞きながらの見学です。まずは、「ガリバーウオーク」を楽しみます。川の博物館のもう一つの名物が、「荒川大模型173」です。荒川の源流となる「甲武信岳」から、東京湾までの173キロを1/1000の縮尺で再現した、日本一の大型立体地形模型です。荒川にかかる150あまりの橋や鉄道、ダムなどの施設が再現されています。1/1000といっても、なかなかの距離になるので、屋外に設置されています。
ガリバーウオークは、川の博物館の学芸員の方にガイドしてもらいます。大人である保護者や先生たちは、より知識が膨らみました。子どもたちだって、なかなかのものです。お弁当タイムで、問題を出します。「荒川の長さは、日本で何番目ですか?」これには、5歳男の子が15番目と即答です。「では、荒川で日本一のところがあります。それは何?」これは、じっくり考えた男の子が、「川の幅かな?」と正解です。川幅の定義は、堤防から堤防までの距離です。鴻巣市(こうのすし)と吉見町(よしみまち)の間は、川幅2537メートルあり、日本一の川幅と認定されています。平成19年9月の台風9号では、川幅いっぱいまで増水したそうです。
川の博物館の位置は、ちょうど、「山から街へ」景色が移り変わる場所です。子どもたちは、山側と街側の景色を比較しながら、納得していました。このまま下流へ歩いていくと、保育園ホワイトきゃんばすのある場所にやってきます。上江橋・JR川越線鉄橋・治水橋を確認します。そして、いよいよ東京湾の荒川河口へ。「お台場」「葛西臨海公園」そして、何と言っても「東京ディズニーランド」があるので、子どもたちの目が輝きます。「そうなんだ・・・荒川の終わりにディズニーランドがあるんだ!」と、子どもたちの会話が、荒川からディズニーランドのアトラクションに変わっていきます。(笑)
川の博物館の館内でも学びがたくさんありました。秩父山地から切り出した木材を水の力で下流に押し出すために作られた「鉄砲堰(てっぽうぜき)」が、1/4の縮尺で再現されています。実際に水が流れてすごい迫力です。また、荒川を使って物資の輸送に使われていた「荷船」の解説もありました。子どもたちは、ワークショップで「カタツムリ」を作ります。自分で作った大切な作品がお土産になりました。
こんな感じで、午前の部は大人だけでなく、保育園の子どもたちも小学生も「荒川」に興味を持つことができたようです。ガリバーウオークで、ガイドが荒川源流の山頂から、じょうろで水を流し(雨を降らせる)、それが川になって流れていく演出で「つかみはOK!」になったようです。(笑)
つづきは、あした。
2024年
5月
31日
金
サラリーマン川柳 2023年
今日は、朝から台風並みの豪雨でした。太平洋上を北上する台風1号は、温帯低気圧になりましたが、関東から遠ざかってくれたので、明日の遠足はお天気になりそうです。保育園では、寺子屋以外のチビちゃんたちは、「マラカス」を手作りしました。ヤクルトサイズの容器を使って、チビちゃんでも自分の手のひらに収まるサイズです。今日のお土産になったので、おうちでは、シャカシャカうるさいかもしれませんね。
寺子屋園児は、体操教室です。 平均台の上を歩く年少園児は、今まではコロコロ転んでいたのですが、ずいぶんとバランスが取れるようになってきました。まだまだコースアウトしたり、順番が守れなかったりと、ぐだぐだですが、少しずつ前進しています。
さて、昨日、第一生命保険から、2023年のサラリーマン川柳コンクールの作品が発表されました。私も、このサラリーマン川柳を毎年楽しみにしています。ということで、上位10作品を皆さんと楽しんでみます。
1 増えるのは 税と贅肉(ぜいにく) 減る贅沢(ぜいたく)
2 物価高 見ざる買わざる 店行かず
3 マスクなし 2年目社員の 笑顔知る
4 50代 給与も肩も 上がらない
5 PayPayを 覚えた夫の 無駄遣い
6 ダイエット 動画だけ見て 痩せた気に
7 パスワード チャンス3回 覚える子
8 盗み食い ペットカメラに 映る父
9 アレとソレ 用意済むのが 日本流
10 2度聞くな! 言った上司が 3度聞く
どうですか、今年も傑作が多いですね。1位の作品は、家計と健康面の悩みを上手に掛け合わせていて「なるほど」です。2位の作品は、日光東照宮の三猿「見ざる言わざる聞かざる」をもじった作品ですが、私がPTAに関わっていた時の中学1年生の絵画の作品を思い出しました。タイトルは「見たい・言いたい・聞きたい」です。中学生は、好奇心いっぱいで、何でも見たくて言いたくて聞きたくてという気持ちを絵にした作品です。今でも忘れない素晴らしい作品でした。
今回のサラリーマン川柳には、6万6949句の応募があったそうです。入選100作品の中から、このベスト10が決まりました。投票は5万票とのこと。国民的なイベントですので、応募数も多いですね。
こんな感じで、日常を笑い飛ばす余裕が欲しいものです。
2024年
5月
30日
木
歴史教育の転換期
今日は、屋上ファームでキュウリを4本収穫しました。子どもたちは、キュウリが大好きですので、すぐに行列ができます。園長がカットしたキュウリを配っていきます。塩を少しふって、とれたてのキュウリをいただきました。シャキシャキしています。マルベリーを食べて、次にキュウリを食べる子どもたちです。
さて、2年前から、高校の新学習指導要領で、必修科目として「歴史総合」が始まりました。私のような昭和世代の中学高校時代は、学校の教科書を絶対的に正しい歴史として暗記することが求められました。「鎌倉幕府はいつできた?」には、「1192(いいくに)つくろう鎌倉幕府」と語呂合わせで覚えたものです。ちなみに、鎌倉幕府成立は、今は1185年ですが、昭和世代は1192年で暗記していました。
「歴史総合」は、そんな暗記教育の弊害をなくしていこうという目的があり、世界史と日本史を統合した科目です。かつて、高校での世界史は、覚えることが多くて、選択しない生徒が増えてしまいました。そこで世界史を学ぶ機会を作ること。もう一つは、日本史と世界史を切り分けたまま学んでしまうと、日本の特殊性や優位性ばかりが強調されてしまいます。でも、歴史を深く学ぶには、世界の大きな流れや共通性に着目し、国や個人の価値観の違いによる多様性を知ることが大事です。
最近は、歴史を扱うテレビ番組が面白いですね。「歴史探偵」「英雄たちの選択」などを私は毎回見ています。英雄たちの選択は、史実はあるものの、「あなたならどう選択するか?その理由は」まで、自分だったらどうする?の視点がいいですね。歴史が面白いのは、100人いれば100通りの歴史観があることです。「自分だったこうする」を考えることは、将来、困難に出くわした時に、その解決策を考える訓練にもなるでしょう。
歴史総合の原案作りに関わった、小川教諭はこう言います。「混沌とした21世紀で、歴史を学ぶ意義は大きく3つあります。1つは、過去の人々の営みを参考にして、現在の生き方を見つめ直し、未来をどのように創造するかを考えること。2つ目は、多様な人々の生き方、考え方を理解して、対立を乗り越える思考力を磨くこと。最後は、真実をないがしろにする、今の時代に、何が「ファクト(事実)」なのかを見抜く力を養うことです」
日本人が、どちらかというと苦手にしている分野かもしれません。しかし、新しい歴史教育によって、「自分だったらこうする」と考える力が、間違いなく育つことでしょう。もちろん、自分の主張を押し付けるのではなく、他者の価値観を尊重できるような若者が増えてほしいですね。
2024年
5月
29日
水
高校生「いま関心があること」
今日は、久しぶりに屋上遊びができました。昨夜の台風並みの強風の名残りがあり、まだ風が強かったですが、子どもたちは、残り少なくなったマルベリーを食べます。昨日の寺子屋で作った「マルベリージャム」は、朝食でトーストに塗ったり、ヨーグルトに入れたりで、あっという間になくなったおうちが多かったようです。そして、今日の寺子屋は、「廃材工作」です。課題は自由でしたので、ゴジラ・アイスクリーム・恐竜・クラゲのおうち・スポーツカーなどなど・・・子どもたちの発想で、素敵な作品が出来上がりました。
さて、明日の日本を担う「若者」である、高校生が、どんなことに関心をもっているか、気になりますね。ある538人の高校生のアンケートの中から、「いま関心があること」をピックアップします。
物価高騰について・・・もしこのまま高騰し続けたら、私たちが大人になったときにはどうなってしまうのか。
人種差別・ジェンダー問題・・・生まれ持った自分で選べないものによって不当な扱いをうけるようなことがあってはならないと思う。
アイドルのあり方・・・最近SNSでアイドルの容姿を批判している投稿を見て、顔が整っているだけがアイドルの条件ではないと思った。
地球温暖化・・・地球温暖化が進んで、氷が溶け、動物たちがいなくなっているから、どうにかしたいと考えている。
筋トレ・スキンケア・勉強・・・自己肯定感を満たすため、自己不足感を払拭するために行うもの。
格安サイトで服を買うことは?・・・格安サイトの裏には低賃金で長時間働かされている人がいるわけで、そういう人を助けるには、どのようなお金の使い方をしたらよいのか、知りたい。
どうですか・・・大きな問題から、身近な現実論まで、高校生が関心のあることは、いろいろありますね。内容よりも、きちんと問題意識を持つことが大事ですね。
ちなみに、小学生がなりたい職業で、上位にくる、「スポーツ選手」は、今回の538人の高校生に聞いてみると、全体の1.7%しかありません。YouTuberは、たった一人だけだったようです。高校生は「環境問題に携わっている会社」「児童福祉に関わりたい」など、仕事を通じて、社会課題と向き合いたいと考える生徒の割合いが増えるようです。より、現実的で、いま関心があることにつながっていますね。
2024年
5月
28日
火
着衣泳を広めるプロジェクト
今日は、寺子屋の時間で、マルベリージャムを作りました。屋上で、マルベリーを生食している子どもたちですが、ジャムにすれば、トーストに塗ったり、ヨーグルトに入れて食べることもできます。鍋にマルベリーの実を入れて、グツグツ・・・子どもたちが、スプーンで少しずつグラニュー糖を入れて、かき混ぜます。最後にレモン汁をかけます。カップにマルベリージャムを入れてお土産です。モノだけでなく「コト」があるので、子どもが親にうんちくを語りながら、楽しんで欲しいですね。
さて、皆さんは、「着衣泳」(服を着たまま泳ぐ)経験をしたことがありますか。まず、ないでしょうね。私もTシャツで泳ぐことはありますが、ズボン&靴を履いたまま泳いだことはありません。「着衣泳を広めるプロジェクト」という団体があり、そのリーダーは、あの「岩崎恭子」さんです。1992年バルセロナ五輪で、競泳史上最年少の金メダリストになったレジェンドです。
岩崎さんは、20年ほど前のテレビ番組の「金メダリストが着衣泳に挑戦」という企画で、初めて体験したそうです。波のあるプール泳いだそうですが、それはそれは、ヘロヘロになったそうです。そして、東日本大震災の時に、着衣泳のおかげで命が助かったというニュースを知り、着衣泳の大切さを広めていかなければいけないと思ったそうです。
着衣泳では、普通に泳いでもうまく動けません。基本は、頭と足を浮かせた「背浮き」という姿勢だそうです。履いた靴などの浮力を生かすので、服や靴を脱いではいけません。ペットボトルやビニール袋も浮力には役立ちます。登下校中であれば、ランドセルも効果的だそうです。
保育園では、7月末にサマーキャンプを行いますが、屋上プールで、ライフジャケットを着て浮く練習をします。水が苦手な子は、泳ぐ以前に「浮く感覚」を持ちにくいようです。
岩崎さんは、「世界的に見ても、これだけ多くの学校にプールがあるのは日本くらいです。義務教育で水泳を扱う訳をもう一度考えるべきです。水泳を教えることも大事ですが、着衣泳を取り入れて、命を守るための水泳指導を学校で行うべき」と、強く訴えます。
小学校の水泳の時間で、着衣泳がカリキュラムとして、当たり前に取り入れられるようになれば、遊び感覚で、「命の大切さ」を体験することができますね。
2024年
5月
27日
月
見えない「努力の壺」
今日は、お楽しみのイベントがありました。4Fに新しく「キッズランドUS」という室内大型運動施設が誕生しました。朝10時の開園と同時に、保育園の園児全員で遊びに行きました。だいたい園児の8割くらいは、家族と遊びに行ったことがありますが、保育園の友だち同士で遊ぶのは、楽しさが何倍にもなるようです。
ふわふわドーム・ボールプール・エアートランポリン・アスレチック・馬パカパカ・キャンプスペース・ブランコ・トランポリン・乗り物いっぱい・ゲームコーナー・おままごとコーナー・衣装コーナーなどなど、一日中でも遊べるところです。1時間30分があっという間に過ぎて、子どもたちは汗だくになって、満足顔です。おうちでは、ママパパにマシンガントークで、今日の出来事を話し続けるでしょう。(笑)
さて、「子どもを変えた親の一言」の中から、見えない「努力の壺」の話をします。人が何か今までできなかったことに挑戦しようとすると、心の中に「努力の壺」のようなものができると言います。ところが、その壺には4つの特徴があるそうです。
1つ目は、人によって壺の大きさが違うことです。すぐにできるようになる人もいれば、なかなかできるようにならない人がいるのは、そのためです。
2つ目は、「努力の水」を入れ続けなければ、水は乾いてなくなってしまうということです。油断して、努力することを休んでしまうと、あっという間に努力の水は乾いてしまいます。
3つ目は、努力の水が一度でも壺からあふれ出れば、その後に減ることはあっても、なくなってしまうことはないとうことです。自転車に乗ったり、水泳や掛け算九九も、一度できるようになったことは、全くできなくなってしまうことは、ほとんどありません。ちょっと努力すれば、すぐに元に戻ります。
4つ目は、大人の壺より子どもの壺の方がずっと小さいことです。大人になってから努力をしても、なかなか上達しないものです。子どもと大人が一緒に努力し始めたら、子どもの方がすぐに上達するのです。
どうですか・・・あなたの心の中の壺は、努力の水で満たされていますか。我が子に上手に話をして、子どもの「努力の壺」を刺激してみませんか。まぁ~子どももそれぞれですので、効果がなかったら、他の言葉を考えてくださいね。
2024年
5月
26日
日
和ろうそくの魅力
今日は、6月1日に親子遠足で訪問する「埼玉県立 川の博物館」に打合せで行ってきました。天気予報は、今のところ快晴ではありませんが、台風は、関東の太平洋上を通過していると思われますので、お日様の下で遊びたいですね。目玉の「水上アスレチック」は、今日も親子で大賑わいです。チケットも完売するほどの大人気コーナーになっています。詳しい話は、当日のお楽しみです。
さて、今日は「和ろうそく」の話です。一般的に、洋ロウソクが石油系の原料と糸でできた芯で細い灯りになるのに対し、和ろうそくは、櫨(はぜ)などの植物性の原料が主体で、芯に和紙を使います。よく、観光土産で、美しい絵が描かれた和ろうそくを見ることがありますね。
琵琶湖を見渡す、滋賀県にある、和ろうそくの大與(だいよう)の4代目、大西巧(さとし)さんは、「国産・天然の植物100%」のみを扱います。生活様式の変化で従来の需要は減り続けます。2011年には、「お米のろうそく」で、グッドデザイン特別賞を受賞します。関心を呼ぶものの、主な取引先であるお寺での需要が減っていきます。和ろうそくではなく、価格の安い洋ロウソクに切り替えていくのです。
そこで、大西さんは、思い切って海外市場に打って出ます。「夢あるやん、行け!」と3代目の猛反対の中、弟が背中を押します。2019年に渡米し、10日間の営業ツアーで、日本での一年分を売上げたのです。素材を生かした風合いが受け入れられ、欧米風のインテリア雑貨店を中心に取引が増えたそうです。
「私たちが作る和ろうそくの哲学に共感してもらえたと思います。地下から掘り起こす化石燃料ではなく、地上にあるものを原料にすれば、営みに無理がない。そんな価値観を分かち合えた」と大西さんは言います。
もちろん、洋ロウソクと比較すると、和ろうそくは価格が高いです。家庭で使うタイプでも1本300円以上はします。和ろうそくは、ろうが垂れることや油煙をほぼ発生させません。そして、匂いもほとんどないそうです。我が家には、仏壇がありますので、一度和ろうそくを灯したいと思っています。みなさんも、少し「和ろうそく」を気にしてみてください。
2024年
5月
25日
土
学習障害への合理的配慮
今日は、久しぶりに小学生女子と年長女子が、ローラーブレードを楽しみました。一番得意な子が、どんどん先に進んでいきます。「みんな~おそいよ!」と言うと、「これ以上スピード出したら転んじゃうから」と、自分のペースを守る女子です。子どもは、たいがい無謀な挑戦をしてしまうことが多いですが、冷静な女の子に アッパレです。
さて、新年度がスタートして2か月が過ぎようとしています。特に1年生にとっては、初めての小学校生活で、得意なことも苦手なことも見えてきます。発達障害の中でも、自閉症スペクトラム障害や注意欠如多動性障害などは、子どもの行動から判断できることが多いですが、発達障害の一つである「学習障害」については、小学生になって、実際に授業が始まってから目立ってきます。
黒板の字を読むのが苦手。ノートに字を書くのが苦手。算数の計算が苦手。もちろん、単に子どもが不得意な分野であることが多いですが、読み書きや計算など、能力のごく一部だけが極端に苦手な場合は、学習障害の可能性があります。
例えば、A君は字を書くのが苦手でした。幼稚園の頃から、字が裏返しになるなど正確に書けません。小学校入学後には、黒板の文字をノートに写せない、ひらがなが正確に書けないなど、しんどい時間を過ごすことになりました。A君は、知的発達に遅れはなく、幼稚園までは元気に普通に過ごしてきたそうです。お母さんが持参したノートや授業での経過から学習障害である「書字障害」と診断されました。A君の担任は、黒板を写さなくてもいいようにプリントを用意するなど工夫してくれて、A君は楽しく登校できているようです。
この担任のように、工夫して支援することを「合理的配慮」といいます。車椅子の方のための段差解消、難聴の方に伝わりやすくするための工夫など、令和の現代は、様々な場所で「合理的配慮」が進んでいます。この4月からは、民間企業や私立校でも、障害者差別解消法で、合理的配慮が義務付けられています。
学習障害の場合、子どもの「苦手」は治せません。「苦手」に合わせた対応が必要になるのです。これからの世の中が、「合理的配慮」の和で広がるとうれしいですね。
今と比較して、昭和の駅のホームにはあるものがありません。何だと思いますか。それは、黄色の点字ブロックです。今では、当たり前に駅のホームに張りめぐされていますが、つい昔は、合理的配慮はなかったのです。
2024年
5月
24日
金
インティマシー・コーディネーターという仕事
今日は体操教室です。年少園児たちは、ようやく自分で着替えて、水筒を飲めるようになってきました。まだまだ動きは、ヘロヘロで、よく転びますが、「慣れる」ことも成長の一つですね。体操教室の前に、運動会で行う組体操の練習から始めます。「ブリッジ」もずいぶんと様になってきました。こちらは、練習あるのみです。(笑)
さて、今日は、あまり聞き慣れない「インティマシー・コーディネーター(IC)」という仕事についての話です。知っていますか。この仕事は、決してAIに奪われない、ヒトでしかできない仕事です。そして、日本には、この仕事を行っている人は、たった二人しかいません。
映画やドラマの撮影現場で性的な描写やヌードシーンなどにおいて、俳優の同意を取りながら、監督の意向を聞き、制作を円滑に進める調整役です。私は、こんな仕事があることなど知りませんでした。
アメリカなどでは、新人俳優など現場での力が弱い人間が、監督などに、無理やり意にそぐわないシーンを強要されることがありました。2017年にはアメリカで、MeToo運動として、主に女優の側から、性的シーンの撮影における安全確保を求める声が世界的に広がりました。そんな中で、インティマシー・コーディネーターという仕事が生まれたのです。まだ最近誕生した新しい仕事と言えます。
日本に2人いる1人の西山ももこさんは、「ICは、俳優を守る『正義の味方』というイメージで見られがちですが、私たちはあくまでも撮影が安全に行われるための調整役。正義の味方でもないんです」と語ります。西山さんがICの資格を取得したのは、2020年ですので、まだ4年前です。
西山さんは続けます。「私は、映画などに性表現がない方がいいとは思いません。そこに意図や必要性があれば肯定します。だからこそ、だれかの犠牲の上に作品を作ってはいけないのです。俳優、監督、スタッフ全員が安全に良い作品を作るために調整をします」
「ノーという勇気」もギャラの交渉さえも、西山さんは俳優たちのために、調整能力を発揮するのです。
もちろん、現在つくられているすべての映画に、インティマシー・コーディネーターが、配置されているわけではありません。でも、必要な仕事であることには変わりありませんね。かつて、俳優志望の後輩に、「役において、脱ぐシーンがあってもやるのか?」と聞いたことがあるのですが、「ストーリーに必然性があれば、脱ぎます」と答えたのです。俳優・芸能の世界は、私の知らないことが多いので何とも言えませんが、今日は、インティマシー・コーディネーターという仕事の存在だけは覚えてください。
2024年
5月
23日
木
家庭菜園で癒される
今日は、屋上ファームで、チビちゃんたちをメインに、インゲン豆の種をまきました。先日の寺子屋では、「そらいろのたねをまくよ!」と言っても園児たちは信じてくれませんでしたが、チビちゃんたちは、「やった!おうちが、はえてくるかもしれないね」なんて、かわいいことを言っています。
こんな感じで、保育園の子どもたちは、いつも遊んでいる屋上にファームがあるので、野菜にかかわる生活を当たり前に経験しています。そんなこともあって、おうちで、家庭菜園をする家族が多いです。連絡ノートにも、「○○を収穫しました」というコメントをよく見かけます。
とうことで、今日は家庭菜園の話です。近ごろ、家庭菜園に興味を持つ女性が増えているようです。男の場合は、なぜか「畑仕事」というイメージですが、女性だと「家庭菜園」という言い方になるのは、不思議ですね。(笑)
家庭菜園は、一戸建てなら庭で、マンションならベランダでプランターだってできます。市民農園のような場所も、最近は増えてきました。行政が管轄する農園なら、年間でも1万円かからないくらいで借りられます。
週末は農園中心という独身OLは、遊びに誘われても、畑仕事を終わらせてから合流するそうです。「うちの子かわいいでしょ」と、収穫した野菜を仲間におすそ分けです。もちろん、家庭菜園は思い通りにならないこともあります。芽が出なかったり、突然枯れたり病気になったりします。家庭菜園の先輩にアドバイスをもらいながらコミュニケーションも図れますね。台風や大雨の時は気が気でなくなります。例えば、夏野菜の代表「トマト」は、1本の茎を成長させるために、枝芽を欠く作業が必要になります。保育園の屋上ファームでも1日何もしないと、枝芽がたくさん出てきます。週末作業だと、半日はこんな作業で時間が流れます。でも、「手間暇をかけた分だけ成果が見えます。私にとって、最高の癒しです」と、独身OLにとっては、極上の時間になっているようです。
東京都心でも仕事帰りに立ち寄れる農園もあります。お台場の「ダイバーシティ東京プラザ」の屋上は貸農園になっています。値段は、1区画(3平方メートル)で、月額1万円と、かなり割高ですが、レインボーブリッジを見ながらの畑仕事なんて・・・最高ですね。
「土をいじり、作物を収穫する」ことは、農耕民族のDNAを持つ、人間にとって、プラスのスイッチが入ることは間違いないでしょうが、現代社会のストレスからも回避できて、癒される時間になっているのです。一人でも農園で多くの人と出会うことができるし、ファミリーなら最高の時間です。
さて、「タキイ種苗」が20歳以上の600人にネットアンケートを行った結果、「家庭菜園で野菜などを作っていますか?」の問いに、規模の大小はある者の、21.8%もの人が家庭菜園を行っているとの結果が出ました。私は、正直多いと思いました。
家庭菜園用のコスチュームもどんどんオシャレになっていますね。自分の時間や趣味を大切にするライフスタイルの中に、「家庭菜園」は、堂々の上位ランクインですね。
2024年
5月
22日
水
わくわく教室でおにぎり作りました
毎日、何かしら、明るいニュースが流れるように、暗いニュースもテレビをつければ、子どもの目に入ります。「暗いニュース、子どもに見せる?」のアンケート調査では、「見せる」「見せない」「どちらとも言えない」が、それぞれ1/3ずつに分かれるようです。
見せる派は、「特に子ども関連の事件や事故などは、あえて見せて説明して危険回避を教える」「子どもが疑問に思ったことは、親の考えや事実を正直に伝えた方が子どものためになる」。見せない派は、「世界が怖いものだと植え付ける可能性があるので、知るのはまだ早い」「戦争などはまだ理解できず、戦いごっこのネタになるだけだから」「地震などの災害は、トラウマになりやすいから」。
親の考え方や、子どもの性格で対応は変わるのでしょうが、親子の会話のきっかけになり、子どもが自分で考えることにつながるように、親は持っていきたいですね。
さて、今日は、年長園児8人が、「わくわく教室」で学び合いました。今回は「米について学び、おにぎりを自分たちで作る」です。歩いてすぐの公民館のキッチンに向かう年長園児たち・・・「やった!今日はわくわく教室だ!」と歓喜するものの、具体的に何をするのか、説明できる園児は数人です。(笑)
かっぽう着姿になり、手を洗って、「わくわく教室」がスタートしました。稲が大きくなって、米が収穫できる流れを本で学びます。実際に稲穂から1粒の米をちぎって、もみ殻を手ではがして、玄米にしてみます。5歳男の子は「何だか、茶色っぽくて、おうちの米と色が違う」ことに気がつきました。なかなかの観察眼です。
米を研ぐという言葉も覚えました。最初のとぎ水は、牛乳みたいに白かったのに、4回目は、普通の水に近くなってきました。子どもたちは、おうちでも、米を研ぐところから手伝いをすることでしょう。そして、耐熱ガラスの鍋で10分間中火でお米の様子を観察します。鍋の底からブクブクと泡が出てきて、米が踊り出します。ごはんの匂いがしてきました。そして、泡が鍋の上までモクモクと上がってきます。火を弱火にしてさらに10分、最後は蒸らしてごはんが炊きあがりました。おうちでは、炊飯器でご飯を炊くので、中の様子がわかりませんが、今日は、ガラスの鍋なのでまる見えです。
そして、いよいよ、子どもたちのおにぎり作りです。おかか醤油おにぎりは、三角おにぎりにします。鮭おにぎりは、のりを使って、自分が作りたい、自由作品としました。ハート形のおにぎりがあったり、海苔をちぎって顔にする園児たち。「何を作ったのか、わからなくなっちゃった」という園児もいました。もちろん、自分で作ったおにぎりを「いただきます!」です。あっという間に完食でした。
6月1日の親子遠足と11日のお菓子工場見学では、年長園児は自分でおにぎりを作ってくることでしょう。今日も、子どもたちの「わくわく」を大いに引き出すことができました。最後に、「ママやパパに伝えたいこと」を一人一人話してもらいます。「おにぎりを自分で作ったことが楽しかった」「米を研ぐのが、初めてで楽しかった」「鍋の中でお米がいい匂いだった」などなど・・・今日は、お米のこと・ごはんのこと・おにぎりのこと・・・など、会話が弾むことでしょう。
しばらくは、ママの料理のお手伝いが続きそうです。(笑)
2024年
5月
21日
火
宿題って必要? ②
今日は朝から快晴です。いつもよりも少し早く屋上遊びを始めました。桑の木のまわりには子どもたちが集まり、マルベリーのつまみ食いが始まりました。令和の時代には、あまり見られないワイルドな光景です。そして、カメ池では、今シーズン初めての「卵」を採集しました。4つの卵を飼育ケースに入れて、子どもたちと観察します。この卵は、ニホンイシガメかクサガメか、それともイシガメクサガメハーフのウンキュウか・・・楽しみです。赤ちゃんガメ誕生は2か月後です。
さて、宿題って必要?2日目は、宿題不要派の意見を中心に聞いてもらいます。東京都庁そばの新宿区立西新宿小学校は、全学年で、毎日の宿題を昨年春から「原則なし」にしました。夏休みの読書感想文も自由研究も一律には求めていないそうです。長井校長の考えは、「児童それぞれの学習の進み度合いを踏まえず、単に計算ドリルや漢字練習を一律に課すことに疑問を感じていました。児童自身が『自分に必要なことだ』と思えない宿題では、効率は得られない」とのことです。
もちろん、西新宿小学校では、宿題なしのほったらかしではありません。「自学ノート」という取り組みを行っており、児童が自分でテーマを考えて調べたことをまとめ、先生に見せるのです。例えば、社会の授業をきっかけに中東情勢に興味を持ち、新聞記事を切り抜いて感想を書いたり、自学ノートに「長い国名」ランキングをまとめて先生に提出する児童があったそうです。ある保護者は、「宿題がないことが、興味を持ったことを掘り下げたり、遊びの中にも勉強の芽があることに気づいたりする良いきっかけにもなっています」と言います。
こうした、「宿題をなくす学校」は、各地で増えているそうです。長崎市立長崎中学校は、2022年度から一律の宿題をやめ、生徒本人が決めた内容で家庭学習に取り組んでいます。山形県新庄市や岐阜県でも自主学習に転換する動きがあるようです。
そもそも、日本での宿題の始まりは、近代的な学校の整備が進んだ、明治時代の1900年代初頭とされています。「音読・漢字・計算ドリル」といった宿題は、日本の学校教育の習慣として、根付いてしまったようです。昭和の頃は、「宿題って必要?」なんて、思う人などほとんどいなかったのかもしれませんね。
令和の今、改めて聞きますが、あなたは「宿題は必要だと思いますか?それとも、なくした方がいいですか?」
私が考えるには、夏休みの自由研究などを除いて、毎日出されるような日本の宿題の多くは、「認知能力」という、学習能力を高める内容です。これには、どうしても個人差があって、一律の宿題では、問題が発生します。ところが、自分で考える課題は「非認知能力」を高める内容です。自主性が問われるのです。
宿題がどうのこうの前に、「子どもたちに必要な学力は?」を考えると、非認知能力の割合が今後高くなっていきます。そうであれば、宿題という言い方が適切かはわかりませんが、「自分で考える」「仲間と協力する」課題をこれからは多くしていかなければならないと思います。
「従来の習慣化した宿題からの脱却・・・そして、子どもたちが自分で考える新たな課題への変換・・・」これで、決まりでしょ。
2024年
5月
20日
月
宿題って必要? ①
今日は雨になってしまったので、教室内でプチ体操教室です。サッカーのドリブル・マット運動・とび箱・鉄棒など、しっかりと体を動かしました。雨の日は屋上遊びができないので、お昼寝タイムに熟睡できるように、運動のプログラムが多くなります。
さて、私が小・中学生の頃は、宿題は、ほぼ毎日出ていた記憶があります。そして、宿題を忘れようものなら、先生からきつく叱られました。今でも、ある調査では、毎日宿題を出す小学校教員の割合は90%以上もありますが、どうやら、「宿題なし」の学校が増えつつあるようです。そこで、今日・明日は、「宿題って必要?」について考えます。
今日は、「宿題賛成派」の意見を中心に取り上げます。学校のカリキュラムを定めた小学校向けの「学習指導要領」には、「家庭との連携を図りながら、児童の学習習慣が確立するよう配慮する」とう記載はありますが、「宿題」という言葉はありません。中学校向けも同様です。宿題を出す出さないは、実は学校の判断に委ねられています。
昨年8月、高松市議会に「宿題の原則廃止」を求める陳情が提出されました。ところが、賛成は、市議40人中1人にとどまり、不採択となりました。高松市の教育委員会は「学習習慣を作る」といった面で、宿題は有効だとしています。
では、子どもたちの意見はどうでしょうか。放課後に教室を開放している埼玉県新座市の小学校で話を聞くと、「面倒くさいけど、将来の役に立つ。算数の問題がすらすら解けるようになった時はうれしかった」「宿題がないと、ユーチューブを見たり、ゲームをしたりしてしまう」という声が聞こえてきました。
教員の意見は、「子どもに学習内容を定着させるには、何回も反復させることが大事。家庭でその機会を作る宿題の役割は大きい」「塾や通信教育で勉強させる家庭もあれば、その余裕がない家庭もある現実を見てきた。宿題は、全員に平等に勉強させることがでる。生きていくのに不可欠な学力を下支えする面もある」といったところです。
う~ん・・・ここまでの意見は、おっしゃる通りの内容ですね。宿題をなくして、子どもたちの自主性を伸ばすような取り組みだって、あるはずでは・・・
明日は、宿題不要派の意見を考えることにします。
2024年
5月
19日
日
ウォーターボーイズ
誰もやってこなかったことを周囲の困難を克服してやり遂げるというストーリーは、たまらなく大好きな私です。埼玉県立川越高校の文化祭では、何万人もの観客を魅了する、今も続く「ウォーターボーイズ」は、1986年に初めて披露されました。
当時3年生で水泳部員だった、現在は55歳の北川さんは、引退した7月下旬に仲間に呼びかけます。「シンクロやろうぜ!」。3年生11人のうち、北川さんの他に5人が賛同しました。しかし、文化祭当日は、1・2年生が試合で、「水泳部は活動なし」と学校には伝えていたそうです。今からの申請は、通らないと諦め、6人は「ゲリラ的に決行するしかない」と決断したのです。
カーン、カーン、カーン・・・部員の一人が演技を告げる鐘を鳴らしました。「何が起きるんだ」来場者たちが、プールの横にある4階建ての校舎の窓から、一斉に顔を出します。それを合図に、北川さんは、仲間とプールサイドの真ん中に駆け出し、一列に並びます。女子の水着に似せようと、上半身はタンクトップ姿。「始めます」と叫ぶと、水中へと飛び込みます。
6人は水面に浮き、プールに円を描く。水中で声を出しながら足を上げ、手をそろえて踊った。最期は3段ピラミッドの一番上の部員が、後方宙返りで締めくくった。歓声がプールにも届く。「みんなで心を通わせて一つのことをやり遂げ、誰かに喜んでもらうことの素晴らしさを知った」と北川さんは語ります。
ゲリラ公演は大成功し、2年後には水泳部が正式な企画として始めた文化祭限定の「男のシンクロ」は、川越高の名物になっていったのです。それから10年が過ぎた1999年、当時の部長畠山さんは、「おれたちの代で大きなことをやろう」とテレビ番組に電話をかけると、報道番組「ニュースステーション」で取り上げてくれることになったのです。
そして、ついに「ウォーターボーイズ」は、2001年9月に映画化されました。そして、大ヒットしたのは、まだ記憶に新しいところですね。畠山さんは、俳優たちに演技指導をする大役を任されたのです。
ゲリラ公演を行って「男のシンクロ」を初めて行った北川さんは、大手出版社の「小学館」に入社し、「図鑑NEO」シリーズの編集を行い、大ヒット図鑑にしました。「新しいものを取り入れなければ意味がない」という気持ちだったそうです。
そして、映画化につながった畠山さんは、2浪して歯学部に入学します。現在は親知らずの抜歯に特化したクリニックを開いたそうです。2か月先まで予約が埋まっている人気だそうです。
どうも、この二人には、「新しいことを考え、誰もやっていないことに挑戦する精神は、水泳部で学んだ私の原点」という思いがあるようです。こんな話を聞くと、保育園の子どもたちには、こんな生き方をしてもらいたいなぁ~と、思ってしまう私です。
2024年
5月
18日
土
寝台列車は必要です!
今日は、小学生が7人も集合です。屋上では、マルベリーの実をずっと採っていました。「これ、午後のおやつで食べるんだ!」と、ザルにいっぱい収穫してくれました。木に登り、収穫したマルベリーをきちんと洗うまで、自分たちでやり遂げます。さすが、小学生ですね。
さて、昨日のブログでは「リニア新幹線」の話をしましたが、今日は対極にある「寝台列車」についてです。まずは、寝台列車と聞いて、何をイメージしますか。まずは、1988年に青函トンネルが開通して、飛行機を使用しない北海道への観光需要が高まるとみて、上野-札幌間で「北斗星」・大阪-札幌間で「トワイライトエクスプレス」が相次いで導入されました。北斗星では、すでに斜陽になっていた食堂車をつないで、フランス料理のフルコースを提供しました。豪華個室寝台を連結するなどして、鉄道での移動そのものを旅として楽しんでもらう発想が、ヒットにつながりました。「北斗星」も「トワイライトエクスプレス」も豪華な「カシオペア」も廃止されてしまいますが、今でも「JR九州のななつ星」「JR東日本の四季島」「JR西日本の瑞風」らの不定期の豪華列車に引き継がれています。今でも平均倍率が14倍だそうで、なかなか予約ができない人気列車です。
では、ここで問題です。現在、唯一定期運行を続ける寝台特急は何でしょうか?それは、1998年に運行開始となった「サンライズ瀬戸・出雲」です。東京駅を一緒に出発しますが、岡山で車両が切り離されて、四国の高松と山陰の出雲に向かいます。今でも、週末は予約が取りづらい列車です。
国鉄時代の話ですが、「ブルートレイン」という言葉を聞いたことがありますか。東京から九州を結ぶ「あさかぜ」が有名ですが、専用の20系客車を製造し、編成を固定し、冷暖房を完備、窓を閉め切ることで騒音を低減、空気ばね台車で振動も抑える車両は、またたくまに大人気となりました。私も父の実家が福岡県でしたので、「はやぶさ号」に小学生の頃に乗りました。廊下通路に折りたたみイスで、ずっと車窓を眺めていました。わくわくして、眠れなかった記憶があります。しかし、ブルートレインの全盛期は長く続かず、新幹線が博多まで伸び、飛行機との競合もあり、2005年の「あさかぜ」がラストランとなりました。
世の中が、タイパ(時間対効果)を求める風潮が高くなり、夜通し、時間をかけて移動する寝台列車は減ってしまいました。しかし、旅行というものが、「非日常」の頂点とするならば、「寝台特急」「夜行列車」での旅は、「非日常」のもっとも大きな演出効果となることは間違いありません。
旅のスタイルが、さらに多様化していく今後・・・やっぱり「寝台列車」は、必要です。こう思うのは、私だけではありませんよ!個人的には、豪華寝台特急でない、座席タイプの夜行列車の復活を願う私です。上野ー青森間を走っていた夜行急行列車は、私が学生の頃には3本もありました。「八甲田(東北本線経由)」「十和田(常磐線経由)」「津軽(奥羽線経由)」・・・なんかが復活したら、たまらんのです。(笑)
2024年
5月
17日
金
リニアモーターカーって本当に必要!?
今日から、体操教室の前に、教室内で「運動会の組体操」の練習をスタートさせました。年長・年中園児は、すでに経験していますが、年少園児にとっては、「組体操」は、高い壁です。今日は、「かかし」→「飛行機」→「ヨット」→「ブリッジ」の4つだけですが、グダグダです。先輩たちにお手本を見せてもらって、フォローしてもらって、少しだけ、形になった感じです。まだ先は長いので、あせらずに、じっくりと教えていきます。
さて、リニア新幹線で、岐阜県内の14か所の水源で、井戸などの水位低下が起こり、いったん工事を中断したというニュースが入ってきました。これで、また開業日が延びてしまうのかと少し残念な気持ちになった人が多かったと思います。もっと言えば、静岡県内の工事をストップさせていた、静岡県の川勝知事が突然の辞職を表明したので、「これで、早期開業に弾みがついた!当初予定の2027年品川ー名古屋間開業は、JR東海は断念したけど、2030年くらいには何とかなるのでは・・・」と思ったのも、つかの間です。
リニアモーターカーに関しては、私がまだ子どもの頃から、ずっと話題になっていて「夢の超特急」という、プラスのイメージばかりが私の頭にはインプットされてきました。リニア構想は、私が生まれる前の1962年(昭和37年)に、東京ー大阪間を1時間以内で結ぶ超高速鉄道をつくるというビジョンから始まります。最初の東京オリンピックが行われた昭和39年に、同じく東海道新幹線が開業したので、リニアモーターカーは、新幹線開業の2年前には、構想があったことになります。
1979年(昭和54年)に、初の実験車両が走り、無人走行で517キロを記録し、世界最速の記録を出しました。それから、何度も試験運転が繰り返されたのです。何度も、実験が行われ、その映像を見てきましたが、いつの間にか「いつになったらできるんだよ!」という感じにもなりましたね。1962年の構想から、当初予定していた2027年に開業したとしても、65年もかかったことになります。どれだけの、時間と金が動いたことか。
東京ー名古屋間を40分、将来は東京ー大阪間を67分で結ぶ、時速500キロの超特急です。リニア新幹線が開業すると「首都圏・中京圏・近畿圏の三大都市圏が一つの巨大都市圏となり、人と人とが会うことで新たなイノベーションが生み出され、余暇の過ごし方などライフスタイルの変化を通じて豊かで多様な暮らしを実現するなど、新たな可能性が生まれる」と考えられます。JR東海が自費でリニアを建設するので、「民営」ではあるものの、リニア新幹線は国策であることは間違いないです。
私たち国民は、リニアからは「夢」のイメージが強く与えられますが、コロナ禍が終わり、国民の価値観も変わりました。ここにきて、「負」の側面も含めて、きちんと議論すべきではないかという考えが大きくなってきたようです。環境問題は、やはり、ないがしろにされてる部分が多いのです。
私は、鉄道に乗るのが大好きですので、リニア新幹線が具体化した時は、胸が躍りました。しかし、品川ー名古屋間286キロのうち、約86%がトンネルであることがわかって、「なんだよ!リニアは地下鉄で車窓を楽しむことができないじゃないか!」と、急に気持ちがさめてしまいました。旅をするなら、富士山を見ながら、普通の新幹線か東海道線でのんびりがいいと思っています。
「国」の立場は、もう後戻りできない!かもしれませんが、もう一度「リニアモーターカーって本当に必要?」を議論するべきなのかもしれません。
2024年
5月
16日
木
日本一来館者数の多い図書館
マルベリー(桑の実)のつまみ食いが、激しくなってきました。木に登って、他の園児が届かない場所で、むさぼり食べる5歳男の子。どろんこ広場にある桑の木は、小さいのに枝にびっしりと実がついています。高い所にある枝を切って子どもたちに渡すと、原始時代のヒトが、木の実に集まるような、そんな光景に映ります。そして、体長10センチほどのヒヨドリもマルベリーを食べています。鳥たちも、ここは、しっかりと栄養を取っているようです。
さて、昨日は午前中には保育園を抜けて、勤務していた会社のOB総会に出席しました。司会進行が私の仕事です。元日に能登半島地震が起きた、石川県金沢市から参加した方の話を聞くことができました。震災の生々しい話と、インバウンドで外国人観光客が激増している話です。テレビでは、円安を反映して、箱根の高級ホテルに泊まり、ランチを貸し切りする豪華な旅行を楽しむ外国人を取り上げますが、現実は、どうも違うようです。金沢駅から兼六園までは、3キロほど離れているので、通常はバスかタクシーを利用するのですが、外国人は、大きなリュックサックを背負って、歩くのだそうです。タクシーなんてとんでもなくて、バスにも乗らないのです。白人系の外国人は、お土産の爆買いなど全くありません。
今日は、そんな金沢市にある「石川県立図書館」の話です。2022年7月に、香林坊という金沢の中心街からバスで20分ほど離れたところに、移転オープンしました。何と、この図書館の2023年度来館者数は、102万6046人です。1日ざっと3000人近くの人が訪れる計算です。今まで1位だった岡山県立図書館が、年間80万人弱ですので、ダントツで、日本一来館者数の多い図書館となりました。
日本の図書館の99%が、「日本十進分類法(にほんじっしんぶんるいほう)」という、0から9までのアラビア数字のみを用い、大まかな分類から細かい分類へと、順次10ずつの校も項目に細分していく手法で、書籍が並んでいます。例えば、「文学」は「9xx」→「日本文学」は、「91x」→「(日本文学の)小説・物語」は「913」といった感じです。図書館の棚に、こうして数字が書かれているのを見たことがありますね。
しかし、石川県立図書館は、「子どもを育てる」「仕事を考える」「生き方に学ぶ」「本の歴史を巡る」「暮らしを広げる」等々の12のテーマ別にブロックが分けられて、多くの本が面で並んでいます。
管理する側の都合では、日本十進分類法が一番適していますが、読む側に立てば、石川県立図書館の分類の方が、分かりやすくて、本を探す楽しみが増えますね。よく、本屋さんが「イベントコーナー」を作って、推しの本を紹介するような感じです。
そして、驚くことに、こんなサインがガラス窓に次々と投影されます。「記念撮影はお好きな場所で」「閲覧エリアは、ふた付の飲み物持ち込みOK」「おしゃべりOK」「お食事は文化交流エリアで」
どうですか・・・図書館では、おしゃべりをしていると、しーっと注意される場所だったはずなのに・・・今までの図書館の概念が吹っ飛びそうです。
まだまだあります。モノづくり体験スペースには3DプリンターやUV印刷機などがあり、たとえば、新商品の試作品をつくることができます。月に1回、無料で30分のミニコンサートを「だんだん広場」で開いているそうです。オーケストラにとっては、有料の公演に呼び込むきっかけになるようです。
「調べものデスク」という窓口があり、利用者の相談にのり、課題の解決に導くという場所もあります。
私は、石川県立図書館に行ったことはありませんが、これ以外にももっとわくわくするような仕掛けがたくさんあるのでしょう。保育園では、子どもと図書館で本を借りるライフスタイルのママが何人かいますが、こんな図書館が増えていったら、一日中過ごしても飽きないですね。
「子どもに本をたくさん読ませたい」のきっかけになる図書館が、こんな感じで変わっていくのはうれしいですね。
2024年
5月
15日
水
2050年の日本の姿②
昨日の寺子屋では、保育園で飼っている「カブトムシの幼虫」の観察をしました。15匹いるのですが、7月には成虫になります。サナギになる前の、最後の幼虫です。4歳の女の子に「幼虫のお腹にある黒い点は何?」と質問されました。調べてみると、この黒い点々があるのがオスで無いのがメスだそうです。私は、幼虫ではオスメスの区別はつかないと思っていましたが、この黒点でわかるようです。子どもの観察眼は大したものです。
さて、昨日のブログで2050年の日本は、ドラえもんのような世界になっていると言いましたが、今日は、現実的な話です。
都市への人口集中、地方の過疎化問題は、日本の大きな問題ですが、2045年には、東京の人口が減少に転じると言われています。国民は、天災への備えを真剣に考えるようになってきます。南海トラフトや首都直下型といった大地震も予想される中、人口も政治機能も一極集中している東京が被災したらどうなるのか。物流は途絶え、食料や生活用品を確保できなくなる。ひょっとしたら、政府が機能するかもあやしい。その混乱は、これまでの震災の比ではない。そう語るのは、東京大学の養老(ようろう)名誉教授です。
彼は、2050年には、都市への人口集中が解消され、人々が地域ごとに食糧やエネルギーを自給自足して暮らすような、日本の望ましい姿になっているのでは・・・と言います。
「自活する力が重要になる。都会的なシステムに依存せず、自分と身の回りの人で、食糧やエネルギーを自給自足しながら生活を持続させる。文化人類学では、あり合わせのもので、上手にやりくりすることを『ブリコラージュ』というが、その実現が個々に求められる。一つ一つの地域も、そんな生活に見合う、小さなサイズが適切だ。テクノロジーの進化が様々な問題を解決するはずだという話はよく聞く。しかし、物事には必ず両面がある。何かが解決され、楽になることは、何かを考えなくなることでもある」
養老教授は、合理性、経済性、生産性を追求してきた時代とは、まったく逆の方向に進んでいくはずだ。と語ります。一人一人が実感を持ち、暮らしを足元から積み上げていく。それぞれが自活し、居心地の良い日常を送れるようになれば、未来は平和だと言います。
どうですか・・・ドラえもんの世界もいいですが、「幸福な人生」という観点で考えると、私は、こちらの未来に魅力を感じます。みなさんが望む2050年は、どんな日本になっていると思いますか。
2024年
5月
14日
火
2050年の日本の姿①
今日は、晴天で屋上遊びができました。子どもたちは、すぐに「桑の木」のまわりに集まります。目的は、桑の実(マルベリー)を食べることです。年長園児は、自分で赤黒く熟した実を食べています。小さい子は、職員からもらいます。「桑の実をむさぼり食べる子どもたち・・・」とっても、ワイルドです。(笑)
今日は、見学に来ていたママがいたのですが、桑の実の説明を園長がしていると、年長の男の子が、そのママに「マルベリーだよ。食べていいよ」と渡したのです。なんと、優しくて、気遣いのある対応に、感動する園長です。
さて、今日は2050年の日本がどうなっているか?の未来予想です。今から26年後なんて、近い未来と考える人も多いでしょうが、ズバリ当てるのは、難しいですね。人間は、今から100年前に飛行機を開発し、空を飛び始めました。今では、世界中を飛び回り、ロケットで宇宙にも行っています。人間が想像できることで、実現できないことはないと言われていますので、100年後にはタイムマシンができてもおかしくありませんね。
社会を変えるような技術革新を目指す国の大型プロジェクト「内閣府ムーンショット」で、広報を担当する村木さんの話では、2050年は、「ドラえもんの世界になっているかもしれない」そうです。ドラえもんが持ち込んだ、22世紀の技術の多くは実現しているのではないか。と言います。
自宅にある3Dプリンターでボタンを押せばおいしい料理ができるとか、自動車の自動運転が当たり前になり、料理、運転、掃除などは、もはや趣味になっているのかもしれません。仕事の多くはロボットが代替できるようになっていて、人間はもっとクリエイティブで、本当にやりたいことに専念するようになる。複数の職業を持つことも可能になっていく。
もちろん、変えたくないことは、そのまま残ると考えられ、紙の書籍だったり、リモートワークが増えても、人と直接会う機会は大きくは減らない。いわば、人間くさいところは残っていくのでは・・・。いずれにしても、2050年には、生活のために、面倒なことや気が乗らないことをする必要はなくなっているのではないか。好きなことを追求でき、心の余裕が増える世の中が実現しているのでは・・・と村木さんは言います。
1555年、今から400年以上前に、ノストラダムスが「1999年7月に人類が滅亡する」と予言しました。日本でも、大ブームになりましたね。ちょうど、公害などの環境問題が日本で多発したこともあって、私も、少しは不安にかられ、1999年の8月になって、ホッとした記憶があります。
ドラえもんの世界・・・大いに結構。未来は明るくと信じていきたいですね。2050年、日本の若者が自尊心や誇りを持ち、その先も明るい将来を描いて暮らせる国になって欲しいものです。
2024年
5月
13日
月
ハラスメントの境界線
今日の連絡ノートには、土曜日の保育参観の感想がびっしりと書かれていました。ふだん子どもたちが、どんな風に屋上遊びをしているのかが分かり、一緒に遊べて楽しかったことと、防災の話も大いにためになったようです。親子で収穫したタマネギでジンギスカンを楽しんだファミリーもありました。
ジンギスカンといえば、羊の肉を食べますが、1歳未満をラム肉と言い、1歳以上をマトンと呼びます。今、日本中の動物園では、羊の毛刈りが行われています。毛がなくなった羊は、まるでヤギのようですね。羊は、毛を取るために家畜化された動物なので、人が刈ってあげないと一生伸び続けてしまうのです。今、毛を刈るのは、熱中症対策だそうです。
そして、もう一つ「食べ物」の話ですが、昨日のブログで紹介した「男気トマト」。桶川まで行って買ってきました。家にあったトマトと食べ比べると、とても濃い味がします。様々なメディアで取り上げられるだけありますね。
さて、今日の話は「ハラスメント」です。私が大好きだったドラマ「不適切にもほどがある」にでてくるような、今では絶対NGがはびこっていた昭和。「セクハラ」という言葉がなかった時代。「歩くセクハラ」のようない人も、せいぜい「デリカシーのない人」で片付けられ、野放しになっていたことを考えると、ハラスメントに対する意識が高まったことは良いことだといえます。
また、「逆パワハラ」という言葉も生まれ、部下が自分の間違いを認められずに「自分が失敗した原因は、管理職や先輩が注意喚起してくれなかったからだ!」と捉えたり、上司から挑戦を促された時に「やりたくないことを強制的にやらされている」と訴えるケースもあるようです。
ここ数年の管理職向けの研修で重宝されてきたのが「ハラスメントで何がNGか」を伝授する内容だそうです。つまり、ハラスメントの境界線をさぐる内容ですね。でも、ちょっと待った!です。ハラスメントになるかどうかは、お互いの信頼関係で変わってくるのではないかと、昭和世代の私は思うわけで、一律の境界線など引けないでしょ・・・という見解です。
そんな感じですので、今はハラスメントに対して「回避的なマネジメント」に走る管理職が増えてきたそうです。「飲み会やランチに誘わない」「ミスをしても厳しく指導しない」「必要以上にコミュニケーションを取らない」「フィードバックはあまりしない」という上司と部下の距離を感じる職場になっているようです。
私がサラリーマン時代に管理職になったのは、平成になってからですが、部下の趣味や好みといった個人情報まで、頭の中には当たり前にインプットしていました。その理由は、コミュニケーションを図るためには、当然必要な情報と考えたからです。仕事以外の会話も重要であることは言うまでもありませんね。
これからの時代、ハラスメント回避で、さらに、上司と部下は表面上の付き合いになっていくのでしょうか。間違いなく言えるのは、リーダーシップによってすべてを解決するのではなく、チームのメンバーが主体的に行動するような組織が、これからの「組織のあり方」になっていくのでしょう。チームで解決するという思考を持った個々のスキルが問われるのです。
2024年
5月
12日
日
男気トマト
昨夜、北海道や東北の日本海側で、オーロラが見られたというニュースを見て、「えっ!日本でオーロラ見られるの?」と驚きです。詳しい説明はできませんが、太陽フレアが原因で、世界の多くの場所でオーロラ観測ができたそうです。私の友人から、北欧とアラスカで見たオーロラの画像を見せてもらったことがあります。今回日本で見えたオーロラは、えっ!?という感じで、私たちのイメージする映像ではなかったですが、胸が躍る出来事でしたね。
そして、昨日保育参観で親子で収穫した「タマネギ」を朝食でサラダにして食べました。赤タマネギです。奥様曰く、水にさらすと栄養が流れてしまうので、辛みが少ない新タマネギは、切った後に、空気に少し触れさせるだけで大丈夫とのこと。きざみ海苔をかけて、ポン酢で食べました。「うまい!辛くない!」で、朝から幸せです。(笑)
さて、今日の話は「男気トマト」です。埼玉県桶川市にある手島農園のトマトです。遊び心があるネーミングですが、ここのトマトは、水を与えないで栽培した濃厚トマトなのです。
ホワイトきゃんばすファームでも、先日24本のトマトの苗を植えましたが、もともとトマトの原産地は、南米アンデス山脈ですので、雨がほとんど降らない地域です。トマトは、水分を多く含むと、味が水っぽくなるといわれていますので、保育園でもなるべく水を与えないようにするのですが、晴天が続き、苗がシナっとなってしまうと、どうしても水やりをしてしまいます。
「男気トマト」は、種から苗の段階まで、少ない水で成長する力をつけさせようと、1日おちょこ1杯分の水だけで育てます。苗は夕方にはしおれ、夜露で明け方に回復するという繰り返しです。枯れるか、枯れないかギリギリを見極める栽培を1か月続けます。そして、一定の大きさまで育った後は、長期栽培用のハウスに植え替え、その後は水を一切与えずに育てるそうです。
トマトは、土や空気の中の水分をかき集めるようにして生きるそうです。そうやってつけた実は、格段に濃い味に仕上がります。「もう他のトマトは食べられない」「トマトが苦手な子どもが食べられた」という驚きの声が上がります。
手島農園も、「男気トマト」がブランドトマトとして確立するまでには、多くの苦難があったようです。「無料で商品を試食で使っても構わない」とスーパーに試食コーナーの設置をお願いして、お客様に食べてもらうことを実践してきました。
江戸時代から続く農家を2011年に継いだ11代目の手島孝明さんは、明治乳業で13年営業などの仕事を経験しました。そこで培った考え方が、既定路線の農業を改革する力になり、困難を乗り越えることができたのです。
これだけ、うんちくを語りながら、まだ、私は「男気トマト」を食べたことがありません。今日、桶川に買いに行こうかな。(笑)
2024年
5月
11日
土
令和6年度 保育参観
今日は、保育参観を行いました。今年度の新人園児8名のうち、体調不良などで、5人が欠席となってしまいましたが、保育園の中に、パパママ、おじいちゃんおばあちゃん、きょうだいと一緒なので、日常の保育園と違って、元気よく走りまわり、無駄な動きが多い子どもたちです。(笑)
保護者の自己紹介が終わると、今回は、「おうちで地震!どうする?」というタイトルで、東京消防庁に勤務するパパに話をしていただきました。「では、スペシャルゲストの登場です!」に、本物の制服姿のパパが登場したのです。教室内は、園児も保護者もどよめきます。「園長先生の発動を受けて、やってきました!」と、ちゃんと笑いをとります。大事なポイントは、いくつもあるのですが、一番印象に残ったのは、「子どもの名前を呼ばない」です。「○○ちゃん・・・大丈夫かい?」と声をかけると、子どもは、親の方へ移動してしまうので、地震が落ち着いたら、子どもの確認をするのがベストです。どうですか、親の気持ちとしては、いち早く子どもの名前を呼んでしまいますね。
そして、ママへのプレゼントは「ママありがとう!マグネット」です。冷蔵庫の扉で活躍しますが、子どもたちが、ママの顔を描いたので、世界で一つだけのプレゼントです。ママに抱きしめられて、濃厚な時間を過ごした子どもたちは、いよいよ屋上へGO!です。
今回は、屋上でいつも子どもたちがやっている遊びを親子で楽しみました。自転車に三輪車、タイヤアスレチックに砂遊び、しゃぼん玉、お絵かき、野球にドッジボール、カメのエサやりなどなど・・・保護者にとっては、連絡ノートに職員が書く遊びの内容が、よくわかったと思います。
親子レースも盛り上がりました。板の橋渡りと台車カートの親子競争です。寺子屋園児は、親を台車に乗せて、子どもが引っ張ります。この手のレースでは、必ず本気モードのパパママが現れます。(笑)
最後は、親子で玉ねぎの収穫を楽しみました。赤ちゃんの頭ぐらいのビッグタマネギが、ゴロゴロと収穫できました。赤タマネギもあるので、おいしいサラダが楽しめそうです。
しっかりと2時間・・・親子で、保育園の日常を楽しんでもらいました。子どもたちにとっては、パパママと一緒なので、ずっとわくわくしながらの時間だったようです。
タマネギを持って、満足そうに帰る親子を見ると、うれしい気持ちになります。マルベリー(桑の実)も、少しだけ楽しんでもらいました。今日は、親子の会話を充実させて欲しいですね。
本日出席いただいた保護者の皆様・・・お兄ちゃん、お姉ちゃん。本当にありがとうございました。
2024年
5月
10日
金
チーム担任制
今日は、寺子屋園児が屋上にタイヤアスレチックを完成させました。事前に、黄色・青色・ピンク色の3色で、板に色塗りをしていました。タイヤや収穫用ボックスを積み上げて、なかなか楽しそうなタイヤアスレチックの出来上がりです。早速、自分たちで楽しむ子どもたちです。
明日の保育参観では、教室内でママにプレゼントをした後に、屋上に移動して、親子でいつもの遊びを一緒に楽しんでもらいます。その一つが、タイヤアスレチックです。天気予報も晴れですので、明日は大いに楽しんでもらいます。
さて、みなさんは、自分の仕事のスキルをアップさせるために、今までどうやってきましたか。勉強して知識アップ、資格を取る、研修を受けるなど、それぞれあると思いますが、私の場合、一番効果的だったのが、「上司や先輩の技を盗む」です。セロベースの自分から、次々とアイデアが浮かぶことは難しいので、とにかく盗み、自分流にアレンジして、さも、自分が考えたかの如く振舞うのです。(笑)
しかし、「先生」という仕事は、「一国一城の主」のイメージが強く、なかなか他の先生の技を盗むことは難しいですね。
富山県南砺(なんと)市は、市内のすべての小中学校で、「チーム担任制」を導入しています。二人の担任が、2学年合同の授業を行うのです。例えば、小学校3年と4年の道徳の授業が合同で行われます。先生は、3年と4年の担任二人です。「学校のルールって何がある?」と、授業の進行役を4年の担任が務めます。児童から「廊下を走らない」「スマホを持ってこない」「教室で眠らない」など様々な意見が上がります。補佐役の3年生の担任は、それぞれの机を回り、ワークシートに書かれた児童の意見をチャックします。担任がチームを組むことで、お互いのやり方を学び、自らのスキルもアップするとうわけです。
南砺市が「チーム担任制」を導入した背景には、残業の常態化や世代交代により若手教員が増えたことがあったようです。ベテランの大量退職で、指導技術の伝承が減り、教育力低下が危惧されたからです。教員同士が得意教科の授業を担当し合うことで、授業の質も高められたようです。
南砺市では、2020年度から「チーム担任制」を導入していますが、制度導入後に新任が年度途中で退職した事例はゼロになったそうです。1学級だと生活集団が固定されてしまいますが、2学年ごとに教えると、子どもたちの顔ぶれが、毎年度入れ替わり、多様な意見に触れることが可能になりますね。今のところ、道徳・生活・音楽・図工・家庭科・体育などで、合同授業が行われているそうです。国語や算数、社会といった授業でも、異学年で学び合うことも可能です。
異年齢保育のホワイトきゃんばすでは、学年別の合同授業が、どれだけ効果的かは、経験上よく理解できます。私たちが、大人になって社会人となれば、そこには、同じ学年のチームや組織はありません。人は、必ず異年齢の環境でコミュニケーション能力を高めていくのです。
南砺市の「チーム担任制」は、教員にもよし、児童・生徒にもよしの取り組みですね。
2024年
5月
09日
木
どうせ行くなら楽しい地獄
今日は、マルベリー(桑の実)が少しだけ、赤黒く熟してきたので、子どもたちと食べてみました。まだ、酸味が強かったですね。明後日の保育参観で、パパに木に登ってもらって収穫してもらいます。マルベリーをむさぼり食べる子どもたちのワイルドな姿を見てもらいます。そして、1、2歳児の園児たちと「トマト」の苗を植えました。これで、ミニトマト12本・中玉トマト6本・大玉トマト6本、合計24本となり、夏野菜の代表であるトマトをこの夏もたくさん子どもたちと食べようと思っています。
話題は変わりますが、「はて?」というセリフが、今年の流行語ベスト10には必ず入るのではと、勝手に思う私です。このセリフは、女性に弁護士資格が認められていなかった時代に法曹の世界を志すヒロイン・寅子が活躍する朝ドラ「虎に翼」で、寅子が、?となった時に口にするセリフです。日本初の女性裁判所長になる「三淵嘉子」さんを描いたストーリーですが、毎朝、多くの人を元気にしていますね。
寅子が女学校卒業直前に、母役の石田ゆり子さんに、お見合いして結婚しなさいと諭されます。法科へ行きたいのは、お見合いから逃げるためだと母が言うと、「そうだよ、だって私、やっぱりお見合いはしたくない。婚姻制度について調べれば調べるほど、心躍るどころか心がしぼんでいく」と言います。母は、「あなたのような頭のいい女が幸せになるには、頭の悪いふりをするしかない。だから、あなたはできるだけあなたに見合った素敵な殿方と見合いすべし」と続けると、寅子は「愛してくれてありがとう。でも、私には、お母さんがいう幸せも、地獄にしか見えない」と、どうせ進むのなら自分で選択した「楽しい地獄」へ行くことを決心するのです。
朝ドラのヒロインは、一人でぐんぐんと時代を切り開いていく、スーパーヒロインのようなイメージが強いですね。もちろん、寅子もパワフルで、自分の意見をきちんと言える人物に描かれていますが、「スーパーヒロイン」ではなく、「シスターフッド」です。
「シスターフッド」という言葉は、聞き慣れない人が多いかもしれませんが、1960年代から誕生した言葉です。女性同士の連帯や親密な結びつきを示す概念です。寅子は、ドラマの中では、決して一人で戦っているのではありません。法科の仲間たちと前に進んでいますね。現代のシスターフッドは、SNSやメディアで、女性たちの絆を積み上げる活動につながっています。
朝ドラは、当時の時代背景が見えてきます。寅子の同窓生たちは、はつらつとしていますが、通りを歩く他の一般女性たちは、明るい顔をしていません。どちらかというと、しんどそうな顔をしています。寅子のように、法科という道を見つけた人は、まだ誰も踏み入れたことのない、いばらの道でも、恵まれているのかもしれません。苦難も楽しく乗り越える寅子の今後が楽しみですね。
2024年
5月
08日
水
キツネとタヌキ
屋上ファームの「エンドウ豆」が終了しました。1か月以上、子どもたちが収穫をがんばり、お土産で、おうちでもたくさん食べました。エンドウ豆を茹でて、マヨネーズをかけて食べるだけでも、あっという間に食卓から無くなる のです。次の植え付けの準備で、エンドウ豆を引っこ抜くと、ダンゴムシが、ざっと500匹以上出てきました。虫嫌いが見たら倒れてしまうかもしれません。しかし、子どもたちにとっては、最高の観察タイムです。飼育ケースにダンゴムシを集めることに夢中です。「先生見て見て!」という瞳は、輝いています。ここは、私が子ども頃の昭和と、まったく変わらないですね。(笑)
さて、今日はキツネとタヌキの話です。ある森に、キツネとタヌキが住んでいました。キツネは走るのが得意なのですが、泳ぐのが苦手です。一方、タヌキは泳ぐのが得意なのですが、走るのが苦手です。そこでキツネとタヌキは、峠のお地蔵様に願い事をかなえてもらうことにしました。
「お地蔵様、キツネの私は泳ぐのが苦手です。得意になるようにしてください」「お地蔵様、タヌキの私は走るのが苦手です。得意になるようにしてください」すると、お地蔵様がしゃべったではありませんか。「キツネさん、泳ぎが苦手でもいいじゃないですか。あなたは走るのが得意なのだから、その力をもっと伸ばしてごらん」「タヌキさん、走るのが苦手でもいいじゃないですか。あなたは泳ぐのが得意なのだから、その力をもっと伸ばしてごらん」キツネとタヌキは、お地蔵様からの言葉を黙って聞いていました。
その日の夜、夕ご飯を食べながら、キツネとタヌキは話し合いました。タヌキが言います。「お地蔵様の言う通りだよ。私たちは一人一人違うのだから、自分の良さをもっと伸ばせばいいんだよ」ところが、キツネは言います。「お地蔵様の言うことはおかしい。私は走るのが得意だけど、泳ぎも得意になりたいんだ」
さぁ~これを読んだあなたは、キツネとタヌキのどちらの考えに近いですか。もちろん、どちらかが正解で、どちらかが不正解ということはありません。親として、我が子にはキツネかタヌキか、どちらの考えを伝えますか。
保育園としては、子どもたちに、キツネのように「あれもこれもできるように、がんばってみよう!」と言いたいところですが、これも、相手次第です。この言葉が、プレッシャーに感じる園児もいます。
大人からのアドバイスは、自分がキツネの思考でも、相手のことを考えてタヌキの選択もあるでしょうし、その逆もありますね。「アメとムチのバランス」と同じように、子どもに対してのアドバイスは、なかなか難しいものです。そうだ。一番いいのは「自分で考えてごらん」かもしれません。
2024年
5月
07日
火
接客の身だしなみが緩和へ
ゴールデンウイークが終わり、今日から「日常」の保育園生活が始まりました。今年は、故郷への帰省以外は、わりと近場で過ごした家族が多かったようです。それでも、日々の活動記録を連絡ノートで拝見すると、「体力おばけ」と言われるくらい、子どもたちはアクティブです。「保育園で早くお友だちと遊びたい」という園児も多かったようで、今日の保育園は、連休明けですが、いつも通りです。
さて、最近では、小売店や飲食店などで働く人たちの身だしなみが、つい数年前と比較しても変化していますね。髪の色を明るく染めたり、ネイルを施したり・・・個人の好みや価値観を尊重した自由な装いは、従業員の意欲向上や人材確保にもつながっているようです。
といった感じで、「時代の流れ」と肯定的に受け止められるようになったものの、私のような昭和世代は、やっぱり、飲食店や食品を扱う店舗では、「清潔な身だしなみ」でないと、「ちょっとなぁ~」という気持ちになるものです。
就職情報会社マイナビが昨年実施した調査では、全国559社のうち、36.7%が直近5年間で、従業員の身だしなみの規定を緩和していました。多様性や個性を尊重するというものの、本音では、人手不足が深刻化し、売り手市場になっているからです。服装規定の緩和は、ファッションに関心の高い若者を呼び込む方策の一つになっています。
スーパーのアピタ・ユニーは、2022年、創業以来初めて服装ルールを緩和し、頭髪と爪の色を自由としました。当初懸念したお客様からの否定的な反応はごくわずかで、むしろ、個性的な外見がお客様とのコミュニケーションのきっかけになったり、白髪を染めているシニア世代の従業員から「自由になれる」と喜びの声が上がり、職場の雰囲気が明るくなったそうです。
回転寿司チェーンのスシローは、昨年11月、髪の色などに関する見だしなみのルールを改めた際、イスラム教徒の女性が頭を覆うために直用するスカーフも認めたそうです。
また、従業員が付ける名札の見直しも進んでいます。客によるつきまといや理不尽な要求などの「カスタマーハラスメント(カスハラ)」から、従業員を守るためです。タリーズコーヒーは、2022年に名札の表記をイニシャルのみにしたそうです。従業員がSNS上でつきまといの被害を受けたためです。「安心して働ける」とのことです。
男性のヒゲを認めたあるスーパーでは、退職を検討していた従業員が撤回を申し出たという例もあったそうです。外国人の従業員が増えている今、「人材の定着、確保にもつながるはず」という考えです。
働くスタッフの人材確保という現実は理解しますが、やはり、お客様がどう受け止めるかが大事ですね。「当店の服装ルールは、○○です」としっかりと打ち出し、お客様にきちんと説明できていることが必要だと思う、昭和世代の私ですが、みなさんは、どう思いますか。
2024年
5月
06日
月
サザエさんの「昭和図鑑」⑨ 食べ物
昨夜は、府中にある大國魂(おおくにたま)神社の「くらやみ祭」に行ってきました。1000年以上の歴史がある、大國魂神社の例大祭です。神事は人の目に触れてはいけないという考えで、灯りをともさずに「くらやみ」の中で行われていたことから、こう呼ばれているようです。今では、もちろん「くらやみ」ではないですが、かつては、男女無礼講で、子孫繁栄を願ったといわれています。
昨日の5月5日は、「おいで」といわれる、「神興渡御(みこしとぎょ)」が行われ、祭りのクライマックスでした。大太鼓をまるでバットのようなバチで叩きます。その大きな音と共に、この祭りの重厚な時間が味わえるのです。太鼓の音と、人々が身につける烏帽子(えぼし)には、太鼓の神輿が所属する屋号が書かれており、その雰囲気もこの祭りの威厳を保っているのです。こんな歴史のある祭りですので、すごい人ごみです。大國魂神社の境内に並ぶ500ほどの屋台で、まともに買い物ができないくらいの、人人人でした。ちなみに、直径2メートル2.5トンの世界最大の太鼓が、先頭を露払いとして登場しました。
くらやみ祭では、交通規制がひかれていましたが、そんな中でもウーバーイーツで食べ物を運ぶ姿を何人も見かけました。コロナが終息しても、食べ物を出前する手段として、今でも需要が高いですね。
昭和の頃の「出前」は、もっとカッコよかったですね。自転車に乗って、何段にもそばを重ねて、まるで曲芸のような出前が、昭和にはよく見られました。そば屋、すし屋、ラーメン屋が、昭和の出前の定番でした。自転車の曲芸の他には、スーパーカブと呼ばれる、出前専用に開発された50ccバイクで配達をします。
ここで問題です。昭和の「出前」と、現在のフードデリバリーでの一番大きな違いはなんでしょうか?
はい。それは、食器を返すか返さないかの違いです。昭和の出前は、食べ終わった頃を見はからって。食器を取りにいきました。現在のように、紙やプラなどの捨ててもいい簡易容器ではなかったので、出前を取ることは、とても贅沢な食事だったのです。昭和の頃は、来客があった時には、出前をとっておもてなしをしたのです。
昭和の出前は、エコでもあったのですね。そして、出前専用の業者があったわけではなく、そば屋さんなどの各店舗が、「店舗外売上」の獲得のために、チラシを配って、外商活動を行ったのです。昭和の「商いの魂」を感じますね。
2024年
5月
05日
日
サザエさんの「昭和図鑑」⑧ 子どもの遊び
昨日は、次女を連れて「もんじゃ焼き」を食べに行きました。はい、今や観光地となっている「月島」のもんじゃストリートです。私の祖父が、月島から歩いて行ける「佃島」に住んでいました。小学生の時から、一人で電車に乗って、おじいちゃんのおうちに、よく遊びに行っていました。この時は、今のようにもんじゃストリートではなく、ただの「西仲商店街」です。かつては、地元の子どもたちが安くておいしい「もんじゃ焼き」を食べていたのですが、昭和が終わり、いつのまにか観光地化し、墨田川沿いには、高層マンションが立ち並びます。私たちが食べていた店に、外国人が入店しました。スマホの翻訳機能で店員さんとやり取りして、チーズがたっぷり入ったもんじゃ焼きを注文します。店員さんが作っていましたが、この体験は、まさに日本の思い出の一つになったことでしょう。「アメージング!」と叫んでいたような~(笑)
さて、今日は子どもの日ですね。昭和の子どもの遊びを思い出してみます。「あやとり」をやったことはありますか。一人でも二人でもどこでもできる遊びですが、私が小学校の頃は、クラスで女子だけでなく男子もやっていました。「東京タワー」「橋」「ほうき」などの定番技で盛り上がります。あやとりには、約3千種類の技があるそうです。でも、あやとりは、今でも、保育園でたまに子どもたちが遊んでいます。
「チャンバラ」は、まさに昭和の男子の、ごっこ遊びの代表的なものでした。私より年上世代では、時代劇のマネが多かったようです。あのスピルバーグ監督の「スターウォーズ」に出てくるライトセーバーは、日本の時代劇の映画に影響を受けたものと言われています。もちろん、保育園の子どもたちも、プラスチックの刀を手に今でも戦っています。
そして、「おままごと」は、女子の定番ごっこ遊びです。「ままごと」は漢字で書くと、「飯事」となります。保育園の子どもたちの多くは、「おままごと」=「料理ごっこ・食べ物屋さんごっこ」と思えるくらい、食べものを作っていることが多いです。漢字の意味などもちろん知らないですが、フライパンを使って、草やファームの野菜を使って料理をしています。
あれ?昭和の子どもたちの遊びは、もっとたくさんありますが、「あやとり」「チャンバラ」「おままごと」は、令和の子どもたちにとっても、遊びの選択肢の一つとして、残っています。
昭和も、令和の今でも、子どもたちは、遊びを作る天才です。それは、時代が流れても変わらないことですね。
2024年
5月
04日
土
サザエさんの「昭和図鑑」⑦ 場所
昨日行った、わたらせ渓谷鉄道の始発駅「桐生」から200メートルほど歩くと、「西桐生」というレトロで小さな駅があります。上毛電鉄の始発駅です。「中央前橋駅」という、JR前橋駅からかなり離れた場所までの区間を1時間かけて走ります。昭和の時代に、京王井の頭線で走っていた車両が現役で活躍しています。上毛電鉄は、自転車を車内に持ち込むことができて、地元の高校生が通学に使用し、住民がちょっとした買い物に自転車で乗り込みます。
上毛電鉄は、スイカやパスモといったICカードは使えません。もちろん、自動改札ではなく、改札口では、駅員さんが特殊な鋏で、入鋏(にゅうきょう)します。このシーンわかりますか?切符に、鋏を入れることで、使用開始を示したのです。この入鋏作業が、いつのまにかスタンプに代替えされ、今では、当たり前の自動改札となり、スタンプも姿を消すのです。改札で駅員が、鋏をカチカチさせる音が、またたまらなくいいのです。上毛電鉄には、「改札口で駅員が鋏を入れる」場所が、まだ残っていたのです。
駅には、今はなくなってしまった場所が、まだあります。何かわかりますか?そう、「伝言板」です。私もこの伝言板を書き込んだことがあります。「太郎へ・・・もう待ちきれないから、悪いけど先に行ってる。次郎」のようなメッセージです。これが、1990年代には、携帯電話の普及が進んだことから、必要性がなくなりました。また、落書きが増えたことで、伝言板の役割も消えていったのかもしれません。
私が学生の頃、駅で待ち合わせをしている時に、「伝言板」を読むのが楽しみでした。中には、イラスト付きの芸術的なメッセージもありましたね。令和の今は、携帯で簡単に検索できるので、待ち合わせ駅に遅れることも少なくなりましたが、昭和のアナログ時代では、「○○駅まで、だいたい1時間くらいだろう」と、勘に頼っていました。早く到着するか遅刻するか、その人の性格次第でした。私も、大学時代にデートの約束で、池袋駅に待ち合わせをしました。時間になっても彼女は現れません。30分経過して相手の家に電話すると「家を出た」とのこと。こうなったら、意地でも待ってやろうと、本1冊読み終えてしまいました。待つこと2時間、これは、今でも破られることのない、私の待たされ時間の最高記録となりました。家を出るのが30分遅くなったことと、バスの大渋滞が理由でした。2位間も待つと、怒りを超えて、悟りの境地になり、一切文句を言わなかった自分を思い出します。(笑)
昭和の駅にあった「伝言板」・・・令和の駅で見つけることができたら、うれしいですね。手書きのぬくもりがいいのです。
2024年
5月
03日
金
サザエさんの「昭和図鑑」⑥ 環境問題
今日からゴールデンウイーク後半戦ですね。私は、プチ旅に行ってきました。場所は、わたらせ渓谷鉄道です。群馬県の桐生(きりゅう)から、栃木県の間藤(まとう)まで、渡良瀬川沿いを走る路線です。トロッコ列車が観光列車として走っており、今日はすべてのトロッコ列車が満席でした。
美しい景色を楽しんだのですが、もう一つの目的がありました。わたらせ渓谷鉄道は、国鉄・JR時代は「足尾(あしお)線」として運行されていました。私が中学生の頃に、足尾駅で切符を紛失してしまい、駅員からは、キセルの疑いをかけられた苦い記憶がありました。結局ポケットにありました。(笑)
「足尾銅山」を聞いたことがありますか。足尾は、江戸時代から昭和にかけて、約400年にわたって「銅山のまち」として栄えていたのです。1610年に銅山が発見されると、幕府の管轄下におかれます。多くの人たちが集まり、江戸の中期には、千軒の家があったとされています。
明治時代になると、機械による技術向上や、設備の導入で生産量を急速に伸ばしました。明治二十年代には日本の銅の40%を産出する日本一の銅山となりました。富国強兵や、世界大戦後の高度成長期など、日本の近代化を進める日本産業の礎の一つとなったのです。
しかし、足尾銅山には、光だけでなく影の部分もありました。私が中学時代の現代国語の教師の夏休みの課題が、社会派の小説を多く書いた城山三郎さんの「辛酸(しんさん)田中正造と足尾鉱毒事件」です。そう、影の部分は、銅山から排出された、「鉱害」が、人や自然環境を壊していったことです。
足尾銅山の鉱毒で甚大な被害を受け、反対運動の急先鋒となった谷中村(やなかむら)は、絶体絶命に危機にありました。鉱山の資本家と結託した政府が、村の土地を買収し、遊水池として沈めようとしていたのです。反対運動の指導者、田中正造は、国会議員でしたが、村を守るため、政治権力に法廷での対決を挑みます。しかし、それは苦難に満ちた闘いで、国は全く動かず、田中正造は、天皇に直訴するも通じません。
こうして、足尾銅山鉱毒事件は、日本最初の公害闘争となったのです。その後、環境問題が取り上げられるようになりました。「水俣病」は、熊本県水俣湾周辺の化学工場などから海に排出された水銀に汚染された魚を長期間、日曜的に食べたことによる中毒です。「イタイイタイ病」は、岐阜県神岡鉱山から排出されたカドミウム汚染です。
令和の時代なら、環境が最優先で、開発が進められるようになりましたが、昭和以前は、経済を優先することに、多くの政治家は、疑問すら思わなかったのです。
皆さんは、わたらせ渓谷鉄道のトロッコ列車の観光を考えたら、必ず、足尾銅山に寄ってください。ただし、観光施設では、あまり影の部分は見えてきませんね。「足尾銅山を世界遺産に!」の活動が行われています。私見ですが、世界遺産になるには、「ここで400年も銅を産出したんだ」だけではダメです。負の遺産にもスポットを当てて、環境問題にまで巻き込んだ、日本で最初のまちというフレームでアピールしてもらいたいですね。
足尾銅山は、昭和48年に閉山となりました。掘られた坑道の長さは、東京→博多間に匹敵します。閉山から、50年以上が過ぎているので、わたらせの自然は、見事に美しく復活しています。
2024年
5月
02日
木
サザエさんの「昭和図鑑」⑤ 道具
今日は、ようやく晴れました。ふだん子どもたちが、タイヤアスレチックで遊んでいる、長い板に、水性ペンキで色を塗りました。スカイブルー、ピンク、イエローの3色です。どうせ遊ぶなら、華やかにカラフルに楽しもうという作戦です。ペンキを塗る子どもたちの目が真剣です。
さて、今日の「昭和図鑑」は、平成・令和の子どもたちが知らない道具「マッチ」です。私が、小学生くらいの頃は、ライターよりも、マッチを使った記憶の方が残っていますね。父に、マッチの擦り方を教えてもらって、先の少し膨らんだ部分を箱のヘリで擦るのが、なんともわくわくしました。シュッと炎が上がる瞬間が、たまらなかったです。でも、むやみにマッチを使うと、火事になると、本気で大人から怒られたものです。
保育園の読み聞かせで、「マッチ売りの少女」の話をすると、最後は、寒さに凍えて少女が死んでしまう悲しい物語にもかかわらず、子どもたちは、マッチをよく知らないので、悲しみに浸ることもありません。
ガスコンロや石油ストーブに点火する時に、マッチを使いましたが、一番多くマッチが使われたのが、タバコに火をつける時です。そのため、「スナック」や「バー」が、マッチを配っていました。箱に、店のデザインや広告を印刷したマッチを宣伝用として使用したのです。
サザエさんでは、マスオさんが、上着のポケットから、スナックやバーのマッチが見つかってしまって、ばつの悪い顔をします。私の父親の世代は、まさに、「あるある」の光景だったのです。この頃は、マッチのコレクターもたくさんいたようですね。
実は、私は今でもマッチを使っています。仏壇のろうそくに火をつける時には、やっぱり、ライターよりもマッチがしっくりきます。ほのかな火薬の香りもいいものです。
マッチは、ライター以前の火をつける道具ではありますが、なんとなく、夜の世界の大人の時間が垣間見えるような、そんな不思議な道具ですね。この夏のサマーキャンプでは、マッチを使い方を子どもたちに教えることにします。
2024年
5月
01日
水
サザエさんの「昭和図鑑」④ 事件
5月に入りました。昨日4月の保育園のDVDを保護者の皆様に渡したのですが、早速、視聴した親子・・・体操教室で、空中回転するすご技を見せてくれた5歳男の子のママは、その身体能力に驚愕したそうで、おじいちゃんおばあちゃんに動画を送ったそうです。男の子の「どや顔!」が目に浮かびます。(笑)
今日は、朝からまとまった雨です。そこで、子どもたちは「母の日」プレゼント制作をしました。何ができるか?5月11日の保育参観までのお楽しみですが、たいがい、子どもたちは、事前にママに話してしまいます。(笑)
さて、今日は「3億円事件」です。昭和には、数えきれないくらいの事件が発生していますが、私も子どもながら、この事件のインパクトがいかに大きかったかを父に熱く語られて記憶しています。昭和43年、東京都府中市で金融機関の現金輸送車に積まれた約3億円の現金が、白バイ警官に扮した男に奪われるという、後世にまで語り継がれる前代未聞の大事件が起きたのです。この3億円は、東芝の府中工場の従業員に支払われるはずのボーナスでした。この事件を機に、多くの企業で、給料の銀行振り込みが普及したそうです。給料袋を手渡しするというイメージは、令和の若者では考えられないでしょう。
当時の3億円は、今の価値では、10億円に値すると言われています。令和になって、10億円強奪事件が起きたとなれば、やっぱり大事件ですね。
様々な謎が解決されないまま、3億円事件は、昭和50年に時効が成立しました。この3億円には、日本の保険会社で保険が掛けられていたので、ボーナスは翌日には全従業員に支給されました。その保険会社も再保険をかけていて、日本以外の保険会社で全額分が補填されたのです。よって、日本国内で金銭的損失を被った人がいなかったことから、被害総額2億9430万の語呂で「憎しみのない強盗」とも言われたのです。
しかし、捜査に投入された警察官は、延べ17万1346人、捜査費用は7年間で9億7200万円以上が投じられるなど、空前の大捜査となったのです。3億円事件は、日本犯罪史に名を残す未解決事件となり、多くの映画やテレビドラマなどで放映されてきました。
時々、府中街道を車で走ると、西国分寺駅を過ぎて、3億円事件の現場を通過します。私の頭の中に、白バイ姿の犯人の顔がよぎります。この犯人が生きているならば、まだ70歳前後です。何を想うか・・・ですね。
2024年
4月
30日
火
サザエさんの「昭和図鑑」③ 社会
今日は、屋上遊びの時間になると、雨が上がりました。子どもたちには、屋上ファームの仕事を頑張ってもらいます。まずは、ようやくホームセンターで見つけた「白なす」の苗を植えました。昨年、この白なすを育てたのですが、とろけるように美味しくて、今年も挑戦です。黒いなすの苗は、多くの種類が売っていますが、白なすは、たまに見かけるだけです。急いでゲットしました。
そして、ついに菜の花をすべて引っこ抜きます。「俺は、力持ちだ!」という園児が集まって、あっという間です。長い間、この菜の花は、花摘みだけでなく、食べる方でも活躍しました。菜の花畑の後には、ミニトマトを植えます。寺子屋の時間では、サツマイモの苗を植えました。これは、夏をはさんで、しっかりと大きくなって秋に収穫です。芋ほりで、子どもたちと盛り上がります。
さて、今日は、昭和の社会では当たり前に行われていた「ストライキ」を思い出してもらいます。ストライキとは、労使交渉において、労働者が、賃金アップや労働環境の改善を求めて労働を行わずに抗議することです。
昭和の終わりには、「スト決行」のニュースを聞かなくなりましたが、昭和30年代後半から50年代までは、。春闘(春の賃上げや夏のボーナス交渉)の季節になると、メーカーや工場だけでなく、電車やバスもストライキを決行することが頻繁にありました。ピーク時は、全国で年間千件以上もあったそうです。
電車が止まれば、サラリーマンは通勤できず、会社を休むことになります。組合側は、「賃上げ要求をのまないと、ストライキをするぞ。そうなれば、社会は混乱し、鉄道会社の信頼を落とすことになるぞ!」と、会社側にゆさぶりをかけるのです。しかし、当時は、「やれるもんならやってみろ!」とばかりに、会社側も強気で、労使ともに、妥結への歩み寄りが、なかなかされなかったのです。
私も、高校大学時代、ストで電車が動かないので、休校となり「ラッキー!」と思ったものの、電車が動かないので、どこにも遊びに行けず・・・という記憶が残っています。しかし、現在は、働き方も様々で、正社員でも労働組合に加入していない人も増えています。労働組合の存在意義は、昭和と令和では大きく異なっているのが現実なので、今後ストライキなんかないだろうと、思っていました。
ところが、記憶に新しいところで、昨年8月31日に、西武百貨店池袋本店でストライキが行われ、お店は、まる一日定休日となりました。このストライキが行われた目的は、池袋西武で働く仲間を守る、お客様から愛されるブランドを守る戦いでしたので、他の百貨店の組合トップたちも応援に駆けつけました。世論も「よくがんばった!」とひいき目に受け止めたのです。
私は、サラリーマン時代に、東京支部の執行委員長をやったことがあります。労使交渉では、社長に対して、きちんとモノを言いました。業務では、なかなか言えませんが、組合のトップの立場で、「組合員の生活を守る」という大義のために戦ったのです。もちろん、殴り合いのケンカではありません。言葉による交渉ですので、勉強もしなければ、経営者相手に言い負かされてしまいます。
「要求通りの回答がなければ、スト決行!」という切羽詰まった状況を何度も経験しました。とても、熱かったですね。令和の時代だって、ストライキに変わる、熱い何かが、働く若者の中に必ずあるのでしょう。時代が変わっても、そこは変わらないで欲しいですね。
2024年
4月
29日
月
サザエさんの「昭和図鑑」② 生活習慣
昨日は、田無神社に行ってきました。少しミーハー(昭和です)な言い方をすれば、金・青・赤・白・黒の五龍神が鎮座する最強パワースポットです。そんな神社知らない?と思ったあなた。今年は「辰年」ですね。ここには5つの龍がこの神社を守っているのです。それぞれの龍には、行列ができていました。私も、しっかりと並んでお参りをします。私は、初めて参拝するので、いきなり、願い事をするのではなく、住所と名前を言って、「初めてお参りさせていただきます。よろしくおねがいします」だけにとどめます。これが、初参拝のルールです。
さて、昨日は田無近辺に、「大正10年創業のたばこ屋」という、古い看板を掲げたたばこ屋さんを見つけました。たばこの販売は、昭和も令和の今も許可制で、一定の範囲内にたばこ屋がある場合は販売許可が出ません。昭和20~30年代のたばこ屋は、たばこを売ることはもちろん、公衆電話が設置され、切手やはがきの販売も担当していました。
ところで「たばこ屋」というと、なぜかおばあちゃんが店番をしていることが多いと思いませんか?それには理由がありまして、たばこの仕入れ価格は小売価格の約9割で、利益率は、わずか1割程度しかないのです。そのために、昭和のたばこ屋は、自宅兼店舗で「小遣い稼ぎに高齢者が営むもの」と見なされていたのです。
そんなたばこは、昭和の生活習慣の中に、しっかりと根付いていました。たばこをふかしながらの会議など、どの会社でも見られたのです。私が20歳代の営業会議では、会議室が、たばこの煙でいっぱいでした。(笑)
日清戦争後の1898年(明治31年)、政府は国家収入を増やす目的で、たばこの製造販売を「国営化」し、国が喫煙を奨励したこともあって、成人男性の喫煙率は、ピーク時1966年(昭和41年)は、なんと83.7%もあったのです。昭和の終わり頃から、たばこが体に与える害悪が広く知られるようになり、喫煙者が減っていきます。昭和60年には、日本専売公社が民営化され、受動喫煙の防止を目的とした改正健康増進法が2018年(平成30年)に成立しました。令和4年の直近のデータでは、喫煙率は男性25%、女性は7%だそうです。
今では、電車の中では、喫煙することができないばかりか、駅での喫煙も禁止されるようになりました。歩きたばこはNGで、街の片隅にある喫煙所で、肩身が狭い喫煙者の姿を見るだけです。今の若者は、たばこを吸うことがオシャレとも思わないし、他の楽しいことがたくさんあるし、単純に健康リスクを考えているのでしょう。近い将来には、紙たばこは、なくなっているのかもしれませんね。
2024年
4月
28日
日
サザエさんの「昭和図鑑」① 仕事
世の中は、昨日からゴールデンウイークです。テレビ報道を見ていると「安・近・短」がキーワードだそうです。安い値段で、近場を日帰りなど短いスケジュールで…といった意味です。円安で海外旅行もアジアの近場で過ごし、国内旅行も宿泊料金アップで日帰りで過ごす人が多いようです。観光地に人があふれているのは、円安で日本にやってくる外国人です。
そもそも「安近短」という言葉は、昭和の終わりにバブル崩壊で、贅沢ができない状況になり、旅行は「安近短」で過ごすということで、使われた言葉です。私のような昭和世代は、「安近短」という言葉を聞くと、昭和を思い出します。
ということで、ゴールデンウイークは、昭和の懐かしさに浸ってもらいます。日本国民に深く愛されているサザエさんは、戦前から戦後の復興期、高度成長期と日本人の心に寄り添った名作漫画です。最初は、昭和21年~49年に、夕刊フクニチ、朝日新聞など新聞紙上で連載されました。新聞で毎日掲載されたサザエさんは、当時の世相が色濃く反映されています。
今日は、昭和にあって、令和の今では、ほとんど見ることがなくなった仕事の一つ、「エレベーターガール」の話です。
昭和の女子たちの憧れの仕事の一つが、エレベーターガールでした。制服&帽子の当時の最先端の服装で百貨店のエレベーターに乗降する女性は、昭和4年に、松坂屋上野店に初めて配属されたそうです。
昭和の終わりまで、多くの百貨店のエレベーターに乗務し、運転の操作や各階の案内をしました。バブルが崩壊し平成となり、百貨店業界全体が経営不振に陥ります。人件費節減のターゲットとして、エレベーターガールが矢面に立たされます。また、誰でも簡単に操作ができるエレベーターの普及もあって、日本初のエレベーターガールを排出した、松坂屋上野店では、2007年(平成19年)に廃止となりました。
私は、入社初年度は、日本橋の三越本店に配属となったのですが、喜左衛門(きざえもん)に行くと、そこに当時、奉仕部という部署だった、エレベーターガールが昼食をとっているではありませんか。22歳の私は、同じテーブルに座ったのは言うまでもありません。(笑)ちなみに、喜左衛門(きざえもん)という言葉は、三越の隠語で「食事」という意味です。「喜左衛門に行ってきます」と言えば、「食事休憩に行ってきます」という意味です。
令和の今では、エレベーターガールは、絶滅危惧種になったと思いますか。大丈夫です。
私が知る限りでは、日本橋髙島屋で立派に仕事をしています。日本橋髙島屋には、国の重要文化財になった手動式のエレベーターがあります。このエレベーターは、エレベーターガールでないと動かせないのです。私が日本橋髙島屋を担当していた時は、必ず、1階正面入口から入店し、手動式エレベーターにリスペクトしてから仕事をしていました。(本当です)
そう、令和では、エレベーターガールの仕事は、付加価値としてお客様の支持をいただいているのです。そう簡単になくなりませんね。
2024年
4月
27日
土
イチローズモルトの立役者
今日は、小学1年生男の子が久しぶりに保育園にやってきました。積もる話があったようで、小学校生活のことをたくさん教えてくれました。1年生ですので、まだ午後の授業はなく、給食が終わると学童保育へ移動する生活だそうです。今は、新しい環境を自分の力で乗り越えようとしているところです。「こうすればいいよ」と園長からの一方的なアドバイスは控えて、聞き役に徹しています。こうして、小学生になってからも成長を見ることができるのが、うれしいですね。
さて、今日は「イチローズモルト」の話です。もう世界的に有名になった2004年創業の埼玉県秩父にあるベンチャーウイスキーです。設立者の肥土伊知郎の名前に由来して、ウイスキーは、イチローズモルトとうネーミングです。
しかし、イチローズモルトは、最初から爆発的なヒットとなったわけではありません。ここには、ブランドアンバサダーとして活躍する「吉川由美」さんの存在がありました。いくら良質の酒を造っても、その良さを正確に伝えないと、売れる物も売れません。
彼女は、イチローズモルトブームが起こる前の、2005年に帝国ホテルでバーテンダーとして働いている時、棚に並ぶ世界中のウイスキーの先に広がる世界にひかれたそうです。本を読み知識を得るが物足りず、本場のスコットランドに旅立ちます。その後、ニューヨークで過ごした2年間で英語を勉強し、2011年には、スコットランドに単身移住します。蒸留所に住み込み、夏は世界中のウイスキー愛好家が集まるバーで働く日々を送ったそうです。そこで飲んだ、日本のウイスキーのおいしさに驚くのです。
秩父蒸留所のウイスキーを国内外に伝える仕事をしたいという思いが募り、帰国後に面接を受けて採用されます。イチローズモルトを知ってもらうため、世界中でセミナーを開くなど、地道な活動で、2013年からは、売上が急増します。今では、「秩父といえばウイスキー」と認知されるようになったのです。
そして、2019年には「ワールドウイスキー・ブランド・アンバサダー・オブ・ザ・イヤー」を吉川さんは受賞します。
どうですか・・・今では、多くの人に知られる「イチローズモルト」ですが、こんな、縁の下の力持ちの存在があったのです。なかなか、手に入りませんが、飲む機会があれば、「吉川由美」さんの存在を思い出してください。
2024年
4月
26日
金
給食が不安
今日の体操教室では、プログラムの最後に「チャレンジタイム」がありました。助走して踏み台をジャンプ→目の前のとび箱に手をつかないで、空中で前回りして着地です。どうですか、イメージできましたか。この大技に、年長男子4名が挑戦しました。体操教室の先生からは、「ビッグ4」と呼ばれ、ずば抜けた身体能力があります。そして、この大技を見事クリアーするのです。私もビデオに撮りながら、思わず「スゴイ!」と叫んでいました。
さて、今日の話は「給食」です。新年度がスタートし、小学校1年生の児童にとっては、「好き嫌いが多い」「食べるのが遅い」という不安を抱える保護者も多いかと思います。
保育園ホワイトきゃんばすでも、今まで多くの園児が、この問題にぶつかってきました。例えば、小食の園児に対しては、最初は少なめに盛りつけて、おかわりを促して完食体験を経験させる。ふりかけごはんにするなど、子どもが好きな食べ方にする。苦手な食材は少なめにしたり、小さく切って、食べられたら大げさに褒める。みそ汁の野菜が苦手な園児は、スープごはんにしてみる。
子どもへの対応は、一人一人違うので、今までトライしたやり方は限りないですね。そんな中で、一番効果があったのが、屋上ファームで収穫体験した野菜を「これは、みんなが屋上でとった野菜だよ。新鮮でおいしいからね~」すると、他の園児から「おいしい!おいしい!」の大合唱が起こり、つられて食べられるようになります。今、屋上ファームでは、絹さやエンドウ豆が収穫ラッシュですが、効果があるのは、ファームで自分が収穫した野菜だけで、スーパーで買った絹さやエンドウ豆は効果がないようです。
小学生の子どもを持つ親で、我が子の給食に不安がある場合は、具体的に担任とすり合わせしておくのが大事ですね。ただし、「よろしくおねがいします」だけではいけません。①食べるのが遅い理由②家庭での工夫③本人の気持ち④これまでの体験・・・など、具体的に伝えるのがいいですね。
「本人は『早くしなさい』と求められるとプレッシャーを感じてしまうので、保育園時代は、『ゆっくりでいいよ』と言われると時間内に完食できていたようです」といった伝え方です。小学校で給食を食べる時間は、だいたい20分です。
難しいことではありますが、『給食の時間が苦手』と子どもに思わせないようにしたいものですね。
2024年
4月
25日
木
石川佳純サンクスツアー
今日は、汗ばむような陽気になりました。屋上遊びの子どもたちは、汗びっしょりです。終わりを迎える「菜の花」を引っこ抜く作業を「力持ち集合!」の掛け声で集まった園児たちの力でやってみました。「ぼくは…わたしは力持ちよ!」と園児がたくさん集まります。自己肯定感の高い子どもたちです。この場所には、ミニトマトの苗を植えます。
さて、卓球女子の五輪メダリストで、昨年5月に現役を引退した石川佳純さんが、全国各地を巡回し、子どもたちに卓球を教える「47都道府県サンクスツアー」が、先日、ちょうど折り返し点の24回を終えたそうです。
正直、スター性のある石川さんなら、タレント活動で稼ぎまくることもできるでしょうが、彼女は、子どもたちの成長のために、どのようにアスリートが貢献すればいいか、その一つの形を示しています。
石川さんのツアーの理念は「スポーツの魅力と、応援してくれたファンへの感謝を伝えること」だそうです。卓球の技術も教えますが、決して競技普及だけにはとらわれません。行く先々で、子どもたちに「卓球じゃなくてもいいから、いろいろなことにチャレンジしてほしい」と強調します。
あの大谷翔平選手が、日本全国の小学校にグローブを送ったのは、「このグローブでキャッチボールをしてスポーツを楽しむきっかけになってもらいたい」という考えで、野球以外のスポーツも挑戦して欲しいと願っているそうです。石川さんは、12歳で故郷の山口市を離れ、大阪の中学に進学します。「夢に向かう、人生でも大きな一歩でした。そんな経験を踏まえ、子どもたちには『きっかけ』を見つけてほしい」と願っています。
石川さんは、2月に、中学生活の不安を感じる小学6年生を前に、チャレンジ精神の価値を説きます。「新しい生活が始まると、うれしいこと、楽しいこと、もしかしたら苦しいこともあるかもしれない。でも不安を気にせず飛び込んで。好きなことは『なぜこんなにエネルギーが湧くのだろう』という気持ちにさせてくれる。自分が『これだ』と思えるものに出会えるように、どんどん挑戦してほしい」と背中を押します。
子どもたちから「やめたくなったことはありますか」と質問されると、「何度もあります」と素直に答えます。「落ち込んだり、頑張っても結果がダメな時も、『昨日より今日』と思って、工夫を重ねてきた。努力は、良い時も悪い時も続けられるから大事なんです」と言います。
どうですか、石川さんのメッセージに目を輝かせて聴き入る子どもたちの姿が想像できますね。こういった、現役選手や元アスリートが子どもたちと交流し、スポーツの魅力を伝える機会が、これからもどんどん増えていくとうれしいですね。
2024年
4月
24日
水
オタフクソースのお好み焼課
今日の連絡ノートには、昨日のピクニックランチのお弁当箱が空っぽで、「ママお弁当作ってくれてありがとう」という我が子のコメントに、涙する母親が4人もいました。やはり、ママへの最高のプレゼントは「空っぽのお弁当箱」でした。
今日は、その流れで食べ物の話です。広島の人たちが愛するのは、広島カープだけでなく、お好み焼きとそれに使われる「オタフクソース」です。私は、何人かの広島出身の知り合いがいますが、お好み焼きを語り出すと、「お好み焼きは、○○じゃないといけない」という長いウンチクが始まります。そして、「オタフクソース」が決め手と言います。
大阪のお好み焼きは、具材を混ぜて焼きます。もちろん、こちらも私は大好きですが、広島人は、こう言います。「広島のお好み焼きには、サンドイッチの美学がある。上から、生地、キャベツの甘味、香ばしい豚バラ肉、パリッと焼いた麺、一番下に卵のうまみが重なり、ソースをまとっている。層の上から下まで、一口で食べないとダメなんだ。おいしいお好み焼きは、キャベツが甘いんだ」なんて話が止まりません。(笑)
そんな、広島のお好み焼きを引き立てる「オタフクソース」は、2022年10月に100周年を迎えた、老舗企業なんです。そして、「お好み焼課」というユニークな部署があるそうです。
1998年に発足した「お好み焼課」は、今まで20年以上も、お好み焼きの普及、研究に特化した部署だそうです。店を開業したい人のために焼き方の研修、小学校での出前授業を開く。お好み焼き店を食べ歩いて市場調査やお好み焼きを研究して新しいレシピ作りもしているそうです。まさに、お好み焼きを作り、食べることが仕事なのです。
どうですか・・・こんな部署があるからこそ、広島のお好み焼きは、今でも広島人のDNAとして、組み込まれているのかもしれませんね。そして、オタフクソースは、会社の利益を考えれば、いかにオタフクソースが売れるようにするか・・・でしょうが、お好み焼き文化を守り、広げていくことが、社会的役割なのかもしれません。
お好み焼課は、今では、新入社員の人気部署ナンバーワンだそうです。そして、世界に向けて、お好み焼きを広げようとしています。外国人相手に、全編英語版の「お好み焼き教室」も行っているようです。新入社員研修では、海外を旅して、その土地の人にお好み焼きを知ってもらう取り組みがあるようです。
さぁ~そろそろ、お好み焼きが食べたくなりましたね。今日は、広島風にチャレンジしてみませんか。
2024年
4月
23日
火
生成AIの利用に挑戦すること
今日は、寺子屋園児は「ピクニックランチ」でした。今年度1回目ですので、年少の寺子屋3番さんにとっては、初めて、屋上にレジャーシートを敷いてのお弁当タイムです。事前に近くの公園で、家族のピクニックを経験し、お弁当箱を開けて、自分で食べる練習をした年少の男の子もいました。年長園児は慣れたもので、「ママお弁当作ってくれてありがとう!」と、ここぞとばかりに、ビデオカメラに向かって話します。ママにとっては、空っぽのお弁当箱が、一番のプレゼントですね。全員完食です。
さて、小中学校では、オンラインツールを使っての授業が当たり前になってきました。そこで、生成AIを使っての授業を導入したいと考える先生も多くなっています。でも、「自分の頭で考えない」といった、マイナス面への影響も気になるところです。最近起きたことでは、中学校の理科の授業で誤った情報をコピペして答えた生徒が多数出て、問題になった出来事もありました。
そこで、ある人のアドバイスを聞いてもらうことにします。
「AIツールを教育に取り入れる際は、批判的思考を育むことが重要です。まず、AIを情報のソースではなく、アイデアの発想や解決策を見つけるための補助ツールとして位置づけ、生徒が自ら考える力を伸ばすよう導くことが大切です。また、生徒がAIを使用した場合には、その情報をどのように得たかを正確に報告させ、情報の出典を批判的に評価する習慣を身につけさせましょう。授業ではAIの機能と限界を理解し、誤情報を見分ける技術やリテラシーを高める内容を取り入れることが望ましいです」
どうですか・・・このコメントは、皮肉なことに、生成AIに200字以内で回答してくださいと指示して、出てきた文章です。私は、「しっかり書けた模範回答」と、何の疑いもなく思いました。
インターネットとう言葉が、今では当たり前に使われていますが、インターネットを使うようになったのは、私が社会人になってからです。最初は、会議資料も手書きで作り、OHPという道具を使って、投影していました。PHS→携帯電話→スマホの流れも、ここ数十年の短いスパンでの出来事です。
生成AIを規制しよう…という流れは、現実的に不可能でしょう。ならば、生成AIを導入して、私たちは、人間として「どう扱うのがいいのか」を考えるしかないですね。生成AIが作成したアドバイスは、的を得ていますが、そんなのイヤと考えるなら、自分で考えるしかありません。
2024年
4月
22日
月
大人の「学び直し」
今日は、今年度初の階段レースをしました。まずは、階段を使った避難訓練からです。1階から、さらに降りた場所に非常ドアがあることを確認してから、ガチの階段レースです。年少の寺子屋3番園児は、階段を下りるのが少し怖いようで、手すりにつかまって、ゆっくりと降ります。保育園の帰りも、時々階段を利用しながら、慣れるのが一番です。
さて、昨日、BSNHKの「舟を編む」というドラマが最終回でした。三浦しをん原作で、2013年には、松田龍平・宮﨑あおい主演で、映画化もされたので、知っている人も多いと思います。主人公が、新しく刊行する辞書『大渡海(だいとかい)』の編集部に迎えられ、個性豊かなメンバーと辞書の世界に没頭していく姿を描いた作品です。「辞書は、言葉の海を渡る舟、編集者はその海を渡る舟を編んでいく」という意味で、この書名が付いています。
私は、中学時代の現代国語教師の影響で、辞書で引いた言葉には、必ず傍線を引いていました。中学高校、そして社会人になっても使い続けています。今でも、辞書を引くと、たまたま傍線が引かれてあって、「いつ調べたんだろう?」と想いを巡らせます。スマホですぐに、言葉の意味が調べられる時代ですが、やっぱり、辞書を使うと、「学んだ」という気持ちになるものですね。私にとっては、辞書は「大人の学び直し」でもあります。
みなさんは、「ガクサン」というコミックをご存知ですか。「学習参考書」というニッチなテーマを扱った、教育者の間でも話題になった佐原実波作の作品です。舞台は、学習参考書を取り扱う出版社です。そこへ中途入社した茅野うるしが配属されます。同じ部署には、ありとあらゆる参考書を熟知している参考書オタク福山が、上司として、うるしとかかわります。
この作品の神髄は、単に参考書の紹介にとどまらず、福山は、勉強の仕方が分からない中学生に、参考書を使って勉強することの意義を説きます。「体系的に何かを理解していくその方法をものにしろ。そうすりゃ年を食っても勉強以外でも好きなことを何だって身につけられる人間になれる」つまり、勉強することは、学びの方法を身に付けることでもあると言うのです。
どの参考書を使うかだけでなく、「どのように」使うかに焦点を当てる本作は、実在する参考書が取り上げられています。
中学高校生は、勉強しなければ・・・とあせる中で、勉強のやりかたがわからないことが多いですね。この本では、その方法を具体的に教えてくれます。そして、私たち大人になってからの勉強は、やらされる勉強ではなく、「やりたい勉強」をすることが多いです。そんな時に、この「ガクサン」がパートナーとして役に立つのかもしれません。
2024年
4月
21日
日
お肉の話
保育園の子どもたちは、よく回転すしのチェーン店の名前を出します。「お寿司大好き」というよりも、サイドメニューや演出を楽しんでいるようです。日本人の魚離れは年々進んでいて、2011年には、魚の消費量が肉に抜かれてしまいました。私は、肉も魚も大好きですが、やはり肉を食べる機会が増えています。
今日は、全国食肉事業協同組合連合会が、子ども向けに出している「なるほど!ザ・お肉ブック」で、お肉の勉強です。あくまで、子ども向けです。
和牛の場合、約30キロで生まれてきます。すぐに立ち上がり、10か月で体重は約300キロにもなります。2年半かけて、しっかりとおいしい肉になるように育てられて、30か月後に約750キロになって食肉センターに出荷されます。750キロは、ざっと小学6年生18人分です。
家畜としては、世界で一番多いのが豚です。豚は、半年で約10匹、1年間で約20匹の子ぶたを生みます。生まれた時の体重は、わずか1.5キロですが、6か月後には約110キロになって、出荷されます。常に何かを食べているというイメージですね。
これよりも、もっと短いサイクルで、出荷されるのが、ニワトリです。ニワトリの卵は、約20日間温められて、ひよこになります。そのあと、わずか50日で大人になって、出荷されるのです。和牛や乳牛の「黄色のイヤリング」には、10桁の番号が書かれています。この番号は、牛肉になった時のラベルやプライスカードも書かれていて、牛が生まれたところや育ったところなどがわかるようになっています。安心・安全の取り組みですね。
お肉の部位も大事です。牛肉のステーキなら「サーロイン」でローストビーフなら「モモ肉」。豚肉のとんかつなら、ヒレもいいですが、ほど良い脂肪が、コクと甘さを感じる「ロース」が、私は好きですね。鶏肉は、モモ・ムネ・手羽さきなどそれぞれ特徴があります。肉の部位によって、どんな料理があうのか、我が子と楽しむのもいいですね。
最後に、「いただきます」と「ごちそうさま」の意味を子どもと一緒に考えてみましょう。「いただきます」には、頭の上に食べものを押し上げて「いただく」と、牛豚鳥などの命を「いただく」ことの両方の意味があります。どちらも、食べものに対して「ありがとう」の気持ちを伝える言葉です。
「ごちそうさま」の「ちそう」は、漢字で「馳走」と書きますが、「馳走」には「走りまわる」という意味があります。走りまわって食べ物を用意してくれた人たちに、無事にごはんを食べて命をつなげたことへの「ありがとう」の気持ちを伝える言葉なのです。
まだ、小さい子どもには通用する、大切な食育ですね。
2024年
4月
20日
土
学校は楽しくするところ
本日登園した、小学校1年生の女の子は、ふだんは、寡黙で、ペラペラとおしゃべりをするようなタイプではありませんので、「小学校はどうだい?」と聞いてみると、友だちになった3人の女の子の話をしてくれました。そして、同じ小学校には、5人の卒園児が通っているのですが、他の4人の様子も教えてくれました。みな、元気に頑張っているようです。
今日の女の子のように、「楽しい」と思うのはうれしいことですが、そもそも、学校は楽しいところではありません。こう言うと、えっ!?と思いますね。
ある教師の話です。「私が教師になって間もない頃のことです。授業がうまくできず、子どもたちとの関係もうまくいかず、学校が楽しくなくなってしまいました。そこで、先輩の先生に相談することにしました。その先輩は、しばらく私の話を黙って聞いてくださったのですが、私が話し終えると、こう言ったのです。『○○先生。学校はたのしいところじゃないんだよ。楽しくするところなんだよ』この言葉を聞いた私は、目から鱗が落ちるような思いがしました」
どうやら、この先生は、学校が楽しくない原因を周りに押し付けていたのです。これは、学校に限らず、私たちの職場環境でも当てはまりますね。自分が主体的に動きもしないで、上司、先輩たちや社風のせいにして、「やる気が出ないんだよ!」と言っていることなど、私にも心当たりがあります。
ここ数年間は、コロナへの感染防止のために、多くの学校行事が延期や中止になってしまいました。「コロナだから仕方ない」とあきらめて、「楽しくない時間」を過ごした人も多かったと思います。しかし、そんな中でも、楽しくすることができたのかもしれませんね。
今日の小1女子は、きっと、自分の力で学校を楽しくする行動を自然と行っているのだと思います。そして、私たち大人は、子どもが「楽しくない」と言ってきた時に、じっくりと話を聞いて、「じゃ、楽しくするにはどうすればいいか・・・考えて見ようよ」と、一緒に知恵を出すのが大切ですね。
2024年
4月
19日
金
1970年の大阪万博
毎年のことですが、年少園児の体操教室は、バタバタです。体操着に着替えるのが、まずは大きな壁です。うまくいきません。水筒を自分で飲むのもままならない園児もいます。先生と先輩たちの力を借りて、てんやわんやで頑張ります。体操教室本番でも、マットに寝転がって、まるで、ゲームコーナーのボールプールのごとく、はしゃいでしまいます。こうして、ハチャメチャ体操教室が始まるのです。今は、じっと辛抱の時です。(笑)
さて、来年2025年に行われる大阪万博は、建設が間に合わないとか、参加国が減少するとか、そもそもやる必要があるの?とか、問題が山積みですが、1970年に行われた大阪万博は、それはそれは、すごい盛り上がりでした。私も、一応、親に連れて行ってもらったのですが、子どもだったので、ほとんど覚えていません。
この1970年の大阪万博のコンサートで名曲が発表されました。ジローズの「戦争を知らない子供たち」です。♬戦争が終わって僕らが生まれた~戦争を知らずに僕らは育った~♪という歌ですが、ご存知ですか。
現在の日本の大人たちの大半は戦争を知りません。私も同じです。もちろん、子どもたちも戦争を知りません。ところが、世界中には「戦争しか知らない子どもたち」がたくさんいます。
奈良・薬師寺の大谷師は、こんな法話を説いています。「朝から雨が降っていると、大半の皆さんは、今日はついていないな、と考えます。しかし、空から雨ではなく弓矢や槍が降ってきたらどうします。ましてや、爆弾やミサイルが落ちてこないのは、とても幸せなことではないですか」
まさに、1970年の大阪万博は、日本の高度成長期と重なったことも大ブームの要因でしたが、平和の祭典という意味も大きかったと思います。ならば、2025年大阪万博も、平和を考える機会になれば、意義ある祭典となるのでしょう。
2024年
4月
18日
木
おじさん1人ディズニー
エンドウ豆を毎日必死になって、収穫する3人きょうだい。葉の色も豆の色も緑なので、まずは見分けることが大事です。次は、どのくらいの大きさなら収穫可能か・・・これも、経験によって、食べ頃サイズを収穫できるようになりました。給食に使用されるので、貢献度が高いのです。(笑)
さて、今日は夢の国の話です。コロナ前、まだ東京ディズニーランドに年間パスポートがあった頃、何人かの「1人ディズニー」を楽しむ人を知っていました。アトラクションに乗ることよりも、パレードを楽しむ人たちで、全員女性でした。ところが、最近では、「おじさん1人ディズニー」というライフスタイルが現れたようです。もともと、他の遊園地と違って、東京ディズニーランドは、カップルやグループ、家族で行くところとう概念は当てはまりませんが、さすがに「おじさん1人」は、???ですね。
あるおじさんの場合は、「きっかけは十数年前に娘を初めてディズニーシーに連れて行った時です。その日は、ディズニーシーの人気キャラクター『ダッフィー』のぬいぐるみの発売日でした。並ぶのが大嫌いだったのですが、娘のために2時間半並んで買い与えると、娘はとんでもない素敵な笑顔を見せてくれたのです」これを機に、このおじさんは、シーズンごとに発売されるダッフィーシリーズのグッズを購入するために、ディズニーシーに通うようになり、はまったそうです。「あそこは夢の国というだけあって、僕のようなごりごりのおじさんがダッフィーのぬいぐるみを抱えて1人で歩いていても受け入れてもらえるんです」と語ります。
そもそも1人ディズニーは、ショーやパレードを見学する際は、推しのキャラクターやダンサーの近くを陣取りたい。自分の好きなアトラクションだけを楽しみたい。食事の時間や内容もすべて自分の好みで決めたい。こんな人が、一人で行くメリットを感じているのです。おじさん1人客によく見られるのが、ビールとつまみを片手に、水辺の静かなベンチでたたずむ姿だそうです。
どうですか・・・「おじさん1人ディズニー」を理解できましたか。誰にも邪魔されずにゆったり落ち着いて、非日常的な空間に身を浸すことができるのが、まさに至福の時間なのでしょう。東京ディズニーランドの楽しみ方は、どんどん広がっているようですね。

 子どもたちの笑顔のために!働くママを応援!
子どもたちの笑顔のために!働くママを応援!